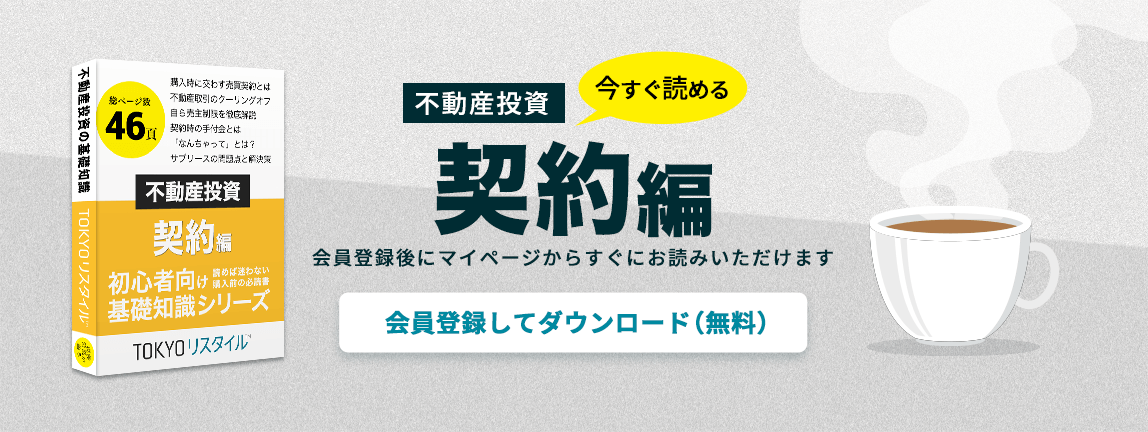誰でもわかる!登記簿謄本・登記事項証明書の全貌や申請方法を徹底解説!
- 更新:
- 2023/07/12
本記事は動画コンテンツでご視聴いただけます。
不動産投資をする上で「登記簿謄本」という言葉を聞く機会は多いと思います。また登記簿謄本と合わせて「登記事項証明書」も聞いたことがあるのではないでしょうか。
実は登記簿謄本と登記事項証明書はほぼ同じものです。管理方法により名称が変わりますが、基本的には同一のものとなります。また、実際に謄本を見てみると、難解な用語が多く、初心者の方には読み解くのが難しいかも知れません。
そこでこの記事では、不動産投資を行う上で使用頻度が高い「登記簿謄本・登記事項証明書」について、その基本的な内容や見方、交付請求の具体的な方法までを詳しく解説していきたいと思います。
- 目次
- 登記簿謄本とは
- 登記事項証明書とは
- 登記事項証明書は内容によって4種類
- 登記簿謄本・登記事項証明書を理解しよう(見方)
- 登記簿謄本(登記事項証明書)の3つの交付請求方法
- 交付申請書へ必要項目を記載
- 地番・家屋番号・所有者の調べ方
- よくある疑問
- まとめ
登記簿謄本とは
登記簿謄本とは、土地や建物における所在地・面積・所有者の氏名等、その土地や建物の権利関係が記載されている文書のことです。登記簿謄本によって、不動産は法務局によって法的に管理されています。また不動産登記法により申請すれば誰でも閲覧・取得が可能です。
登記事項証明書とは
結論から言えば、登記簿謄本と登記事項証明書の内容は同一のものです。管理方法の変更によって名称が変わっただけで、中身に相違がある訳ではありません。これまで登記簿は紙として記録されていましたが、現在ではデータとして保存され、インターネット上で管理されています。紙でまとめられていた情報を複写したものが「登記簿謄本」、インターネット上で管理されている情報を複写したものを「登記事項証明書」と理解しておけば間違いないでしょう。
とはいえ、実際の取引シーンでは両者をまとめて「謄本」と呼ぶケースもあるため、それが「登記簿謄本」と「登記事項証明書」のどちらを指しているのかは、文脈から都度判断できるようにしておきましょう。
登記事項証明書は内容によって4種類
「登記事項証明書」には、役割が異なる4種類があります。
- 全部事項証明書
- 現在事項証明書
- 閉鎖事項証明書
- 一部事項証明書
これら4種類の中から、そのときの目的に応じて最適なものをチョイスして適宜取得する必要があります。それぞれの証明書がどのような役割があるのか、次の項目で説明していきましょう。
全部事項証明書
全部事項証明書とは、特定の不動産について過去から現在に至るまでの全登記情報が記録されている証明書のことです。
所有権の移転履歴、抵当権の設定や抹消、差し押さえの有無など、事細かに記載されているため「登記事項証明書が必要」と言われた場合には、先方から指定があるなど特別な理由を除いて「全部事項証明書」を取得しておけば、問題ありません。ただ、取得対象が分譲マンションの場合など不動産物件によっては、証明書の量が膨大になることもあるので注意しておくようにしてください。
とはいえ、これは敷地権化されていない場合であり、敷地権化されていれば対象箇所を探すのは容易です。対して、戸建ての場合は1つずつ出ますが、土地と建物の所有者が別の場合はそれぞれ1つずつ出てくることを覚えておいてください。
現在事項証明書
現在事項証明書とは、過去の情報は記載されずあくまでも現在の権利関係だけに絞って記載されているシンプルな証明書です。例えば、過去にその不動産を担保に借り入れをしたなどといった情報を開示したくない場合などには非常に有効な証明書といえます。
金融機関などからの融資を受ける場合に提出を求められた場合は「全部事項証明書」が必要になることもありますが、その不動産の所有者が自分であるということを証明するだけの目的であれば、現在事項証明書で十分と言えます。
閉鎖事項証明書
閉鎖事項証明書とはこれまでに閉鎖された不動産の情報を証明するための書類です。土地の合筆や建物の取り壊しの影響で消滅した不動産があると、登記記録が閉鎖されるため、そうした不動産の登記情報を証明するために必要になります。
ただし、覚えておかないといけない注意点が2つあります。
1つ目はこの「閉鎖事項証明書」に記載されている情報は「全部事項証明書」にも記載されていない内容であるということです。2つ目は、対象の物件が閉鎖してから土地なら50年、建物なら30年で登記情報の保存期間が切れてしまうため、それ以前の古い情報の場合は取得できなくなっている可能性があります。
一部事項証明書
証明書にも多くの種類があることを解説してきましたが、一部の項目だけ書類として出したい場合は「一部事項証明書」を使いましょう。登記情報の記載情報の内容から一部を抜粋して取得する登記事項証明書です。
例えば、分譲マンションのような不動産の中で自分の保有分だけを証明したいと思って「全部事項証明書」を取得請求した場合、その分譲マンション全室の所有者や担保権といった全ての情報が記載されたものとなります。
この場合は1通だけ取得したつもりでも結果的に100ページを超えてしまう可能性があります。そのため登記情報の中に含まれる膨大な不必要情報の中から必要な情報を確認するだけでも一苦労となりかねません。適宜選択して取得するようにしましょう。必要な部分が明確にわかっている場合などは、この「一部事項証明書」の取得が便利です。
登記簿謄本・登記事項証明書を理解しよう(見方)
それでは次に、謄本の見方について見ていきましょう。登記簿謄本(登記事項証明書)は、以下4つの部分に分かれて記載されています。
- 表題部
- 権利部(甲区)
- 権利部(乙区)
- 共同担保目録
それぞれの意味について解説していきます。
表題部
表題部は、その不動産の所在地や広さ、現在の所有者といった基本情報が記載されている部分です。この記載内容は、対象となる不動産が土地なのか建物なのかで記載内容が異なります。それぞれについて解説していきましょう。
土地の場合
まず、対象となる不動産が土地の場合についてです。
正確な所在地を把握するためには、建物を表す「所在」の欄と土地の管理番号である「地番」の欄の内容を合わせて読む必要があります。
地目
宅地や田・畑、山林や公衆用道路、雑種地といった土地そのものの用途が記載されている箇所です。場合によっては記載内容と現在の状況とが異なっている可能性もあるため、注意が必要となります。
地積
対象となる土地の面積が記載されていますが、この値は必ずしも正しいとは限らないことから、売買などの取引が絡む場合には注意するようにしましょう。
原因及びその日付(登記の日付)
対象となる土地が表示登記(その土地の存在特定を目的として表題部を登記すること)された原因と日付が記載されています。
所有者
その土地が表示登記された時点で、所有者となっている人の情報になります。
ここで知っておくべきことは、この箇所の目的は「不動産の特定」であるということです。住所や氏名が記載されていますが、名前が記載されているからといって、第三者に対する対抗力は一切ありません(表題部への登記には対抗力が具備されていないため)。
建物の場合
次に対象となる不動産が建物だった場合です。
「所在」は、その不動産がある住所の番地までが記載されているため、敷地の特定が可能です。その上で、「所在」とは別の欄にある「家屋番号」によって建物が特定できます。
種類
その不動産の使用用途が記載されており、具体的には居宅や店舗、共同住宅、事務所や倉庫・車庫といったものです。
構造
その建物自体が使っている建築材料、屋根の種類、何階建てなのかという3点が記載されています。
床面積
各階それぞれの面積です。
もし、主要な建物と一緒に使うために存在している建造物(物置や車庫など)がある場合は「附属建物」の欄に記載します。
原則としてひとつの建物に対してひとつの登記簿が作られますが、この「付属建物」は別です。しかし、この「付属建物」についても土地のときと同様に、記載されている構造や床面積といった数値が現状と異なっている可能性があることは理解した上で、事前調査を綿密にするなどの対策を講じるようにしましょう。
権利部(甲区)
最初に表題登記を行ったときから現在に至るまで、いつ、誰から誰に所有権が移転していったのかが記録されている箇所です。この権利部(甲区)には売買による所有権の移転だけでなく、相続や贈与、競売や差押え、仮登記、そして買戻特約といった内容もしっかりと記録されています。
もし差押えや仮登記などの記録がある不動産を購入しようとしている場合は要注意です。次に解説する権利部(乙区)の内容をしっかり確認するようにしましょう。
権利部(乙区)
ここは先ほどの権利部(甲区)で記したような所有権以外の権利について記載がされています。先ほど注意しないといけないとお伝えしましたが、この権利部(乙区)には、抵当権や根抵当権など、不動産の担保権に関して記載されていることがあるためです。
その理由は、この不動産が担保としてどれくらいの金額を借り入れて抵当に入ったのかといったことまではわかるのですが、その借り入れがその不動産を購入するための住宅ローンなのか、その他の理由なのかが判断できないという特性があるからです。その上、そうして借り入れた負債が現在どれくらい返済されていくら残っているのかの記載がありません。こうした内容は登記簿謄本だけでは判断できないのです。
もしこの状態でしかるべき対応を取らずに不動産を購入してしまった場合、後になって抵当権を行使されて立ち退きを命じられる可能性があります。そうならないためにも、もし権利部に特筆すべき内容の記載がある不動産を購入しようとしている場合は、しっかりと調査して相応の対策を講じておくようにしましょう。
登記簿謄本(登記事項証明書)の3つの交付請求方法
登記簿謄本は、定められた申請と手数料を支払えば誰でも取得・閲覧することができます。
ここでは登記簿謄本の3つの交付請求方法を解説します。
法務局で請求する
最も多くの人は、法務局の窓口で交付請求します。これは法務局や法務局の出張所、支局など、全国各地の窓口で申請用紙に記入して交付請求するやり方です。
昔は管轄地域の法務局でしか取得、閲覧はできませんでしたが、今は全国の法務局で申請可能となりました。登記簿謄本がデータ化されたことにより、情報を全国で管理できるようになったためです。そのおかげで、管轄関係なく場所を問わずに取得や閲覧ができるようになりました。
まずは窓口へ行き、所定の申請用紙に記入して提出し、手数料を支払います。開庁時間は午前8時30分~午後5時15分です。
窓口で交付請求する際は、閉庁ギリギリではなく時間に余裕を持ち、早目に行くことをおすすめします。
登記簿謄本・登記事項証明書の交付申請の手順
交付請求は、法務局や出張所、支局の窓口に置いてある「登記事項証明書交付申請書」に必要事項を書いて1通あたり600円の収入印紙を貼り提出します。
郵送で請求する
郵送での交付請求も可能となります。窓口へ行く時間がない場合や、遠方に住んでいる場合は、便利な郵送で交付請求しましょう。郵便の交付請求も、法務局窓口でするのと大して変わりません。書類を提出し手数料を支払うことで、郵送で受け取ることが可能です。
登記簿謄本・登記事項証明書を郵送で受け取る手順
まずは法務局のホームページから「登記事項証明書等の交付請求書の様式」をプリントアウトしましょう。その書類に必要事項を記入し、登記簿謄本1通につき600円かかる手数料を、必要な枚数分の収入印紙を貼り、返信用封筒を同封して最寄りの法務局に郵送します。返信は約1週間です。返信用封筒にも切手を貼ることを忘れないようにしましょう。
オンライン交付請求(オンライン登記事項証明書請求)
登記簿謄本は、オンラインでの交付請求も可能です。
登記・供託オンラインシステムの利用手順
オンラインの申請は、まずインターネットのWebブラウザから「登記・供託オンラインシステム」にアクセスします。初めてのオンラインの交付請求は、申請者自身の情報を登録する必要があります。住所・氏名・電話番号・メールアドレスなどの必要情報を入力しましょう。
登録の後に、登記簿謄本の交付請求に進うことができます。
手続分類の「不動産」の右側にある、手続名「登記事項/地図・図面証明書交付請求書」をクリックし、表示の必要事項を入力すると登記簿謄本が取得できます。
オンラインによる手数料の支払いは、インターネットバンキングかPay-easyのどちらかを選択します。
オンラインによる交付請求の一番のメリットは、夜9時まで申請可能なことです。通常の窓口は午前8時30分~午後5時15分しか開いていないやめ、仕事などで間に合わない人もいると思いますが、オンラインは午後9時までの交付請求で、翌日もしくは翌々日には郵送で登記簿謄本が送られてきます。早く届くのでオンライン交付請求も便利な申請方法です。
しかも受取り先を自宅・勤務先・最寄りの法務局や、市役所庁舎内の法務局証明サービスセンター窓口、など複数の受け取り方法を選ぶことができます。
ちなみにオンライン登記事項証明書請求では、会社の謄本も取得可能です。身分証明書の代わりにこのような証明書を発行して使用することもあるため、こうした請求方法は覚えておいた方がいいでしょう。
交付申請書へ必要項目を記載
法務局に直接出向き、登記簿謄本(登記事項証明書)を得るために「登記事項証明書交付申請書」に必要事項を記入して提出しましょう。この書類はインターネットからダウンロードすることも可能です。
申請書の提出には、身分証の提示や押印は必要ありません。
ここからは実際の交付申請書とともに、記入する項目毎にその書き方を解説します。
氏名・住所
申請者の氏名、住所を記載します。
種別、群・市・区、町・村、丁目・大字・字
種別は申請する土地、もしくは建物のどちらかにレ点を付けます。
登記事項証明書が必要な建物や、土地の住所を書きます。
地番
地番とは、法務局が全ての土地に付けている数字のことです。これは住所とは違うため注意しましょう。また地番は住所の「▲丁目■番」の「■番」に該当することもありますが、必ずしもそうではないため確認することが必要です。
家屋番号
家屋番号も、地番と同様に法務局が付けた番号のことです。特にマンションは、家屋番号がないと対象の不動産を特定することができません。
請求通数
必要な登記事項証明書の枚数を書きましょう。
財団・船舶・その他
この項目に関しては、土地や建物の場合は、ほぼ記入する必要はありません。
共同担保目録の有無
これは抵当権に関わる項目です。「共同担保目録の有無」にチェックすると共同担保目録も取得可能となります。
必要な登記事項証明書をチェックする
マンションの登記事項証明書が欲しい場合は「専有部分の登記事項証明書・抄本」や「一部事項証明書・抄本」をチェックすれば問題ありません。
地番・家屋番号・所有者の調べ方
次に、請求に必要な地番・家屋番号・所有者の調べ方について解説していきます。
地番
地番の調べ方を3つ解説します。
法務局に電話して教えてもらう
昔は法務局に電話しても地番を調べてもらうことは出来ませんでした。しかし現在では、電話での問い合わせも可能となりました。
電話する場合は管轄の法務局の公式HPを確認し、地番・家屋番号の照会・各種証明書等の発行への問合せ用の番号があるか見てみましょう。
ブルーマップを使用
ブルーマップとは、一般に販売されている地図ではなく、住所から地番が分かるよう記載された地図帳のことです。
これは住所地図に、登記所の公図を重ねて作成された地図となり、地番は青で書かれています。それによりブルーマップという名称となりました。
ブルーマップは国立図書館や、法務局に管轄地域のブルーマップがあります。またブルーマップをインターネット上で閲覧可能としたサービスを提供する企業もあります。インターネットで検索してることをおすすめします。
路線価図から調査する
また国税庁が公表した路線価図を使って確認することも可能です。これは公式サイトに公表している路線価図から確認場所を検索し、その近辺に地番情報が記載があるかを確認する方法です。
家屋番号
家屋番号の調べ方を見ていきましょう。
登記情報提供サービスを使う
一般社団法人民事法務局協会が運営する「登記情報提供サービス」を使って検索することができます。この際に、検索物件の地番が必要となります。
権利書
建物や土地の権利証を見れば、家屋番号が記載されています。
固定資産税納税通知書
「固定資産税納税通知書」がある場合は、課税明細欄を見ると記載があります。
市区町村役場の税務課で確認する
市区町村役場の固定資産税の担当部署で「固定資産税評価証明書」「固定資産税の名寄帳」を取得し家屋番号を確認することができます。
管轄する法務局の登記所に電話で問い合わせる
確認したい建物や土地の管轄する登記所に電話で問い合わせれば調べてもらえます。
所有者が分からない場合
土地の所有者が分からない場合も、管轄の法務局で確認しましょう。もしも分からない場合は、日常的に所有者を確認している不動産業者にお願いしてみるのも一つの手です。
よくある疑問
ここまで、登記簿謄本(登記事項証明書)の概要や見方、申請方法について解説しました。本章では、登記簿謄本に関するよくある疑問について見ていきたいと思います。
登記簿の閲覧・取得にはどのくらいの費用が掛かる?
まず最初に、実際の費用はいくらになるのかについてご紹介します。以下の表をご覧ください。
| 区分 | 方法 | 1通あたりの費用 |
|---|---|---|
| 取得 | 窓口 | 600円 |
| 郵送 | 600円 + 送料(174〜232円) | |
| オンライン請求/郵送受取り | 500円 | |
| オンライン請求/窓口受取り | 480円 | |
| 登記事項要約書の取得 | 450円 | |
| 閲覧 | オンライン閲覧 | 335円 ※個人利用の場合のみ、別途登録料300円が必要 |
このように取得手数料がかかりますが、ページ数の多い「全部事項証明書」でも、ページ数の少ない「現在事項証明書」でも、いずれの場合も1通50枚までは同一の手数料で取得可能です。そのため、誤った証明書を請求したがために再度請求するリスクを冒すくらいであれば、最初から「全部事項証明書」を請求しておく方が安全と言えるでしょう。
登記簿の閲覧履歴は残るのか
上記で解説した通り、請求時に個人情報を入力するとはいえ、全ての不動産の登記簿を誰でも閲覧することができるので、閲覧した履歴が相手に分かってしまうのではないかという不安があるかと思います。しかし閲覧履歴の情報が分かることはありません。これは逆も然りで、あなた自身所有の不動産の登記簿を、仮に知らない誰かが閲覧したとしても、その閲覧者の存在や正体を知ることはできないのです。
閲覧や取得にあたって、本人確認はされないのか?
なんと登記簿謄本(登記事項証明書)の閲覧・取得にあたっては、申請者の本人確認すら必要ありません。先ほど、きちんと登記されている不動産なら全国どの物件でも、誰でも登記簿の閲覧や取得が可能であることは解説しましたが、まさに文字通り「誰でも」取得が可能となっているのです。
尚、取得にあたっては、事前に対象不動産の情報を整理しておくことをお勧めします。マンションの謄本を取得する場合は不動産の地番と家屋番号が必要となるので、事前に管轄の法務局に電話して教えてもらうようにしましょう。
また戸建の場合は、地番と地図を照らし合わせて対象の建物を探し、建物の家屋番号を取得してからでないと、謄本をもらうことはできませんので、こちらも事前に調べておくようにしましょう。
まとめ
本記事では、登記簿謄本(登記事項証明書)について、その全体像や申請方法、よくある疑問について解説しました。聞き慣れない言葉があると、必要以上に難しく考えてしまいますが、一つひとつを理解するとそこまで難しいわけではないことがお分かりいただけたのではないでしょうか。
もし、どうしても難しいと感じたり、自信がない時には、信頼できる不動産業者に相談してみましょう。日常的に登記簿謄本を利用する業者であれば、取得の力になってくれるはずです。
登記に限らず、不動産投資に関してご不明な点がございましたら、是非お気軽に当社コンサルタントまでお問合せください。