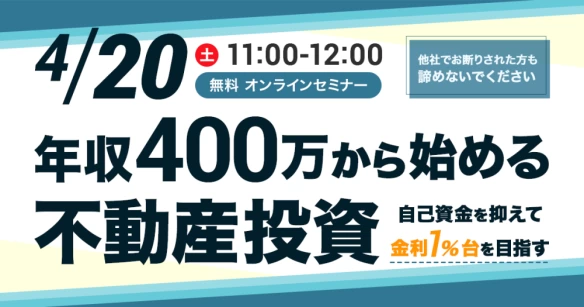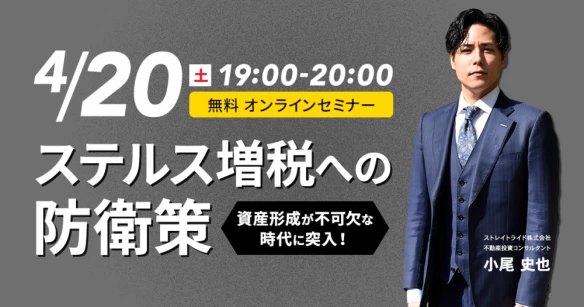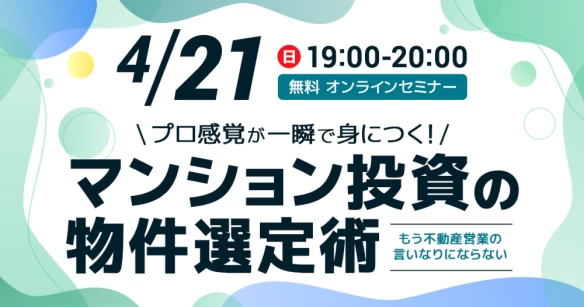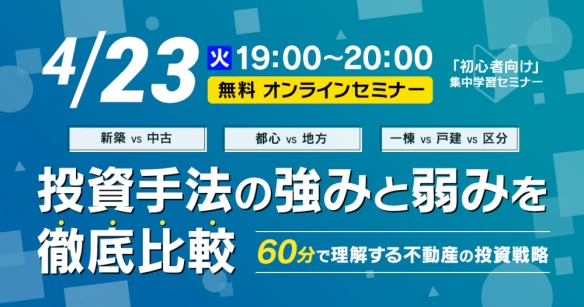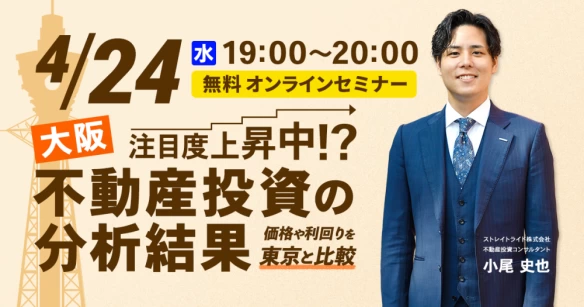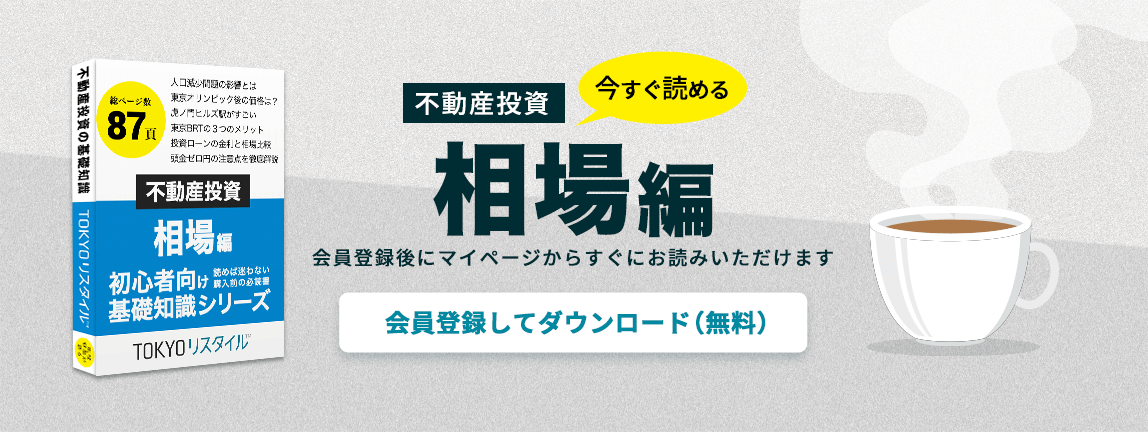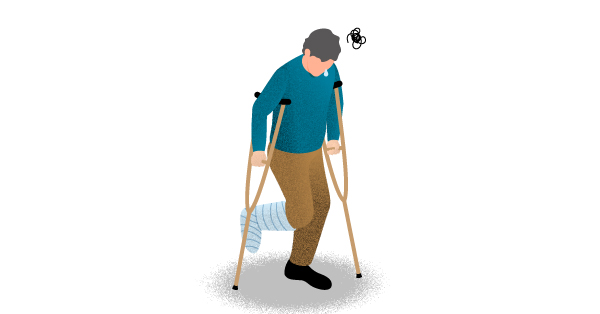ソフトバンクGが「アーム」社の米IPOを進行中!これまでの経緯と今後の動向を解説
- 更新:
- 2023/07/12

全世界の携帯電話に使われる半導体の、99%以上のシェアを誇っている「アーム」社。アーム社の全株式を所有するSB(ソフトバンク)グループの孫代表は、アーム社のアメリカ市場へのIPOを計画しています。
2022年に「NVIDIA」社へのアーム社売却計画が失敗して以降、かねてからIPO計画は進められていましたが、ついにその動きが本格化し始めました。
今回はこの「アーム社」に着目し、アーム社とはどんな企業なのか、これまでどのような経緯をたどり、今回の米IPO計画に至ったのか見ていきましょう。
アーム社とは?
アーム社(Armホールディングス)は、イギリスのケンブリッジに本社機能を置いた半導体メーカーです。1990年に設立し、一時はイギリスの上場企業にもなりました。現在ではイギリス上場を廃止し、日本のSB(ソフトバンク)グループの傘下企業となっています。
まずはアーム社の主要な特徴について見ていきましょう。
ほとんどの携帯電話メーカーに採用されるCPUを設計
2023年現在、アーム社が設計開発した「ARMアーキテクチャ」をベースとしたCPUは、ほとんどの携帯電話メーカーに採用されています。Apple、ファーウェイといったiOS・Android市場を席巻する2社に採用されているというだけでも、どれだけのシェア率があるか見当がつくのではないでしょうか。実データはありませんが、99%以上のシェアがアーム社といわれています。
最近では、ゲーム業界を賑わせる「Nintendo Switch」や、無線LANを中心としたネットワーク機器にも採用。さらには2023年1月、Appleの「Macbook」への搭載もスタートし、ついに業界トップのインテルに迫る勢いです。今後も家電・自動車・PCなどあらゆる分野に採用されていくでしょう。
自社でCPUの製造はしていない
アーム社が同業他社と根本的に異なるのが「自社でCPUの製造をしていない」という点です。アーム社ではあくまで設計開発と、ライセンス提供のみを行っています。
かつてアーム社で営業戦略責任者を務めていたアントニオ・J・ヴィアナ氏は、2013年の「なぜアームは自社で半導体の開発・製造をしないのか」という某社記者の取材に対して、下記の3つの理由を語りました。
- アームは顧客ニーズに対し、迅速かつ小回り良く対応する任務がある
- 半導体ファンドリー最大手「台湾TSMC」とパートナー関係を構築している
- ニーズを満たすためには製造工場よりも「人材」に投資をする必要がある
アーム社が目指しているのは、あくまで顧客ニーズを押さえた設計と開発です。製造については最大手ファンドリー「台湾TSMC」とのパートナー関係を構築しています。そのため、あくまで「自社で製造工程を持つ必要はない」という姿勢を貫いているのです。
2016年にSBグループにより買収される
当時すでに業界を席巻しつつあったアーム社ですが、2016年9月5日にSBグループにより買収されました。買収金額は約3兆3,000億円となっており、これはかつてソフトバンクが行ってきた「ボーダフォン日本法人」の1兆7,820億円、「スプリント・コーポレーション」の1兆8,000億円の2つの大規模買収をも上回っています。
アーム社の立ち位置は、自社製造こそしていないものの「半導体メーカー」です。買収の発表がなされた当時は、「なぜソフトバンクが多額の投資をして半導体メーカーを買うのか?」という疑問も飛び交いました。
SBグループがアーム社を買収した理由
先ほど解説したようにSBグループは2016年、3兆3,000億円を出してアーム社を買収しました。ここまでの巨額の投資をして、SBグループがARMを買収した理由とはなんだったのでしょうか。その理由を紐解いていきます。
最大の理由は「パラダイムシフトへの先行投資」
SBグループの孫代表が語った、アーム社を買収した最大の理由は「パラダイムシフトへの先行投資」です。パラダイムシフトとは、その時代や分野において「常識」とされていた認識が革命的に覆されることを指します。代表的なパラダイムシフトの例は、スマートフォンの普及によるコミュニケーションや情報収集方法の変化でしょう。
孫代表は、「SBグループのもつインターネット系のインフラと、アームのチップ設計技術がシナジーを生み、新たなパラダイムシフトを生むのでは?」と推測していたのです。とはいえ、孫代表は買収時点で具体的なビジネスモデルを策定していたわけではありませんでした。
SBグループは過去にも「ボーダフォン」社を買収し、大きな成果を挙げています。ボーダフォン社のもつ携帯電話産業は「もうすでに成熟しきっている」と言われていたため、当時このボーダフォン社の買収は「意図不明な暴挙だ」とすら騒がれました。これに対して、孫代表はこのように語っています。
「私は成熟した携帯電話の世界に投資するつもりはまったくない。これからやってくる、携帯がモバイルインターネットになる、その入り口に投資をするんだ」
過去に行ってきたSBグループの大規模買収は、すべて「投資」が最大の目的。アーム社の買収も、将来的なパラダイムシフトによる利益の最大化を見込んだものだったのでしょう。
「シンギュラリティの時代が来る」という孫氏の確信があった
孫代表は、「シンギュラリティの時代が来る」という確信をもって事業に臨んでいます。シンギュラリティとは、AIが人知を超える転換点のことです。具体的なビジネスモデルがないとは言えど、「アームの微細なチップに記録されたビッグデータが、あらゆるAIを動かすようになる」という確信をもっていました。
孫代表は19歳の頃に、サイエンスマガジンに掲載されていたチップの拡大写真を見た時から、「シンギュラリティの時代到来」を確信していたと語っています。そしてこの2016年のタイミングで、シンギュラリティの最大の鍵を握るのは「アーム社」だと確信し買収を決断したのです。
あくまで中立的立場でイノベーションに投資する
半導体設計を行うアーム社と、携帯電話・インターネット産業をメイン事業としているSBグループには、直接的な競合要素はありませんでした。それゆえに、世間から「なぜ半導体メーカーを買収するのか」といった意見が出たのも分かります。
あくまでSBグループが目指したのは、「共通のビジョンを持ち、中立的な立場で資金投資を行い、グローバル規模の成長に期待する」ことです。直接的にアーム社の事業には関わらないものの、常に資金投入を進めていく。そしていずれはアーム社がイノベーションを起こし、最大規模の利益をSBグループにもたらすというのが狙いだったのでしょう。
過去には米NVIDIAへの売却が検討された
アーム社によるパラダイムシフトを確信していたSBグループですが、2020年2月にはアーム社の全株式をアメリカの最大手半導体メーカーである「NVIDIA」社に売却すると発表。2016年には前向きにアーム社買収の思惑を語っていただけに、世間からは「アーム社の買収もやはり投資活動の一部でしかなかったのか」という落胆の声も上がりました。
しかし2022年2月に、このNVIDIAへの売却活動を断念すると発表しています。またも世間から「なぜ?」という声が上がりました。売却活動を断念した理由や、SBグループのアーム社に関するその後の動向を見ていきましょう。
独禁法への抵触を主な理由に断念
売却断念の主な理由は、独占禁止法へ抵触するリスクの発生です。すでに半導体業界最大手であったNVIDIAが、各社に設計したチップのライセンスを販売していたアーム社の事業を買収することには、同業他社が半導体事業へ参入できない環境を作ってしまい、業界の成長をストップさせてしまうリスクがありました。
2021年12月2日には、米国連邦取引委員会(FTC)が「エヌビディアによるアームの買収差止めのために審判開始申立て」を行い、買収を差止める流れが加速しました。独禁法のほかにもさまざまな規制に抵触する恐れがあったため、最終的にSBグループはアーム社の売却をストップせざるを得なかったのです。
参考公正取引委員会
手付金12.5億ドルはSBグループの利益に
最終的に売却は失敗に終わったものの、手付金となる12.5億ドル(約1,448億円)は、NVIDIA社からSBグループへ支払われています。代わりに、NVIDIA社はアームの20年間にわたるライセンス利用権を取得しました。
一見SBグループが得をしているようにも見えますが、20年間のライセンス利用権による影響は大きく、トータルで見ると損をした可能性があるともいわれています。
SBグループは手放せなかったアームの米IPOを狙う
SBグループは、手放すことができなかったアーム社の米IPO(上場)を狙っています。そもそもNVIDIAへの売却を決断する際には、「IPOするか、売却するか」の2択から検討していました。
NVIDIAの売却に失敗したことで、SBグループはアーム社の米IPOを狙った動きを加速しています。「むしろ、NVIDIAへの売却ではなくこのIPOが本来のプランだった」と、孫代表が強気な一面を見せる場面も。このIPO計画について、もう少し詳しく見ていきましょう。
SBグループのアーム米IPO計画とは
先述したように、SBグループは売却できなかったアーム社の米IPOを狙って活動中です。アーム社のIPOが実現すれば、アメリカ直近10年で最大規模の株式公開になるとして注目を集めています。SBグループのアーム社米IPO計画について、目標や今後の予定を見ていきましょう。
IPOで80億ドルの資金調達が目標
SBグループは今回のアーム社米IPOで、最低でも80億ドル(約1兆円)の資金調達を目標にしています。アーム社の価値は約370億ドルと評価されており、実際の評価額がこれを超過した分が資金調達額となる見込みです。
評価額は300億ドル~700億ドル
評価額のレンジは、昨今半導体関連の株価が不安定となっている影響でなかなか定まりません。評価額は300億ドル~700億ドルとする案が各バンカーから提示されています。アーム社およびSBグループは500億ドル以上の評価額を望んでいますが、実際のところは「市場の動向次第」な部分が大きいでしょう。
2023年4月にIPO申請、同年後半に株式公開を計画中
アーム社は2023年4月下旬に、IPO申請を非公開で行う見込みです。具体的な時期はまだ判明しておらず、市場動向を見て正確に判断するとされています。
同年2023年後半には株式公開がスタートできるよう計画を進めており、全世界の投資家からも注目を集めています。直近1月には、Apple社が「MacBook」にアーム社のCPUを搭載したこともあり、今後はPC市場を席巻するという期待も。今後の動向から目が離せません。
米市場での上場は日本より圧倒的に基準が高い
アメリカ市場でのIPOは、日本よりも圧倒的に基準が高いといわれています。今回アーム社が狙っているIPOはどのようなものなのか、詳しく見ていきましょう。
米市場で上場するための条件とは
アメリカの主な株式市場は「ニューヨーク証券取引所」(NYSE)と「ナスダック」(NASDAQ)の2つです。NYSEには老舗企業、ナスダックにはIT企業が上場する傾向がありますが、最近ではその線引きは曖昧になっています。
2つの市場の中でも世界1位の時価総額を誇る「NYSE」と、日本の「東京証券取引所」の上場条件をいくつか比較してみました。例えば株主数をみると、NYSEは2,000人以上、東京証券取引所は150人以上が上場条件です。また流通株式数は、NYSEが110万株以上、東京証券取引所は1,000株以上となっており、圧倒的な差があることが分かるでしょう。
このようにアメリカと日本では、根本的に上場時の規模感が異なります。その中でも最大規模と騒がれているアーム社の上場は、世間にどれだけの影響を与えるか計り知れません。これが、アーム社の上場が騒がれる理由のひとつです。
これまでの日本企業の米市場上場例
これまでに日本企業も、いくつかアメリカ市場への上場を果たしています。日本企業で初めて「NYSE」に上場したのは、1970年のソニー社です。ソニーはNYSE上場により多額の資金調達に成功し、事業成長し現在も名を轟かせています。
2番目に上場したのは、1971年のパナソニック社でした。ソニー社と同様、現在も日本国内で良く名を聞く大手メーカーではありますが、こちらは2013年に上場を廃止しています。とはいえパナソニックは「上場の目的は果たした」としており、ネガティブな廃止ではありません。
最近ではメディロム、吉通貿易などの企業が「NASDAQ」に上場しました。昨今NASDAQの担当者が日本のファンドへ積極的に営業しているという話題も上がっており、今後スタートアップも含め日本企業がNASDAQ上場を目指す動きが加速する可能性が示唆されています。
まとめ
SBグループが「パラダイムシフトへの先行投資」を理由にアーム社を買収してから7年。NVIDIAへの売却が一度は検討されたものの、売却断念によりアーム社のIPO計画が加速しています。
2023年度中には、IPO申請と株式公開が一挙に行われる予定です。評価額のレンジもまだ定まらず、全世界の投資家が動きに注目しています。今後の半導体産業発展の目線からも、アーム社の成長に期待が高まるばかりです。

この記事の執筆: 及川颯
プロフィール:不動産・副業・IT・買取など、幅広いジャンルを得意とする専業Webライター。大谷翔平と同じ岩手県奥州市出身。累計900本以上の執筆実績を誇り、大手クラウドソーシングサイトでは契約金額で個人ライターTOPを記録するなど、著しい活躍を見せる大人気ライター。元IT企業の営業マンという経歴から来るユーザー目線の執筆力と、綿密なリサーチ力に定評がある。保有資格はMOS Specialist、ビジネス英語検定など。
ブログ等:はやてのブログ