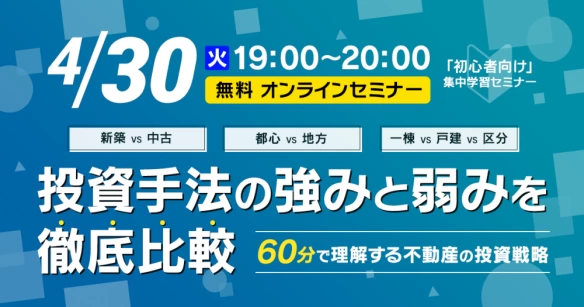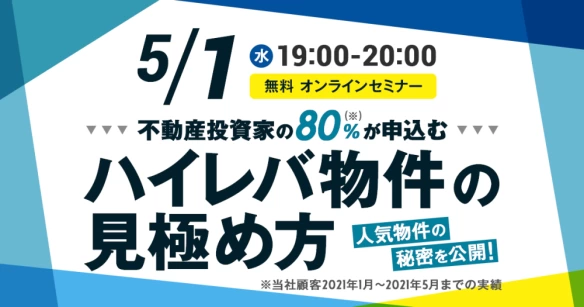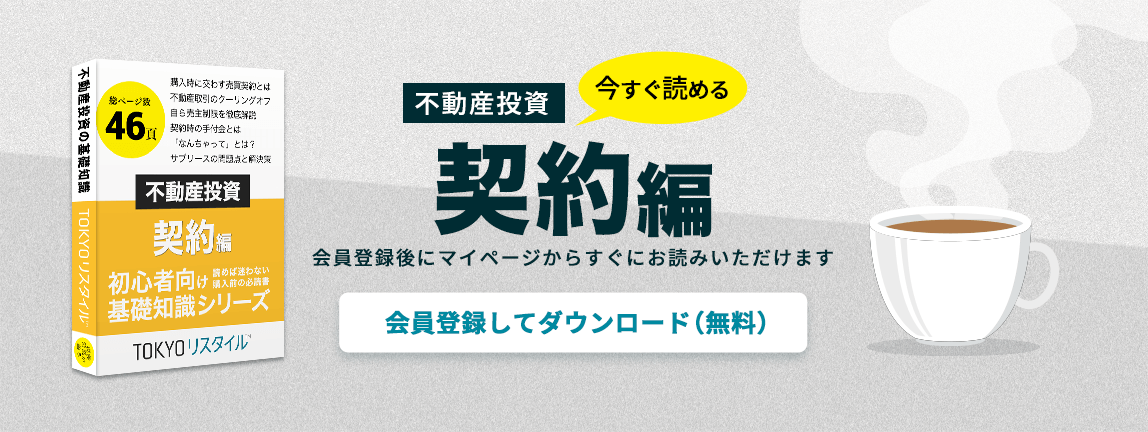悪徳リフォーム営業に注意!迷惑な訪問販売の5つの手口と6つの対策を徹底解説
- 更新:
- 2023/06/19

「訪問販売は消費者トラブルの温床」というイメージをお持ちの方が多いのではないでしょうか。特に迷惑な悪徳リフォーム業者による訪問販売の被害は年々増えています。手口も巧妙化しており、具体的な事例や対策を知っておかないと、いつか被害に遭ってしまうかもしれません。
今回は不動産業者である当社の目線から、リフォーム業界にはびこる悪徳業者の5つの手口について徹底解説します。具体的な6つの対策や万が一契約してしまった場合のアクションについても解説するので、この記事を読めば悪徳リフォーム業者に関するトラブルを回避できるようになるでしょう。
悪徳リフォーム業者は増えている!
悪徳リフォーム業者はなかなか減らず、むしろ増え続ける傾向にあります。まずは相談件数の推移や、悪徳リフォーム業者が減らない原因について詳しく見てみましょう。
悪徳リフォーム営業の相談件数推移
国民生活センターによると、悪徳リフォーム業者に関する相談件数は年々増えています。2019年 ~ 2022年の「訪問販売」と「点検商法(無料点検を装って高額請求をする商法)」の相談件数推移は下記のとおりです。
| 項目/年度 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022中期 |
|---|---|---|---|---|
| 訪問販売 | 8,007 | 8,785 | 9,753 | 6,745(前年同期6,779) |
| 点検商法 | 5,760 | 7,024 | 7,431 | 5,324(前年同期5,169) |
参考国民生活センター「訪問販売によるリフォーム工事・点検商法」
2019年には約8,000件だった訪問販売の相談件数は、2021年時点で10,000件近くまで増加しました。2022年の本統計作成段階でも、2021年の同時期とほぼ同等の件数となっています。そして、訪問販売よりも増加傾向にあるのが点検商法です。2022年の最終的な点検商法の相談件数は、ほぼ間違いなく前年を超えてくるでしょう。
なぜ悪徳リフォーム業者は減らない?
悪徳リフォーム業者が減らない原因は、主に下記の3つといわれています。
- 建設業許可がいらない
- 素人にはリフォームの必要・不要が分かりにくい
- 給料が歩合制のケースが多い
最大の原因といわれているのが「建設業許可がなくてもリフォーム工事ができる」点。実は1件あたり税込500万円未満の工事は、建設業許可どころか資格・免許すらなくても契約できます。そのため「とりあえず理由をつけて工事をむりやり契約し、後は適当に施行する」という悪徳業者が後を絶ちません。営業トークで「シロアリがいる」「瓦が壊れそう」などと伝えた際、素人目では本当にそうなのか確認できないのも原因のひとつです。
さらに悪徳リフォーム業者の多くは、歩合制の給与体系を採用しています。つまり、とにかく工事の件数を取れば、営業マン本人に入る給料が増えるというわけです。ギリギリ法に触れない範囲で営業マンは高額な給料がもらえて、会社もしっかり儲かる構図が成立しているのが、悪徳リフォーム業者がはびこる原因といえるでしょう。
悪徳リフォーム営業の手口
悪徳リフォーム業者は、主に下記5つの手口でお金を取ろうとしてきます。
- 無料点検を装って高額請求をする
- 設備を壊して自作自演する
- 口約束で勝手に工事を始め、後から法外な高額費用を請求する
- 「保険金がおりるからタダでリフォームできる」と言ってくる
- 工事費用を支払ったとたんに音信不通になる
手口を押さえておけば、実際に怪しい営業マンが来た際に契約してしまう心配はありません。ぜひ事例とあわせてチェックしておきましょう。
手口①:無料点検を装って高額請求をする
よくある問題
自宅に「住宅を無料点検している」という業者が来た。無料ならと思ってお願いしたところ「屋根の瓦が壊れている」と言われたが、もらった見積もり金額が異常に高い気がする…
「悪徳リフォーム営業の相談件数推移」でも触れたように、非常に多いのが無料点検を装って高額請求をする「点検商法」です。「無料で設備を点検して回っています」といって、家に上がり下記のような箇所をチェックしようとします。
- 床下
- 屋根
- 浄水器
- 給湯器
- 換気扇
チェックした後「シロアリがいる」「漏電しているから部品を交換しないと火事になる」などと脅し、設備の交換や修理を強引に勧めてきます。より悪質な業者は「点検したら壊れていたので直しました。部品代をください。」と強引に請求してくるケースもあるので注意が必要です。
また水道局や消防署、自治体の人など公務員になりすまして点検に来るケースもあります。公務員が訪問営業をするのはあり得ませんが、それを知らずに「公務員なら大丈夫」と安心して家に上げてしまう人が少なくありません。
手口②:設備を壊して自作自演する
よくある問題
近所の家の屋根を工事していたという業者が「お宅の屋根に違和感があるから、登って見てみましょうか」と言ってきた。お願いしたところ、壊れた屋根の写真を撮って帰ってきた。修理を打診されたが一度帰ってもらい、家族や友人に相談したところ「これはわざと壊されている」と言われてしまった。
最悪のパターンが、設備を壊して自作自演をしてくる手口です。無料点検やリフォームの見積もりを理由に家に入り、バレにくい浄水器や給湯器、屋根などを壊して修理費用を請求してきます。床下にシロアリの卵を置いていくとんでもないケースも。当然器物損壊罪などの犯罪行為にあたりますが、証拠を確保するのが難しい・そもそも住人が気付かないためになかなか立件には至りません。
手口③:口約束で勝手に工事を始め、後から法外な高額費用を請求する
よくある問題
飛び込みのリフォーム業者と契約して施工してもらったが、事前に口頭で聞いていた金額より請求額が大幅に高かった。
口約束で勝手に工事をスタートし、後から事前に伝えていない法外な高額費用を請求してくる手口も少なくありません。この手口には、下記3つの特徴があります。
- 絶対に見積書を出さない
- 契約書を締結する気がない
- 部材・設備ごとの金額を教えてくれない
見積書や契約書などを残してしまうと後から高い金額を請求できないため、絶対に書類を発行しようとしません。また明細の概念がないため、部材・設備ごとの金額も教えてもらえないケースがほとんどです。
手口④:「保険金がおりるからタダでリフォームできる」と言ってくる
よくある問題
「お宅の家の壁にヒビが入っている。火災保険の保険金を使ってタダでリフォームできるので、やらないか」と言われた。興味はあるが、本当にできるのか、合法なことなのか疑問。
「保険金がおりる」という理由で、無料のリフォームを勧めてくる手口も非常に多いです。確かに保険金を使えば無料でのリフォームは可能ですが、本来保険の適用範囲は自然災害に限ります。自然劣化・経年劣化は保険の適用外となるため、無料で工事をするには保険会社に対して「災害が原因で壊れた」とウソの申告をしなければいけません。
最大の問題は、この保険会社への申告は保険の契約者しか行えないこと。つまり仮に業者が代わりに申請を出したとしても、自分が保険会社にウソをついたことになるので、バレれば後から「保険金詐欺」として立件されてしまう可能性があります。しかし業者はこの保険金の手続きについて無関係なため、ほぼリスクなく高額な工事ができるというわけです。
手口⑤:工事費用を支払ったとたんに音信不通になる
よくある問題
リフォームをお願いしていた業者と連絡がつかなくなった。料金はもう支払ってしまったので取り返したいが、どうすることもできない…
工事費用を支払ったとたんに音信不通になり、施行してもらうこともお金を返してもらうこともできなくなってしまうケースがあります。このケースの大半は「実は提示してきた社員証・名刺がまったくウソのものだった」というもの。存在しない住所・電話番号のため連絡は取れず、名前すら違うため身元もわかりません。防犯カメラにでも映っていない限り特定は難しく、泣き寝入りせざるを得ないのが現状です。
悪徳リフォーム営業の被害を回避する6つの対策
悪徳リフォーム業者の5つの手口を紹介しましたが「これさえ押さえておけばほぼ被害に遭うことはない」といえる下記の6つの対策があるので、ぜひ押さえておきましょう。
- そもそも訪問営業を相手にしない
- アポなしで来る点検業者は無視する
- 書面で相見積もりをとる
- 営業マンの身元・会社の存在を確認する
- その場で絶対に契約しない・作業させない
- 必ず契約書を取り交わす
それぞれ詳しく解説します。
対策①:そもそも訪問営業を相手にしない
そもそも種類を問わず訪問営業を相手にしないのが、悪徳リフォーム業者対策としてもっとも有効な対策です。インターネットが普及した現代では、個人宅への訪問営業はメジャーな方法とはいえません。すべてが悪徳業者というわけではありませんが、そもそも家に来る業者をシャットアウトすれば、被害に遭うリスクはほとんどなくなるでしょう。
対策②:アポなしで来る点検業者は無視する
アポなしで来る電気・ガス・水道などの点検業者は無視しましょう。地域のガス会社などが点検に来る際は、事前に電話などで一度連絡を入れてくるのが当たり前です。アポなしで来た時点で「悪徳業者だ」と判断すれば、無用なトラブルを避けられます。
対策③:書面で相見積もりをとる
書面で相見積もりをとる方法も非常に有効です。悪徳リフォーム業者は後から法外な金額を請求したいと考えているため、とにかく書面で金額を残すのを嫌います。そのため、先手を打って「他からも見積もりを取って比べるので、見積書をください」と伝えればOK。ここで見積書を出してこないようなら、間違いなく悪質業者だといえるので必ず断りましょう。
対策④:営業マンの身元・会社の存在を確認する
必ず来た営業マンの身元や会社の存在を確認しましょう。大手企業や自治体の名をかたり、偽名を使っているケースもあるので、社員証や名刺だけではなく身分証明書を見せてもらうのがポイントです。出すのを渋る場合や社員証・名刺と名前が一致しない場合は、ほぼ確実に悪徳業者のため早々に断るのが無難でしょう。
対策⑤:その場で絶対に契約しない・作業させない
その場では絶対に契約せず、作業もさせないようにしましょう。契約は一度保留にして営業マンを帰らせ、信頼できる別のリフォーム業者に相談してみてください。金額やリフォーム箇所が適切かどうか確認してくれます。また「手口②:設備を壊して自作自演する」で解説したように、見積もりや点検を装い自宅のものを壊されてしまう可能性もあるので、そもそも作業をさせないのがポイントです。
対策⑥:必ず契約書を取り交わす
法外な請求を避けるため、契約時には必ず正式な契約書を取り交わしましょう。本来、リフォームも含めた建設工事では契約書の作成が義務となっています。なお契約書には下記の内容が明記されているか確認してください。
- 着工日・竣工日
- 会社の住所と連絡先
- 工事費用の明細
- 支払い方法・日時
契約書に詳細な記載があれば、万が一法外な金額を請求されても契約書を理由に棄却できます。工期遅れや支払いに関するトラブルも防止できるので、必ず契約書を取り交わしてから工事をスタートさせましょう。
もし悪質リフォーム営業と契約してしまったら?
万が一悪質なリフォーム営業と契約してしまった場合にできることが2つあります。順にチェックしていきましょう。
クーリングオフする
契約書がある場合は契約から8日後まで、ない場合は無期限で「クーリングオフ」の制度を使い、契約そのものを取消できます。
内容証明郵便で、業者の事務所に「解約通知書」を送りましょう。ただし訪問販売で契約したこと、自分から電話・訪問をしていないことが条件です。もし一度保留にして後から業者の事務所等で契約してしまった場合には、クーリングオフを適用できないので注意してください。
住まいるダイヤルや消費生活センターに相談する
「住まいるダイヤル」「消費生活センター」など、悪徳リフォーム業者に関する相談ができる窓口があります。契約してしまった後はもちろん、悪徳リフォーム業者と疑わしい営業マンが来たときの相談も可能です。過去の事例などをもとに適切なアドバイスをしてもらえるので、迷ったら一度相談してみましょう。
| 住まいるダイヤル | 営業時間:平日10:00 ~ 17:00 電話番号:0570-016-100 |
|---|---|
| 消費生活センター | 営業時間:平日10:00 ~ 12:00・13:00 ~ 16:00 電話番号:188(局番なし) |
まとめ
悪徳リフォーム業者による被害は年々増えているので注意が必要です。無料点検を装って高額な請求をしてきたり、口約束での契約をいいことに後から法外な金額の請求に切り替えたりしてきます。
被害に遭わないためには、そもそも訪問営業を相手にしないのが最大の対策となります。家に来る営業を全部断るのに抵抗がある場合は、その場で絶対に契約しない・作業させないのを徹底し、必ず契約書を取り交わしましょう。万が一契約してしまった場合は、クーリングオフ制度での解約や各種窓口への相談を検討してみてください。

この記事の執筆: 及川颯
プロフィール:不動産・副業・IT・買取など、幅広いジャンルを得意とする専業Webライター。大谷翔平と同じ岩手県奥州市出身。累計900本以上の執筆実績を誇り、大手クラウドソーシングサイトでは契約金額で個人ライターTOPを記録するなど、著しい活躍を見せる大人気ライター。元IT企業の営業マンという経歴から来るユーザー目線の執筆力と、綿密なリサーチ力に定評がある。保有資格はMOS Specialist、ビジネス英語検定など。
ブログ等:はやてのブログ