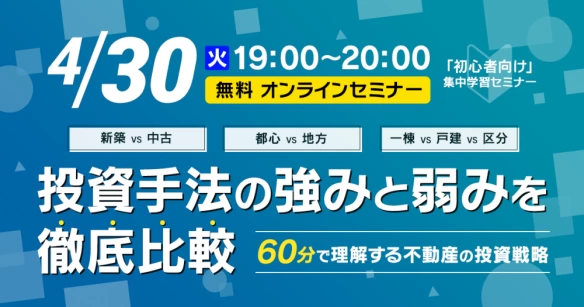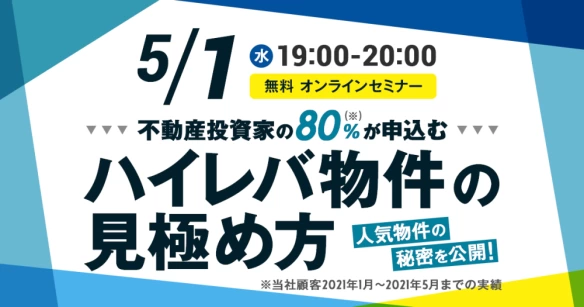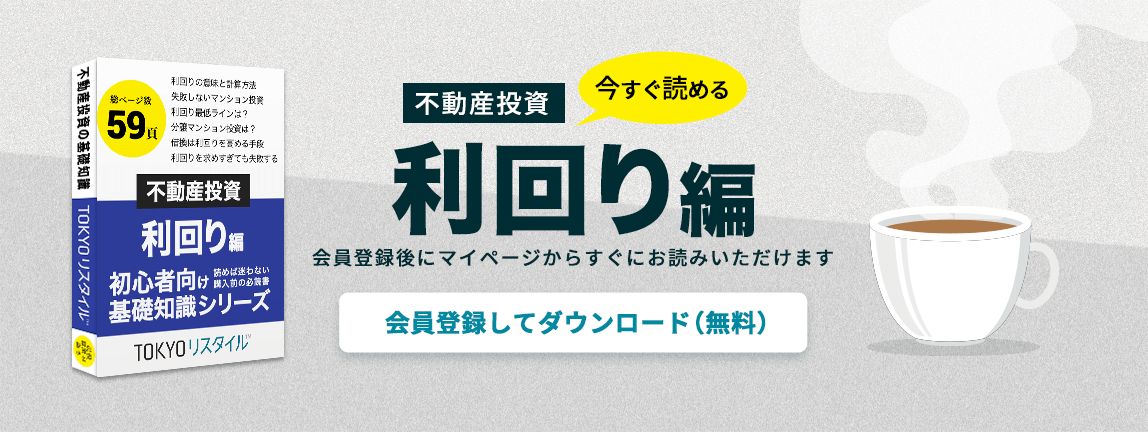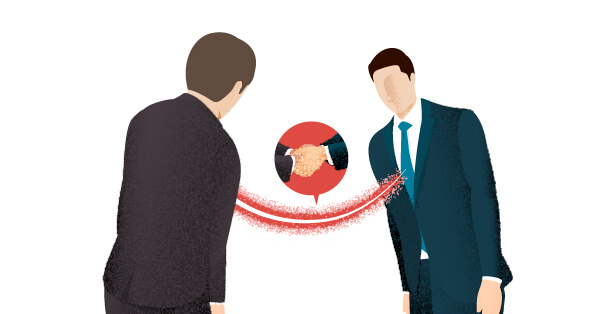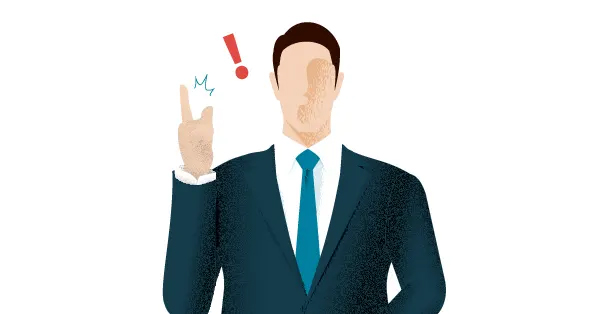不動産の証券化とは?基本的な仕組みや売り手・買い手のメリットとデメリットをわかりやすく解説!
- 更新:
- 2023/06/19

「不動産の証券化ってたまに聞くけど、結局どういう仕組みなのかよく分かっていない」
「証券化不動産に投資するメリットとデメリットは?」
昨今の投資ブームも背景にあり、企業が不動産を証券化すること、投資家が証券化不動産への投資をすることがよりメジャー化してきています。しかしその基本的な仕組みや、証券化不動産へ投資するメリットやデメリット・リスクをまだ把握できていない方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は不動産証券化の仕組みから、売り手・買い手それぞれのメリット・デメリットを詳細に解説します。また「不動産の証券化は難しくて良く分からない」というイメージの原因となってしまっている専門用語についても分かりやすく解説するので、この記事を読めば不動産の証券化の基本をしっかりと理解できるでしょう。
- 目次
- 不動産の証券化とは?
- 不動産の証券化は難しくない!専門用語を分かりやすく解説
- 【売り手側】不動産の証券化によって得られるメリット・デメリット
- 【買い手側】不動産の証券化によって得られるメリット・デメリット
- まとめ
不動産の証券化とは?
不動産の証券化とは、賃料収入を裏付けに有価証券を発行することです。「不動産を担保に証券を発行するため」だけに設立された法人(SPCと呼ぶ)に不動産を売却または信託し、証券を発行します。つまり、証券化によって不動産を金融商品として取引できるようになります。とはいえこれだけ読んでも難解に感じる方が多いと思うので、具体的な仕組みや証券化の目的について詳しく見ていきましょう。
不動産証券化の仕組み
不動産証券化の基本的な仕組みは下記のようになっています。
- SPCが不動産オーナーとして投資家に出資金を募る
- 不動産の所有者(主に企業)がSPCに不動産を売却する
- 家賃収入などを出資金額に応じて投資家に分配する
先述したように、SPCは証券を発行するためだけに設立された法人のため、最初は現金をはじめとした資金を持っていません。しかし投資家から集まった出資金を元手にして、元の所有者(オリジネーター)から不動産を購入することが可能となります。
つまり元の所有者は売却によりリスクのある不動産を手間なく現金資産に変えられ、投資家は小口から投資ができるWin-Winの構図が成立する、という仕組みとなっています。詳しい元の所有者と投資家のメリット・デメリットは、記事の後半で詳しく見ていきましょう。
不動産証券化の目的
不動産証券化の最大の目的は「不動産の流動性リスク」の軽減です。不動産は一般に金額が大きいため、売却先は非常に資金力があり、さらに不動産にニーズのある買い手に限られます。「資金が必要だ」と思ったタイミングで不動産を即時に売却し、資金調達するのは非常に困難でしょう。そのため不動産は流動性が低く、リスクのある資産として位置づけられています。
しかし証券化ができれば「不動産にニーズを感じているが、一件まるごと購入はしたくない」富裕層から「資金力が高くなく、小口資金で投資を始めたい投資家」まで、幅広い層からの資金調達が可能となります。一件まるごと売却を検討しなくても不動産を現金資産化でき、保有し続けるリスクを軽減できるというわけです。
不動産証券化が始まった背景
不動産の証券化そのものが始まったのは、1931年に「抵当証券法」が施行されたタイミングです。しかし、本格的に一般化してきた背景は1991年の「バブル崩壊」にあるといわれています。
バブル崩壊以前は、土地価格をはじめ不動産価格が上昇の一途をたどっており「土地神話」と呼ばれるまでに「不動産を持っている = 安泰」というイメージがありました。しかしバブルの崩壊により倒産する企業が増え、所有していた不動産が「売却できない不良債権」として処理されるケースが増えたのです。
この頃から「不動産はリスクの高い資産」として認識され始め、企業の「なるべく不動産を資産として持たないようにしよう」という意識も高まり始めます。徐々に法整備も進み、1998年にはSPCを設立しての証券化を合法とする「特定目的会社による特定資産の流動化に関する府立(通称SPC法)」も施行されました。昨今では物価高・不景気に伴う「投資ブーム」も到来しており、証券への投資はより身近なものとなるでしょう。
不動産の証券化は難しくない!専門用語を分かりやすく解説
「不動産の証券化がよく分からない」といわれる最大の理由は、その専門用語の多さです。しかし専門用語さえ理解してしまえば、証券化はそこまで難しいものではありません。頻出する下記5つの専門用語について解説します。
- オリジネーター
- SPV(特別目的事業体)
- SPC(特別目的会社)
- アレンジャー
- レンダー
それぞれ見ていきましょう。
オリジネーター
オリジネーターとは、証券化する不動産の元の所有者(= 売り手)を指します。「原所有者」「原債権者」と呼ばれるケースもあるので、あわせて覚えておきましょう。売却検討時に証券化を行うか、どのようなスタイルで証券化が行われるかは、オリジネーターの意向を反映して検討・決定されます。
SPV(特別目的事業体)
SPVとは「Special Purpose Vehicle」の略語で「特別な目的を持った事業体」を指します。証券化における「特別な目的」とは下記の3つです。
- 不動産の所有
- 不動産の運用
- 投資家からの資金調達
なおSPVは、証券化のスタイルによって合同会社や投資信託など、さまざまな形式で設立されます。「不動産証券化の事業全般を担うのがSPV」と覚えておきましょう。
SPC(特別目的会社)
SPCとは「Special Purpose Company」の略語。SPVが「事業体」なのに対し、SPCは実質的に表立って不動産の証券化事業を動かす「特別な目的を持った会社」を指します。SPCには下記3つのスキーム(枠組み)があり、それぞれ特徴が異なります。
| スキームの種別 | 概要 |
|---|---|
| GK-TKスキーム | ・合同会社を設立する場合 ・金融庁への届け出不要で簡単に資金調達できる ・もっとも一般的なスキーム |
| TMKスキーム | ・特定目的会社を設立する場合 ・不動産取得税などの節税効果がある ・取締役や監査役をたてる必要がある ・設立に2ヶ月程度の手続き期間がかかる |
| REITスキーム | ・不動産投資法人を設立する場合 ・投資信託商品として定着している |
もっとも一般的なのは、合同会社を設立する「GK-TKスキーム」です。また普段から積極的に投資活動をしている方は、すでに投資信託商品として定着している「REIT」の購入経験があるかもしれません。
アレンジャー
アレンジャーは証券会社や信託銀行などを指します。不動産の証券化にはさまざまな煩雑化した手続きを伴うため、専門知識が豊富な証券会社や信託銀行に実務を任せるのが一般的です。
レンダー
レンダーとは、SPCに対し不動産の購入資金を融資する機関です。銀行や信用金庫が該当し、利息によって収益を得ています。SPCが投資家からの出資金のみで不動産購入代金をまかないきれない場合、低金利で貸付してくれるレンダーを見つけられるかが運用のカギとなります。
【売り手側】不動産の証券化によって得られるメリット・デメリット
ここからは、売り手(オリジネーター)・買い手それぞれの不動産証券化によって得られるメリット・デメリットを解説します。まずは売り手側のメリット・デメリットを見ていきましょう。
売り手側のメリット
売り手(オリジネーター)側のメリットは下記の3つです。
- リスクの分離ができる
- 海外の投資家に高値で売却できる可能性が高まる
- 自己利用・買戻しも可能
売り手側のメリット①:リスクの分離ができる
先述したようにバブル崩壊以降、不動産は「リスク資産」として認識されています。たとえば法人がSPCを設立し不動産を売却すれば、財務諸表から高額なリスク資産である不動産がなくなるため「リスクの低い経営ができている」として企業価値の向上効果が見込めます。同時に、現物不動産の保持では難しい即時の資金調達が実現可能です。
なお最近では上場企業レベルともなると、証券化によりリスク資産のない経営を目指すのがもはや当たり前となっています。上場企業は会社の資産内容を公開しなければならないため、考えてみれば当然の流れといえるでしょう。
売り手側のメリット②:海外の投資家に高値で売却できる可能性が高まる
不動産の証券化では、国内のみならず海外の投資家からも出資を受けられます。海外の投資家は為替差損益なども考慮したうえで投資を行っているため、為替の動き次第でより高い価格で不動産を売却できる可能性があります。
売り手側のメリット③:自己利用・買戻しも可能
通常とは異なる条件もありますが、不動産の全部ではなく一部のみの証券化も可能なため、残した部分は自己利用できます。発行された証券をすべて買い戻せば、再び自己資産としての不動産活用も可能です。
売り手側のデメリット
売り手(オリジネーター)側のデメリットは下記の2つです。
- 投資対象として魅力がないと証券化が困難
- 手間やコストがかかる
売り手側のデメリット①:投資対象として魅力がないと証券化が困難
投資対象としての魅力が薄い不動産は、投資家の出資も見込めないため証券化が困難です。具体的には、証券化が可能なのは下記のような不動産に限られます。
- 安定的な収益が見込める
- 将来的な値上がりが期待できる立地である
特に地方の不動産などは現状ほとんど証券化されていません。地方都市にある一部の不動産の事例しかなく、国土交通省も地方創生・地域活性化の観点からこの点を問題視しています。しかし、明確な対策がほとんど出てこないのが現状です。
売り手側のデメリット②:手間やコストがかかる
不動産の証券化には煩雑な手続き・申請が必要なため、非常に手間がかかります。先述したように実務的な部分はアレンジャー(証券会社や信託銀行)に任せるケースが多いですが、それにも大きなコストがかかります。不動産の証券化を行えるのは、ある程度人的・金銭的なリソースを割ける企業のみに限られるでしょう。
【買い手側】不動産の証券化によって得られるメリット・デメリット
続いて、買い手(投資家)側のメリット・デメリットを詳しく解説します。
買い手側のメリット
買い手(投資家)側のメリットは下記の2つです。
- 小口資金で不動産投資ができる
- 分散投資がしやすい
買い手側のメリット①:小口資金で不動産投資ができる
通常の不動産投資では、小規模なワンルームマンションの購入であっても数百万円 ~ 数千万円の投資資金が必要です。しかし証券化不動産であれば、5万円程度の小口資金から投資をスタートできます。投資ブームの現代において、手を出しやすい少額から投資が可能なのは大きなメリットといえるでしょう。
買い手側のメリット②:分散投資がしやすい
1つ目のメリットと被る部分もありますが、証券化不動産の場合は小口資金での投資が可能なため、リスク回避ができる分散投資を簡単に実現可能です。一般的な不動産投資では市場の動向や自然災害などの影響で物件の価値が低下する場合があるため、1件だけの保有には大きなリスクを伴います。複数の証券を購入し分散投資をしておけば、万が一の事態が発生しても被害を最小限に食い止められるでしょう。
買い手側のデメリット
買い手(投資家)側のデメリットは下記の2つです。
- 現物不動産より利益が減る可能性がある
- リスクが分かりづらい
買い手側のデメリット①:現物不動産より利益が減る可能性がある
証券化不動産への投資は現物不動産よりも利益が減り、収益性が低くなってしまう可能性があります。これは売り手が証券化を行うのに、多額のコストがかかっているためです。ただし大規模な不動産であればあるほど、不動産価格に対する証券化にかかるコストの割合は小さくなるため、あまり影響は大きくありません。
買い手側のデメリット②:リスクが分かりづらい
証券化不動産へ投資する大きなデメリットとして「リスクの分かりづらさ」が挙げられます。現物不動産への投資は「入居者がいなくなり空室が出たら家賃収入がなくなる」「老朽化で物件価値が下がる」などリスクがある程度明確化しており、それぞれに応じた対策が可能です。
しかし証券化不動産の場合は、何がどうなると資産価値が落ちてしまうのか、リスクとその要因が明確化されていません。分散投資により総合的なリスクを抑えることは可能ですが、本質的な不動産ごとのリスクを捉えて投資をするのは非常に困難といえるでしょう。
まとめ
不動産の証券化とは、賃料収入を裏付けに有価証券を発行すること。SPCと呼ばれる法人に不動産を売却または信託し、証券を発行します。証券化すれば不動産を金融商品として取引することが可能となり、企業の資産価値向上や効率的な資金調達、投資家の小口資金での積極的な投資が実現されます。
証券化不動産への投資は少額投資によるリスク分散が可能なため、投資家にとって魅力的ではありますが、リスクが非常に分かりづらいという欠点があります。現物不動産に投資するより、実ははるかに利回りが低いケースもあり得るでしょう。当社では現物不動産に投資するメリットと考えられるリスクを詳細にお伝えできるので、ぜひ興味のある方は一度お気軽にご相談ください。

この記事の執筆: 及川颯
プロフィール:不動産・副業・IT・買取など、幅広いジャンルを得意とする専業Webライター。大谷翔平と同じ岩手県奥州市出身。累計900本以上の執筆実績を誇り、大手クラウドソーシングサイトでは契約金額で個人ライターTOPを記録するなど、著しい活躍を見せる大人気ライター。元IT企業の営業マンという経歴から来るユーザー目線の執筆力と、綿密なリサーチ力に定評がある。保有資格はMOS Specialist、ビジネス英語検定など。
ブログ等:はやてのブログ