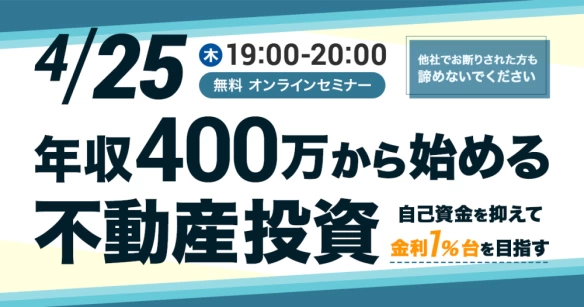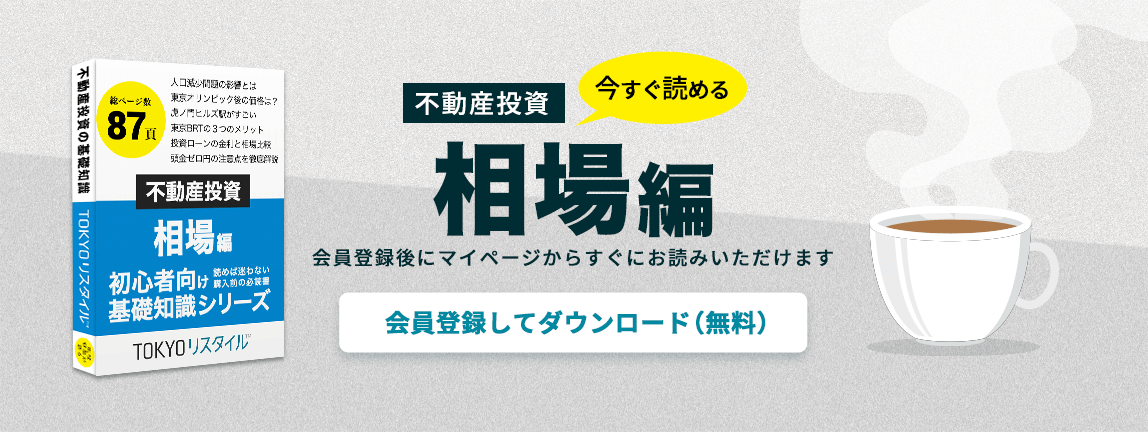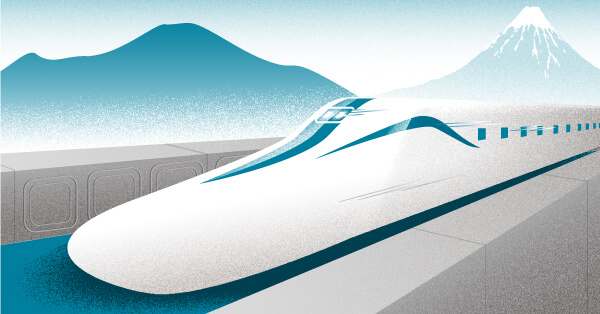不動産大暴落!?生産緑地の期限が切れる2022年問題は本当にやばいのか?
- 更新:
- 2022/11/18

皆さんは、「2022年問題」という言葉を聞いたことがあるでしょうか?この問題は、不動産業界に大きな影響を与える可能性があるとして、様々な方面で懸念の声が挙がっています。
2022年問題、その概要は、「市街化区域内に存在する『生産緑地』の指定の期限が切れることによって、都心部の宅地の供給が大幅に増加し、不動産価格が下落する可能性がある」という内容です。とはいえ、この説明は大変複雑で分かりにくいでしょうし、その裏に隠されている農地を巡る歴史も全く見えてきません。
そこで本記事では、「そもそも生産緑地ってなんなの?」という根本的な疑問も含めて分かりやすく解説するとともに、2022年問題はそれほど懸念すべき問題なのか、という点までお伝えできればと考えています。
生産緑地を巡る歴史とは?
それではまず、2022年問題の要因となっている生産緑地について、その背景を見ていきたいと思います。そもそもの話は、1970年代まで遡ります。
始まりは1970年代から
1970年当時、日本は高度経済成長期の真っ只中にあり、急激な勢いで全国の土地が開発され、ある意味ではアンバランスな程の都市化がなされました。さらにその勢いの中で、1974年に『生産緑地法』が公布され、市街化区域内の農地を宅地に転用するような動きが起こりました。この『生産緑地法』の影響により、市街化区域内の農地の固定資産税が大幅に上がり、結果として宅地にせざるを得ない状況にまで追い込まれたのです。
土地の開発によって都市化が進むのは喜ばしい一方で、人々の中に「もっと農地を保護した方がいいのではないか」「市街地の中にも、緑を保全することは重要だ」という声が高まりました。そういった世論を受けて、1991年3月には上記の生産緑地法が、とうとう改正されることとなったのです。
改正生産緑地法の内容とは?
1991年3月に生産緑地法が改正をされ、市街化区域の農地が大きく2種類に分けられることとなりました。即ち、原則通り宅地化を進める「宅地化農地」と、保全対象となる「生産緑地」です。そして後者の生産緑地では、農地を保護するための施策として、「固定資産税の大幅な緩和」「相続税の納税猶予措置」が適用されることとなったのです。
上記の改正生産緑地法の登場により、市街化区域で農業を営む人々にとって、引き続き農業を営むことのインセンティブが生まれました。簡単に言うと、「国が保護してくれるのだから、宅地にするよりも、このまま農地として利用した方がお得だ」という風に考えるようになったのです。
ここで、一つ疑問が浮かびます。それは、「生産緑地に指定されることで、どのくらいのメリットがあるのか?」ということでしょう。では以下に、解説していきます。
生産緑地に指定されるメリットとは?
生産緑地に指定されるメリットは大きく2つです。それは、固定資産税の軽減と、相続税の支払いの猶予です。
まず、固定資産税の軽減についてですが、こちらは驚くほどの軽減措置がなされています。具体的には、生産緑地の固定資産税は、市街化区域の宅地に比べて「数十分の一〜数百分の一」にまで下がります。
例えば、市街化区域の1,000㎡の土地(評価額1億)があったとすると、宅地の場合には年額約140万円もの固定資産税がかかる一方で、生産緑地の場合には年額僅か7千円ほどで済むわけです。これが、生産緑地の一つ目のメリットになります。
そして、二つ目のメリットは、相続税の支払いの猶予です。
一般的に、被相続人が死亡し、相続人に対して財産の相続が行われた場合には、その財産に対して税金が課せられます。これが相続税です。一方で、生産緑地の指定を受けた農地の場合には、この相続税の支払いを猶予することが可能です。これにより相続人は、相続税によるキャッシュアウトをせずに、農業を引き継ぐことが可能となるのです。
以上二つのメリットは、当時農業に従事している人々にとって大変魅力的でした。その為、多くの農地が生産緑地の指定を受けたのです。
一方で、生産緑地の指定を受けることによるデメリットがあったのも事実です。そしてそのデメリットが、現在の2022年問題に大きく影響を及ぼしているのです。
それでは、以下ではそのデメリットについて見て行きましょう。
生産緑地指定のデメリットとは?
上記では、生産緑地に指定されることの二大メリットについて見てきました。それに対して、生産緑地には大きなデメリットも存在します。それは、「30年間の営農義務」です。
営農義務、というとなんだか仰々しいですが、簡単に言えば「優遇する代わりに、30年間しっかりと農地として使ってね」という制限です。この制限のために、生産緑地を途中で宅地に変更したり、農地以外の用途で使用することが出来なくなってしまったのです。
勘の鋭い方であれば、すでに問題の本質にお気づきになっているかも知れません。そう、改正生産緑地法の適用が1992年でしたから、その営農義務制限の期限が、2022年に切れることとなるのです。
生産緑地に指定されている農地は全国に約1.3万ヘクタールも存在しているため、これらの農地が一斉に売り出された場合の不動産業界への影響は計り知れないものがあると考えられてきました。
今後の動き
不動産業界に対する影響はどのくらい?
これまで、2022年問題が東京の不動産業界に与える影響は甚大なものになるだろうとの予想が至る所で立てられてきました。それもそのはずで、全国約1.3万ヘクタールの生産緑地の内、なんと約4分の1が東京に属しているからです。東京都に存在する生産緑地は、東京ドーム約684個分にも相当します。
特に、東京23区の約20%を占める世田谷区は、高級住宅街などで知られており、賃貸需要も非常に高いです。もし仮に世田谷区の農地が宅地に転用され、建物用地として売却されたとなれば、各デベロッパーが放っておかないでしょう。
2019年の政府の対応
では、この2022年問題は実際に不動産業界に対して大きな影響を与えるのでしょうか?実は、ここ最近になって、2022年問題に対して政府が対策を打ったのですが、あまり世間では認知されていないようです。
その内容とは、新たな「特定生産緑地制度」の制定です。この制度は、2019年4月に制定された制度であり、生産緑地指定から30年が経過した農地を特定生産緑地として市町村が指定することで、税制優遇を継続させ、買取の申し出ができるようになる期間を10年間延長することのできるシステムです。
もっと簡単に言うと、「30年経ったとしても、今の制度をあと10年延長できるよ!」という制度なのです。
皆さんもお感じかとは思いますが、これは明らかに問題の先送りでしょう。一方で、2020年の東京オリンピック後に不動産価値が下落するのではないか?と言われている昨今の情勢を鑑みれば、少なくとも10年間は問題の発生を先延ばしできたのは評価すべきであるかも知れません。
まとめ
本記事では、世間で話題になっている2022年問題について、その概要と、最新の状況について解説を行ってきました。
記事内でも解説した通り、2022年問題とは、都市部の農地を守るための取り組みである「生産緑地」の30年間の営農義務が終了に差し掛かり、多くの農地が一斉に宅地に転用されることで土地の供給量が急激に増加し、結果として不動産価格の下落を引き起こすのではないかとされている問題です。
ですが、2019年4月の「特定生産緑地制度」の制定により、10年間の問題の先送りがなされることとなり、ひとまず事態は鎮静化されました。とはいえ、10年後に再びこの問題と向き合わなくてはならないのも事実です。
今後の日本経済に大きく影響する可能性がある問題ですので、しっかりと今後の成り行きを見守るようにしましょう。