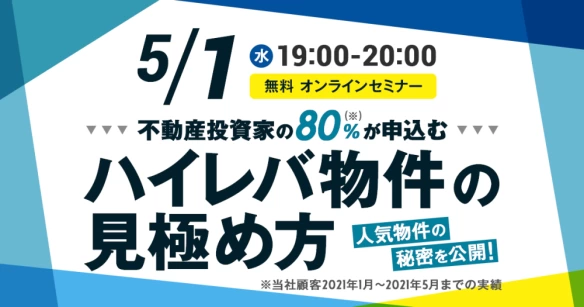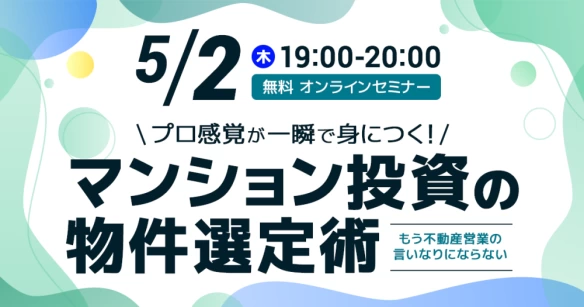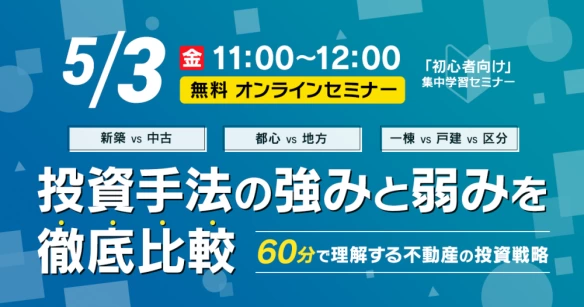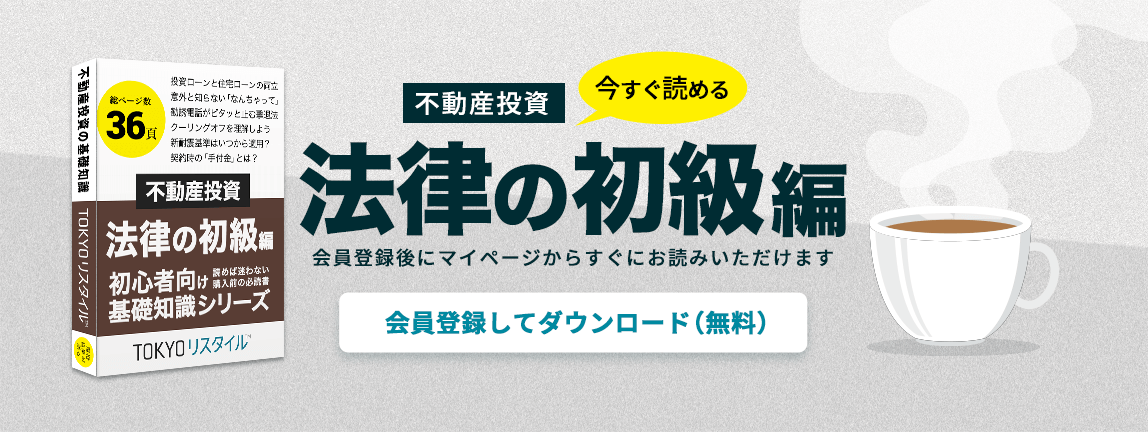不動産投資で賃貸借契約を締結する際の留意点は?オーナーから見た3つのポイントをわかりやすく解説!
- 更新:
- 2024/02/20

不動産投資では、物件への入居希望者と賃貸借契約を締結することにより家賃収入が得られます。しかし、初めて不動産投資をする場合は「どうやって契約を締結するのか」「契約することでトラブルに巻き込まれたらどうしよう」などと賃貸借契約に対する不安が大きいのではないでしょうか。
特に初めて不動産投資をする方は、自分が物件を借りたことはあっても、貸したことはほぼないでしょう。そこで本記事では、不動産投資で賃貸借契約を締結する際の留意点をオーナー目線から解説します。不動産投資での賃貸借契約について不安がある方は、最後までご一読ください。
- 不動産投資で想定される入居者とのトラブル
- 契約締結時の留意点①:契約締結前に入居者審査をしっかり行う
- 契約締結時の留意点②:賃貸借契約書の内容に合意したうえで契約を締結する
- 契約締結時の留意点③:契約時に重要事項や特約についての説明をしっかり行う
- サブリース契約ではサブリース会社と賃貸借契約を締結する
- まとめ
不動産投資で想定される入居者とのトラブル
不動産投資で考えられる入居者とのトラブルとして、入居者の家賃滞納や規約違反が挙げられます。規約違反の具体例は、騒音、楽器演奏、ペットの飼育など。特に音に関するトラブルは多く、「日本音響学会誌」に掲載された論文によると、共同住宅における「住宅音」に関する苦情対象のトップ3は、重量床衝撃音(子どもの歩行など)、床鳴り、外部騒音とされています。

訴訟となった音源で一番多いのは、直上階住人の足音でした。この調査からも、住宅内外の音がトラブルに発展しやすいことがわかります。

引用丸山明恵・井上勝夫「判例分析からみた音環境トラブルの実態」(日本音響学会誌 72 巻 10 号(2016),pp. 662–668)
不動産投資物件の賃貸借契約で基準となるのは「借地借家法」です。借地借家法では、入居者(借主)が有利になっています。貸主であるオーナーは、入居者がトラブルを起こした場合でも、正当な事由がないかぎり退去させられません。オーナーは入居者を簡単に退去させられないことから、未然にトラブルを防ぐ必要があります。
契約締結時の留意点①:契約締結前に入居者審査をしっかり行う
ここからは、入居者とのトラブルを回避するために、契約締結時に留意すべきポイントを一つずつ見ていきましょう。
不動産投資で賃貸借契約を締結する際は、入居者審査を行います。入居者審査(入居審査)は、入居希望者が、投資物件を安心して貸せる相手かどうかを判断する大切な工程です。以下の事項を重点的に確認しましょう。
- 家賃の支払い能力
- トラブルを起こす可能性
- 入居希望者以外の連絡先
入居希望者の人当たりがいいからと安心して支払い能力を調べないと、実は家賃の入金が滞りがちな入居者だった、という可能性もあります。話したときの印象だけで判断せず、勤続年数や勤務先といった支払い能力の有無についてもしっかり調査することが大切です。家賃滞納のリスクをより減らしたい場合は、勤続年数や年収、連帯保証人の基準などを厳しめにすることも検討しましょう。
契約締結時の留意点②:賃貸借契約書の内容に合意したうえで契約を締結する
賃貸借契約のトラブルを回避するには、賃貸借契約書に記載された内容を理解し、双方合意の上で契約することも欠かせません。
賃貸借契約書とは、賃貸借契約を締結する際にオーナー(貸主)と入居者(借主)の間で交わされる契約に関する書面です。賃貸借契約の締結により、入居者はオーナーの持つ物件に住めるようになり、オーナーには入居者からの家賃収入が入るようになります。
前述の通り、賃貸借契約ではオーナーが不利な立場です。だからといって、必要以上にオーナーに不利な契約を締結する必要はありません。オーナーと入居者が合意した上で、借主に有利となる特約も付加できます。オーナーと入居者双方が賃貸借契約書の内容について合意した上で契約することで、賃貸借契約で起こりうるトラブルを回避できるでしょう。
賃貸借契約書に記載すべき項目
ここからは、国土交通省が出している「賃貸住宅標準契約書(以下「標準契約書」と記載)」に記載された項目を基準に、賃貸借契約書に記載すべき内容や留意点を紹介します。
標準契約書は「賃貸借契約をめぐる紛争を防止し、借主の居住の安定及び貸主の経営の合理化を図ることを目的として」作成された、賃貸借契約書のひな形です。6項目からなる頭書と条文の項目に分かれています。
では、標準契約書に沿って、記載すべき内容とその留意点を見ていきましょう。
①賃貸借の目的物
標準契約書の冒頭には、賃貸借の目的物 = 投資用物件の概要を記載します。以下の事項について記載しましょう。
- 入居者に貸し出す物件の名称・所在地
- 物件の建て方(共同住宅、一戸建てなど)
- 部屋番号
- 面積
- 設備の有無(トイレ、浴室、給湯設備、コンロ、冷暖房設備など)
- 電気・ガス・水道設備についての詳細
- 付属施設の有無(駐車場、バイク置場、自転車置き場、物置、専用庭など)
この記載が実情と違っていると、トラブルの元となります。物件の現状通りに記載しましょう。
②契約期間
次に、契約期間を記載します。具体的には、開始日と終了日、契約期間となります。開始日と終了日は1日単位で記載可能です。契約期間と更新有無、解約についての規定は、頭書の後ろにある条文の項目に記載しましょう。
標準契約書の条文には、オーナーと入居者が協議の上で更新できること、入居者が解約を申し出る場合は30日前に伝えることと記載があります。しかし、借地借家法第26条では、貸主(オーナー)から契約更新しない場合は期間満了の1年前から6ヶ月前に伝えなければならないと規定。さらにオーナーが契約解除を申し出るときは正当な事由がないと認められません。従って、入居者から解約の申し出がされない限りは、契約は自動的に更新されるとみなされます。
③賃料等
賃料等の項目には、賃料、共益費、敷金について記載します。金額だけでなく、支払期限と支払い方法の記載も必要です。支払方法は、振込、口座振替、持参のいずれかを選択する形式がいいでしょう。
振込もしくは口座振替の場合は振込先の情報(金融機関名、口座種別と番号、振込手数料負担者)を記載します。持参の場合は持参先を記載しましょう。附属施設利用料やその他支払いが必要な場合は、その旨を記載します。
頭書に記載されていない以下の事項は、別途条文に記載が必要です。
- 1ヶ月未満の契約期間を設定した場合は、日割り計算すること
- 賃料や共益費の価格は、オーナーと入居者間での話し合いで変更可能であること
2020年の民法改正により、敷金については敷金から家賃の未納分を差し引いた残額を返還しなければならないと定められました。同時に、入居者には通常損耗や経年劣化による原状回復義務がないことから、これらの金額を負担する必要はないことも明文化。原状回復費用を入居者に負担して欲しい場合は、別途特約を定めなければなりません。
原状回復費用と敷金については、後ほど詳しく解説します。
④貸主及び管理業者
貸主及び管理業者の項目には、オーナー(貸主)と管理業者の住所、氏名(会社名)、電話番号を記載します。この部分が間違っていることにより、入居者の信頼が損なわれてしまうかもしれません。正確に記載しましょう。
⑤借主及び同居人
借主及び同居人の項目には、以下の項目を記載します。
- 入居者(借主)の氏名、年齢、電話番号
- 同居人の氏名と年齢
合わせて、緊急連絡先の住所、氏名、電話番号、借主との関係も記載が必要です。契約を締結する際は、この部分を間違いなく記載してもらうことも大切となります。
⑥家賃債務保証業者/連帯保証人及び極度額
標準契約書は、2018年に「家賃債務保証業者型」と、極度額の記載欄を設けた「連帯保証人型」の2種類に分けられました。民法改正や、家賃債務保証業者を利用した契約の増加を踏まえた改正です。2種類とも、本項目以外は同一内容となります。
連帯保証人型は、連帯保証人がいる場合に使用します。連帯保証人の住所、氏名、電話番号と、極度額を記載しましょう。極度額とは、連帯保証人が入居者(借主)の債務を担保する上限額です。2020年の民法改正により、極度額の記載が必須となりました。
保証人が家賃債務保証業者である場合は、家賃債務保証業者型を使用しましょう。家賃債務保証業者の所在地、商号(会社名)、電話番号、家賃債務保証業者登録番号を記載します。
禁止事項
標準契約書では、条文にて本契約に関する禁止事項を定めています。代表的な禁止事項は、以下の通り。
- ピアノの持ち込みや使用
- 石油ストーブの使用
- ペットの飼育
- 喫煙
- カラオケ
この他、賃借権の譲渡や転貸で契約した本人以外が住むことも禁止しておきましょう。店舗を営む、民泊に使うなど、物件を住居以外の用途で使用して欲しくない場合も、禁止事項として明記しておくことをおすすめします。
契約書には原状回復に関する条件や特約も記載する
先述の通り、入居者には物件の原状回復義務はありません。しかし、特約により、ハウスクリーニングなどの原状回復費用を入居者に負担してもらう場合があります。
国土交通省が定めた「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改定版)」によると、退去時の原状回復における負担割合は、以下のように分けられています。
| 負担者 | 負担割合 |
|---|---|
| オーナー(貸主) | ・経年劣化の部分 ・設備交換を含む部分 |
| 入居者(借主) | ・通常の使用範囲を超え、経年劣化・通常損耗以外の部分 ・管理の悪さに起因する部分 |
ハウスクリーニングの費用は、通常はオーナー(貸主)負担ですが、特約により入居者(借主)負担とすることも可能です。後からトラブルとならないよう、退去時の原状回復費用は誰がどこまで負担するのか、きちんと記載しておきましょう。
参考マンションの退去費用は誰が支払う?原状回復ガイドラインに沿って徹底解説!
契約締結時の留意点③:契約時に重要事項や特約についての説明をしっかり行う
不動産投資においては、賃貸借締結時に重要事項や特約についての説明を行い、入居者に契約内容を理解してもらうことが大切です。重要事項説明(重説)とは、不動産の賃貸借や売買取引に先立って、宅建業者より契約両当事者に対して不動産に関する重要事項の説明を行うこと。宅地建物取引業法(宅建業法)第35条に定められた事項です。
不動産会社に仲介を依頼している場合、宅建業者となる不動産会社が重要事項説明を行います。しかし、自分が直接入居者と契約を締結する場合は、自分で説明をしなければなりません。
重説は、重要事項説明書をベースにして行います。重要事項説明書とは、以下のような賃貸借契約に関する重要事項が記載された書面です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 土地の概要 |
・所在地 ・地目 ・面積 |
| 建物の概要 |
・所在地 ・家屋番号 ・種類及び構造 ・床面積 |
| 売主の情報 | ・売主の住所、氏名 |
| 対象となる宅地又は建物に直接関係する事項 |
・登記記録に記録された事項 ・都市計画法・建築基準法に基づく制限の概要 ・私道に関する負担に関する事項 ・飲用水・電気・ガスの供給施設及び排水施設の整備状況 ・建物状況調査の結果の概要 ・建物の建築及び維持保全の状況に関する書類の保存の状況 ・当該宅地建物が土砂災害警戒区域内か否か ・石綿使用調査の内容 |
| 取引条件に関する事項 |
・代金及び交換差金以外に授受される金額 ・契約の解除に関する事項 ・損害賠償額の予定又は違約金に関する事項 ・支払金又は預り金の保全措置の概要 ・金銭の貸借のあっせん ・賃料及び賃料以外に授受される金額 ・契約期間及び更新、解除に関する事項 ・用途その他の利用の制限に関する事項 ・敷金等の精算に関する事項 ・担保責任の履行に関する措置の概要 ・管理委託先 |
| その他の事項 | ・供託所等に関する説明 |
特に、敷金の返還方法(全額返金するのか、原状回復に掛かった費用を引いて返金するのか)や退去予告の期間、禁止事項などはトラブルの原因となります。過去には、重説の不適切な取扱により業務停止となった不動産会社もありました。不動産投資において賃貸借契約時のトラブルを回避するには、重要事項や特約についての説明をしっかり行ってくれる不動産会社を選ぶことが大切ともいえるでしょう。
サブリース契約ではサブリース会社と賃貸借契約を締結する
サブリース契約とは、マンションやアパートといった集合住宅形式の不動産投資物件を不動産会社が一括で借り上げるシステムです。サブリース契約を締結していると、空室になっても、満室想定時における家賃の80 〜 90%分の収入が保証されます。
サブリース契約は、オーナーとサブリース会社の間で賃貸借契約を締結します。サブリース会社が入居者と契約するため、オーナーは入居者とは契約しません。サブリース会社との契約においても借地借家法が適用されます。こちらも、オーナーが不利な賃貸借契約となる点に注意が必要です。
参考サブリースは解約できない?これで完璧!メリットから問題点まで一挙解説
まとめ
不動産投資において、賃貸借契約は入居者との信頼関係を築くための大切なポイントです。物件の賃貸借契約におけるトラブルを未然に防ぐには、事前に部屋の状態を確認しておくことはもちろん、契約書や重説により事前に契約内容を説明し同意を得ておくことが最善策といえるでしょう。
当社の物件を希望された場合は、物件の状況を包み隠さずお伝えします。入居者とのトラブルが心配な場合は、疑問が解消できるまで購入をお勧めしません。購入後も、トラブル回避のためのアドバイスをさせていただきます。
不動産投資における賃貸借契約で疑問や不安がある場合、ぜひ当社の無料相談を活用していただければ幸いです。漠然とした不安はもちろん、個別の物件に関する相談でも構いません。豊富な経験を持つ不動産投資コンサルタントが、経験に裏打ちされた中立的なアドバイスを行います。不動産投資の賃貸借契約に関する疑問や不安を解決するために、ぜひ当社の無料相談をご活用ください。

この記事の執筆: 堀乃けいか
プロフィール:法律・ビジネスジャンルを得意とする元教員ライター。現役作家noteの構成・原案の担当や、長野県木曽おんたけ観光局認定「#キソリポーター」として現地の魅力を発信するなど、その活躍は多岐に亘る。大学および大学院で法律や経営学を専攻した経験(経済学部経営法学科出身)から、根拠に基づいた正確性の高いライティングと、ユーザーのニーズに的確に応えるきめ細やかさを強みとしている。保有資格は日商簿記検定2級、日商ワープロ検定(日本語文書処理技能検定)1級、FP2級など。
ブログ等:堀乃けいか