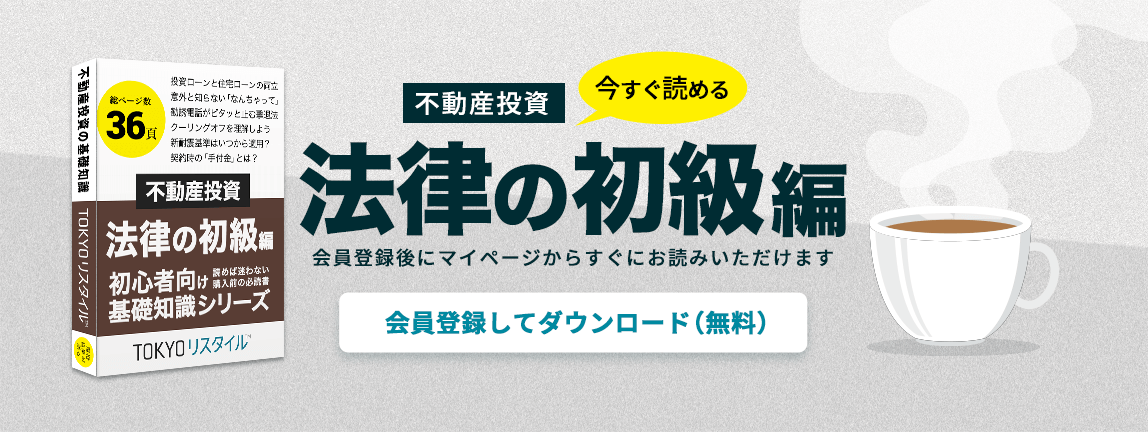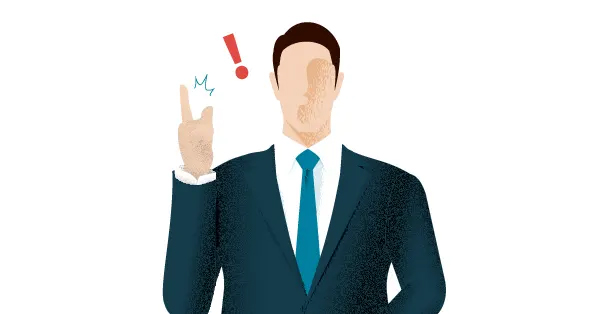定期借家契約と普通借家契約の違いとは?不動産投資の視点から見るメリット・デメリット
- 更新:
- 2023/06/19

不動産投資においてよくある心配が、「賃借人との退去にまつわるトラブル」や「家賃の減額可能性や契約期間の不確定さにより収益が予測しづらい」といったことではないでしょうか?
従来より、一般的に利用されてきた普通借家契約は「入居者保護」の観点から賃借人優位になっており、トラブルが起きた場合に賃貸人に不利になっているケースも見受けられます。
こういった状況を受け、平成11年に新しく定期借家制度が成立、翌年施行されました。
そこで本記事では「そもそも定期借家契約とは?」というところから普通借家契約との違い、不動産投資の観点から見るメリット・デメリットについて解説します。
「定期借家」と「普通借家」とはそもそも何なのか?
定期借家と普通借家はどちらも賃貸借契約の形式であり、借地借家法の一部改正により定期借家制度が創設されました。
ここでは借地借家法についての簡単な説明と、定期借家と普通借家の違いについて見ていきましょう。
借地借家法とは?
簡単に説明すると借地借家法とは、民法で規定されている賃貸借の中で特に生活に欠かせない「土地建物」の賃貸借において賃借人の立場を保護するために成立、1992年に施行された法律です。
契約の効力や更新などについて定められており、「有償」かつ「一時使用ではない」建物の賃貸借については借地借家法の規定が用いられることになります。
「普通借家」「定期借家」とも借地借家法に規定されている建物賃貸借の形式になります。
契約の「更新」と「解約」に関する規定の違い
普通借家契約と定期借家契約の違いは主に「更新」と「解約」についてです。
| 普通借家契約 | 定期借家契約 | |
|---|---|---|
| 更新 | 合意更新または法定更新 (期間の定めがある場合) |
原則的に更新せず終了 双方の合意があれば再契約可 |
| 解約 | 賃貸人側からの解約には 「正当な理由が必要」 申し入れから6か月後に終了 |
原則途中解約は 賃貸人・賃借人とも不可 |
普通借家契約であれば、契約で定めた期間(一般的には2年)が終了する前に更新の契約を交わし、そのまま更新することが一般的です。
一方、定期借家契約とは「定期」とあるように契約時に定めた期間が終了したらそのまま終了する契約であり、賃貸借を続行するためには再契約が必要になります。
また、賃貸人、賃借人とも原則として契約で定めた期間の途中解約はできない決まりになっています(条件を満たせば可能)。
定期借家制度ができた背景
借地借家法の一部改正で平成11年12月に成立した「良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法」により定期借家制度が創設され、平成12年3月に施行されました。
それでは、なぜ普通借家制度が存在するにも関わらず、定期借家制度が新たにできたのでしょうか?それには「賃借人が守られすぎる」という問題点がありました。
具体的にどういった点なのかもう少し詳しく見ていきましょう。
従来の「普通借家契約」における問題
従来の普通借家契約においては、賃貸物件に住む賃借人が住まいを失い不利益を受けることがないように、賃借人が保護されるような規定があります。
この中で問題となるのが次の2つです。
- 賃貸人から更新拒絶するには「正当な理由」が必要
- 法定更新の存在
入居者を保護するという目的を果たす一方で、この2つの規定により賃借人の立場が強くなりすぎてしまい、賃貸人に不利な面が出てきてしまいました。
問題①:賃貸人から更新拒絶するには「正当な理由」が必要
普通借家契約においては、賃貸人が解約を申し入れる場合や賃借人からの契約の更新を拒否する場合には「正当な理由」が必要であると借地借家法第二十八条で定められています。
この「正当な理由」となる「建物の使用を必要とする事情」や「建物の状況(老朽化など)」などが賃借人に有利な解釈となっており賃貸人の主張が認められにくいのが現状です。
そのため建物が古くなり建て替えや解体を行いたくても賃借人に退去してもらうためには1件1件交渉を行ったり多額の立ち退き料を支払ったりする必要があり、資金計画に大きく影響を与える事態が考えられます。
問題②:「法定更新」の存在
普通借家契約では、定めた期間が経過した後は合意がなかった場合でも更新に合意したとみなされる「法定更新」という規定があります。
そのため契約期間満了後に賃借人が住み続けた場合、速やかに異議を述べないと期間のない契約更新となってしまいます。
定期借家制度は、賃貸人がこういった普通借家契約による問題を受けることなく安定した資金計画の元に賃貸経営が行えるようになり、ひいては賃貸住宅の供給が増える効果を狙って創設されたのです。
定期借家のメリット・デメリット
定期借家の「契約期間内の契約は確保される」という特徴には、メリット・デメリットがそれぞれあります。
不動産投資という観点を元に、賃貸人側から見たメリット・デメリットについて述べていきます。
定期借家のメリット
定期借家のメリットを一言で述べると、賃借人とのトラブルや短期解約といった「不確定要素を回避しやすい」という点です。
メリット①:賃借人とのトラブルを回避しやすくなる
メリットの1つ目が賃借人とのトラブルを回避しやすくなる点です。
定期借家契約には法定更新がなく、双方の合意のもと再契約をしなければ原則賃貸借契約は終了します。
賃借人に滞納や他の入居者とのトラブルがあった場合、再契約を行わなければ賃貸借契約は終了するため、契約期間の満了に伴い、スムーズに退去してもらうことが可能となります。
メリット②:契約期間を自由に設定できる
2つ目のメリットが、契約期間を自由に設定できるという点です。
定期借家契約であれば、更新を前提としない契約のため立ち退きなどでトラブルになりにくく、建て替えや解体がスムーズに行えるだけでなく、契約期間が決まっているため収益の見通しを立てやすくなります。
メリット③:賃借人優位を解消できる
3つ目のメリットは、定期借家契約を締結することにより、賃借人が過度に優位な状況を解消できるという点です。
普通借家契約においては一般的に、理由に関わらず賃借人が一か月前に申し入れを行えば解約できます。
しかし定期借家契約では契約期間を賃貸人が設定でき、賃借人からは以下のような要件がない限り中途解約の申し入れはできないように定められているため、従来の賃借人優位が解消されます。
- 居住の用に供する建物でその床面積が200平方メートル未満のもの
- 転勤、療養、親族の介護その他のやむを得ない事情により、賃借人が建物を自己の生活の本拠として使用することが困難となった場合
定期借家のデメリット
一方、定期借家のデメリットは、大きく分けて次の2点です。
- 普通借家の相場より家賃を安く設定する必要がある
- 再契約・契約終了の際に手続きが必要
デメリット①:普通借家の相場より家賃を安く設定する必要がある
デメリットの1つ目が定期借家の場合、普通借家の相場より家賃を安く設定する必要がある点です。
なぜかというと、契約期間で無条件に契約が終了する定期借家契約は普通借家契約より賃借人の立場が弱くなるため、通常同じ家賃の価格帯であれば普通借家の物件を選択されてしまうためです。
デメリット②:再契約の場合に手間がかかる
デメリットの2つ目が、賃借人とトラブルがあった場合にスムーズに契約終了させられる反面、問題がない場合でも都度再契約をする必要があるため書面や契約の手間が発生するという点になります。
デメリット③:1年以上の契約の場合、契約終了の通知が必要になる
デメリットの3つ目が、一年以上の期間の定期借家契約を結ぶ場合、期間満了の1年前から6か月前までの間に期間満了で定期借家契約が終了することを賃借人に通知する義務が定められている点です。
不動産投資における留意点
最後に、「定期借家」「普通借家」に関係する不動産投資における留意点について解説します。
留意点①:事前に普通借家か定期借家かを決めておく
まず賃借人を募集する際、事前に普通借家契約にするか定期借家契約にするかを決めておく必要があります。
途中での切り替えは難しい
普通借家契約を途中で定期借家契約へ切り替えるのは賃借人側が不利になるため、同意が得られにくく難しいでしょう。そのため、定期借家と普通借家どちらが適しているかをあらかじめ物件ごとに考える必要があります。
賃料の改定が原則的にできない
定期借家契約は契約期間中、賃料の改定が原則的にできません。そのため周辺の家賃相場が上がった場合、相対的に賃料が低くなる可能性があります。
留意点②:治安の状況に応じて、2種類の契約を使い分ける
国土交通省の令和3年度住宅市場動向調査報告書によると、民間賃貸住宅に住み替えた世帯の中で定期借家制度利用の契約は1.9%に留まっています。
その理由のひとつとして、同報告書によると定期借家制度を「知らない」と答えた回答者が62.8%であるという認知度の低さも大きいでしょう。
そのため物件周辺エリアの治安が良い場合は普通借家の方が募集も来やすくなりますが、治安にやや不安があるときは、定期借家も選択肢に入れると良いでしょう。
留意点③:定期借家契約にするためには要件がある
定期借家契約にするためには以下の4つの要件があり、どれか1つでも怠ると普通借家契約になってしまうため注意が必要です。
- 契約期間を定める
- 契約の更新がないという特約を定める
- 書面により契約をする
- 定期借家契約であることを記載した書面を別途交付して賃貸人(あるいは代理人)が説明する
留意点④:「普通借家」「定期借家」どちらが良いかは物件による
このように定期借家契約には決まり事も多く、基本的には普通借家で募集することが多いです。
比較的治安が良くて入居者トラブルがないエリアであれば入居者を集めやすい通常の普通借家契約の方が適しています。しかし、物件エリアの治安や入居者層がやや気になるようであれば多少募集賃料が低くなったとしても入居者とのトラブルに発展するリスクを回避するために定期借家契約も検討すべきでしょう。
まとめ
普通借家と定期借家の違いは、簡単にまとめると「定期借家は契約期間の終了に伴い更新せず終了する契約」ということです。
定期借家には「賃借人との退去に関するトラブルを回避しやすい」「収益の見通しが立てやすい」というメリットがある反面、「様々な手順が必要」「普通借家の家賃相場より家賃が低くなる」というデメリットがあります。
普通借家と定期借家、どちらの契約形態が適しているかはエリアの人気度や想定される入居者の属性によるところが大きいでしょう。
どのような契約形態にするかを決める前に、両者の長所と短所、物件の状況を知った上で検討することが重要です。当社では多くの実例から、どのような形で不動産投資を行うのが最適かアドバイスさせていただきます。実際の運用においては、当社コンサルタントにぜひご相談ください。

この記事の執筆: ひらかわまつり
プロフィール:宅地建物取引士・賃貸不動産経営管理士資格を有するママさんライター。親族が保有するマンションの管理業務経験を有するなど、理論・実務の両面から不動産分野に高い知見を持つ。また、自身でも日本株・米国株や積立NISAなどを行っていることから、副業や投資系ジャンルの執筆も得意としている。解像度の高い分析力と温かみのある読みやすい文章に定評がある。不動産関連資格以外にも、FP2級、日商簿記検定2級、建築CAD検定3級、TOEIC815点、MOSエキスパートなど多くの専門資格を持つ。
ブログ等:ひらかわまつり