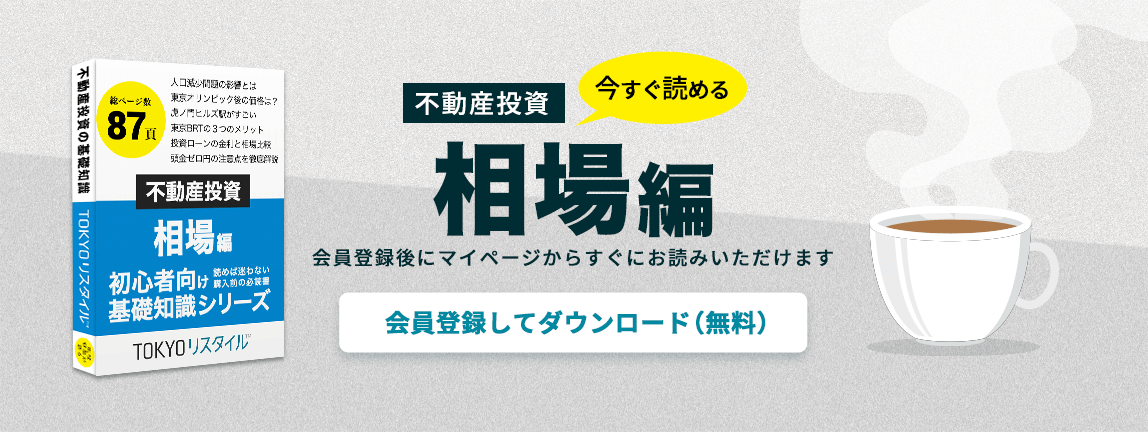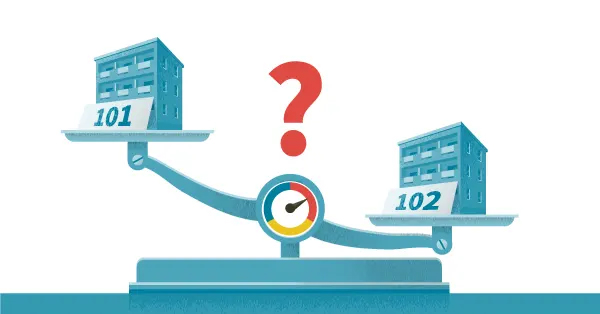液状化ハザードマップ作成の手引きを確認しよう!地震、洪水、大雨、自然災害と共にある日本のハザードマップ
- 更新:
- 2023/06/26
本記事は動画コンテンツでご視聴いただけます。
住宅に長期的な被害をもたらす液状化現象。地震をはじめとする自然災害の多い日本では、個人個人が災害対策への危機感を持って生活を送ることが、被害を最小限にとどめるために重要です。しかし現状の液状化現象のハザードマップでは、なぜ液状化現象が発生するのか、それによる被害リスクはどの程度のものかが記されておらず、備えに関する情報が少ないとの指摘がありました。また、東京電機大学の安田名誉教授によると、各自治体が作成した液状化ハザードマップは、精度や作成条件が統一されていないことから、被害リスクが伝わりにくくなっていると言います。
そこで国土交通省は2021年2月26日に「リスクコミュニケーションを取るための液状化ハザードマップ作成の手引き」(以下、手引き)を同省公式サイトにて公開しました。そこには、液状化現象による被害リスクとハザードマップを作成するための共通事項などが記されています。本記事では、手引きに書かれている内容から、液状化ハザードマップの重要性について解説します。地震発生時に住宅を守るために必要な情報となりますので、本記事を参考に、公式の情報をしっかり一読しておきましょう。
液状化ハザードマップとは?
日本では、高度経済成長期に急速な都市化が進められ、臨海部や谷部を埋め立てることで市街地を拡大してきました。しかし、このような埋め立て地では、大きな地震によって液状化現象が発生しやすいことが過去のデータより明らかになっています。液状化危険箇所を分かりやすく示すことで、その地域に住む居住者と行政が共通認識として確認するための資料が液状化ハザードマップです。しかしハザードマップには、液状化現象がなぜ発生するのか、被害リスクに備えるために何ができるのかといった事前知識が記されていません。実践的な対策としては、個人が液状化現象についての理解を深めることが重要で、液状化ハザードマップが住宅を守るための「リスクコミュニケーション」として力を発揮することが大切なのです。
液状化現象とは?
液状化現象とは、地震発生時に地盤が液体状になることです。震度5以上の地震が発生し、揺れている時間が長いほど、液状化現象の被害も大きくなるとされており、埋め立て地のほか、海岸や河川の扇状地など、地下水位が地表面から10m以内の場所で発生しやすい傾向があります。液状化現象が起こると、建物が沈んだり、地中の水や砂が地表に噴き出したりするなどの被害をもたらします。
2011年3月12日に発生した東日本大震災では、震源地から遠く離れた東京湾周辺でも液状化現象による被害が発生したため、今後30年以内に高い確率で発生すると言われている南海トラフ地震や首都直下地震などに備えて、液状化現象の周知と対策が進められています。
液状化現象が起こるとどうなる?
液状化現象が発生したからといって、直接命に関わることはほとんどありません。しかし、被災後の生活に大きな影響を及ぼす可能性があり、液状化現象によって起こるさまざまな被害が複雑に絡みあうことで、被害の長期化、また復興の遅れに繋がります。特に、住宅や暮らしへの被害が大きいことから、侮ってはいけない現象なのです。では、以下で具体的な被害例をご紹介しましょう。
住宅の沈下、傾斜、倒壊
液状化現象が住宅に与える被害として最も甚大なのが、住宅の倒壊です。地面が陥没することから、倒壊までは至らずとも、沈下、傾斜する恐れがあります。特に鉄筋コンクリートに比べて重さの軽い木造住宅は、建物の基礎となる部分が浅く設計されているため、液状化現象の影響を受けやすいです。
また、傾斜した住宅で生活を続けると、平衡感覚が狂い、頭痛やめまい、吐き気などの健康被害を及ぼすことがあります。
地中の配管の損傷
地面が陥没することで、上下水道やガス管など、地中を通る配管が破損することもあります。そのため、仮に住宅被害がなかったとしても、液状化現象の影響でライフラインの一部が断絶され、生活に支障をきたすことも考えられます。
噴水・噴砂の発生
地中の水圧が高くなることで、地中にある砂や水が勢いよく噴き出す危険もあります。マンホールなどの人工物が飛んでくることもあるため、怪我に注意しましょう。また、地表が砂や水まみれになり、交通が普賢になることから、むやみな外出は避けた方がいいでしょう。避難で外を歩く際は、注意が必要です。
リスクコミュニケーションを取るための液状化ハザードマップ作成の手引き
震災被害が尾を引く原因となり得る液状化現象。前述した通り、現在の液状化ハザードマップでは、液状化現象の被害リスクが伝わりにくく、情報が不十分です。では、理想の液状化ハザードマップとはどのようなものなのでしょうか。国土交通省のホームページにて公開されている手引きをもとに、以下にポイントをまとめました。
液状化現象に対する共通意識を持つ
液状化ハザードマップを作成し、活用するためには、実際にハザードマップを利用する居住者と作成する行政とのあいだで、対象地域の液状化現象発生傾向や住宅被害へのリスクなど、共通意識を持つことが重要です。
例えば「地域全体の液状化現象発生傾向」を把握することが挙げられます。居住する地域内のどこで液状化現象が発生しやすく、それがどう分布しているかを知っておくことで、液状化被害に対する予備対策が可能になります。液状化現象が発生した際の行動パターンや液状化現象に対する理解を深められるよう、地域の地形や特徴を加味した情報をハザードマップに記載しましょう。
共通項目と選択項目
現在の液状化ハザードマップは「精度や作成条件が統一されていない」と前述しました。地域ごとに液状化現象の被害リスクは異なるものの、地図の表示縮尺や掲載する情報の内容や量など、利用する居住者がひと目で分かるよう配慮することが大切だと、手引きには記されています。また、主要交通網や主要施設など、位置関係が把握しやすい情報が掲載されている地図をもとに作成することなど、誰が見ても分かりやすいハザードマップにするための共通項目が定められています。
共通項目は以下です。
- 地域の液状化発生傾向図
- 指定緊急避難場所、指定緊急避難所
- 緊急輸送道路等の主要交通網(道路・鉄道等)
- 避難路や物資輸送路となりうる主要交通網の位置確認
- 役場、警察、消防等の防災関係機関
- 災害時の問合せ先
また、対象地域ごとの液状化現象発生傾向をより深く理解するために以下の「選択項目」も定められています。
- 過去の地震による液状化発生箇所
- 避難場所や避難所等の安全性(耐震性)
- 避難経路の位置と安全性(耐震性)
- 給水所、仮設トイレ、利用可能な井戸等
- 災害ゴミ(土砂含む)の収集・廃棄場所
- 防災倉庫や消防団車庫等
- 既存のボーリングデータ情報(ウェブ地図の場合)
- 液状化危険度をイメージするための地盤情報の確認
また、紙媒体のハザードマップは掲載情報に制限がありますが、ウェブを用いることで幅広い情報を広めることも可能です。その際は、利用者が見やすいよう導線を工夫することや、デザイン、情報の整理がより重要になります。一人ひとりが液状化現象に対する理解を深められるよう、実践的なハザードマップの作成を心掛けてください。
ハザードマップが活用されるよう周知させる
液状化ハザードマップが作成できたら、活用してもらえるよう周知させましょう。これまでは、「揺れやすさマップ(震度分布図)」や「地域の危険度マップ(建物倒壊危険度分布図)」などの付属資料として公開されていたことにより、液状化ハザードマップの認知度や液状化現象に対する危機感は低い傾向があります。
直接命を脅かす現象ではないために、意識が二の次になってしまいがちな液状化現象ですが、住宅を守り、被災から1日でも早く復興するためには、液状化現象による被害を最小限にとどめることが重要です。ワークショップを開催するなどして、液状化ハザードマップの活用方法や被害リスクを知ってもらうための取り組みを行い、周知を確実なものにしましょう。
参考ハザードマップのユニバーサルデザイン化とは?何が変わる?不動産投資への影響も解説
まとめ
長期的で甚大な住宅被害をもたらす液状化現象。国土交通省が公開した手引きをもとに、分かりやすい液状化ハザードマップを作成し、地域全体の共通意識として周知させることが大切です。本記事では、液状化現象についての解説と、手引きのポイントについてまとめましたが、詳細はこちらからチェックしてください。