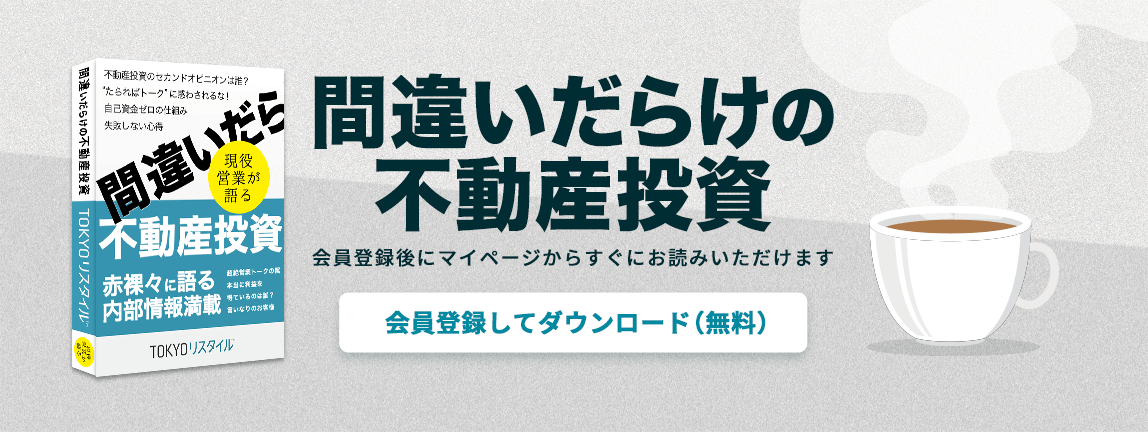サブリースは解約できない?これで完璧!メリットから問題点まで一挙解説
- 更新:
- 2022/10/25
本記事は動画コンテンツでご視聴いただけます。
不動産投資を行う際に心配になるのは空室による家賃の減収です。
空室が増えるとそれだけ毎月の収入が減ってしまうので、オーナーにとってはできるだけ避けたいものですよね。このリスクを回避できるサブリースというシステムはご存知でしょうか。サブリースを行う会社と契約を結ぶことで、空室の場合も一定の家賃収入を得ることができます。
しかし、よく知らないままに契約してしまうと後々契約上でトラブルが発生することも少なくありません。では、サブリースとはどのようなもので、なぜ注意しておく必要があるのでしょうか。
今回はサブリースの特徴や、予想されるトラブルとその防止法についてご説明します。
サブリースとは
サブリースとは、マンション、アパートなどの集合住宅形式の不動産投資物件を不動産会社が一括で借上を行うシステムです。この契約をすることで、空室になっても不動産の所有者には満室想定の家賃の80~90%が定額で入ってくることが保証されます。
空室であろうが、満室であろうが一定の収入が保証されることから「一括借上制度」「家賃保証制度」とも呼ばれています。空室リスクを回避するための方法のひとつです。
サブリースのメリット
サブリースの最大のメリットは、空室リスクを回避できることでしょう。不動産投資において、空室リスクは事業計画に関わる大きな問題です。ローン返済や修繕費等のメンテナンス費用の観点からも、空室が出ることによる減収は事業計画の根幹を揺るがしかねません。サブリース契約をすることでそのリスクを回避することができます。
また、サブリースでは通常の管理委託契約と同様、家賃の集金や入居者とのトラブル対応なども契約会社に行ってもらえます。物件の管理状況が悪くなれば客付けに影響するので、オーナーだけではなく管理会社が苦労することになります。 主体的に管理を行ってくれるため「契約したあとはお任せ」のようなスタイルで不動産投資を行うことができるのです。
さらに、確定申告時の事務作業が非常に簡素化できるのもメリットのひとつです。通常の確定申告では、入居者個別に入退去時の収支を処理しなければいけませんが、サブリースの場合、収支管理をするのは契約した不動産会社とのやりとりだけです。非常に簡素化され、帳簿作成が楽になります。
空室リスクを回避できるだけではなく、毎月の管理や事務作業に時間がとれないという方にとってもサブリースは魅力的なシステムといえるかもしれません。
サブリースのデメリット
サブリース会社は、個人の賃借人と同じ借主の立場での契約となります。そのため、サブリース契約には借主の権利が守られる「借地借家法」が適用されます。借地借家法は賃借人を守るための法律ですので、借りる側が非常に有利な契約になっています。
第一に、サブリースは借主であるサブリース会社が有利な契約だという点は抑えておくべきでしょう。
また、一般的にサブリースでは、家賃保証が80%~90%と設定されている場合がほとんどです。通常の不動産投資よりも入ってくる額が少なくなるということは、資金計画をたてる上で頭に入れておく必要があります。
サブリースを解約することの利点
先述のように、サブリースにはメリットとデメリットが存在します。空室を回避しながら管理を一任できる一方で、持ち主が不利になる契約が交わされてしまうのがサブリースです。ここではさらに別の視点から、サブリースを解約したらどのような利点があるかをご紹介します。
①利回りが改善する
サブリースの保証額が家賃の80%~90%となることから、サブリース契約を交わすことで家賃収入および利回りが減少することになります。また、契約によっては持ち主が敷金・礼金を受け取れないケースもあります。
空室リスクが低い物件であれば、サブリースを解約することで家賃収入の向上によって利回りが改善し、キャッシュフローが良くなります。特に都心部のアクセスの良い物件であれば、空室リスクが低く入居付けも難しくないため、サブリース解約による恩恵が大きくなります。
②出口戦略が決めやすくなる
利回りが改善するということは、反対にサブリース契約時には利回りが低下することになります。
そのため、サブリース契約がセットになっている物件は公示される利回りの数値が低く、投資家に避けられる傾向にあります。また、サブリースの契約先の会社が決まっていることから、新たに購入する投資家は「このサブリース業者は信頼できるのか」というチェックから入る必要があります。
すなわち、サブリース契約が前提の物件を嫌がる投資家が一定数いるため、売却が困難になるおそれがあります。
サブリース契約を解除することで、新たな買主視点では「利回りが良好で、自分の信頼できる管理会社とやり取りができる物件」となります。不動産投資は売却という出口戦略までが重要な事業計画となるため、物件が売れやすくなることは投資家にとって大きな利点になります。
③管理会社を変更できるようになる
サブリース契約により管理をお任せできることはメリットでもありますが、リフォーム業者や交換設備の選定、入居審査などもサブリース会社に一任されます。
悪徳なサブリース会社であれば、一定のキックバック報酬を得る条件のもと、高額なリフォーム業者と結びついている可能性があります。そのため、サブリース会社の主導で行うリフォームや設備交換は、通常よりも割高になるリスクがあります。また、空室率を下げることを最優先に、家賃の支払い能力の低そうな入居希望者でも入居付けしてしまうおそれもあります。
サブリース契約を解除することで、自身の信頼できる会社に各種手続きを依頼できるようになります。不動産会社とのつながりも投資家の財産であることを意識し、優良な不動産会社と関係性を構築するようにしましょう。
サブリース契約で予想されるトラブルの原因とは?
前述した通り、サブリース契約は不動産会社側に有利なものとなっています。空室リスクを回避するためとはいえ、気軽に契約してしまうと後々トラブルに発展する可能性もあるでしょう。
中には知識の少ない大家さんを対象に、サブリースの詳細をあえて伏せたまま契約を行う業者もいるようです。
サブリースを契約する前に起こりうる問題を予測し、できるだけ回避できるよう備えておくことが大切です。
家賃保証は年々下がる
サブリース物件が投資物件として売りに出されていることも少なくはありません。中にはかなりの高利回りのものもありますが、多くの場合、その時点のみ高利回りとなっているので要注意です。
というのは、家賃保証の金額は段階的に下がっていくケースが非常に多いためです。
通常、サブリース契約は2年、5年といった期間で家賃保証の金額が下がっていきます。
一定の家賃は保証されているとはいえ、段階的に収入が下がっていくわけですので、キャッシュフローは刻々と悪化していきます。非常に事業計画のやりにくい投資物件となるでしょう。
サブリース契約をする前に、その問題をよく考慮して事業計画をたてなければなりません。
途中解約されるおそれがある
通常サブリース契約は、不動産会社から解約の要求ができるようになっています。一定の収入があるものと計画していても、途中で契約が解約されてしまうリスクをはらんでいるのです。
不動産会社が中途解約できるのは、サブリース契約が前述した「借地借家法」に従って行われるからです。そのため、普通の賃借人が賃貸契約を解除できるのと同様に、不動産会社もサブリースを解約することができます。
契約期間中でも、稼働率などの関係で不動産側から解約されることもありえるということを頭に入れておきましょう。
オーナーからの解約は簡単にできない
不動産会社からオーナーへのサブリース解約の申し入れは簡単です。しかし、オーナーからの解約は簡単ではありません。このことが、様々な問題を引き起こす一因となっています。
通常の賃貸契約は、契約の更新時期に更新を望まなければ解除することができます。
しかし、サブリースの場合、投資物件の空室リスクは不動産会社が負います。満室にするためにかける手間や費用は全て不動産会社持ちです。不動産会社が苦労して客付けして満室稼動させようとするのに、大家さんが自由に解約できるのでは、サブリース業そのものが成立しません。
サブリース会社はあくまでもその物件を借りている「借主」の立場です。正当な理由がない場合、オーナー側からの契約解除はできないとされています。よって、契約解除にサブリース会社が応じない場合は、正当事由が必要となるのです。
この正当事由は、物件個別の事情がからみ、裁判所で様々な判例が出ています。
正当事由として認められるケース
オーナー側からサブリース契約を解除できる正当事由に当たるのは、「立ち退き料を支払う」「物件を売却する」「老朽化による取り壊しを行う」「自身や親族が住人となる」といったケースです。
サブリース会社としては、収入が見込める物件のサブリース契約を解除「される」立場となるため、管理をしてきた物件からの収益を手放すことになります。そのため、サブリース会社に恩恵がなければ解約請求を通すことはできません。まず正当事由となるケースとしては、持ち主が立ち退き料を支払うことで会社の損失を補填することが挙げられます。
また、物件の売却や取り壊しを選択することで、貸主が物件の持ち主ではなくなります。この場合は物件の貸主と借主という関係ではなくなるため、サブリース契約を解除する正当事由となります。
サブリース契約がセットになっている物件は売却が困難であることは先述しましたが、サブリース契約が解除されたタイミングで物件を引き渡すことで、スムーズな売買が可能になります。例えば物件の購入検討の問い合わせが来た際に、先方には「現状はサブリース契約があるが、引き渡しの時点では契約が解除される想定である」といった内容を伝えることで、購入が成約する可能性が高まります。
正当事由にならないケース
サブリース契約解除の正当事由に当たらないのは、「利回りを向上させたい」「高く売却したい」といった持ち主側の金銭的な事情です。
サブリース契約は借主であるサブリース会社の利益を守るための契約となるため、貸主だけが得をする要求は正当事由として通らないことを覚えておきましょう。
ただし、サブリース会社が家賃や保証額を貸主に支払わず、数ヶ月単位で滞納するような事態になれば、正当事由の有無に限らず契約を解除することができます。借主に落ち度がない場合は、正当事由のもと契約を解除する交渉を行いましょう。
オーナー側の解約には時間がかかる
正当事由が認められサブリースの解約に同意を得られても、実際の解約までに時間がかかるのが普通です。
通常サブリース会社は簡単に解約されないように、契約書に「解約する場合は、半年前に書面で通知しなければならない」などの条項が盛り込まれています。 そのため、契約書には解約の6ヶ月前に書面により通告することや、そもそも解約条項がなく、解約で違約金を徴収される可能性もあります。
サブリース業というビジネススキームからしても、これは避けられない問題であり、この点についてよく理解した上でサブリースを検討すべきでしょう。
違約金が発生する可能性がある
先ほど述べたように、サブリース契約に中途解約の条項が記載されていない場合、オーナーからの解約は非常に困難です。もし中途解約の条項があったとしても、高額な違約金を支払うことが書かれている場合が多くあります。
違約金の有無については、
サブリース解約のための手順とは?
サブリースの解約を進める際には、大きく分けて3つの手順を踏むことになります。特に先述の通り、貸主側からのサブリース解約は簡単にはできず、高確率でサブリース会社との交渉が必要になります。具体的に手続きの流れを確認しましょう。
手順① サブリース契約書の解約条項を確認する
解約の手続きを進めるために、まずは契約時に交わした契約書を見直しましょう。書面に記載されている解約条項を確認します。
解約の事前通告や違約金に関する記載を確認することで、予期せぬ齟齬や出費が生じるリスクを防いで解約通知書の作成に移ることができます。
手順② サブリース会社に解約通知書を送付する
解約通知書の送付前に、サブリース会社に電話またはメールで解約の旨を通達しましょう。通達後に、解約通知書をメールまたは郵送にて送付します。
解約通知書には「物件の名称」「持ち主の氏名・住所」「サブリース会社名・所在地」といった基本的な情報、「解約通知日」「契約終了希望日」といった具体的な日程、「準じる解約条項」「違約金・立退料」があればその内容を記載します。
手順③ サブリース会社と交渉を進める
解約の合意が取れない場合、サブリース会社と交渉を行います。サブリースを専門とする弁護士や不動産会社が仲介する形で、契約解除を進めていきます。
先述のとおり、サブリース契約の解除には正当事由が求められるなど、交渉の際には法的な解釈が必要になります。不動産のオーナー1人では交渉に限界があるので、専門知識のある第三者に交渉を依頼するようにしましょう。
サブリース解約後にやるべきこと
サブリース解約の合意が取れた後は、持ち主が鍵や敷金を保管している場合、サブリース会社に移管して解約が完了します。その後は通常の不動産投資と同じように、新たな管理会社や入居者との契約が必要になります。具体的にその後の手続きを見ていきましょう。
新しい管理会社を見つける
自身で物件を管理する場合を除き、不動産の管理会社と新たに契約を行います。管理会社は自身の信頼できる不動産会社を選定しましょう。サブリース解除の際に仲介を依頼したのが不動産会社の場合、物件の管理もその会社が行っているのであれば依頼するのも一つの手です。
サブリースの解約に手間取ると、「会社とのやり取りは面倒だし全部自分で管理しよう」といった考えに至る方もいます。しかし、サブリース契約にて物件の管理を一任していた状態からすべて自身での管理に移行すると、やることが一気に増えて賃貸経営が破綻しかねません。
オーナー自身が変化に段階的に慣れるためにも、サブリース解約後は管理会社と新たに契約することをオススメします。
入居者と改めて賃貸借契約を締結する
管理会社との契約が終わった後は、管理会社が変更になった旨を入居者に通達し、新たに賃貸借契約の合意書を交わします。
基本的には管理会社が窓口に立ちますが、契約手続きの進捗はオーナーも把握しておくようにしましょう。
空室の場合は、改めて賃貸募集をかける
空室がある状態でサブリースを解約すると、空室部分の家賃保証額が入らずに収支が悪化します。できれば解約手続きを進めている間に、並行して入居付けも行うようにしましょう。
解約手続きと並行して賃貸募集を行うメリットとして、「サブリース会社の企業努力で入居付けが行えなかった物件に、オーナー自身が入居付けを行っている」という状況が、交渉に有利に働く可能性があります。サブリース会社を利用する利点が薄いことをアピールすることで、貸主に有利に解除手続きを進めることが見込めます。
ただし、賃貸募集にも物件の掲載や広告の費用が掛かる点に注意しましょう。特に違約金を支払う場合には、手元資金がショートしないように入出金管理をしっかり行うことを推奨します。
サブリースのトラブルを防ぐには?
サブリースは不動産側に有利な契約となるため、契約期間や違約金などのトラブルが発生する可能性をはらんでいます。
しかし先ほどご説明したように、空室の場合のリスクを抑え、事務作業も簡略化できるなど不動産投資の上で心強い制度でもあります。できるならばトラブルを避け、上手に利用したいところです。
では、サブリースで予想されるトラブルを避けるためにはどのような方法があるのでしょうか。
契約書をよく確認する
不動産業は、売買から賃貸まで、全て法律に基づいた契約によって成立しています。サブリース契約も例外ではありません。契約書の内容をよく確認することは、不動産投資のあらゆる場面で必要なことです。
サブリース事業を行っている不動産会社は玉石混交で、社員も様々な能力の人がいます。そのため、大雑把な説明をされてもそれでよしとしないことが重要です。
サブリース契約時には、問題になりそうな点や不明な点についてはきちんと説明を求めて、その契約に納得がいくまで確認をしていくことが重要になります。
事業計画を軽視しない
家賃保証がされる場合であっても、事業計画を軽視してはいけません。
空室リスクが大きく、客付けが上手く行かなかった場合などは、保証される家賃が大きく下がる可能性もあります。また、不動産会社がサブリース事業として失敗と判断すれば、撤退、つまり契約を途中解除されてしまうおそれもあります。
また、サブリースの場合は売却のチャンスを逃しやすいともいえます。サブリースは通常の賃貸より入ってくる金額が少ないので、投資物件としての価値は下がってしまいます。出口戦略まで考えた事業戦略を考える場合、この点も視野に入れるべきでしょう。
サブリースで家賃が保証されるとはいえ、不動産事業を行うことには変わりありません。手抜きせずにしっかりと事業計画をたてましょう。
専門家やサブリース問題解決センターに相談する
サブリース契約の解除で問題が発生した場合は、自力での解決は非常に難しいでしょう。
法律の専門家である弁護士に相談することをおすすめします。サブリース解約の問題などを多く扱っている弁護士、法律事務所を探して相談してみましょう。
また、サブリースで起こった問題を解決するための団体も設立されています。
「サブリース問題解決センター」は法務大臣認証ADR機関提携団体です。サブリースの適切な取引を普及し、健全な不動産運用を目指す活動をしています。
サブリース物件に不安や疑問がある場合には、このような団体に気軽に相談することができます。無料相談会も開かれていますので、日時を公式サイトで確認するのがいいでしょう。
また、サブリースの適正な取引を目指すための勉強会も定期的に開催されているので、サブリース物件を所有の方で不安のある方は、一度参加してみるのもおすすめです。
参考【完全版】マンション投資で失敗しないための5大知識とは!?
まとめ
サブリースは空室期間の家賃を一定額保証してくれます。不動産投資のリスクヘッジとして考えたい選択肢のひとつといえるでしょう。 しかし、一般的に不動産会社有利の契約となるため、あまり考えずに契約してしまうと、途中で解約ができなかったり、違約金が発生したりというトラブルに発展する可能性もあります。
サブリースの契約を結ぶ前にはメリット・デメリットを踏まえてよく検討し、必要があれば専門家や団体に相談することも大切です。第三者の力も借りながら、自分でも知識をつけてサブリース契約を賢く利用しましょう。