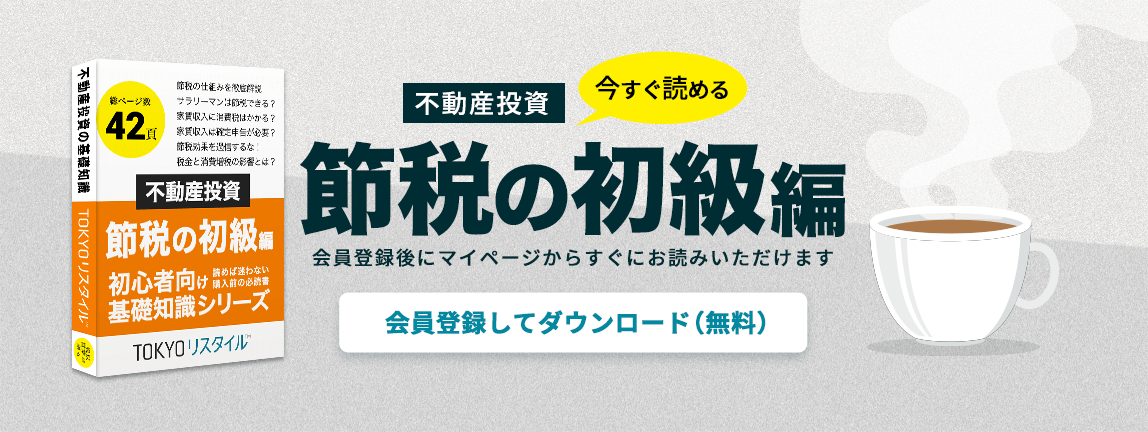最大400万円もお得に!住宅ローン控除を使いこなそう!
- 更新:
- 2023/10/25
本記事は動画コンテンツでご視聴いただけます。
マイホームを買う時に利用する住宅ローンですが、お得な控除が複数あるのはご存知でしょうか。「なんとなく減税されるイメージはある」と曖昧な知識の方も多いのが現状です。年に一度の手続きなので、わからないことが多いのも頷けます。
今回は控除を使って賢くマイホームを手に入れる為に、住宅ローン控除の基礎知識から、必要なものまでまとめて解説していきます。購入前から頭に入れておくことでお得になる仕組みもあるので、ぜひ覚えておきましょう。
住宅ローン控除とは何か
住宅ローン控除とは、住宅ローンを組んでマイホーム(新築・購入・改築・建て替え)を手に入れた際、ある条件を満たすと控除が受けられるという制度です。年末のローン残高から所得税が差し引かれ還付される「税額控除」で、国民の住宅購入を促進させる為に国が行っている制度です。
新築住宅で控除を受けるための条件
新築・中古・増築に関わらず、住宅ローン控除を受ける為には、購入した年の確定申告が必須条件になります。
会社に勤め給与をいただいている方は、初年度に確定申告をしておくと、2年目以降は会社で年末調整を行うだけでよくなります。確定申告を自分でする必要はなくなるので、比較的簡単に手続きできます。
新築住宅で控除を受けるための5つの条件
1.住み続けること
マイホームを手に入れてから半年以内に居住し、住宅ローン控除が受けられる年の12月31日まで住み続けること。
2.合計所得金額
合計所得金額が3,000万円以下であること。
住宅ローン控除を受ける年の所得で判断
3.床面積は50㎡以上
マイホームの床面積は50㎡以上あり、床面積の半分以上は居住スペースであること。
床面積とは以下のことを指します。
- 登記簿上の床面積であること。
マンションの場合、階段などの共有部分は床面積に含まない - 事務所兼住宅の場合、すべてを含めた建物の床面積になる。
- 夫婦や親子の共有名義のマイホームは、階段や通路などの共有部分を含めた床面積になる。
マンションの場合は専用部分の床面積
4.借入金や債務、10年以上の分割
マイホームを手に入れるための借入金や債務があり、10年以上の分割になっていること。
土地の借入金含む
債務の対象となるもの
- 金融機関
- 独立行政法人住宅金融支援機構
- 地方住宅供給公社
- 独立行政法人都市再生機構
- 勤務先
- 建設業者
※勤務先から借り入れる場合、金利が0.2%以外だと住宅ローン控除の対象外になってしまいます。また、身内や知人からの借り入れも、控除対象外となるので気を付けましょう。
5.特例な課税適用
特例な課税適用を受けていないこと。
住み始めた年 + 前後2年の合計5年間に、マイホームを譲渡した長期譲渡所得など
参考不動産投資ローンと住宅ローンを両立することはできるのか?
中古住宅で控除を受けるための条件
個人が中古の住宅を購入した場合、住宅ローン控除が受けられるのは以下の3つの条件を満たした時です。
①建築後に使用された家であること。
中古住宅とは基本的に完成後1年以上経過しているものを指しますが、控除を受ける条件としては、使用されていることがポイントになります。
②前の章で紹介した「新築住宅で控除を受けるための条件5つ」を満たしていること。
③現代の耐震基準を満たしていること。
以下の3ポイントのうち、どれかが当てはまる住宅であれば可能です。
耐火建築物なら築25年以内
木造などの非耐火建築物なら築20年以内であること。
耐震基準適合証明書か、耐震等級1以上の証明ができている住宅であること
どちらかの証明書があれば、築年数の基準を超えていても住宅ローン控除を受けることが可能です。
※証明書の有効期限は2年間で、日付が2年を超えていると控除対象外になるので、注意が必要です。
「既存住宅売買かし保険」に加入していること
この保険は、国土交通省指定の保険法人が提供しており、保険の加入条件が耐震基準に適合していることなので、耐震性の証明にもなります。
※既存住宅売買かし保険は、住宅の引き渡し前に取得しなければなりません。
中古住宅は耐震性がポイントになりますが、中古マンションでも同じことがいえます。
マンションの耐震診断は個人では行えず、管理組合が実施するものなので、あらかじめ耐震診断が行われている物件を選ぶようにしましょう。
増築や改築の際に控除を受けるための条件
個人が住宅ローンを使って増改築工事を行った場合、以下の5つの条件全てを満たしていることで、住宅ローン控除を受けることができます。
①自分が住むマイホーム用の増改築であり、その後も継続的に住む家であること
②増築後、登記上の床面積が50㎡以上あり、「新築住宅で控除を受けるための条件5つ」のうち1ー5が当てはまること
③以下6種類のいずれかに当てはまる工事であり、なおかつ増改築等工事証明書が発行されていること。
- 大規模な模様替えや修繕・改築・増築の工事
- 区分所有の壁・床・階段の過半を修繕または模様替えする工事
- 住宅の居室・調理室・浴室・便所・洗面所・玄関・納戸・廊下。
一室の床や壁の全部を修繕または模様替えする工事 - 耐震基準を満たす為の修繕または模様替えの工事
- バリアフリー用の改修工事
- 省エネ用の改修工事
④100万円以上の増改築工事費用であること。
⑤増改築工事費用の総額の半分以上は、住居用工事に使うこと。
以上が、住宅ローン控除を受ける為の条件一覧です、条件を満たし賢くお得にローンを返済していきましょう。
住宅ローン控除額はいくらくらいになるか
住宅ローンの控除は最大400万円まで可能ですが、あくまで最大であり下記の条件に当てはまる人のみとなります。
- ローン残高が4,000万円以上ある
- 年間の所得税と住民税が40万円を超える
この場合、上限の400万円が控除される仕組みです。
ローン残高の1%で、10年間にかけて毎年40万円ずつ
※所得税だけでは控除しきれない場合、住民税からも控除されます。
課税総所得金額の7%と13万6,500円を比べて、小さい方が上限になります。
一つ実例を見てみましょう。
- 3,000万円の物件を住宅ローンで購入した
- 年末のローン残高は2,800万円
- 所得税15万円/住民税10万円
このケースの場合、住宅ローン控除額はローン残高の1%なので28万円が控除されます。
所得税15万円は、ローン控除額28万円以内なので、全額控除されます。
更に28 - 15万の残高13万円を使って住民税にも適用できます。
住民税10万を丸々控除しても3万円余りますが、この余りに関しては他の控除に回したり、翌年に繰り越すことはできません。自身の控除額を簡単にシュミレーションすることもできるので、そうしたサイトも活用していきましょう。
住宅ローン控除の必要書類早見表(初年度用)
住宅ローン控除を受ける為に必要な書類は、初年度と2年目以降では異なります。ここでは初年度用の必要書類をまとめます。また住宅ローン控除を受ける為には、初年度に確定申告をする必要があります。覚えておきましょう。
①確定申告書
確定申告ができる期間は、翌年2月16日 〜 3月15日で、税務署か国税庁のサイトから確定申告書類を取得することができます。
確定申告とは:1月1日 〜 12月31日の1年間で所得を得た人が、所得金額に応じて納税する。
もしくは超過額を還付申告し、返金してもらう制度です。
②マイナンバー記載の住民票もしくはマイナンバーカード
マイナンバーが記載されている通知カードか、マイナンバー記載の住民票が必要です。
申告者は本人で、マイホームを購入した居住地の住民票を役場で取得しましょう。
③借入金の年末残高等証明書
12月31日時点での住宅ローン残高がわかる書類は、借り入れしている金融機関から取得することができます。
通常は10月頃に金融機関から郵送されてきますが、不安な方は早めに準備しておきましょう。
④登記事項証明書
建物と土地の登記事項証明書が必要です。
住宅ローン控除の条件である床面積50㎡を超えている建物か、この書類から判断します。
登記事項証明書はどこの法務局でも取得可能です。
⑤建築請負契約書もしくは売買契約書のコピー
新築・中古・増改築のどれか判断する為に必要な書類です。
| 建築請負契約書 | 新築・増築工事を請け負った建設会社から取得 |
|---|---|
| 売買契約書 | 売買契約した不動産会社から取得 |
⑥住宅借入金等特別控除額の計算明細書
書類に必要な項目は以下の4点です。
- マイホームの住居割合
- 住み始めた日
- 住宅ローン残高
- 計算した控除額
住宅ローン控除額の計算式は基本的に「住宅ローン年末残高 ✕ 1%」で算出できますが、より明確に出すため国税庁のホームページを参照することをおすすめします。
また、計算明細書は納税所か、国税庁のサイト(確定申告等書類作成コーナー)からも可能ですので、ご参照ください。
以上6点が必ず必要になる書類ですが、条件に当てはまる場合のみ、プラス2点の書類が必要になります。
リフォームした場合
リフォームした場合は、増改築工事を請負った建築会社から「増改築等工事証明書」を取得し提出します。
控除条件である工事内容や金額に当てはまるか確認する為です。
補助金や贈与を受けた場合
贈与を受けたり補助金を利用した場合、金額を証明する書類のコピーが必要です。補助金を交付した法人・贈与した人から取得します。
多い人では合計8点の書類が必要になりますので、申請時期から逆算して準備しておきましょう。
住宅ローン控除の必要書類早見表(2年目以降用)
2年目以降は確定申告書と、以下2点の書類を所轄税務署に提出します。
①住宅借入金等特別控除額の計算書
以下に当てはまる人は、全てを含む計算書になるので注意が必要です。
- 連帯債務がある人は、住宅借入金等の年末残高の計算明細書
- 補助金等の交付や贈与を受けた人は、取得額の計算明細書
②住宅借入金等特別控除額の計算書
借入先が2カ所以上ある人は、全ての証明書が必要になるので注意が必要です。
給与所得者の場合
サラリーマン・公務員等の給与所得者は、2年目以降は年末調整により住宅ローン控除を受けることができます。以下2点の書類を勤務先に提出してください。
給与所得者の住宅借入金特別控除申告書
確定申告をした年の10月頃「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」が税務署から送られてきます。
控除可能な残り9年分もまとめて送られてくるので、大切に保管しておきましょう。
借入金の年末残高証明書
年末残高等証明書は毎年10月頃金融機関から送られてきます。
※住宅取得資金の借り入れに限る
確定申告前後のスケジュール
住宅ローン控除申請のスケジュールをまとめてご紹介します。全体の流れを把握したい方はこちらをご覧ください。
1年目
1年目は用意するものがたくさんありますが、その分期間にも余裕があります。
10 〜 11月中
年末残高証明書が金融機関から郵送される
11 〜 2月中
- ①住民票を取得
- ②住宅ローン控除計算明細書を税務署から取得
- ③土地建物の登記簿証明書を法務局から取得
- ④税務署もしくは国税庁のサイトから確定申告を取得
- ⑤不動産売買契約書もしくは建築請負契約書のコピーを準備
- ⑥マイナンバーがわかる本人確認書類を準備(マイナンバーカードか住民票
- ⑦補助金や贈与を受けた人は金額を証明する書類のコピーを準備
- ⑧リフォームした人は増改築等工事証明書のコピーを準備
2月 〜 3月中
税務署へ確定申告申請(郵送かサイトから手続き)
10 〜 3月と期間は半年間もあり、ついギリギリまで手付かずの人が多いです。しかし、書類によっては取得するまで時間がかかるものもあるので、準備は早めに行うことをおすすめします。
2年目
2年目はスケジュールはタイトですが、手続きが簡単になっています。
10 〜 11月中
- ①住宅ローン控除証明書が、残り9年分まとめて税務署から郵送される
- ②借入金の年末残高証明書が金融機関から郵送される
11 〜 12月中
住宅ローン控除証明書と借入金年末残高証明書を添付し、会社で年末調整手続きを行う。2年目は自分で用意する書類もないので、ゆとりを持った申請手続きができるはずです。まとめ
住宅ローン控除を申請するための必要書類やスケジュールを解説してきました。住宅ローン控除を受けることができた場合、最大でトータル400万円得することになります。
所得税から住宅ローン控除額を引きますが、金額が余った場合は、住民税からも差し引くことができます。住宅ローン控除を活用して、賢く減税対策していきましょう。