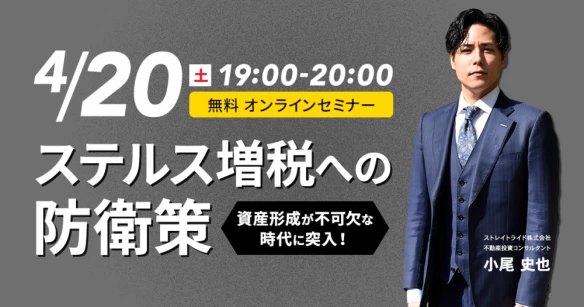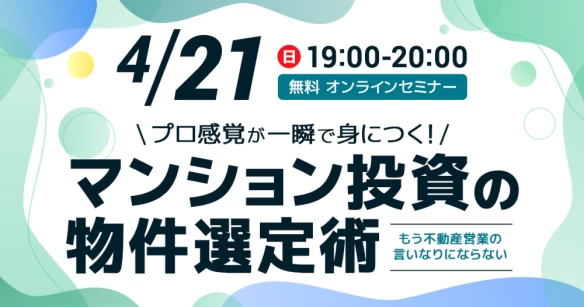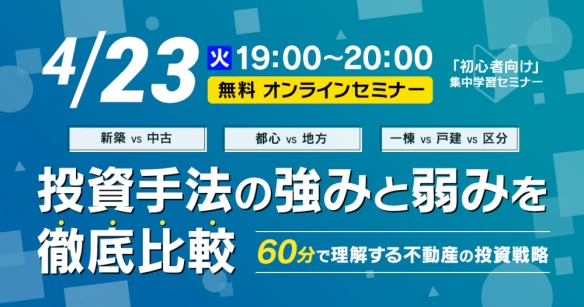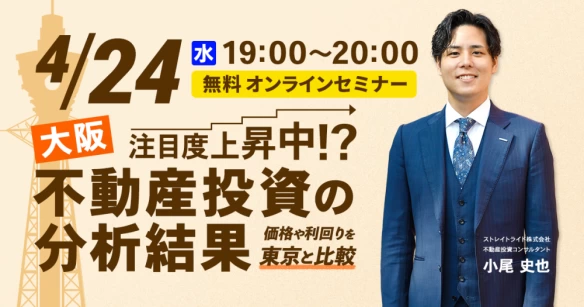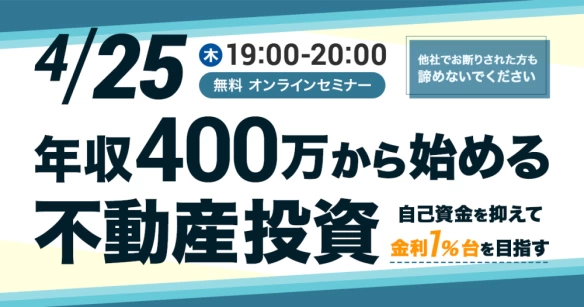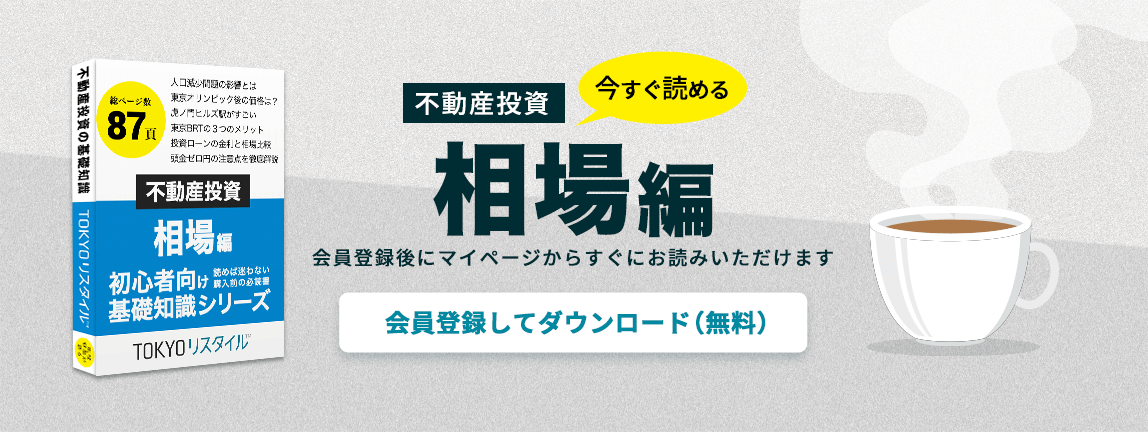不動産投資物件を5年以内に売却するのは要注意!譲渡所得税のしくみとそれでも売却すべきケースを解説
- 更新:
- 2022/06/06

不動産投資を検討している人の中には、短期的な売買で利益を上げたい方もいるのではないでしょうか。
不動産物件は簡単には購入・売却ができず、価格の高さによるリスクもあるため、短期的な売買益を狙った取引は非推奨です。加えて、譲渡所得税のしくみから、5年以内に不動産物件を売却すると損になる可能性が高くなります。
そこでこの記事では、不動産物件の所有期間により変化する譲渡所得税のしくみを解説し、それでも5年以内での物件の売却が推奨されるケースをご紹介します。短期的な売買は非推奨ですが、思考を停止して不動産を保有し続けるのがよいわけでもありません。物件の所有期間という観点から、不動産投資への理解を一歩深めましょう。
5年以内に不動産を売却すると税金が高くなる理由
この項目では、物件の所有期間によって不動産売却時にかかる税金が変化するしくみと理由をご説明します。税金の計算となると身構える方もいるかもしれませんが、複雑な計算式ではないため安心して読み進めてもらえればと思います。
譲渡所得税のしくみ
譲渡所得税とは、譲渡所得に対してかかる税金のことです。不動産物件の場合、譲渡所得は以下のように計算されます。
- 売却価格 −(購入価格 + 売却費用 + 特別控除)= 譲渡所得
売却費用には不動産会社の仲介手数料など、売却時に掛かった諸経費が計上されます。特別控除は自分が住んでいる物件(自己居住物件)の売却などが条件のため、投資用不動産では計算に含まないことが一般的です。
上記の形で計算された譲渡所得に対し、物件の所有期間によって以下のように税率が掛かります。
| 譲渡所得の種類 | 税率 |
|---|---|
| 短期譲渡所得 | 39.63% |
| 長期譲渡所得 | 20.315% |
例えば譲渡所得が1,000万円だった場合、短期譲渡と長期譲渡では約190万円もの差が生じます。ここでの税率とは「譲渡所得税 + 住民税 + 復興特別所得税」の合算となり、いずれも翌年度に納付が必要なものです(復興特別所得税は現時点で令和19年まで実施予定)。
税率にほぼ倍額の差が開くこの短期譲渡と長期譲渡について、区分の基準を見ていきましょう。
短期譲渡所得と長期譲渡所得の違い
短期譲渡と長期譲渡の区分は、物件(土地・建物)の所有期間によって決められます。
物件の所有期間が5年未満の場合は短期譲渡、所有期間が5年以上の場合は長期譲渡となります。2010年に購入した物件を2013年に売却したら短期譲渡所得、2022年に売却したら長期譲渡所得となり、先述の税率で所得税が課せられることになります。
注意点として、物件の所有期間は売却した年度の日付を1月1日として計算することが挙げられます。2010年5月1日に所有した物件を2015年11月1日に売却する場合、所有期間は5年と6ヶ月ではなく4年と8ヶ月(売却日を1月1日とするため)となります。
「長期譲渡所得で税率を計算していたら短期譲渡所得扱いになってしまった!」といった間違いがないよう、このルールについては頭に入れておくようにしましょう。
短期譲渡で譲渡所得税が高くなる理由
短期譲渡が長期譲渡よりも所得税を高く設定されている理由としては、不動産の転売による価格の高騰を防ぐ狙いがあります。
1990年前後のバブル期では、土地を短期間で転売するだけで巨額の利益を得られました。土地価格の高騰により実体経済との乖離が生じたため、大蔵省(当時の財務省)が不動産関連の融資を総量規制するなど金融の引き締めを実施し、バブル経済の崩壊に至ります。
こうした背景から、実際の物件の価値から価格がかけ離れてしまう事態を防ぐため、短期的な不動産の売買を抑制する施策として、譲渡所得の税率に差を設けたと言われています。40%近い所得税率を見ると「高すぎる!」と感じるかもしれませんが、既存の不動産投資家による物件価格の吊り上げを抑止し、若手の投資家の参入機会を作ることにも繋がっています。
税金が高くても5年以内に物件を売却すべきケース
ここまで譲渡所得税についての計算やしくみをご紹介しましたが、短期譲渡所得と長期譲渡所得の税率の差を見ると後者、すなわち物件を5年以上所有すること一択であると思うかもしれません。
しかし、税率の高さを考慮した上でも物件を5年以内に売却したほうがよい場合もあります。こちらの項目では、そうしたケースを1つずつ見ていきましょう。
現在の市場価格が高く、数年で値下がりが見込める
物件の価格査定を利用したところ現在の物件価格が充分に高いものの、数年後には大幅な下落が考えられる場合、所有期間が5年以内でも売却が最適な選択となることがあります。例えば東京オリンピック開催前は、オリンピック後の景気後退のリスクや金利上昇のおそれから、不動産の売却が推奨されたことがありました。
新築プレミアムを除き、マンションの物件価格は築10年間で80%ほどに緩やかに下落すると言われています。物件価格の急落は非常に稀なことですが、日本という国全体での景気動向を考えた際、すぐに売却したほうがよい局面が今後現れる可能性はゼロではありません。
大規模修繕などの大幅な支出が見込める
マンションの場合は築10年目、以降は12年周期が大規模修繕の目安となります。大規模修繕時には大幅な支出が想定されるため、そうした節目を前に物件を売却することが選択肢に入ります。
また、不動産を長期所有しているとデッドクロスという状態になります。デッドクロスになると帳簿上では黒字でもキャッシュフローがマイナスとなり、キャッシュを目減りさせながら不動産を運用しなければならないことがあります。この状態が長期的に続くと黒字倒産に至る可能性もあるため、デッドクロスの発生を回避するか、いち早く脱出する必要があります。
こうしたデッドクロスからの脱出のため、物件をすぐに手放すことが推奨されるケースもあります。ただし、購入後すぐにデッドクロスに至るような、築年数の長い中古物件はそもそも購入しないという手もあります。よほどメリットがない限り、築浅物件を購入することをオススメします。
デッドクロスについて、以下の記事でも詳しく解説しています。
参考不動産投資で避けたいデッドクロスとは?回避方法をメリット・デメリットと共に解説!
物件購入後に致命的な問題が発覚した
基本的には不動産会社による事前説明が義務付けられていますが、不動産購入後に「瑕疵」状態が発覚するケースも皆無ではありません。「瑕疵」とは傷や欠点のことを指し、不動産業界では4つの種類に分けられます。
土地や建物に目に見える形で現れる欠陥を指す「物理的瑕疵」、不動産の周囲環境に問題がある「環境的瑕疵」、建築基準法などの法律に抵触する欠陥を指す「法律的瑕疵」、そしてその他が該当する「心理的瑕疵」の4つです。
心理的瑕疵には、前住人の死去や物件回りでの交通事故、お墓や心霊スポット、騒音、反社会的勢力の存在による心理的な悪影響が含まれます。
不動産の売主および仲介業者が瑕疵について認識していたにも関わらず、事前に買主に告知していなかった場合は宅建業法違反となり、契約不適合責任を問うことで賠償の請求ができます。しかし、特に心理的瑕疵は基準が明確ではないため、「霊感が強い人には心霊現象が感じられる物件」といったものには事前説明の義務が発生しません。
そのため、例えば購入した物件に住人が入居した後、心霊現象を始めとする心理的瑕疵により退去が発生し、ネットの口コミにより拡散され、新たな入居者の獲得が困難になった場合。こうしたケースでは、やむを得ず売却をすることが選択肢に入るでしょう。
また、近隣の大学に通う大学生や、特定の企業に勤めるサラリーマンが住民の大半を占めるような物件では、施設の移転により空室リスクが跳ね上がります。そうしたリスクを考慮し、大学やオフィスの移転が告知されたり噂されたタイミングで、すぐに売却手続きに移ることもひとつの戦略となります。
複数の不動産を売却することで控除を活用できる
不動産物件の譲渡所得税は、事業所得や給与所得との損益通算(利益と損失を相殺すること)ができません。そのため、事業所得で赤字計上することで譲渡所得税の減税を見込むことは、税制上不可能となります。
事業所得や給与所得と損益通算ができるのは長期譲渡所得に該当する居住用財産(自分で住んでいる物件)のため、不動産投資においては当てはまらないと考えてよいでしょう。
一方、例えば不動産Aの売却により損失が生じた場合、その損失額を不動産Bの譲渡所得の金額から控除することはできます。つまり、複数の不動産の売却により損失と利益が発生し、控除を活用することで総合的な利益が見込めるのであれば、短期間での売買に踏み込むのは理に適っています。
複数の不動産を所有しているケースのため初心者向けではなく、総合的な収支判断となるため難易度が高い事例ではありますが、こうした形で控除が活用できることは頭の片隅に入れておくとよいでしょう。
まとめ
この記事では、5年以内に不動産を売却すると税金が高くなる理由や、それでも短期売買が推奨されるケースをご紹介しました。
短期売買が推奨されるケースを見ると、利益の獲得よりも損失を抑えるための選択が大半であることが分かると思います。そのため、基本的にはこうした事例に該当しないような物件を購入することが推奨されます。
具体的には購入後すぐにデッドクロスに至らないよう築古の物件は避けたり、瑕疵物件を購入しないよう事前の物件・周辺の環境のチェックを欠かさないようにしましょう。また、大学や企業の移転による空室リスクを避けるべく、特定の住民層に依存する物件を避けるのも有効です。
売却益に掛かる所得税率の差20%は決して安いものではなく、不動産投資で利益を得るためには計画性をもって中長期的に運用することがベストであると言えます。不動産投資の中長期的な計画は、専門家による協力のもと、個々人のご予算や属性に合わせて立てることをオススメします。当社の不動産コンサルタントの力を、ぜひご活用ください。