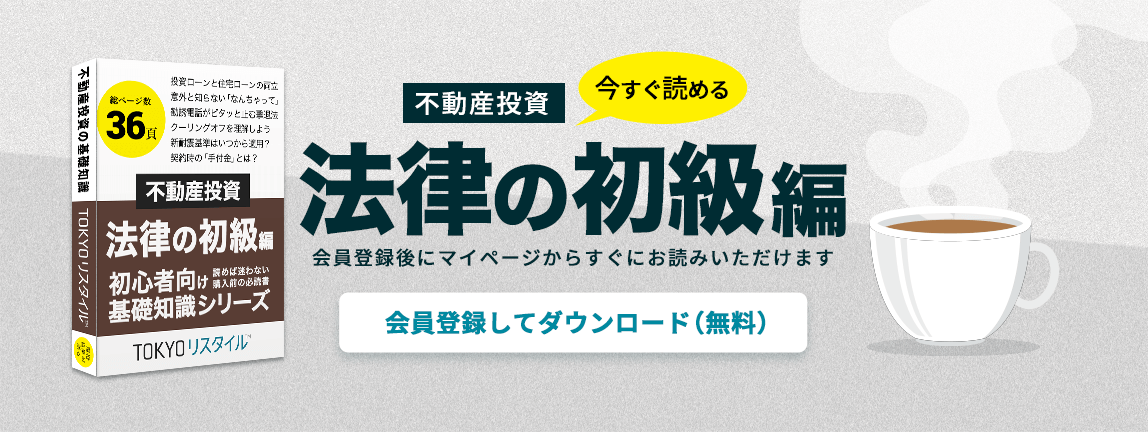【最新版】130万円の壁とは?問題点や不動産所得との関係を徹底解説!
- 更新:
- 2023/07/12

家族の扶養に入っている場合、「130万円の壁」「150万円の壁」「103万円の壁」と言われる収入の上限額が存在します。多くの場合、これらの壁は給料を受け取っている方に該当します。しかし、不動産投資で収入を得ているケースにも密接に関わっているのです。
そこで今回は「130万円の壁」を中心に「○○万円の壁」について解説します。「130万円の壁」の問題点や、不動産投資の収入を得ている場合に「130万円の壁」はどう関係するのかも説明します。壁を越えてしまった場合の手続きも紹介するので、不動産投資と「130万円の壁」の関係が気になる方は、ぜひ最後までお読みください。
- 目次
- 扶養には税法上の扶養と社会保険上の扶養がある
- 不動産投資の収入と所得の違い
- 不動産投資での所得の計算方法
- 不動産投資の収入がある場合に扶養から外れる条件
- 不動産投資の収入で130万円の壁を越えた場合の手続き
- まとめ
扶養には税法上の扶養と社会保険上の扶養がある
扶養とは、「収入や所得・年齢など一定の制限を満たすことで、税金や社会保険の優遇が受けられる仕組み」を指します。扶養は「税法上の扶養」と「社会保険上の扶養」の2種類です。それぞれでの条件について、詳しく解説します。
①税法上の扶養
税法上の扶養とは、家族の扶養に入ることで所得税や住民税が減税される仕組みのことを言います。税法上の扶養に関わる「壁」は、103万円と150万円です。ここからは、いわゆる「103万円の壁」と「150万円の壁」を超えるとどうなるかについて解説します。
103万円の壁を超えると所得税が増える
「103万円の壁」は、給与を受け取っている方が対象です。給与を受け取っている方は「給与所得者」と呼ばれ、下記の控除を受けられます。
- 基礎控除48万円 + 給与所得控除55万円 = 控除総額103万円
受け取った給与のうち、控除額である103万円を超えた部分を「給与所得」と呼びます。収入から103万円を超えた所得に対して所得税が加算されるため、「103万円の壁」と呼ばれているのです。
参考【2023年最新版】所得控除の控除額と計算方法を理解して節税を極めよう!
一方、不動産投資の収入は「不動産所得」となり、給与所得とは別の計算式になります。「不動産所得」は、不動産投資の収入から基礎控除額の48万円と必要経費を引いた額です。不動産所得が基礎控除額の48万円を超えると、超えた分に対して所得税が加算されます。
- 不動産所得 = 不動産収入 -(基礎控除48万円 + 必要経費)
収入が100万円前後ある場合、住民税も加算されます。加算対象額の目安は100万円前後です。収入がいくらあると住民税が加算されるかは、自治体によって変わります。詳しくは、お住まいの自治体に確認してください。
150万円の壁を超えると配偶者控除がなくなる
「150万円の壁」も、給与を受け取っている方が対象です。
配偶者がいる場合、配偶者の給与が150万円までであれば「配偶者控除」と呼ばれる38万円の控除を受けられます。給与収入が150万円から210万円までの間は、配偶者特別控除の対象です。配偶者特別控除は、収入に応じて控除額が減っていきます。
不動産投資で収入を得ている場合、不動産投資の収入から費用を引いた不動産所得が48万円以下であれば配偶者控除が適用されます。ただし、配偶者の所得が1,000万円以下であることが条件です。
不動産所得が48万円以上だと、配偶者控除特別控除の対象となります。配偶者特別控除は所得額が増えるにつれて減少し、133万円以上の所得になると配偶者特別控除がなくなります。
| 所得金額 | 控除を受ける本人の所得が900万円以下 | 控除を受ける本人の所得が900万円以上950万円以下 | 控除を受ける本人の所得が950万円以上1,000万円以下 |
|---|---|---|---|
| 48万円以上95万円以下 | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
| 95万円以上100万円以下 | 36万円 | 24万円 | 12万円 |
| 100万円以上105万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 |
| 105万円以上110万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 |
| 110万円以上115万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 |
| 115万円以上120万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 |
| 120万円以上125万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 |
| 125万円以上130万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 |
| 130万円以上133万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
②社会保険上の扶養
社会保険上の扶養とは、一定の収入以下の場合、家族が加入する社会保険に「被扶養者」として加入できる制度です。社会保険上の扶養から外れると、家族の加入する社会保険から脱退し、自分で国民健康保険・社会保険に入る必要があります。
社会保険上の扶養から外れる金額は、原則として130万円です。但し、一部106万円となるケースもあるため後述します。
130万円の壁を超えると社会保険上の扶養から外れる
収入が130万円を超えると、社会保険上の扶養から外れ、自分で国民健康保険・社会保険に入らなければいけません。これが「130万円の壁」です。
社会保険上の扶養は収入額により判定されます。収入には、雇用保険で支給される失業手当や傷病手当金、通勤にかかる交通費も含まれます。給与収入が130万円を超えただけでなく、不動産投資で得た収入が130万円を超えても扶養から外れてしまうのです。
不動産投資や事業をしている場合は、収入から除外できる費用があります。どの費用を除外できるかは、社会保険組合により違います。130万円の壁を越えたくない場合、加入している社会保険組合に問い合わせて、どの費用が計上できるかを調べておきましょう。
会社によっては106万円で社会保険の扶養から外れる
勤務先の規模や契約形態によっては、年収が106万円以上になると社会保険上の扶養から外れる場合もあります。
社会保険上の扶養から外れ、社会保険に加入する条件は、次のとおりです。
- 従業員数101名以上の企業に勤めている
- 週の所定労働時間が20時間以上30時間未満
- 月額賃金が88,000円以上
- 2ヶ月以上雇用される見込みがある
- 学生ではない
なお、2024年10月からは、従業員数51名以上の企業に勤めている場合に、社会保険上の扶養から外れるようになります。
参考厚生労働省
「130万円の壁」の問題点
社会保険上の扶養から外れる「130万円の壁」の問題点は、次のとおりです。
- 所得で計算する税法上の扶養と比べて、収入額が上昇する
- 社会保険料の支払いが発生するため、年収150万円くらいまでは手取り収入が急激に落ちる
税法上の扶養の計算では基礎控除額があるため、収入が多くても扶養のままでいられる場合があります。しかし、社会保険上の扶養では、基礎控除がなく、さらに傷病手当や失業手当と言った各種手当や交通費も収入に含まれます。そのため扶養から外れやすいことが問題点です。
自分で社会保険料を支払う場合、月に2万円前後の支払いが増えます。月にして20万円程度支払額が増えるため、130万円を少し超える程度だと、額面は増えたのに社会保険上の扶養に入っていた頃より手取りが減るという逆転現象が起こるのです。
社会保険に入っても手取り額が増えるのは、年収150万円からと言われています。社会保険に加入し厚生年金を支払うことで将来の年金額が増えるとはいえ手取り収入が減ることも、「130万円の壁」が持つ問題点であると言えます。
参考【2023年】社会保険料がやばい!値上げの理由や対策、不動産投資への影響を解説
不動産投資の収入と所得の違い
給与を受け取っている場合、税法上の扶養は「所得」で計算され社会保険上の扶養は「収入」で計算されます。不動産投資でも同様です。不動産投資の収入と所得の違いは、次のとおりです。
- 収入 = 不動産投資で手元に入ってきた金額の総額
- 所得 = 収入 ー 必要経費
不動産投資の収入に含まれるもの
不動産投資での収入源は、主に家賃収入です。家賃とともに受け取る敷金、礼金、更新料、共益費、保証金も収入に含まれます。
不動産投資での所得の計算方法
不動産投資の所得は、次の式で計算します。
- 不動産所得 = 収入 ー 経費
次の項目で、不動産投資で経費として計上できる費用を紹介します。
不動産投資で計上できる経費
不動産投資の費用の中で経費にできるのは、次の4種類です。
| 費目 | 備考 |
|---|---|
| 各種税金 | 固定資産税・登録免許税・不動産取得税・地価税・特別土地保有税・事業所税など |
| 損害保険料 | 火災保険・傷害保険・盗難保険・損害賠償責任保険など |
| 修繕費 | 資本的支出にあたる部分は経費計上不可 |
| 減価償却費 | 建物・自動車などの固定資産に対して計上 |
各種税金の中で、所得税や住民税は経費にできません。不動産投資ではなく、不動産を持つ個人にかかる税金だからです。
修繕費の中には、「資本的支出(CAPEX)」と呼ばれる費用があります。資本的支出とは、壊れた部分を修繕するのではなく、資産価値を高める修繕の費用です。資本的支出は修繕には当たらないため、費用として計上できません。
次の3種の出費は、資本的支出に該当します。
- 建物の避難階段の取付けなど、物理的に付け加えた部分の金額
- 用途変更のための模様替えなど、改造または改装に直接要した金額
- 機械の部分品を特に品質または性能の高いものに取り替えた場合で、その取替えの金額のうち通常の取替えの金額を超える部分の金額
不動産投資の収入がある場合に扶養から外れる条件
不動産投資で収入を得ている場合、所得が48万円を超えると、超えた所得に対し所得税が課税されます。そして、所得が133万円を超えた時点で配偶者特別控除がなくなり、税法上の扶養から外れてしまうのです。
不動産所得が48万円を超えた場合と133万円を超えた場合について、それぞれ詳しく解説します。
①不動産投資の所得が48万円以上
給与所得者の場合、基礎控除と給与所得控除を加えた控除額が103万円です。したがって、給与収入が103万円を超えた分に対して所得税がかかります。
一方、不動産投資の収入には給与所得控除がありません。不動産投資の収入から必要経費を差し引いた「所得」が48万円以上になると、48万円を超えた所得に対して所得税がかかってしまうのです。
不動産投資の収入を得ている場合は、収入103万円ではなく所得48万円以上から所得税がかかる点に注意しましょう。
| 給与収入がある場合 | 103万円以上の収入 |
| 不動産投資の収入がある場合 | 48万円以上の所得 |
②不動産投資の所得が133万円以上
不動産所得が48万円から133万円までは、給与所得と同じく、下記の表に応じた配偶者特別控除が受けられます。しかし、不動産所得が133万円を超えた時点で、配偶者特別控除がなくなります。
| 所得金額 | 控除を受ける本人の所得が900万円以下 | 控除を受ける本人の所得が900万円以上950万円以下 | 控除を受ける本人の所得が950万円以上1,000万円以下 |
|---|---|---|---|
| 48万円以上95万円以下 | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
| 95万円以上100万円以下 | 36万円 | 24万円 | 12万円 |
| 100万円以上105万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 |
| 105万円以上110万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 |
| 110万円以上115万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 |
| 115万円以上120万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 |
| 120万円以上125万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 |
| 125万円以上130万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 |
| 130万円以上133万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
パート所得がある場合は不動産投資の所得と合算して計算する
パートで働いていてかつ不動産投資の収入がある場合、下記の方法で計算した所得に対し、控除が計算されます。
- 給与所得を計算する(給与所得 = 給与収入 ー 給与所得控除55万円)
- 不動産所得を計算する(不動産所得 = 不動産収入 ー 費用 ー 基礎控除48万円)
- 給与所得と不動産所得を合算し、総所得を出す
例えば、給与所得が10万円で不動産所得が40万円だった場合、総所得は50万円です。税法上の扶養の上限となる48万円を超えているので、所得2万円分に対して所得税がかかります。
③不動産投資の収入が130万以上
不動産投資の収入が130万以上になると、社会保険上の扶養から外れ、自分で国民健康保険か社会保険に加入する必要があります。給与を受け取っている場合と同じ「130万円の壁」です。
加入している社会保険によっては、実収入から必要経費を差し引いた額を収入にできる場合もあります。どの経費を差し引けるのかは、社会保険組合によって変わるので自分で確認しましょう。
不動産投資の収入で130万円の壁を越えた場合の手続き
不動産投資の収入が130万円を超えてしまった場合、社会保険の扶養を外れて自分で国民健康保険や社会保険に加入する必要があります。
自分で国民健康保険へ加入する際に、必要な手続きを紹介します。
①「健康保険被扶養者(異動)届」「国民年金第3号被保険者関係届」の提出と国民健康保険加入
最初に、被扶養者の削除の届け出をします。社会保険に加入している本人(被保険者)の扶養者として社会保険に加入している方を「被扶養者」と呼びます。被扶養者を削除するには、加入している健康保険組合に次の書類を提出します。
- 健康保険被扶養者(異動)届
- 国民年金第3号被保険者関係届
詳しくは、日本年金機構のサイトをご覧ください。
次に、社会保険を脱退し国民健康保険に加入する場合の手続きです。市区町村役場の窓口で、国民健康保険の加入手続きをします。マイナンバーカードがあれば、デジタル庁管轄の「マイナポータル」からの電子申請も可能です。
②確定申告
不動産所得が年間20万円以上の場合は、該当年度の翌年2月16日〜3月15日までに確定申告が必要です。確定申告は、電子申告もしくは紙面で最寄りの税務署に提出します。
確定申告をしないと、延滞税や無申告加算税といった追徴課税が課されます。不動産所得が年間20万円を超える場合は、必ず確定申告を行いましょう。
参考【2023年最新版】家賃収入は申告していないとバレる?バレない?
③住民税・所得税の納付
確定申告により住民税・所得税の支払いが発生する場合があります。住民税の金額が確定すると、自宅に税額や納税方法の通知が来ます。住民税は年4回の支払いです。所得税は、確定申告後3月15日までに支払います。
住民税や所得税は、払込用紙を使って現金納付する他に口座引き落としができる場合もあります。どの方法でも、納付を忘れることがないように気を付けましょう。
まとめ
「130万円の壁」「103万円の壁」といった控除は、不動産投資の収入にも大いに関係してきます。不動産投資で得た収入や所得はどの壁に該当するのか把握し、損しないようにすることが大切です。
いわゆる「○○円の壁」は働き控えを起こすことから問題視されているため、今後変わる可能性があります。当社でも、常に最新の情報を提供していきます。不動産投資や節税対策で不安な点がございましたら、ぜひ当社の無料相談をご活用ください。

この記事の執筆: 堀乃けいか
プロフィール:法律・ビジネスジャンルを得意とする元教員ライター。現役作家noteの構成・原案の担当や、長野県木曽おんたけ観光局認定「#キソリポーター」として現地の魅力を発信するなど、その活躍は多岐に亘る。大学および大学院で法律や経営学を専攻した経験(経済学部経営法学科出身)から、根拠に基づいた正確性の高いライティングと、ユーザーのニーズに的確に応えるきめ細やかさを強みとしている。保有資格は日商簿記検定2級、日商ワープロ検定(日本語文書処理技能検定)1級、FP2級など。
ブログ等:堀乃けいか