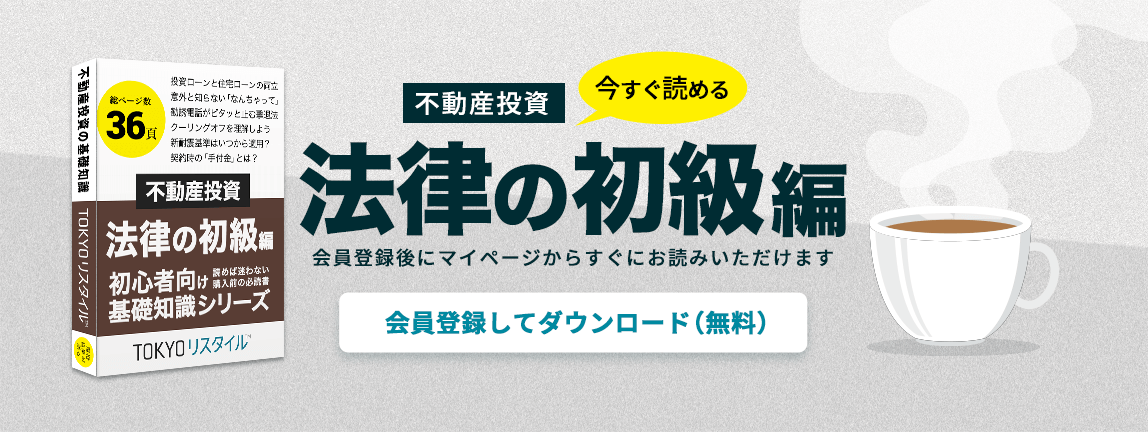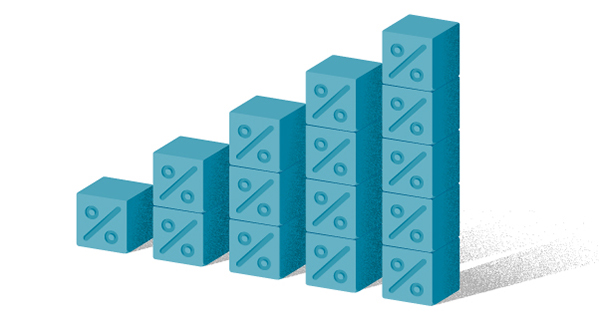銀行や証券会社が倒産したらどうなる?金融商品のセーフティネットについて解説
- 更新:
- 2023/06/19

2024年から新しいNISAが始まるように、国を挙げて国民に投資を呼びかける時代となり、預貯金だけではない資産形成が一般的になりました。民間の銀行や郵便局、証券会社、保険会社など、様々な会社に大切な資産を預ける一方、万が一、お金を預けている金融機関が破綻したらどうなるのか不安に感じることもあるでしょう。
実は日本の多くの金融商品においてはセーフティネットが設定されているため、たとえ金融機関が破綻しても預けている資産は守られる仕組みになっているのです。ただし、一部の例外はあるため注意が必要です。
この記事では、金融商品のセーフティネットについて解説します。
金融商品のセーフティネットとは
そもそもセーフティネットとは、英語のSafty-netをカタカナに直したもので、万が一落下しても受け止められるよう、安全のために設置された網を指す言葉でした。そこから転じて、金融商品のセーフティネットとは、金融商品を扱う機関の経営が破綻した場合に、預金・投資商品・保険などの顧客の財産を守るために作られた仕組みを指します。
証券会社や保険会社、銀行など、それぞれの業界によって作られた制度は異なりますが、万が一のことがあっても財産が守られるようになっています。ただし、安全のための網の間から落ちてしまうことがあるように、金融商品のセーフティネットの対象とならない場合もあるため、注意が必要です。
証券会社のセーフティネット
株式や債券を扱う証券会社では、分別管理が原則とされているため、投資者の利益は守られます。ここでは、証券会社のセーフティネットについて解説します。
分別管理
分別管理とは、証券会社の資産と投資者の投資資金や有価証券を別々に管理しておくことを言います。分別管理をすることは証券会社に義務付けられているため、たとえ証券会社の経営が悪化し、資金が足りなくなったとしても、投資者の資産に影響はありません。
分別管理の対象となるのは投資者の株式や債券だけでなく、売買代金などの現金も含まれるため、投資者の資産はすべて安全に管理されていると考えて良いでしょう。証券会社の破綻後も、投資者は自分の資産の返還を受けることが可能です。
投資者保護基金の補償額
証券会社が破綻した際に、分別管理が行われていなかったなどにより、投資者の資産に不利益が生じるおそれもあります。そんな時は、投資者保護基金が損失を補償してくれます。分別管理と投資者保護基金により、二重のセーフティネットが用意されているということです。
投資者保護基金では、顧客1人につき1,000万円まで補償されます。国内で営業する証券会社では投資者保護基金への加入義務があります。
尚、銀行でも投資信託などの金融商品を扱うことは珍しくありません。ただし、銀行では分別管理は義務付けられているものの、投資者保護基金の補償対象にはならない点に注意が必要です。
補償対象外となるもの
投資者保護基金の補償対象となるものは、1顧客あたり1,000万円までの資産のため、1,000万円を超えた分は対象外となります。
また、外国為替証拠金取引(FX取引)などのデリバティブ取引や、外国市場デリバティブ取引に関わるものは補償対象外です。
株や債券の発行会社が倒産した場合
証券会社ではなく、株や債券を発行している会社が倒産した場合、それらの株や債券を保有していた投資者は大きな損害を受けることになります。
一般的に、株などの発行会社が倒産した場合、市場での売却ができなくなります。利息の支払いや元本の償還が行われなくなることもあり、価値はほぼ無くなってしまうでしょう。このような損失はどこからも補償されません。
株や債券を保有している場合は、常に発行会社の動向を確認し、倒産する前に売却するなど、適切な判断が必要となります。
証券保管振替機構(ほふり)が破綻した場合
「ほふり」と呼ばれる証券保管振替機構は、証券会社から投資家の株などを預かって集中保管し、名義書換や受け渡し、発行会社への通知などを行います。ほふりは非常に重要な役割を果たしていることから、金融庁などからの監督を受け、問題が見つかればすぐに是正される仕組みになっています。
万が一ほふりが破綻したとしても、株などの権利は全て投資家にあるため、投資家が損害を受けることはありません。
保険会社のセーフティネット
保険会社が破綻した場合でも、セーフティネットが用意されているため、加入者の保険契約は守られます。
ここでは、保険会社のセーフティネットを解説します。
保険はどうなるか
保険会社が破綻しても、原則として保険契約は継続されます。保険は一時の利益のために入るというよりも、長い期間や将来の出来事を見据えて加入しているものであるため、破綻と同時に解約や返金となった場合は、本来の利益が守られないからです。
破綻した生命保険会社の契約を引き継ぐ「救済保険会社」が現れた場合は、保険契約は全て救済保険会社に移行します。救済保険会社が現れなかった場合は、「保険契約者保護機構」または同機構が運営する子会社が保険を引き継ぎます。
ただし、保険契約が救済保険会社などに移行して一定期間が経つ前に解約した場合、本来の解約返戻金から減ることがあります。保険会社が破綻したからと言って慌てて解約しないことが大切です。
保険契約者保護機構
死亡保険や医療保険など、人の生存または死亡に関して保険金が支払われる生命保険の場合は、「生命保険契約者保護機構」がセーフティネットとなります。また、偶然生じた事による損害に対して保険金が支払われる損害保険の場合は、「損害保険契約者保護機構」が加入者を保護します。
国内で営業する生命保険会社や損害保険会社は、保険種類に応じて保険契約者保護機構への加入が義務付けられています。ただし、少額短期保険業者は保険会社に該当しないなど、保護の対象とならないケースもあります。
保護の範囲
保険契約は会社の破綻後も続きますが、責任準備金の削減が行われることがあります。多くの場合は破綻時の責任準備金の90%までが補償されますが、これは保険金や年金などで加入者に支払われる金額の90%が補償されている訳ではありません。
責任準備金とは、生命保険会社が将来の保険金や年金などの支払いに備えて準備しているお金のことです。責任準備金が削減されることにより、保険契約の予定利率の引き下げなど、条件変更が行われることもあります。
銀行のセーフティネット
預金としてお金を預けている銀行が破綻した場合でも、セーフティネットが用意されています。ここでは、銀行のセーフティネットを解説します。
保護の範囲
一般的に利用されることの多い普通預金や当座預金、定期預金、定期積立などに関しては、1金融機関につき、1人あたり元本1,000万円までとその利息が保護されます。
たとえば、破綻したA銀行に1人で複数の支店などに口座を所有していて、その元本の合計が1,000万円を超えていた場合、保護されるのは元金の合計1,000万円とその利息のみに限定されます。ただし、家族それぞれの名義で別の口座を所有している場合は、各個人ごとに1,000万円までの元本と利息分が保護されます。なお、一度預金が保護された後、別のB銀行が破綻した場合は、B銀行に預けている元本1,000万円までと利息も保護されます。
現金が1,000万円より多くある場合でも、各銀行の預金額を1,000万円以下に分散しておけば、確実に預金を保護できるでしょう。
保護の対象外となるもの
銀行が破綻した場合に保護の対象となるものは国内にある預金に限られます。つまり、海外支店の預金は保護の対象外のため、返ってくる保証はありません。また、外貨預金や譲渡性預金、保護預かり専用以外の金融債、元本補填契約の無い金銭信託も保護の対象外です。
ペイオフとは
ペイオフとは、預金者保護のために行われるもので、破綻した金融機関に代わって預金保険機構が預金を払戻す制度のことです。
1971年に制度が創設されて以来、2010年の日本振興銀行の経営破綻によって初めてペイオフが発動されました。ペイオフが終結された時点では、元金1,000万円を超えて保護の対象外となった預金の39%に当たる約41億円分がカットされたとのことです。
このように、ペイオフが発動されれば1,000万円を超える預金の全てが返ってこない訳ではありませんが、確実に保護される保証はありません。
ゆうちょ・農協・漁協などの貯金の場合
民間の銀行と同様に、ゆうちょや農協、漁協などの貯金も、元金1,000万円とその利息は保護されます。ゆうちょでは他の銀行と同様の預金保険制度に加入しており、農協や漁協では、農水産業協同組合貯金保険という類似の制度に加入しています。
尚、銀行や信用金庫、信用組合などに預けるお金は「預金」、ゆうちょ銀行や農協、漁協に預けるお金は「貯金」と表しますが、内容に差異はありません。
住宅ローンはどうなるか
金融機関にお金を預けるだけでなく、住宅ローンなどで借り入れをしている方も多いでしょう。ここでは、金融機関が破綻した際に住宅ローンなどの借入金はどうなるのかを解説します。
預金とローン残債を相殺できる
破綻した銀行の預金がローン残債よりも多い場合、預金残高を利用してローンを返済する「相殺」が可能です。特に、預金保護制度の対象外となる1,000万円超の預金がある場合は、保証されない部分の預金をローン残債と相殺すれば、損をすることは無くなります。
ただし、破綻した銀行が自動的に相殺をしてくれる訳ではないため、自分から相殺の手続きを行う必要があります。
住宅ローンは他の銀行に引き継がれる
住宅ローンは不動産という確かな担保があり、銀行にとっても貸し倒れしにくい優良債権であるため、金融機関が破綻しても他の銀行が引き継がれやすいのが特徴です。住宅ローン引き継ぎ後は、破綻した金融機関ではなく、新しい金融機関に返済を続けることになります。
ただし、新しい銀行ではローンの契約内容が変更されるおそれもあるため、注意は必要です。
過去の事例
破綻ではありませんが、過去にシティバンクが個人向け住宅ローンおよび不動産担保ローンの取り扱いを中止した際には、旧UFJ銀行(現三菱UFJ銀行)に債券を譲渡し、金利などの条件変更はせずにローンが引き継がれました。
更に、旧日本振興銀行が経営破綻した際にはイオン銀行が受け皿となり、完全子会社化したため、ローンも合わせて引き継ぎました。一部借入金については、法律で定められた利息を超過していたとして、返金等の対応もされています。
参考旧日本振興銀行からのお借入れにかかるお利息等の一部ご返却について
このように、借り入れをしている金融機関に破綻などが起きたとしても、他の銀行が引き継がれた事例があります。
まとめ
この記事では、証券会社や保険会社、銀行における金融商品のセーフティネットについて解説しました。
主な金融商品にはそれぞれのセーフティネットが設定されているため、金融機関などが万が一破綻しても、大きな損害は出ないことが一般的です。ただし、セーフティネットの対象外となる商品等もあり、必ず保護されるとは限りません。投資や預金をする際には、セーフティネットの対象であるかどうかもリスクの一環として事前に把握しておくと良いでしょう。
不動産投資でローンを組む際のセーフティネットについてなど、不動産投資にご不安がある場合は当社コンサルタントまでお気軽にご相談ください。

この記事の執筆: 丸岡花
プロフィール:宅地建物取引士・FP検定2級を持つ主婦ライター(2児の母)で、300本以上の不動産関連記事の執筆実績を有する。得意ジャンルは不動産・税金・英語・育児。不動産が大好きで、不動産関連のニュースや法改正、市況のチェックが日課となっている。豊富な知識に裏付けされた独自性の高い切り口と、公的機関や学術論文などの1次情報に基づく正確性の高い文章に定評がある。元バックパッカーで旅行・キャンプをこよなく愛し、過去に20か国以上を訪問した経験を持つ。保有資格は宅建士・FP2級に加え、TOEIC895点(米国居住経験あり)、秘書検定1級、保育士など多岐に亘っている。
ブログ等:シュフリーランス