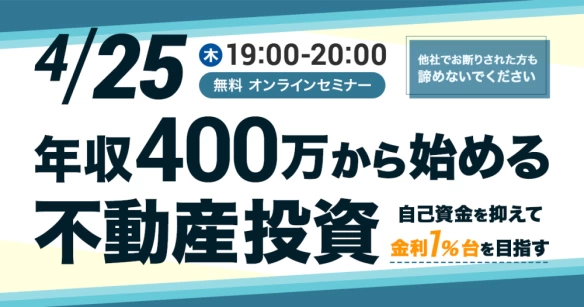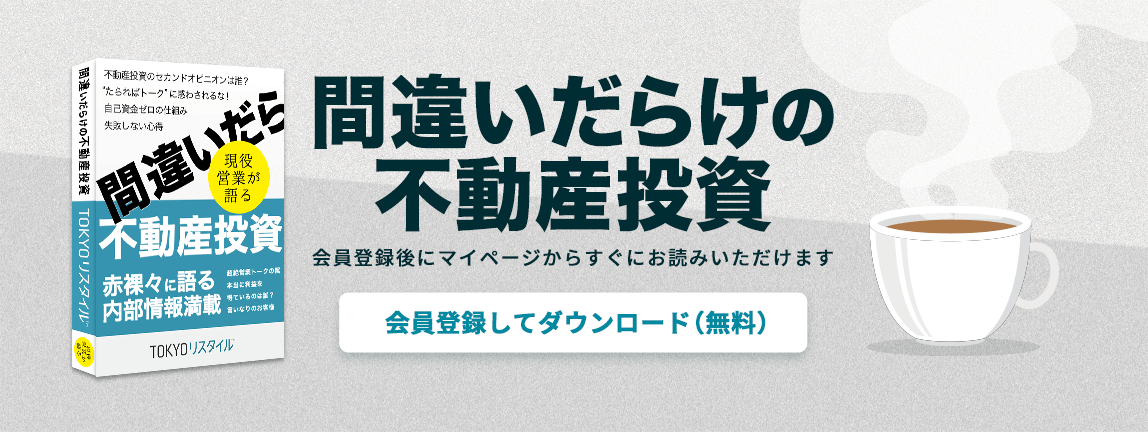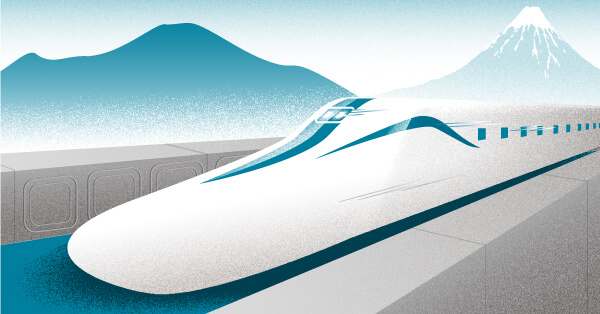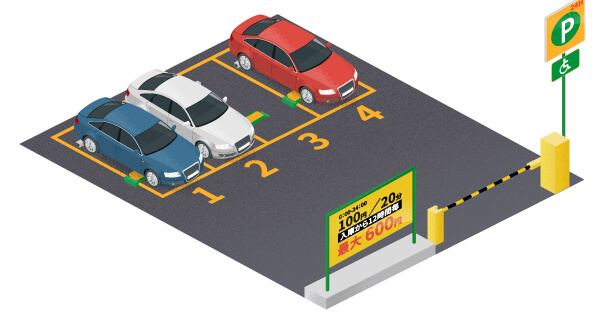年金問題の救世主?不動産投資のススメ
- 更新:
- 2021/09/10

令和元年の6月3日、金融庁より衝撃的なレポートが公表されました。その報告書の名前は「高齢社会における資産形成・管理」というものです。報告書の中では、「このまま日本の高齢化が進めば、各世帯の収入は年金だけで賄うことはできず、平均2,000万円の金融資産がないと破綻する」という非常にセンセーショナルな問題が提起されています。
この報告書の内容は、テレビや新聞で大々的に取り上げられたこともあって、多くの方が耳にされたことがあるでしょう。
そこで本記事では、まず報告書で取り上げられている内容についてまとめるとともに、その対策として、不動産投資が非常に有効であることをお伝えしたいと思います。
金融庁報告書の内容について
金融庁により公表された報告書には、現在の日本の置かれた状況、問題点についてどのように取り上げられているのでしょうか?問題点は、大きく以下のように分けられます。
- 日本社会の高齢化
- 収入、支出の変化
- 金融資産の減少
1つずつ、内容を見ていきましょう。
問題①:日本社会の高齢化
まず1つ目の問題点は、日本社会が高齢化しているという点です。例えば、1950年頃の男性の平均寿命は約60歳でしたが、現在は約81歳にまで上昇しています。さらに報告書によると、現在の60歳の人の1分の1が、95歳まで生きるという記載もあり、まさに「人生100年時代」を迎えようとしているわけです。
この高齢化の状況に、さらに少子化問題が拍車をかけ、世代ごとの人口分布を表す人口ピラミッドは、高齢者が最も多い「つぼ型」となってしまっています。
この高齢化と少子化の相互作用により、若い世代の社会福祉費用の増大など、様々な問題が生じるようになってしまっている、というのが一つ目の問題になります。
問題②:収入、支出の変化
報告書には、日本の問題点として「日本人の収入・支出の変化」が提起されています。まず収入面に着目すると、バブル崩壊の「失われた20年」以降、低水準の賃金が継続しており、金融庁作成のグラフを見ても、ほぼすべての世代で収入が低下していることが読み取れます。
なんらかの景気の劇的な回復がない限り、今後もこの傾向が続くことになりそうです。
また、支出の面ではどうでしょうか。こちらも、バブル期以降、継続して減少傾向にあり、特に30代から50代の支出の低下が顕著に表れています。重い税負担や保険料の支払いなども、この傾向になんらかの影響があるかと思われます。
ニュース等でも取り上げられましたが、高齢の無職夫婦は、収入源の年金額よりも支出の方が5万円程多く、赤字となってしまうことが予想されています、
このように、現在の日本人の収入・支出は、総じて減少傾向にあることが報告されているのです。
問題点③:金融資産の減少
3つ目の問題点は、日本人の保有金融資産の減少があります。これまでわが国では、退職後の老後生活は、大きく退職金と年金給付という二つの軸によって賄われてきました。ところが、近年この退職金給付が、徐々に減少を続ける傾向にあるのです。
まず、退職金給付制度のある企業は、バブル期には約92%もあったにもかかわらず、2018年には80.5%にまで落ち込んでいます。さらに、退職金の平均給付額は約1,700万円~2,000万円となっており、ピーク時から3割~4割も減少しているというのですから驚きです。
昨今の雇用の流動化問題も併せて考えると、おそらく今後も、退職金給付額や制度導入企業の割合が減少することが予想されます。
問題点②でもお伝えしたように、老後の高齢夫婦の収支状況は、常に約5万円の赤字状態が継続する見込みで、その後30年間生きるだけで約2,000万円もの金融資産を取り崩す必要が出てくると言われています。今の退職金給付額の減少傾向を見ても、人生100年時代を生きていくためには資産額が明らかに足りていないことがわかるかと思います。
対策としての不動産投資
ここまで、金融庁が公表した報告書について、そこで取り上げられている問題点を大まかにまとめました。報告書ではこれらの問題の対策として、簡単に言うと「自助」を勧めるようなまとめをしたために、一種の社会問題として「炎上」してしまったのです。
ただ、日本の公的機関が何度も有識者会議を行い、その結果として公表した文書ですから、内容は正しく、おそらく多くの日本人が今のままの年金に頼る人生設計では破綻してしまうことが危惧されています。 文書では、対策としてidecoや株式、債券などへの投資を呼び掛けているのみですが、実は不動産投資も、自身の老後生活のための有効な対策になると言えます。以下では、不動産投資を行うことのメリットについて、お伝えしたいと思います。
メリット①:投資額にレバレッジを利かすことができる
レバレッジとは、またの名を「てこの原理」とも言い、自身の投資額以上の資産を運用することが出来るということを意味しています。不動産投資では、金融機関からの借り入れを行って物件の購入することが出来るため、例えば自己資金をほとんど使わなくても、数千万円の物件を保有することが出来ます。
詳細はレバレッジの解説ページに記載していますが、このレバレッジ効果によって、自己資金を効率的に使って資産形成のスピードを上げることができる、というのは大きなメリットして挙げられます。
参考不動産投資の強み?レバレッジのメリットとデメリットとは?
メリット②:将来的な不労所得を得ることが出来る
良く誤解されがちなことですが、一般的な不動産投資のイメージとして、「リスクが高くギャンブル性が高い」と考えられていることもあるようです。しかし実際は、ギャンブルなど賭け的な要素はあまりなく、コツコツと長期的で堅実な資産運用です。
借入があるうちは、家賃収入額から毎月の返済をきっちりと返していき、完済した時点で毎月の家賃収入が不労所得として入ってくる、というイメージになります。
もちろん、不動産の中でも一発逆転のような儲け話もないことはないのですが、王道のマンション投資のセオリーとしては、上記の通りコツコツと運用するのが肝要です。しっかりと運用して融資を完済すれば、マンション一戸でも数万円の不労所得が入ってくる計算ですから、2戸保有しておけば、金融庁の報告書にある「毎月5万円の赤字」問題はクリアできます。
メリット③:手が掛からず、リスクの管理もしやすい
金融庁の報告書では、資産運用の方法として不動産との表記はありませんでしたが、私個人としては、一般的な会社員の方には株式よりも不動産の方がお勧めです。というのも、株式はどうしても市場の状況にリアルタイムで影響を受けるため、常に市場を観察しておく必要がありますし、株式価値の急落などの事態が起きたとしても、仕事中では対応できないという問題もあります。
よく聞く話として、「株をやっていると、気になってしまって仕事に手がつかない」というのも、会社員の方にあまり向いていないと考える理由の一つです。
一方で不動産は、入居者がいれば毎月安定した家賃収入がありますし、急な問題が発生しても不動産業者に管理を依頼しておけば、自身の手を煩わせることもありません。空室リスクについても、購入時にしっかりと物件を調査し、賃貸ニーズの高いエリアを選択することでリスクを抑えることが出来るのです。
まとめ
本記事では、金融庁が発表して世間を賑わせた報告書について、提起されている日本の問題点を大まかにまとめるとともに、その対策として不動産投資が適している、ということをお伝えしました。
上述した通り、不動産投資は決してギャンブルではなく、数年後、数十年後に向けてコツコツと資産を拡大することのできる堅実な投資手法です。今回の報告書を読んで将来に不安を抱かれた方、不動産投資に興味はあるもののいまいち全体像が分からず踏み出せない、という方。弊社では、不動産投資コンサルタントが個別相談会を実施し、不動産とはなにか、どのような融資プランが良いのか、リスクを抑えるためには何を考えるべきか、など懇切丁寧にアドバイスをしております。
是非お気軽にお問い合わせください。