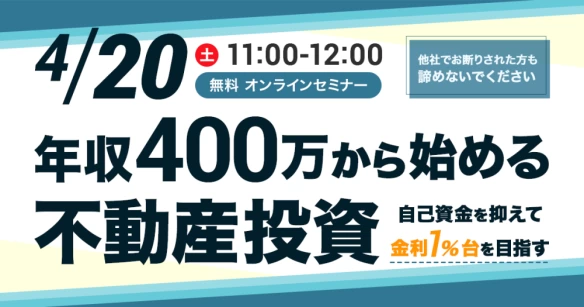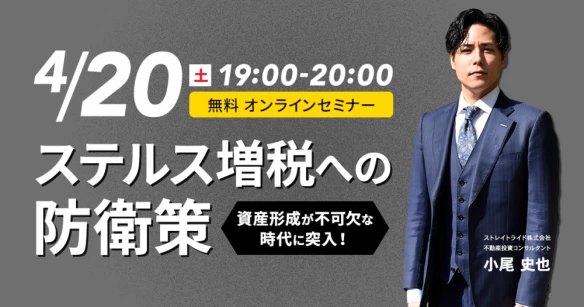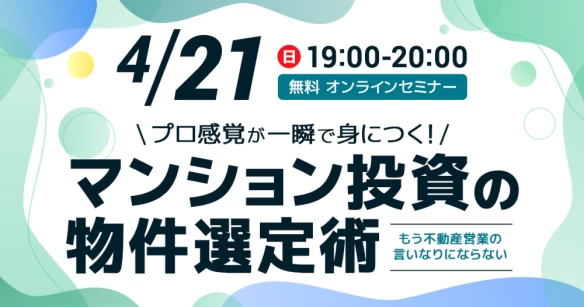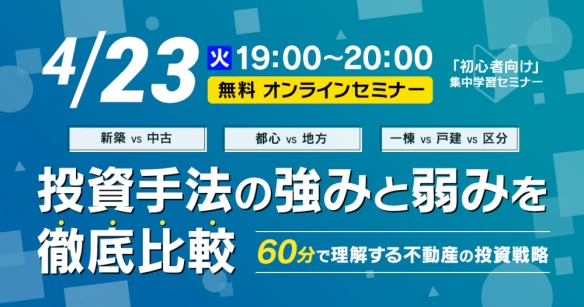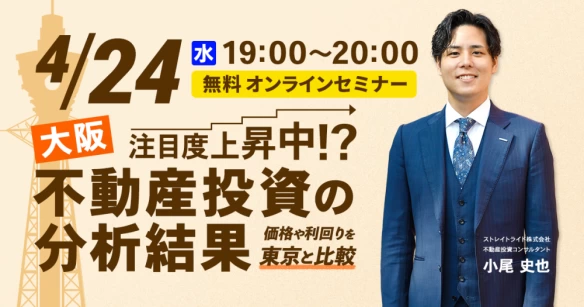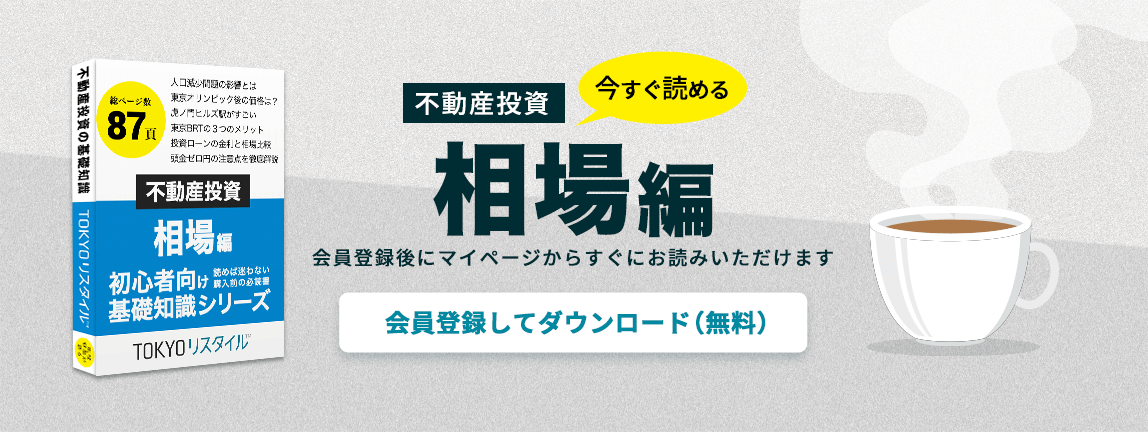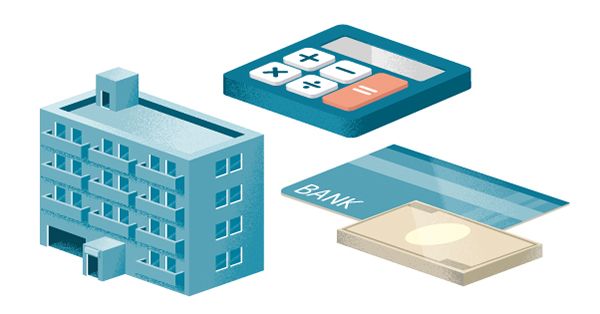不動産投資への影響は!?ロシアによるウクライナ侵攻を徹底解説!
- 更新:
- 2022/11/22

本記事では、ウクライナ危機の最新の状況についてお伝えするとともに、資源不足によるインフレの発生によって、不動産投資の重要性がますます高まっていることを解説していきます。
2022年2月24日、ロシアのプーチン大統領はウクライナへの侵攻を宣言しました。当初は2日間で陥落すると見られていたウクライナの首都キエフ(キーウとの記載もありますが、本記事ではキエフと表記します。)ですが、想像以上のウクライナ軍の抵抗とロシア軍内部のトラブルによって、侵攻から1か月が経過した3月27日現在でも、未だに戦闘が続いている状況です。
テレビやSNSを通じて、ウクライナの破壊された都市や避難する現地の人々の姿が生々しく報道される一方で、地理的にも遠い場所での出来事であるからか、我々が平和に生きるこの世界で、このような惨事が発生しているということを現実味をもって認識しかねているという方も多いのではないでしょうか。
しかし一方で、ロシアによるウクライナ侵攻に対抗する形で、アメリカや欧州諸国が行っているロシアへの経済制裁は、ロシア以外の全世界にも大きな影響を及ぼしており、もちろん日本にも大きな影響が出てくることは間違いないと言えるでしょう。
本記事を読まれている読者の方々の中にも、「今回のウクライナ危機によって日本にどんな影響が出てくるのか」「日本国内での不動産投資の環境に変化はあるのか」といった疑問をお持ちの方がいらっしゃるかと思います。
そこで本記事では、まず今回のウクライナ危機の背景や最新の状況について整理するとともに、今回の戦争が不動産投資にどのような影響を与えるかについて解説をしていきたいと思います。
そもそもなぜ、ロシアはウクライナに侵攻したのか?
ではまず、今回のウクライナ危機が起こった背景について解説をしていきたいと思います。全体像を把握して頂くために、ウクライナの歴史や、最近のウクライナをめぐる欧州とロシアの関係性について見ていきましょう。
ウクライナの歴史
この両国の関係が非常に複雑なものであるということは多くの人々に感覚的に認識されている一方で、どのくらいの長さの歴史が存在するのかという点はそれほど知られていないようです。そこでまずは、簡単に両国の歴史について触れていくことにします。
驚くべきことに、この両国の関係は1,000年以上も前から始まっています。9世紀後半に、現在のキエフにバイキングがキエフ公国を設立したことを皮切りに、10世紀~12世紀にかけて欧州の大国の1つにまで躍り出ました。しかしながら13世紀にモンゴル帝国によって滅ぼされると、その後は複数の国家による支配下に置かれることとなります。
20世紀に入ると旧ソビエト連邦共和国の一部となり、第二次世界大戦ではドイツとソ連の悲惨な戦闘の主戦場となるなど、大きな被害を被ったほか、1986年には領内のチェルノブイリ原子力発電所で事故が起き、多数の人々が命を落すこととなりました。
ウクライナ独立後も続く問題
このようにソ連の一部として厳しい環境に置かれていたウクライナですが、1991年のソ連崩壊に伴って独立を宣言し、独立国としての歩みを開始します。しかしながら、ウクライナは独立国となった後も、ロシアと欧米の狭間で大きな困難に直面することとなりました。
先述の通り、ソ連崩壊後に独立を果たしたウクライナですが、ロシアからは言語や文化が似ており、かつ同じスラブ人であることから、ロシアの「兄弟国」として引き続き勢力圏の1つと認識され続けました。一方欧米諸国からは、ウクライナを対ロシアの最前線にしようという思惑から、NATOに組み入れようとする動きも出ており、これらロシアと欧米諸国の思惑に引きずられる形で、ウクライナ国内でも親ロシア派と親欧米派とが対立するという構造が出来上がったのです。
そして2014年、親ロシア派で知られたヤヌコーヴィチ大統領がウクライナ国民からのデモにより失脚したことを受け、それに危機感を抱いたロシアが、ロシア系住民の保護という名目で武装した集団をウクライナのクリミアに送り込み、形式的な住民投票を経て一方的に自国に編入してしまったのです。
ここまでご覧いただいたように近年のウクライナは、「ロシア系住民の保護」を名目に領土の切り崩しを試みるロシアとの深刻な緊張状態にありました。それが結果として、今回のロシアによるウクライナ侵攻に繋がったのです。
では次に、侵攻から1か月強が経過した3月27日時点での状況を見ていくことにしましょう。
善戦するウクライナ軍と、低迷するロシア軍
本章では、現在のウクライナ危機の状況について見ていくことにしましょう。
キエフ防衛戦の現状
下の画像が、3月24日時点での戦況です。赤枠がロシア軍により掌握された地域を表しています。
ご覧いただけるように、2014年にロシアによって一方的に併合されたクリミア半島は既にロシアの占領下に置かれており、また東方の要衝であるマリウポリも厳しい状況に置かれています。しかしながら、最も重要といわれる首都キエフ攻略は、遅々として進まず、それどころか一部の地域ではウクライナ軍の反攻を受けて撤退を余儀なくされているようです。
元々ロシアは、2日間でキエフを陥落させ、親ロシアの傀儡政権の樹立を狙っていると見られていました。にもかかわらず、ウクライナ軍は引き続き頑強に抵抗を続けており、ロシア軍の犠牲者は既に1万人を超えているとも言われています。
ウクライナ善戦の3つの理由
ウクライナ軍が予想以上に善戦をしているのには、いくつか理由があります。それは、
- ①ゼレンスキー大統領の存在
- ②欧米諸国による支援
- ③ロシア軍の不備
です。
まずやはり何といっても、ゼレンスキー大統領の存在が挙げられます。元々俳優出身のゼレンスキー氏は、選挙時には圧倒的な国民の支持を得て選出されていたものの、近年は支持率を大きく落としており、ロシアによる侵攻の直前の2022年2月には20%台を記録していました。
しかしながら、ロシア侵攻後の2月末には、大統領支持率90%超という圧倒的な数値を叩き出しています。その理由は、SNSなどを活用して、一歩も引かない強気な姿勢を打ち出していることにあると言えるでしょう。彼のこうした姿勢は、ウクライナ国民だけでなく全世界の人々に感銘を与えており、軍の士気の向上や欧米諸国からの支援の取り付けに大きな成果を出しています。
ロシアによる侵攻前には、俳優業出身で政治経験なしのゼレンスキー氏が大統領の座に就くことに対する不安の声も上がっていたようですが、その雄姿は第二次世界大戦でイギリス国民を率いたチャーチル元大統領とも重ねられており、ゼレンスキー氏は「現代版チャーチルだ」との声も上がっています。
思えば、冷戦末期のアメリカ大統領ロナルド・レーガンも、元々はハリウッド映画俳優でした。眉目秀麗で堂々たる演説を繰り広げたレーガン大統領は、対ソ連での「強い大統領」として国民からの絶大な支持を得ていました。国家の非常事態では、俳優出身という特徴が、大きな強みとなるのかもしれません。いずれにせよ、ゼレンスキー氏の存在がウクライナ軍の善戦の大きな理由となっているのは間違いないでしょう。
ウクライナ善戦の2つ目の理由は、欧米諸国による支援です。アメリカだけでなく、ドイツやフランス、イギリスといった欧州諸国がこぞってウクライナに支援物資や資金面での支援を行っています。
中でも特に効果を発揮しているのが、対戦車兵器ジャベリンの存在です。ジャベリンは1996年にアメリカが製造を開始した個人携帯型の対戦車兵器であり、分厚い装甲を有するロシアの最新鋭の戦車でも貫通するほどの高い威力を誇っています。
このジャベリンの特に優れた点は、扱いが非常に容易な点と、精密誘導システムを備えている点です。これまで戦闘経験のない住民も戦闘に参加している今回のウクライナ戦争において、素人でも直ぐに使用することのできるこのジャベリンの存在は、ロシア軍にとって大きな脅威です。また、発射前に攻撃目標をロックしておけば、自動で追尾する精密誘導システムを備えているため、発射して直ぐ隠れることが出来ます。これらの優れた機能により、実際にロシアの戦車部隊が壊滅的な被害を受けているという報道もあります。
ジャベリン以外にも、個人携帯式の対空ミサイル「スティンガー」により、ロシアの戦闘機が複数撃墜されているとの報告が出ています。
参考ウクライナ軍「独創的な防空態勢」で善戦…米欧提供の兵器、機動的に運用 (msn.com)
このように、欧米諸国からの手厚い支援は、ウクライナの戦闘力を大幅に高めていると見ることが出来るでしょう。
そしてウクライナ善戦の3つ目の理由が、ロシア軍の不備という問題です。今回のウクライナ侵攻が起こるまで、ロシアの戦闘力はかなり高いと考えられていました。というのも、ロシアは年間約670億ドルという、米中印に次ぐ膨大な軍事費を投じており、かつクリミア併合で暗躍した優秀な特殊部隊の存在から、「ロシアが本気を出すと恐い」という印象が世界的に持たれていました。
しかしながら、少なくとも今回のウクライナ侵攻に限って言えば、ロシア軍は士気や通信、戦術などの点で複数の不備が見受けられます。ウクライナ侵攻前には、国境周辺に約15万人もの兵士が集まっていましたが、既に10%以上の戦力を喪失していると報じられています。
参考なぜロシア軍は弱いのか…ウクライナの頑強な抵抗を支える対戦車砲「ジャベリン」は勝利の象徴(SmartFLASH) - Yahoo!ニュース
中でも特に大きな問題が、ウクライナがロシアの通信の大半を傍受できているという点です。ロシア軍の通信が暗号化されておらず、軍事行動がウクライナ側に筒抜けになっていると見られており、実際に多くのロシア軍将官が狙い撃ちをされています。
3月27日時点で、計7名の将官が戦死したと報じられており、ロシア軍の指揮命令系統に大きな問題が生じていると見られています。
参考ロシア軍将官7人死亡、1人解任 西側当局 (msn.com)
このように、様々な要因が重なり、当初不利と見られていたウクライナ軍が予想をはるかに超える強さでロシア軍相手に善戦しているのです。欧米諸国からの経済制裁もあって、軍事作戦の継続に問題が生じていると言われるロシアですが、今後どのような展開となるのか、しっかりと注視する必要がありそうです。
それでは次に、今回のウクライナ危機が日本の不動産投資に与える影響について見ていきましょう。
ますます高まる不動産投資の有効性
本章では、今回のウクライナ危機が不動産投資にどのような影響を与えるかという点について解説をしていきたいと思います。結論から述べると、今回の危機を通じて、不動産投資の重要性がより高まったと言うことが出来るでしょう。理由は、これまでロシアやウクライナに依存していた資源の供給が減少することによってコストプッシュインフレが起こるため、インフレに強いと言われる不動産投資が資産の防衛手段としてますます有効となるからです。
これだけでは分かりにくいので、1つずつかみ砕いて説明をしましょう。大きく分けると①資源の供給の減少→②コストプッシュインフレの発生→③不動産投資の有効性の高まり、の3ステップが存在します。
ステップ①:資源の供給の減少
世界各国によるロシアへの経済制裁は、ロシアを確実に蝕みつつあります。ロシアに進出する世界企業が一斉に撤退したほか、カントリーリスクの増大に伴うルーブルの貨幣価値の棄損など、枚挙にいとまがありません。これまでロシアと取引をしていた世界の企業の多くに、何かしらの悪影響が出ることは避けられないでしょう。
しかしながら、最も重大な問題は、やはりエネルギー問題といえます。ご存じの通り、ロシアは石油や資源エネルギーの主要な産出国であり、これらの供給が停滞することによって、世界各国でエネルギー価格の上昇が発生することとなります。
実際に日本でも、ウクライナ危機の影響などにより、電気料金やガス料金の値上げが行われています。
参考4月分の電気料金 過去5年間で最高水準 燃料の輸入価格が上昇 | NHK | ウクライナ情勢
このように資源価格が上昇することによって、ステップ②のコストプッシュインフレに繋がります。
ステップ②:コストプッシュインフレの発生
コストプッシュインフレとは、生産コストの上昇により引き起こされるインフレのことを意味します。そもそもインフレとは、商品やサービスの全体的な価格が上昇することを指しており、これには需要が高まることにより生じるデマンドプルインフレと、供給が減少することにより生じるコストプッシュインフレの2種類が存在します。
今回のウクライナ危機に端を発するインフレは、資源の供給が減少するコストプッシュインフレに分類されており、「悪いインフレ」とも呼ばれます。その理由は、エネルギー価格の上昇に伴う企業の生産活動のコスト増加により、物価が上昇する一方で、賃金が増加しないため、国民の生活が圧迫されるからです。
また、インフレによる影響の一つが、「お金の価値の目減り」です。これはどういうことかと言うと、仮にAという商品がこれまで100円で買えていたにも関わらず、インフレに伴う物価の上昇によってAの価格が200円となってしまった場合、自身が持つ100円の価値が半分になってしまうということです。
つまり、インフレの発生によって、物価だけが上がっていくため、銀行に預金していた現金の価値が目減りしてしまうのです。
これが、不動産投資の価値が高まるという大きな背景となってきます。
ステップ③:不動産投資の有効性の高まり
ステップ②で述べたように、インフレの発生によって現金の価値が目減りするという問題が出てきます。実はこの問題への有効な対策となるのが、不動産投資なのです。
これだけでは理由がわかりづらいと思いますので、不動産投資がなぜインフレに強いのかについて、具体的な例を用いて解説をしていきます。
1,000万円を現金で運用(貯金)するAさんと、不動産投資で運用するBさんがいたとします。ここで、インフレの影響を年間20%と仮定してみましょう。これはつまり、これまで100円で買えた商品が、1年後には120円出さないと買えなくなるということを意味します。
まずAさんが保有する現金は、1年後には20%目減りするために、800万円の価値になります。ここで重要なのは、あくまで額面上は1,000万円のままですが、お金の価値が800万円に下がってしまっているということです。
一方不動産投資を行ったBさんを見ていきましょう。Bさんは、1,000万円を自己資金として9,000万円の借入れを行い、合計で1億円の不動産投資を行いました。ここで、インフレによる影響が出てきます。それは物件価格の上昇です。
インフレの影響で、1億円で購入した物件が、1年後には1億2,000万円に上昇します。物の価値が上昇するのがインフレですから、物件の価格も当然上昇するわけです。
仮にローン残高に変更が無かったと仮定した場合、保有する物件価格の1億2,000万円からローン額の9,000万円を差し引いた3,000万円が残り、インフレ率を考慮した実質の手残りは2,400万円となります。
実際には、インフレ率の影響が直ちに物件価格に反映されるわけではないため、もう少しマイルドに効果が出てくるわけですが、それでもインフレにおける不動産投資の効果がお分かり頂けたのではないでしょうか。
まとめ
本記事では、2022年2月24日に始まったロシアによるウクライナ侵攻について、両国の歴史から最新の戦況、ウクライナが善戦している理由について解説するとともに、今回の危機が日本国内での不動産投資に与える影響について見ていきました。
特に不動産投資についていえば、資源高によるインフレの発生により、インフレに強いと言われる不動産投資の重要性がますます高まっていることをお伝えしました。
まるで地球の反対側で起きているように思いがちな今回の戦争ですが、実は我々の生活とも密接に関係していることがお分かり頂けたかと思います。他にも、世界で起きている事象がどのように不動産投資に影響を及ぼしているのか疑問に思われた方は、是非弊社コンサルタントまでご連絡頂ければと思います。