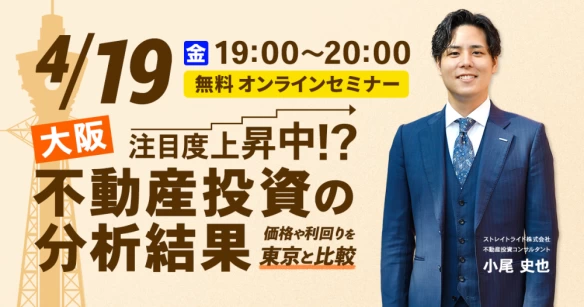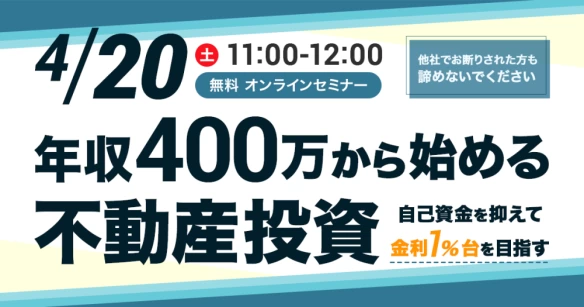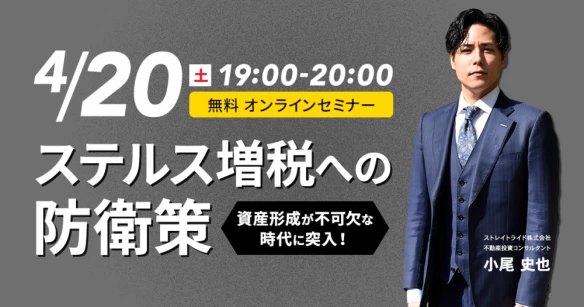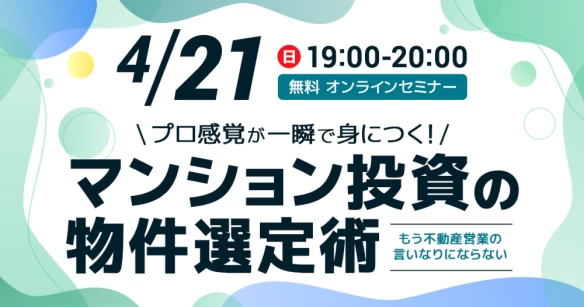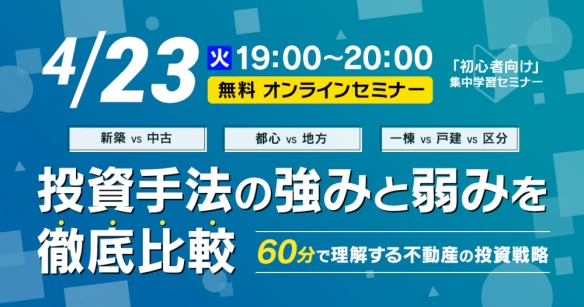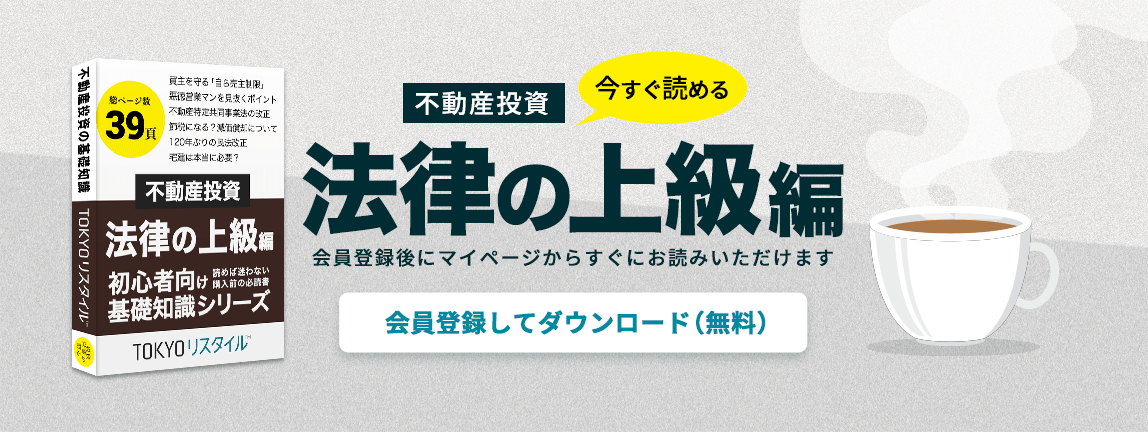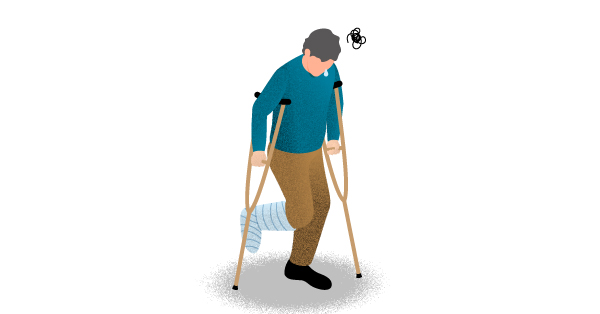不動産特定共同事業法(不特法)の改正の影響
- 更新:
- 2021/09/10

不動産特定共同事業法(不特法)とは、出資を受けて行う不動産取引事業の仕組みを定めた法律です。不動産特定共同事業には様々な規制があり、参加できる業者が限られていたのですが、2017年の法改正によって規制が緩和されました。
そこで、不動産投資家には知っておいてほしい不動産特定共同事業法の改正のポイントとその影響について説明します。
不動産特定共同事業法(不特法)とは
不動産特定共同事業法とは、1994年に公布された法律です。この法律が制定された背景には、1980年代後半のバブル経済があります。地価が高騰したために、個人投資家でも投資できるよう、共同で不動産投資が行えるように法整備がなされました。
この法律の目的は、不動産特定共同事業の健全性と透明性を確保することにあります。そのため、事業を許可制にし、事業遂行に関する債務を明確化することが記載されています。
不動産特定共同事業法は2013年にも改正されています。一定の要件を満たした特別目的会社(SPC)は許可を受けなくても届け出を行うだけで不動産特定共同事業を実施する仕組み(特例事業)が、この法改正により生まれました。具体的には、不動産取引に関する業務と不動産特定共同事業契約の勧誘に関する業務とを、許可を受けた不動産特定共同事業者に委託する必要があります。
2017年の不動産特定共同事業法の改正では、次に説明する「適格特例投資家」という、限定した投資家のみを対象とした場合には不動産特定共同事業を実施できるという特例措置が設けられています。
不動産特定共同事業法の2017年改正のポイント
個人投資家が不動産投資を行えるように、不動産特定共同事業法の改正は、上記の2013年の改正を含めて数度にわたり行われています。というのも、不動産特定共同事業者に許可されるには、原則的に取引業の許可を受ける必要があるので、SPC(特別目的会社)が特定共同事業者に許可されるのは事実上困難だったためです。
このような背景から、特定共同事業者の規制緩和が期待されるようになりました。2017年3月に不動産特定共同事業法の改正案が閣議決定され、同年6月に公布されています。
不動産特定共同事業法の改正されたポイントは4つです。順に説明していきます。
適格特例投資家限定事業の創設
1つめは、適格特例投資家限定事業の創設が可能になったことです。
適格特例投資家限定事業とは、事業参加者が不動産投資の知識や経験を有している投資家のみで構成されている事業を指します。この場合、運営者は不動産特定共同事業の許可が不要になり、届け出だけで十分になります。
不動産特定共同事業者に許可されるためには、先述のとおり原則的に宅地建物取引業の許可を受ける必要があります。しかし、他の宅地建物取引業者に運用業務を委託する場合には、宅地建物取引業の許可が不要になります。また適格特例投資家限定事業では、特例事業のようにほかの不動産特定共同事業者に運用業務を委託する必要はなく、宅地建物取引業者に委託するだけで十分であることも特徴に挙げられます。
2017年の法改正以前の不動産特定共同事業者の認定には、国土交通大臣または都道府県知事によって行なわれていました。そのため、SPCは資本金が1億円以上であるといった厳しい許可条件を満たすことができず、不動産特定共同事業を実施することができませんでした。実際、不動産特定共同事業に認定される事業者は、大手不動産会社がずらりと並ぶありさまでした。
ところが2017年の不動産特定共同事業法の改正後は、規制緩和が進み、中小企業でも特例事業者として認定されるケースが増えています。
小規模不動産特定共同事業の創設
2つめは、小規模不動産特定共同事業の創設です。小規模不動産特定共同事業とは、個人投資家の出資総額を一定規模以下に抑えた事業のことです。地方創生や地域活性への貢献を促すため、小規模不動産への投資を幅広い事業者が参入しやすいように、不動産特定共同事業法は改正されました。
クラウドファウンディングの制度整備
3つめはクラウドファンディングの制度に対応できるように、不動産特定共同事業法を改正したことです。クラウドファンディングとは、インターネットを介してたくさんの人から集金する仕組みのことです。銀行や投資家から集金するのではなく、不特定多数の人から集金するのが特徴で、急速な広がりを見せるようになりました。
クラウドファンディングで集金した資金は、新規事業や投資のために用いられます。クラウドファンディングには大きく分けると2種類あります。1つめは、寄付型のように支援者への見返りを求めないタイプです。2つめは、投資型のように支援者への見返り(リターン)を提供するタイプです。この場合、金銭以外もモノやサービスを見返りとして支援者に提供することが可能です。日本におけるクラウドファンディングは、ほとんどが後者のタイプを採用しています。
従来の不動産特定共同事業法では書面の取引しか想定していなかったのを、クラウドファンディングに対応した整備を行いました。これにより、インターネット上で契約書面を電子的に交付することができるようになり、また出資についても、クラウドファンディング業者が参入できるように制度の整備が行なわれるようになったのです。
特例事業における事業参加者の範囲の拡大
4つめは、特例事業において事業参加者の範囲が拡大されたことです。
前に説明したように、2013年の不動産共同事業法の改正では、届け出をするだけで不動産特定共同事業を実施できる特例事業の制度が設けられました。ところが、特例事業に参加できる投資家は、特例投資家に限定されていました。
2017年の不動産特定共同事業法の改正により、事業参加者が特例投資家のみで構成されている特例事業の範囲を、一定の金額を超える宅地の造成や建物の建築に関する工事などを行なう場合に限定しました。その一方で、それ以外の特例事業については、特例投資家以外の一般投資家も事業に参加できるようになりました。
不動産特定共同事業法改正の目的
2017年の不動産特定共同事業法の改正の背景には3つのポイントがあります。
1つめは、近年空き家や空き店舗といった問題が政策課題として残されている点です。不動産特定共同事業法の改正により、空き家や空き店舗といった小規模の不動産を対象とする不動産特定共同事業において、さらに規制緩和を行なっています。不動産特定共同事業法の改正が、不動産市場の活性化を促すものであることは容易に想像できます。
2つめは、不動産特定共同事業に参画できるのは事実上大企業に限られていた点です。小規模不動産特定共同事業の創設により、中小企業でも小規模不動産への投資が可能になりました。
3つめは、クラウドファンディングのような新しい資金調達方法に対応できるように、制度的な対応を行なう必要があったという点です。不動産特定共同事業法を改正することで、クラウドファンディングを利用する不特定多数の投資家から、潜在的な不動産投資への関心を喚起する意味もあります。
法改正による不動産投資家への影響
不動産特定共同事業法の改正によって、空き家や空き店舗の再生や有効活用に対する小口での投資機会が増えることが期待されます。たとえば京都にある古い町家は売りに出しても買い手がつかないので、取り壊される運命にありました。ところが不動産特定共同事業法の改正によって、京町家再生の小口化商品を用意することで、個人投資家でも不動産投資を行なえるようになります。
またリフォームなどのメンテナンスは地元の中小企業が行なうので、地元に還元できるというメリットも大きいでしょう。
まとめ
いかがでしょうか。不動産特定共同事業法の改正によってこれまで大企業しか手を出せなかった不動産投資に、個人投資家が参加できるようになりました。クラウドファンディングを利用して、潜在的に不動産投資に関心のある人を集められるというのも大きなメリットです。また、空き家や空き店舗対策には社会貢献という面もあり、今回の不動産特定共同事業法の改正には大きな意義があるのです。