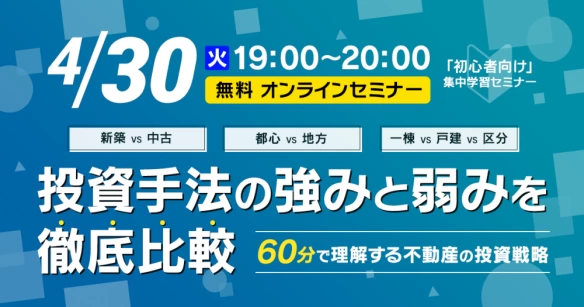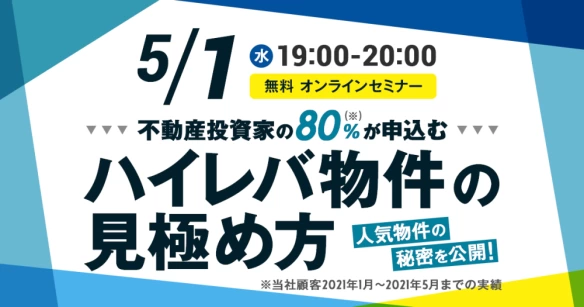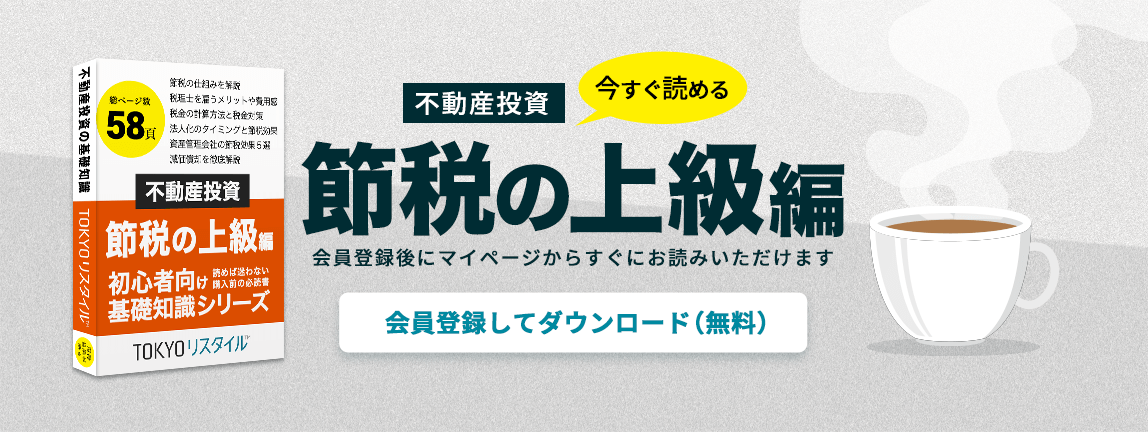会社と役員間の税務に注意!妻を役員にするメリット・デメリットも解説
- 更新:
- 2023/06/19

節税は経営者にとって常に意識しておきたいポイントですが、会社と役員間の税務については注意を払う必要があります。社長を含めた役員と会社の間で金銭のやり取りをしたり、貸借する際には、正しく手続きをしなければいけません。
節税を意識するあまりに、逆に多くの税金を納めることになっては本末転倒です。資産の売買は時価で取り引きするなど、まずは基本的な知識を抑えておきましょう。
この記事では、会社と役員間の税務の基本知識から、資産の売買、金銭の貸借、住宅の貸借について解説します。更に、疑問に感じる方が多い、妻を役員にすることのメリット・デメリットについても合わせてご説明します。
会社と役員間の税務の基本
会社と役員間のやり取りでは税務が発生することが少なくありません。まずは会社・役員間の税務の基本や原則をここでご説明します。
税金逃れはできない
原則として、会社および役員間のやり取りを利用して納税を逃れることはできません。たとえ社長本人であっても、会社と社長を含めた役員は別人格としてはっきり区別し、正当な価格で資産を取り引きすることが基本となります。
もし、会社側にとって有利な条件での取り引きとなった場合、差額は会社の益金として計上され、法人税が課されます。反対に、役員にとって有利な条件で取り引きした場合は、差額は役員報酬として計上されて役員の所得税が上がるうえ、会社は損金不算入となって法人税の面でも損をします。
このように、正しい金額で納税が行われるように、会社と役員間の税務は法律できっちりと定められています。
会社から役員への売却・貸借は時価で取り引きする
会社から役員に資産を売却または貸す場合には、時価で取り引きする必要があります。時価とは、現在売買する際の相場のことです。
例えば、1,000万円で購入した土地が値上がりし、現在の価値が2,000万円になったケースで考えてみましょう。会社から役員にこの土地を売却する場合、時価である2,000万円が正当な価格として判断され、帳簿にも時価を記入する必要があります。
正しい金額に課税される
会社の役員だからといって、会社と役員の金銭が混同することはありません。時価で取り引きすることを原則としたうえで、時価より安い金額で取り引きした場合は得をした方に税金が課される仕組みです。
尚、実際の資産のやり取りがなくても、経済的な利益を受け取った場合も課税対象となるため、注意が必要です。
例:役員のハイヤーと通勤費の関係
会社と役員の経済的利益の取り引きの一例として、ここでは役員が通勤に使うハイヤーの費用について解説します。
原則として、通勤にかかる交通費の税務は役員も一般社員も同様です。交通機関を使った通勤の場合は月15万円までの通勤手当が非課税で、マイカーなどを利用した場合は通勤距離に応じた非課税枠があります。
一般社員の場合、非課税枠を超えた場合は従業員給与として、役員の場合は役員報酬としてそれぞれ課税されます。役員報酬という扱いになった場合は、会社の損金算入ができず、会社としての法人税が高くなるおそれがあります。
そもそも、役員のハイヤーにかかる費用がマイカー通勤などと同様に会社の経費として認められるかどうかは、そのハイヤーが一般的に見て本当に必要か、合理的な手段かなどの観点から多角的に判断されます。そうではなく、ハイヤーが役員に対して経済的な利益をもたらすものと認められる場合は、ハイヤーにかかる費用は役員報酬として課税対象となります。
このように、一般社員に与える通勤手当と比較しても、役員が利用するハイヤーについては慎重に税務を判断する必要があります。個別の状況により税務が異なるため、判断に迷う場合は顧問税理士等に相談すると良いでしょう。
会社と役員間の資産の売買
会社と役員間で資産の売買をする場合も、正しい金額での取り引きを前提とした税務が生じます。ここでは、資産の売買に関する税務を解説します。
資産の売買も時価が基準となる
資産の売買では、時価での取り引きが前提となります。会社から役員に売却するケースでは、時価との差額に課税される仕組みです。反対に、役員から会社に売却するケースは、後述の通り、時価を基準とした複数の決まりが設けられています。
基準となる時価は資産の購入時の価格とは異なるため、適正な時価はいくらかを常に意識しておきましょう。
会社から役員に売却する場合
会社から役員に資産を売却するケースの一例として、会社が所有する時価5,000万円の不動産を役員に売却する場合で考えてみましょう。
時価5,000万円の不動産を1,000万円で役員に売却した場合、そのままでは、役員は税金を少ししか払わないまま、時価との差額4,000万円分の得をしたことになります。
しかし実際は、このような税金逃れができないように法律で定められています。時価との差額4,000万円は、役員報酬と同様であるとして、役員には所得税が課されます。
役員報酬や役員賞与は事前確定届出給与として前もって届け出していなければ会社の損金に算入できません。損金に算入できないことで、会社の経費として認められず、法人税の負担が重くなります。
このように、時価で取り引きしなければ、結果的に会社側も役員側も損をするおそれがあります。
役員から会社に売却する場合
役員から会社に売却する場合は、時価の2分の1未満の金額か、時価以上かなど、時価を基準とした金額によって税務が異なります。
役員が時価の2分の1未満の価格で売却する場合
役員が時価の2分の1未満の価格で会社に資産を売却する場合とは、例えば役員が所有する時価1億円の土地を会社に3,000万円で売却するようなケースです。
役員の購入当時から土地が値上がりしていた場合、土地の売却で得た利益に対しては譲渡所得税がかかります。この譲渡所得税を支払いたくないなどの理由で、時価よりも著しく低い金額で売却したいと考える方がいるかもしれません。
このような税金逃れを防ぐために、時価の2分の1未満で役員が会社に売却した場合は、時価で売却した場合と同額の譲渡所得税がかかります。また、会社は時価との差額を受贈益として法人税が課されます。
役員が時価の2分の1以上かつ時価未満の価格で売却する場合
役員が時価の2分の1以上かつ時価未満の価格で売却する場合とは、例えば役員が所有する時価1億円の土地を会社に7,000万円で売却するようなケースです。
このケースでは、役員側にペナルティはなく、売却価格に応じた譲渡所得税のみが課されます。ただし、会社に対しては、時価と購入価額の差額3,000万円が受贈益であるとして法人税が課されます。
役員が時価以上の価格で資産を売却する場合
役員が時価以上の価格で資産を売却する場合とは、例えば役員が所有する時価1億円の土地を会社に1億5,000万円で売却するようなケースです。
役員の所得税率が譲渡所得税率よりも高い場合、高く売却して譲渡所得税を支払う方が税金が安くなるでしょう。また、会社も多額の損金を計上して法人税を安くできると考えて、時価よりも高額な取り引きを行いたいと考えるかもしれません。
このような税金逃れを防ぐために、時価よりも高額な資産の売買を行った場合、役員には時価1億円で取り引きした場合の譲渡所得税に加えて、時価との差額である5,000万円を役員報酬として所得税が課されます。更に、会社は時価との差額5,000万円を役員報酬として支給したとみなされて損金不算入となり、多額の法人税が生じるおそれがあります。
会社と役員間の金銭の貸借
会社と役員の間で金銭の貸借を行う場合も税務が生じます。ここでは会社と役員間の金銭の貸借に関して解説します。
一般的には金利がかかる
一般的な金銭の貸借には、金利がかかります。住宅ローンやクレジットカードローンなどと同様に、借りている期間に対して定められた金利を上乗せして、貸している相手に返済する必要があります。
ただし、金利は絶対に必要な訳ではなく、一般的には両者の合意があれば無利息で貸し付けることも可能です。
会社が役員に金銭を貸す場合
会社が役員に金銭を通常よりも低い利息または無利息で貸し付ける場合、適正利息との差額は役員報酬として課税されることになります。尚、適正利息がいくらかは国税庁のホームページに記載されています。
ただし、災害や病気などで臨時で多額の金銭が必要だと認められる場合など、例外として適正利息との差額に課税されないケースもあります。
役員が会社に金銭を貸す場合
役員が会社に金銭を適正利息で貸し付ける場合、役員が利息として手に入れた金額は雑所得として課税されます。
また、通常よりも低い利息または無利息で役員が会社に金銭を貸し付ける場合は、原則として適正利息との差額には課税されません。これは、会社の資金繰りが厳しくなった際に、役員が私財を投入して立て直しを図ることが考えられるため、あえて課税はしないという意図があるようです。
会社と役員間の住宅の貸借
会社と役員間で住宅を貸借するケースもあるでしょう。特に、会社が社員に社宅として住宅を貸すことは一般的です。このような住宅の貸借に関する税務を解説します。
会社が社宅を役員に貸す場合
会社が社宅を役員に貸す場合、一定額の適正な賃料を受け取って貸していれば課税の対象にはなりません。ただし、社宅を無償または通常より低い価格で貸している場合は、適正な賃貸料相当額との差額が役員報酬として扱われます。
会社は役員報酬とされた金額は損金不算入となって法人税が上がり、役員は得た役員報酬に対して所得税が課されます。
役員が会社に不動産を貸す場合
役員が所有する不動産を会社に貸すケースでは、適正な賃料で貸しているのであれば特に問題はありません。
ただし、通常よりも高額な家賃を設定している場合は、賃貸料相当額との差額が役員報酬として課税され、会社は損金不算入になることが考えられます。
妻を役員にするメリット・デメリット
会社を運営するうえで、妻を役員にするかどうかで悩む方は少なくありません。ここでは妻を一般社員ではなく役員にするメリットとデメリットを解説します。
尚、この記事では便宜上「妻」と表記しますが、夫や親族でも同じことが言えます。
妻を役員にするメリット
妻を役員にするメリットは主に4つあります。所得の分散により節税できることと、妻自身の資産形成ができること、妻自身が社会保険に加入できること、妻に退職金が支給できることです。
夫だけが多く稼ぐよりも、妻も役員として報酬を得た方が所得が分散され、世帯当たりの所得税や住民税が安くなるでしょう。また、妻自身が役員として報酬を得ることで、贈与税や相続税の心配をせずに妻自身の資産形成ができます。
また、妻が社会保険に加入することで、扶養に入っているよりも会社が負担する社会保険料が軽減されます。更に、妻も厚生年金の報酬比例部分を多く受け取れるようになるため、老後資金を準備しやすくなるでしょう。
加えて、役員となった妻に退職金を支給できることで、会社側としても妻自身にも節税効果があります。
妻を役員にするデメリット
妻を役員にする場合は、会社の登記簿に妻の氏名が公開されることや、対外的な訴訟が起きた際には妻も経営者責任が生じることなどがデメリットです。
節税面では妻を役員にした方がメリットが大きいですが、役員となったからには妻も会社の重要人物として対外的な責任を負うことになります。
妻を役員にする際の注意点
妻を役員にする場合、実際の働きに見合った役員報酬を設定することなどに注意する必要があります。勤務の実態が無いのに役員として登記されている場合、税務署から指摘を受けるおそれがあります。
役員報酬だけでなく、賞与や退職金の金額についても、勤務実態に見合った金額を設定することが求められます。
また、社長の妻が役員という重役に付くことで、他の従業員のモチベーションが下がらないかなど、人間関係にも注視しながら判断することが大切です。
まとめ
この記事では、会社と役員間の資産の売買・貸借などに関する税務や、妻を役員にすることのメリット・デメリットについてご説明しました。
会社を経営するなかで余計な税金を払わずに済むように、会社と役員間では適正な取り引きをすることが大切です。節税のためにできることには、妻を役員にすることの他に、不動産を活用する方法もあります。
不動産投資を活用した節税の詳細は、当社コンサルタントまでお気軽にご相談ください。

この記事の執筆: 丸岡花
プロフィール:宅地建物取引士・FP検定2級を持つ主婦ライター(2児の母)で、300本以上の不動産関連記事の執筆実績を有する。得意ジャンルは不動産・税金・英語・育児。不動産が大好きで、不動産関連のニュースや法改正、市況のチェックが日課となっている。豊富な知識に裏付けされた独自性の高い切り口と、公的機関や学術論文などの1次情報に基づく正確性の高い文章に定評がある。元バックパッカーで旅行・キャンプをこよなく愛し、過去に20か国以上を訪問した経験を持つ。保有資格は宅建士・FP2級に加え、TOEIC895点(米国居住経験あり)、秘書検定1級、保育士など多岐に亘っている。
ブログ等:シュフリーランス