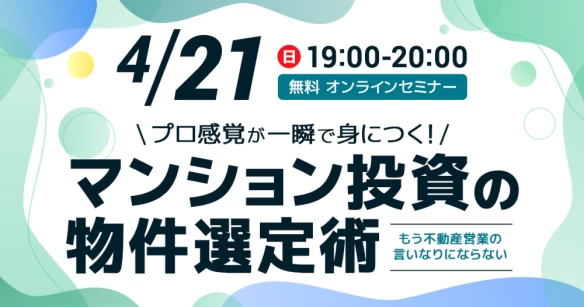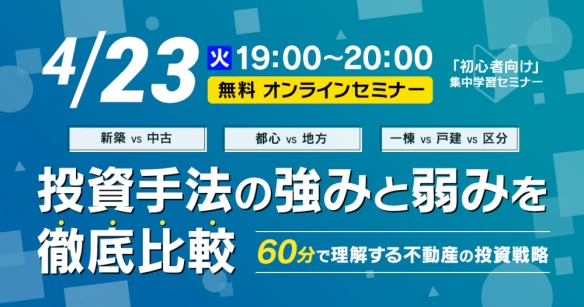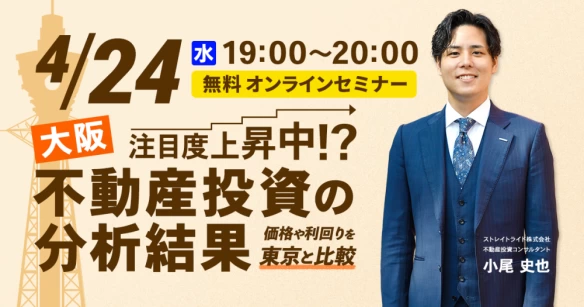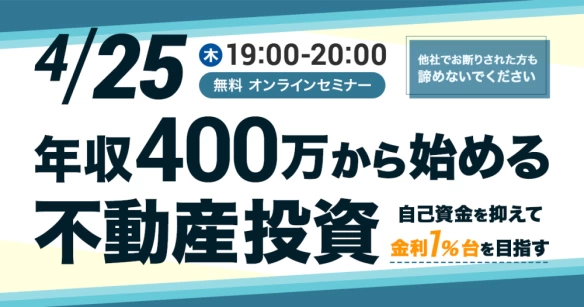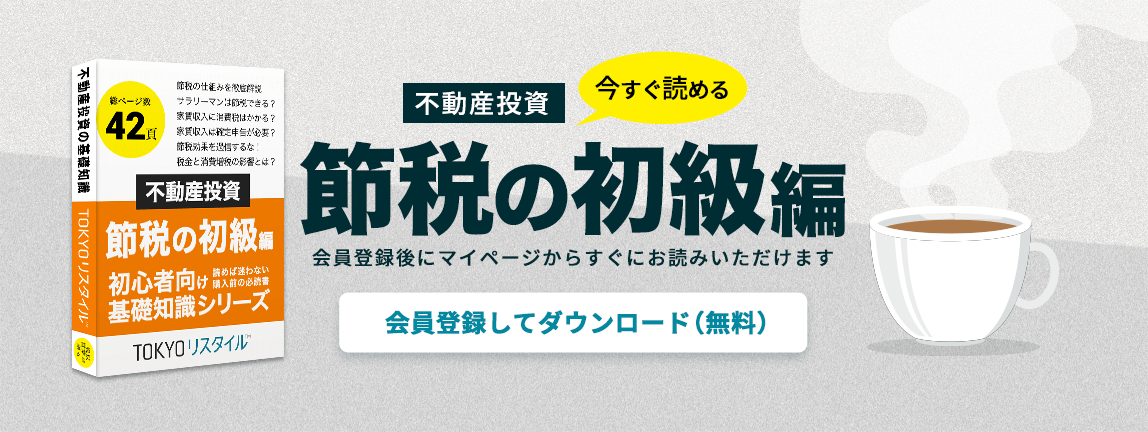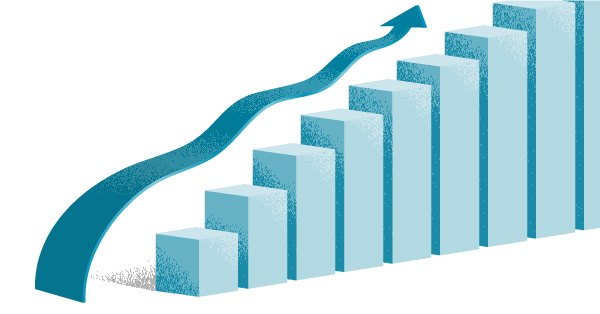【最新版】サラリーマン必見!不動産投資の節税の仕組みを徹底解説!
- 更新:
- 2022/08/23
本記事は動画コンテンツでご視聴いただけます。
老後の2000万円問題や働き方改革、副業の時代など、様々な働き方が問われる現代では、多くのサラリーマンが副業で不動産投資を選んでいます。不動産投資には多くの手法があり、みなさんその中から自分に最適な方法を選んでいます。
不動産投資は資産形成をするための投資ですが、中には節税対策として取り組む人もいます。
「サラリーマンは不動産投資で節税できる」という話を聞いたことがある方は多いのではないでしょうか。確かに不動産投資によって節税はできますし、実際に節税のために不動産投資を検討する人もいます。
ですが、節税目的で投資物件を購入するのはあまりおすすめしません。
あくまでも不動産投資は資産形成のために購入物件を増やし、利益を生むための投資です。節税を目的とするのであれば、不動産投資以外の選択肢を取った方が良いといえます。しかし、その選択肢も不動産投資の節税対策を理解してから選択した方が良いでしょう。
ここでは、不動産投資でサラリーマンが節税できる仕組みを、節税効果の具体的なシミュレーションをしながら説明します。
不動産投資はサラリーマンの限られた節税方法
サラリーマンにとって、不動産投資は数少ない節税手段のひとつです。
通常、サラリーマンには経費として計上できるものがありません。これはサラリーマンの経費は会社が払うからです。例えば事務用品の購入や出張の交通費、お得意様の接待費用などは、後日領収証を会社に提出することで会社が精算します。そのためサラリーマンは経費にできるものがほとんどなく、節税手段が非常に少ないです。
しかし、そんなサラリーマンでも不動産投資で節税をすることが可能です。
サラリーマンの税金は「給与所得」が多いほど高くなります。不動産所得が赤字であれば、確定申告することで赤字分を給与所得から差し引くことができ、所得税や住民税が節税できます。
そして、不動産投資における賃貸経営は副業にあたりません。不動産投資の家賃収入は不労所得なので現職への労働時間状の悪影響を与えないですし、「やむを得ず親から賃貸アパートを相続したため家賃収入がある」というようなケースもあるため、規模が大きなものでなければ、企業では従業員の不動産投資を副業として禁止していないことが多いのです。
不動産投資が節税になる仕組み
サラリーマンの不動産投資が節税になる仕組みを知るには「損益通算」と「減価償却」がキーになります。
不動産所得の損益通算とは
損益通算とは、不動産投資の赤字を給与所得から相殺できる仕組みです。
サラリーマンの給与は、源泉徴収という形で税金が天引きされた状態で支給されています。不動産投資による収支が赤字だった時に損益通算を行うと、給与所得が不動産の赤字分だけ相殺され、払い過ぎた税金が還付されます。
この損益通算による還付を受けるためには確定申告が必要です。
特に不動産投資を始める初年度は、まとまった経費と税金がかかるため赤字になりやすく、節税効果が高いといえます。
初年度にかかる経費は、物件購入の際の不動産会社に支払う仲介手数料、不動産の名義変更手続きで司法書士に支払う手数料、災害保険料などがあげられます。
税金は、不動産購入者に課される「不動産取得税」、不動産登記による名義変更手続きにかかる「登録免許税」、契約書の「印紙税」や「消費税」があります。
参考不動産投資における赤字と損益通算、減価償却による節税について分かりやすく解説!
節税のポイントは減価償却費
減価償却とは、不動産購入費用を、使用可能な年月にわけて毎年費用計上する仕組みです。建物の取得にかかった費用は、取得した年に全額を経費として計上できず、建物の使用可能な全期間にわたり分割して経費計上します。この使用可能期間は、財務省令にて定められた法定耐用年数となります。
減価償却費が節税のポイントなのは、実際に経費の支出がない、帳簿上の費用だからです。
例えば、投資用の不動産を現金一括で購入したとします。物件購入費用を耐用年数で割った金額を減価償却費として毎年経費計上しますが、そうすると、建物代金の支払いは完了しているのに、帳簿上は建物代金として減価償却費が支出されることになり、帳簿の減価償却費分は手元に残ることになります。
このように、手元に残るお金はあるけれど帳簿上は赤字という状況を作ることで、キャッシュフローの悪化を抑えた赤字を作り出すことができます。
サラリーマンの不動産投資節税シミュレーション
具体的にどの程度の節税効果があるかシミュレーションしてみましょう。
サラリーマンのAさんとBさんは、給与所得が同じ700万円だとします。
この場合の所得税率は23%です。そこから所得控除で636,000円を差し引くと、納付する所得税額は974,000円になります。
Bさんは、2000万円のアパート一棟を全期間固定金利3%で、35年ローンで購入しました。
Bさんの初年度の家賃収入と経費は次の通りだとします。
| 家賃収入 | 200万円 |
|---|---|
| 経費 | 264万円 |
経費内訳
| 減価償却 | 134万円 |
|---|---|
| 固定資産税 | 30万円 |
| 管理費 | 10万円 |
| 修繕積立金 | 30万円 |
| 借入金利子 | 60万円 |
この場合、Bさんの不動産所得は年間家賃収入200万円から経費の合計264万円を差し引いた-64万円で、赤字です。
この赤字を給与所得の700万円と損益通算すると、総所得は636万円になります。この場合の所得税率は20%です。そこから所得控除427,500円を差し引くと、納付する所得税額は844,500円になります
Aさんの所得税額は974,000円、Bさんの所得税額は844,500円でその差は129,500円になります。このように不動産所得が赤字の場合、年間で約13万円の節税効果が確認できました。
実際には更に細かい条件や項目も考慮しなければいけませんが、今回は計算をわかりやすくするため、条件を単純化してシミュレーションしています。
参考:所得税の計算式
- 所得税額 = 課税所得金額 × 税率 – 控除額
参考:所得税の税率と控除額
| 所得 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 330万円超~695万円以下 | 20% | 427,500円 |
| 695万円超~900万円以下 | 23% | 636,000円 |
節税目的で不動産投資をするのは間違い
結論から言えば不動産投資は、節税を目的として始めるのはあまりおすすめできません。
シミュレーションのように、確かにサラリーマンは不動産投資で赤字が出れば節税効果が見込めます。しかし、本来は不動産投資の目的は利益を上げて黒字を目指すことです。当然利益がたくさん出れば、儲かった分の税金を納める義務が生じます。
不動産投資で赤字を出し続けるということは、キャッシュフローが悪化することに直結します。いずれは事業そのものが破綻する恐れがあるので、節税のために赤字にすることを目指した不動産投資は健全とは言えないでしょう。
あくまでも不動産投資の目的は、利益を得て家賃収入を得ることです。そして資産を増やし投資家として成功すること。成功している不動産投資家の多くは、適正に納税をしています。経営者として、赤字申告は「融資を受けられない」など、事業継続にも影響がでるため、まずは黒字化を目指して不動産投資を行いましょう。
サラリーマンにとって不動産投資は節税対策になることは確かですので詳しく解説していきます。
サラリーマンが実行できる節税対策
多くの不動産投資家は、副業として不動産投資を行っています。不動産を買い増しするためは、融資額を引き上げる必要があり、そのためにも会社員という立場は非常に有利です。融資をする銀行にとっても、一定の給料が見込める会社員の方が安心して融資が出来ます。そして実際に節税対策になることも。実際にどのような節税対策があるのでしょうか。
経費としての不動産投資。確定申告で申告。
先述した通り、会社員にとっては通常かかる「経費」は会社が負担するものです。給与はそのまま所得として計算され、その金額によって税金が変わります。通常、給与や所得が高い人は、低い人より高い金額の税率により税金を納めます。
具体的には下記が挙げられます。
- 減価償却費
- 仲介手数料
- 租税公課
- 損害保険料
- 管理費、修繕積立金
- 修繕費
- 賃貸管理代行手数料
- 借入金金利
- 税理士費用
- 通信費
- 会議費
- 接待費
- 広告宣伝費
これ以外にも税金など様々な項目があります。このように不動産投資をすることで経費計上できる金額は高くなるでしょう。
経費としての「ランニングコスト」
また、これだけではなく不動産投資において注目すべきは「ランニングコスト」。不動産を運用する場合、毎月かかる金額が一定数はあるため、ランニングコストは経費として申告することができます。物件を購入後の、管理維持費としてのランニングコストは以下が考えられます。
共用部の水道光熱費
物件の共有部分、例えば廊下やエレベーターなどの共用部における電気代や水道がある場合は水道代もかかります。物件の規模や共用部の構造にもよるので、物件購入の計画を立てる段階で凡その金額は想定しておきましょう。
共用部の清掃費用などの維持管理費
共用部のゴミ置き場や、エントランスの掃除費用はオーナーが負担です。多くのオーナーは外注をお願いする場合が多いのですが、大体の相場は月5000〜8000円程度と考えられます。どちらも物件を購入する段階で想定しておきましょう。
複数の物件を所有している場合、その分ランニングコストも上がるため、経費も高額になります。所得からその分を引くことで、税率も大きく変わるといえるでしょう。
参考不動産投資における運用コストに注目!「ランニングコスト」も計算すべし
法人化による節税
法人化に関しては、所属する企業にもよるため一概にはいえません。しかし課税所得が900万~1000万円以上になる場合は法人化した方がメリットがあります。サラリーマンであれば、およその年収が1500万円前後が法人化のタイミングです。
法人化により大きく変わるのは「税率」です。まず、所得税は課税所得が増えるほど税率が上がります。これは超過累進税率で所得が小額の場合は税率が10~20%程度ですが、所得が1800万円を超えると40%、4000万円を超えるとなんと45%にまで上がるのです。これにプラスして、住民税もプラスされるので税率はさらに上がってしまいます。
しかし、先述した税率は個人の場合です。収入が高くなった場合は、法人化して法人税として納税した方が節税となるため、課税所得金額によっては法人化も検討すべきといえるでしょう。
参考900万から?不動産投資を法人化したほうがいいタイミングや節税効果について
減価償却で節税対策
不動産投資をする上で「減価償却」という言葉を聞いたことがある人は多いのではないでしょうか。しかし、節税対策としても有効とされる減価償却に関しては、専門的な部分が強く、きちんと理解している人は少ない印象があります。大切なことなので物件購入前に理解しておきましょう。
簡単にいうと、減価償却とは「劣化する資産を対象にした、その取得費用を一定期間支出として配分すること」を意味します。資産の価値を徐々に下げることで、その分を経費計上出来るのです。減価償却は、実際は支出していない費用を経費として計上する仕組みのため、不動産投資においては減価償却を使った節税対策は有効といわれています。減価償却に関しては、下記の記事で詳しく解説しています。こちらを参考にしてください。
副業としての不動産投資の考え方
不動産投資における節税対策に関して解説してきました。次に、不動産投資と副業に関しての考え方を見ていきましょう。副業として不動産投資に取り組む人の多くは、本業を持ちながら融資を受けて不動産投資に取り組んでいます。副業も所得として計算されるため、納税額が変わります。副業と不動産投資の考え方も理解しておいた方がいいでしょう。
また不動産投資は「借り入れありき」です。そのため本業を持っている方が金融機関からの信用があり、融資を受けやすく物件数を買い増ししやすいといえます。そのため副業として不動産投資を取り組むことは、おすすめです。
家賃収入は副業に当たらない
結論から言えば、家賃収入は副業に当たらない場合がほとんどです。会社にとっての「勤怠への影響が少ない」「物件を相続することはあり得る」などの理由から、不動産投資を副業として禁止していない会社がほとんどです。しかし、一定の規模を超えてしまい「事業」として認識されるレベルにまで発展した際は、副業と認識されません。
その場合は会社への申告が必要となりますし、納税額も変わってきます。注意しましょう。
副業で不動産投資に取り組む際の成功の秘訣
副業を複業と呼び、副業推進の時代といわれる現代では、多くの企業が「副業可」を認めるようになっています。それに伴い、「副業や資産運用をしたい」と思う多くの人が不動産投資に取り組むようになりましたが、残念ながら全ての人が成功しているわけではありません。
不動産営業マンとして、多くの失敗を目の当たりにしてきました。その中で不動産投資がうまく行く人には共通の心構えがあることを発見しました。
その心構えとは「不動産投資を実業として捉えているかどうか」です。不動産投資には幅広い知識や専門分野における知見が必要です。もちろん全ての知識を自分で得る必要はありませんが、基礎的な知識を得る努力は必須です。しかし残念ながら、不動産投資を業者に丸投げしている状態の人も中にはいらっしゃいます。
購入物件の出口戦略や返済計画さえ知らない人もいるのです。これがもしも会社だとしたら、「経営戦略なども立てずに起業した」というのと同じこと。どのように利益を生み出すか、長期的な計画等もないままに起業してもうまく行くとは思えません。不動産投資も同じです。
実業として捉えている人の多くは、不動産業界の知識や物件の知識を得ながら購入物件を増やして資産形成しています。実業の意識を持っている方は、積極的に不動産業界のことを学び、購入物件に繋げ実践を重ねています。そのため、購入物件から空室をだすことなく満室で回すことができるのです。
これには個人の能力や才能は関係ありません。あくまでも心構えの問題です。心構えは自分で調整できるため、現時点で不動産投資をしている人でも見直してみましょう。
不動産屋とパートナーシップを組む
知識を得ることで、不動産会社との強固な信頼関係を築くことができます。不動産投資は情報のスピードや情報量が重要です。時代と共に変化する業界の情報は、業界に精通している人にしか回ってきません。
物件価値を見極めるための条件や情報は重要ですが、その情報は不動産会社にあるものです。そのため、不動産会社と信頼関係を結んでおいた方が良いでしょう。特に副業サラリーマンにとっては、業界内の情報を不動産会社から得ることも多いです。良好な関係を作り上げることが、不動産投資を成功させる秘訣ともいえます。対等に話せるように知識を得ながら、不動産会社との関係性づくりに尽力することは大きなポイントといえるでしょう。
まとめ
今回は様々な節税対策や節税に関して解説してきました。不動産投資は、サラリーマンの数少ない節税手段のひとつです。しかし、あくまでも本筋は利益を増やして黒字を目指すものです。不動産投資における節税は副次的な効果と考えて不動産投資での利益の追求に力を注ぐのが良いでしょう。そもそも節税目的で高額な不動産投資を選択するのはおすすめできません。
不動産投資を成功させるためにも、副業というよりは複数の本業という意識を持ちながら取り組むべきです。高額な金額が動く不動産投資は、リカバリーできないこともあります。購入物件の選択や場所選びなどは非常に重要ですから、慎重になるべきです。「節税対策で」と安易な考えでは成功できるとは思えません。
投資は残念ながら全ての人が成功できるわけではありません。あくまでも実業としての意識を持ちながら、投資を成功させるための心構えや意識を持つべきといえるでしょう。