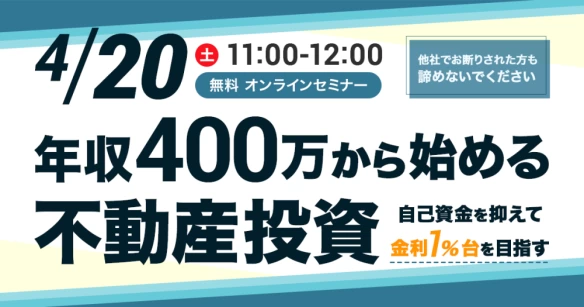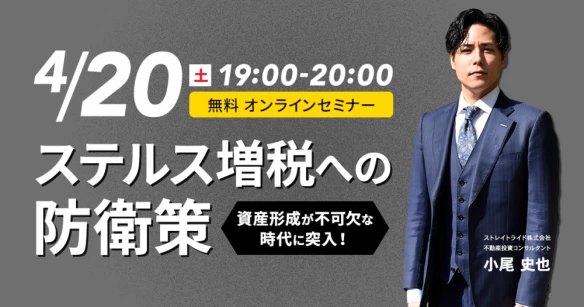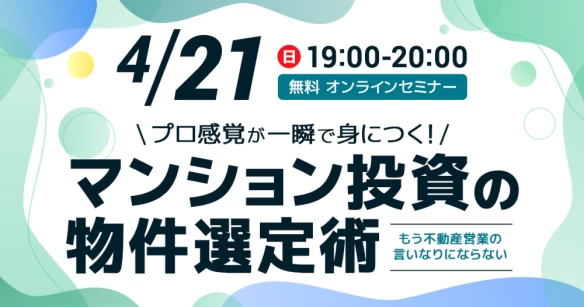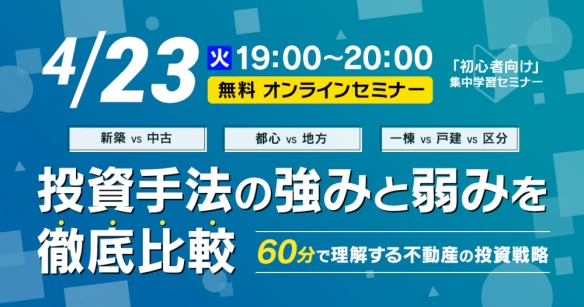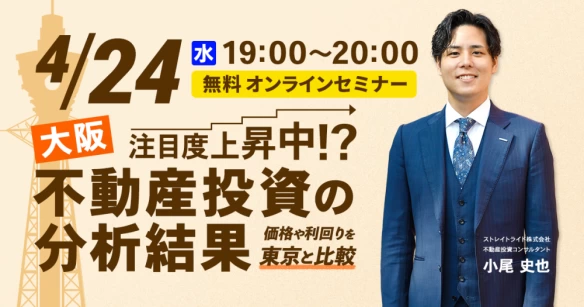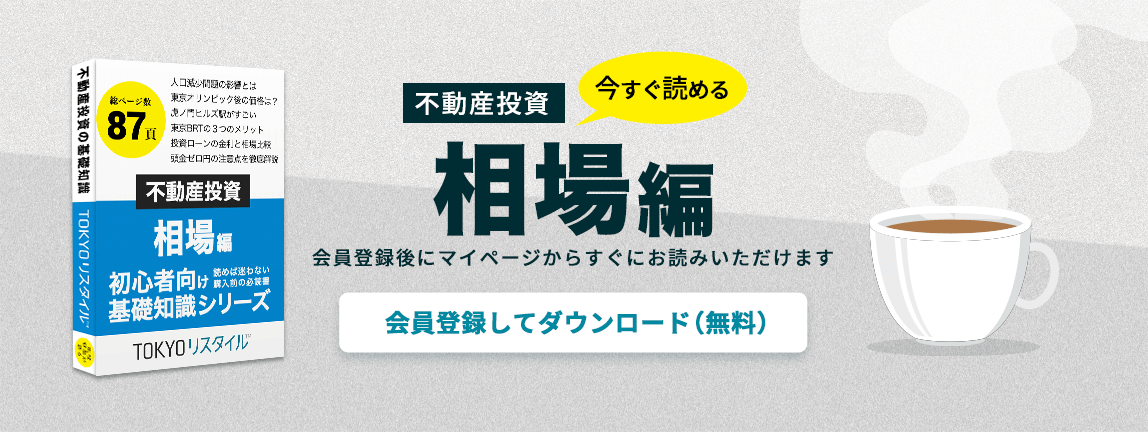ルームシェア向け物件の不動産投資は要注意!?シェアハウス投資が初心者には難しい理由を解説
- 更新:
- 2022/07/07

投資対象となる不動産の種類の1つに、ルームシェア用のシェアハウス物件があります。テラスハウスを中心としたリアリティ番組のブームから、賃貸需要が高まってきた背景もあり、「シェアハウス物件に投資するのもアリなのでは」と思う方もいるかもしれません。
しかし、シェアハウス投資ならではのメリットがある一方で、初心者向けではない理由が存在します。一般の物件と比べてトラブル対応が多く、入居者の獲得や物件の売却が難しいといった、難易度が高くなる要素があります。
そこでこの記事では、まずシェアハウス投資についての概要をご紹介し、シェアハウス投資のメリットやデメリットを解説します。様々な種類の物件に関する情報を押さえておくことは、投資の目を養うことにも繋がります。ぜひご一読ください。
シェアハウス投資の概要
まずはシェアハウス投資についての概要を見ていきましょう。シェアハウスへの不動産投資で問題となった「かぼちゃの馬車事件」についても触れていきますので、合わせてご覧ください。
シェアハウスとは
シェアハウスとは、各入居者の居住スペースとリビング・バス・トイレといった共用スペ―スが備わっている賃貸住宅のことを指します。
ワンルームの居室のみが私用の空間で、残りすべてを共有するパターンもあれば、リビング以外すべての設備が各入居者に割り振られているパターンもあり、様々な構造のシェアハウスがあります。
また、「ルームシェア」とは同居を指すこともあるため厳密にはシェアハウスよりも広義の言葉になりますが、近年のシェアハウス需要の高まりから「ルームシェア向けの物件≒シェアハウス物件」といった意味合いを持ちつつあります。ウィズコロナ・アフターコロナの生活様式として、住民それぞれにプライベート空間がある物件のニーズが高まっている背景もあります。
シェアハウスの入居者の多くは単身者で、ボリューム層は20代~40代と幅広い年代です。女性専用の物件や、起業家向けのシェアオフィスに近い物件もあり、想定する入居者に合わせてコンセプトも多角化しています。
シェアハウス投資とは
シェアハウス投資とは、シェアハウス物件全体への投資を指します。入居者が4名のシェアハウスであれば、各入居者の居住スペースが「ワンルーム ✕ 4人 = 4部屋」、リビングなどの共用スペースが1セットといった形式が一般的です。
ワンルームマンションと同様、入居者は家賃+共益費を支払います。都内のシェアハウスの家賃は7万円程度、共益費は1万円程度が相場のため、入居者は月々8万円程度を払うことでシェアハウスへの入居が可能です。シェアハウスのオーナー視点では、これが1人あたりの家賃収入となり、入居者の数が乗算されて累計の家賃収入となります。
家賃収入の面で魅力的に映る一方、「かぼちゃの馬車事件」というシェアハウス投資に関する事件が2018年に話題となりました。こちらについても見ていきましょう。
かぼちゃの馬車事件とは
かぼちゃの馬車事件とは、女性専用のシェアハウス事業を行っていた株式会社スマートデイズが経営破綻に陥る一連の騒動を指します。
スマートデイズはシェアハウスの投資家と30年間の家賃保証を契約していたにも関わらず、2017年には支払う賃料の減額を投資家に要求。2018年以降は賃料の支払いが出来ず経営破綻となり、投資家が多額の借金を抱えるに至りました。
事件発生後の捜査により、スマートデイズと工事会社やスルガ銀行との癒着が発覚しました。工事会社とは建築費の50%に及ぶ多額のキックバックを契約で取り結んでおり、建築費が不当に釣り上がる(投資家の物件購入費用がかさ増しされる)状態でした。また、スルガ銀行は融資の審査書類や売買契約書を改ざんしており、一般の投資家では得られない額を融資していました。
工事会社との契約やスルガ銀行の不正行為により、莫大な利益を得るスキームを生み出したスマートデイズは、新たな投資家を募るためにシェアハウス物件を林立するようになります。その結果、入居者の確保に難儀し家賃を下げる必要性が生じ、投資家への減額要求や未払いが起こり倒産に至りました。
こうした事件はレアケースであるものの、同様の事件が再発しないよう個人投資家への融資審査基準や銀行への監査が厳しくなり、不動産業界の環境が変化しました。工事会社や銀行を巻き込んだ大きな事件ではありますが、シェアハウス投資自体はかぼちゃの馬車事件のような悪いものばかりではないことは理解しておきましょう。
シェアハウス投資のメリット
シェアハウス投資についての概要を見たところで、シェアハウス投資のメリットをご紹介します。シェアハウス投資では物件のコンセプトを特化し、空室リスクを抑えながら高い利回りを見込むことができます。それぞれ見ていきましょう。
ターゲット層を定めて特化できる
先述のような女性専用の物件や起業家向けの物件のように、ターゲット層を定めることで内装や設備を特化できます。例えば女性向けの小型インテリアを配置したり、日当たりや風通しを良くしたり、高速のWi-Fi環境を整えるといった差別化が考えられます。
また、例えば料理好きが集まる物件としてカウンターキッチンを設置することで、写真や動画映えによりSNSや口コミでの拡散が期待できます。入居者が入居者を呼ぶ環境を整えることで、安定したシェアハウス経営が見込めます。
物件数が増加傾向である
一般社団法人日本シェアハウス連盟発表の『シェアハウス市場調査2020年度版』によると、2013年は約2,700棟だったシェアハウスは2020年には全国に約5,000棟と、右肩上がりで棟数が増加しています。
かぼちゃの馬車事件のような例外を除き、物件数の増加はニーズの増加に基本的には比例します。テラスハウスのようなリアリティ番組の人気に伴い、シェアハウスに憧れる視聴者層が入居需要に繋がったと考えられます。
一般の物件より高い利回りが見込める
先述のように、都内のシェアハウス物件では家賃と共益費を合わせて月8万円程度の家賃収入が1人あたりに見込めます。4人の入居者がいれば「8万円 ✕ 4人 = 32万円」となり、床面積あたりで計算すれば、単身者向けのワンルームマンションよりも資金効率が高くなります。
バス・トイレなどの共用スペースが1つで済むため、費用がかさみがちな水回りの修繕費も抑えることができます。結果的に、シェアハウス物件は通常の物件よりも実質利回りを高く見込めます。
空室リスクを抑えることができる
ワンルームマンションであれば、退去者が現れると新規の入居者が現れるまで家賃収入がゼロになります。退去から清掃等の手続きを経て新規の入居に至るまではどうしてもタイムラグがあるため、空室率をゼロにすることは非常に難しく、家賃収入が途絶える時期はどうしても発生し得るのが実情です。
一方で、シェアハウスであれば既存の入居者が全員一斉に退去することは非常に稀なため、家賃収入がゼロになるリスクは限りなく低いと言えます。
シェアハウス投資が初心者に難しい理由
シェアハウス投資のメリットを見たところで、シェアハウス投資が初心者向きではない理由をご紹介します。一般の物件と比較し、専門の知識やテクニックが必要になるのが大きなポイントです。それぞれ見ていきましょう。
入居者の募集が難しい
シェアハウス物件は一般の賃貸よりも契約に必要な書類が少ないことから、入退去のハードルが低いことが入居者の流動性の高さに繋がっています。しかし、初心者の投資家の方は、一般の物件よりも入居者の募集に難儀することが考えられます。
理由としては、物件情報が載っている不動産のポータルサイトにシェアハウス物件が掲載されないケースが多いためです。シェアハウスの入居者はシェアハウス物件のみが掲載されているポータルサイトや口コミから物件をリサーチする必要があるため、「シェアハウスに入居したい」というニーズが顕在化している層にしかアプローチすることができません。
こうした事情から、シェアハウス物件にはターゲット層を想定して内装や設備を差別化できるというメリットがある一方で、そのような工夫を凝らさないと入居者の確保に難儀するというデメリットもあると言えます。
出口戦略が取りづらい
例えばファミリータイプのマンションの一部屋を手放すのであれば、同じようにマンション投資を行う投資家や、その物件を購入する入居者への売却が考えられます。一方で、シェアハウス物件は同じようなシェアハウス投資をする投資家の数が少ない上、シェアハウス物件に永住しようとする入居者はごく少数です。そのため、売却先が見つかりづらいという難点があります。
物件が中々売却できないということは、不動産投資で利益を出すために重要な出口戦略が取りづらいということです。「物件を売りたくても売れない」という状態は投資においてリスクであることを押さえておきましょう。
入居者同士のトラブルが起こりうる
シェアハウス物件ならではの問題として、騒音や設備の使用方法などのトラブルが入居者同士で起こりうる点が挙げられます。友人・知人同士でのシェアハウスでは問題が起こっても入居者間で解決できますが、他人同士によるシェアハウスのトラブルは第三者の仲介が必要になる可能性があります。
トラブル対応までを管理会社に委ねることも可能ですが、通常の物件よりも管理手数料が高くなる傾向にあります。シェアハウス物件は高い利回りが見込める一方で、管理会社への委託料も高くなり運用コストが掛かるデメリットも存在します。
リノベーションに専門知識が必要
建築基準法により、シェアハウスは一般の住宅とは異なり寄宿舎の扱いとなります。そのため、一般の物件をシェアハウス用にリノベーションする場合は、建築基準法や消防法などの専門的な法律の知識が求められます。
シェアハウスは内装や設備面の自由度が高い一方で、法的な拘束も多い点が初心者向きではないポイントです。
アフターコロナへの対応が必須
新型コロナウイルスの影響から、人々はソーシャルディスタンスやリモートワークの概念によって新たな生活様式に移行しました。シェアハウス物件もこうした生活様式の変化に対応する必要があります。例えば入居者全員がリモートワークを行う場合、入居者が一斉にZOOMによるオンライン通話をしても重くならない通信環境が求められます。
また、万一シェアハウス内で病気や感染症が蔓延した場合、SNSやニュースで拡散され、退去者が現れたり新規入居者の確保が困難になる恐れがあります。このようなリスクを抑えるには、共用設備の使用に関する告知を入居者に徹底する必要があります。また、入居者がそうした取り決めを守るリテラシーを持っているかを見極める目も必要です。一般のワンルームマンションへの投資と比べ、シェアハウスのアフターコロナ対応は難易度が高いと言えるでしょう。
まとめ
今回の記事では、シェアハウス投資についての概要やメリット・デメリットをご紹介しました。
初心者の投資家の方にオススメしたいのは、単身者向けマンションのワンルームへの投資です。都内の築浅物件であれば、入居者の獲得や物件の売却に困るリスクを抑えた運用が可能です。不動産投資をスタートしたい方は、当社の担当による個別面談をぜひご活用ください。