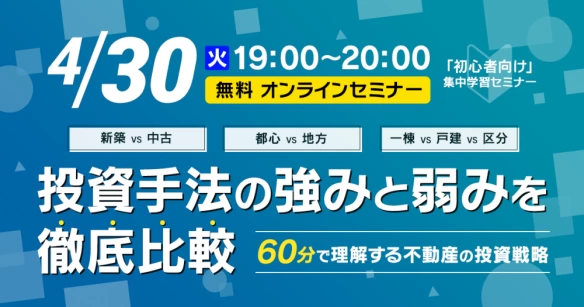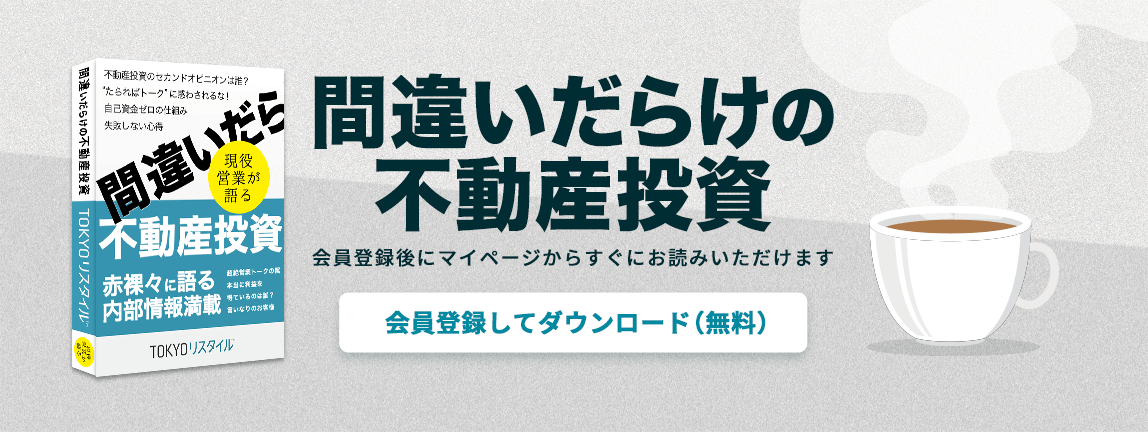不動産投資で地震のリスクを抑えるには?注意すべきポイントを徹底解説!
- 更新:
- 2023/06/21
本記事は動画コンテンツでご視聴いただけます。
地震大国と呼ばれる日本では、南海トラフ地震や首都直下型地震が近い将来に起こると言われています。
国土交通省によると、今後30年以内に南海トラフ地震でマグニチュード8~9クラスの地震が発生する確率は70~80%。首都直下地震でマグニチュード7クラスの地震が発生する確率は70%程度と、それぞれ高い数値が提示されています。
日本での不動産投資を考えた際、やはり地震のリスクを考える方は多いのではないでしょうか。「購入した物件が倒壊したらどうしよう」といった懸念から、不動産投資を迷っている方もいると思います。
そこでこの記事では、まず不動産投資における地震のリスクを解説し、そのリスクを抑えるための地震対策についてご紹介します。また、災害が発生した際の地震対応についても解説します。
日本では小規模のものを含めると地震は毎日発生していると言われており、地震を意図的に避けることは不可能と言えます。しかし、正しい知識をもって地震に備えることは可能です。早速見ていきましょう。
不動産投資で想定される地震のリスク
この項目では、不動産投資にかかわる地震のリスクをご紹介します。不動産投資をおこなう前に把握しておきたい内容ですので、ぜひご確認ください。
リスクその1 不動産物件の価値が下がる
地震の被害に遭った物件は、被害状況にもよりますが、多くの場合は価値が低下してしまいます。
特に土砂崩れや地盤沈下のように、物件だけでなく周辺の環境にも被害が出ている場合は、建物を修繕しても買い手が現れず、物件を手放したくても手放せないという状況も考えられます。
リスクその2 不動産投資での収益が見込めなくなる
大地震の際には建物だけでなく、入居者の状況にも変化が起こることがあります。
東日本大震災の際には経済にも大きな打撃があり、内閣府発行の資料「東日本大震災の経済的影響の特徴」によると、経済的被害は16兆円~25兆円程度とされています。また、厚生労働省発行の「東日本大震災が雇用・労働面に及ぼした影響」によると、震災後の完全失業者数は15万人強から19万人と、約4万人増加していることが分かります。つまり、大地震の後には入居者の経済状況が悪化し、家賃が払えなくなる可能性があるのです。
また、地震によって建物の外壁が剥がれたりガラスが割れたりした場合、入居者がその物件に住めなくなることがあります。入居者が退去すると家賃が支払われなくなるため、収益が見込めなくなってしまいます。
そして、家賃収入が途絶えたとしてもローンの返済は続くため、不動産オーナーの負担が大きくなることも想定されます。物件の被害状況によっては、物件を担保に追加で借り入れをおこなうことが難しいため、修繕が完了し新たな入居者を獲得するまでは大きな金銭的負担が強いられる可能性があります。
リスクその3 不動産修復の費用が掛かる
先述のように物件の外壁やガラスに損壊があった場合、不動産オーナーが修繕費を負担することになります。損壊の度合いにもよりますが、一棟マンション経営の場合、数百万から数千万の負担になることもあります。
また、入居者や第三者に被害が生じた際、不動産の管理状態に瑕疵が見られた場合には賠償責任が問われることもあります。阪神淡路大震災にて、マンションの1階部分が倒壊して入居者が死亡し、不動産オーナーに1億2,900万円の損害賠償責任が命じられた事例もあります。
物件選びのタイミングでできる地震対策
ここまで地震があった際に想定される不動産関連のリスクをお書きしましたが、対策次第では先述のような被害を避けられる可能性は大いにあります。まずは物件を選ぶ段階での地震対策について見ていきましょう。
地震対策その2. 新耐震基準を満たした物件を選ぶ
地震に備えて物件を選ぶ際には、新耐震基準を満たしているかどうかを確認するようにしましょう。
新耐震基準とは、1981年に改正された建築基準法に基づいた耐震基準のことです。1978年の宮城県沖地震において建物の損壊が多く見られたことで、耐震基準の見直しが実施されました。「震度5強程度の中規模地震では軽微な損傷、震度6強から7に達する程度の大規模地震でも倒壊は免れる」という耐震基準で、2022年現在もこちらの基準が適用されています。
社団法人高層住宅管理業協会の東日本大震災 被災状況調査報告によると、東日本大震災により倒壊したマンションは0棟で、建物の大破は0棟、中破は61棟(0.071%)と少数でした。大地震が起きた際、新耐震基準を満たしていれば建物の倒壊はまず起こらないと考えてよいでしょう。
建築確認日が1981年以降のものであれば、その物件は新耐震基準を満たしています。注意点として、建築確認日と竣工日にズレが生じることが挙げられます。建物の竣工が1981年だとしても、建築確認日が1980年であれば、旧耐震基準で認可が下りている可能性があります。
古い物件は老朽化が進んでる可能性が高いので、地震対策の観点で言えば古すぎる物件を選ばないことが得策であるとも言えます。いずれにしても、購入を検討する物件の築年数や建築確認日はチェックしておくようにしましょう。
地震対策その2. ハザードマップを確認する
災害で被害が想定される箇所や、災害発生時の避難場所を記したものを「ハザードマップ」と呼びます。地震によって地盤の液状化現象が起こったり、津波による浸水が起こる可能性のある地域は、ハザードマップに記されています。
先述の新耐震基準を満たしている物件では、建物の倒壊はまず起こらないと言えますが、やはり地震の二次災害である液状化現象や津波については用心するに越したことはありません。物件の購入を検討している地域のハザードマップを確認し、危険度が高くないエリアであるかを確認するようにしましょう。
また、ハザードマップについて詳しくは当サイトのこちらの記事もご確認ください。
参考液状化ハザードマップ作成の手引きを確認しよう!地震、洪水、大雨、自然災害と共にある日本のハザードマップ
地震対策その3. 投資エリアを分散する
一棟マンション経営や1つのマンションで複数の部屋を購入する不動産投資は、管理の手間を抑えることができる一方で地震へのリスクが偏ってしまいます。複数のエリアの物件に分散投資をすることで、地震に対するリスクヘッジをおこなうことができます。
しかし、エリアが離れすぎると管理が大変になることに加え、入居需要を考慮しないと空室リスクも発生してしまいます。各種リスクを比較した上で、戦略的に物件選びをおこなうようにしましょう。
地震対策その4. 地震保険に加入する
地震対策のために、地震による被害の状況に応じて補償を受けられる地震保険に加入するのも一つの手です。地震保険は政府が補償の一部を負担する官民一体の制度で、大地震が起こった際に保険会社だけで補償をおこなえず破綻してしまうことを防いています。
地震保険は単体で加入することができず、火災保険の特約として入ることができます。地震が原因による火災は火災保険の対象外となるため、火災保険単独では地震対策にはならない点に注意です。地震対策に万全を期すためには、火災保険とともに地震保険にも加入するようにしましょう。
地震保険は、物件の損傷の程度によって支払われる保険金が変わります。支払われる保険金は保険金額の割合から、以下のように算出されます。
| 損壊の度合い | 支払われる保険金 |
|---|---|
| 全壊 | 保険金額の100%限度 |
| 大半壊 | 保険金額の60%限度 |
| 小半壊 | 保険金額の30%限度 |
| 一部損壊 | 保険金額の5%限度 |
地震保険の保険金額は、火災保険金額の30〜50%と設定されています。たとえば火災保険額が1,500万円、地震保険額が750万円、損壊の度合いが小半壊だった場合、750万円の30%の225万円が保険金として支払われます。
こちらの計算からも分かるように、地震保険では損傷した物件の修繕費をすべて賄えない可能性があります。地震保険のみに頼らず、物件が新耐震基準を満たしているか、津波や液状化現象の危険が少ないエリアであるかなどを忘れずにチェックするようにしましょう。
地震対策その5. 滞納保証・空室保証制度を利用する
先述のとおり、震災が起こると入居者が経済的に困窮し、家賃の支払いが滞る可能性があります。また、建物の損壊具合によっては入居者が物件に住めなくなってしまう可能性もあります。そうしたリスクを踏まえ、滞納保証・空室保証制度を利用することも一考です。
滞納保証とは、入居者が家賃を滞納した際に保証会社から家賃を立て替えてもらう制度です。空室保証は、物件の空室時に家賃収入を保証会社が補填してくれる制度です。
注意点として、滞納保証と空室保証はどちらも基本的に家賃の80%~90%程度の補填となり、満額は支払われないことが挙げられます。また、保証料は入居者またはオーナーの負担となる点にも注意です。メリットとデメリットを天秤にかけ、各制度を利用するかどうかを考えるようにしましょう。
参考不動産投資と家賃保証会社の関係は?最高裁「追い出し条項」判決まで解説
不動産オーナーが地震災害の発生時におこなう対応
物件選びの段階でとれる地震対策をお書きしましたが、やはり震災による被害を100%防ぐことは難しいものです。そこで、この項目では災害が発生した際に不動産のオーナーがおこなうべき対応を記載します。
地震対応その1. 管理会社に相談する
災害が発生した際は、まずは不動産の管理会社に連絡をするようにしましょう。管理会社と契約している場合、震災後の対応は基本的に管理会社の指示に沿っておこなうことになります。
物件の状態や入居者の安否を確認するべく、現地に向かいたい気持ちが生まれるとは思いますが、有事の際には単身で行動せずに管理会社と連携を取ることを推奨します。
地震対応その2. 入居者の安否を確認する
管理会社と契約をしている場合、入居者への連絡は基本的に管理会社がおこなうことになります。入居者の安否や入居者目線での物件の被害状況は、このタイミングで確認できます。
以降の手順で保険会社に連絡することになりますが、入居者や物件の状況を把握しておくと、保険会社とのやり取りがスムーズになります。「入居者-管理会社-物件所有者-保険会社」の間で情報伝達が円滑におこなえると、災害対応はうまく回っていきます。
地震対応その3. 保険会社に相談する
地震保険や火災保険に加入している場合は、保険金の支払いについての相談をおこなうようにしましょう。入居者の安否や被害状況の概要を伝え、保険会社の指示を仰ぐようにしてください。
地震対応その4. 被害状況を確認する
余震や二次災害が収まったタイミングで、建物の被害状況の詳細を確認することになります。損傷具合で物件の修繕費用が変わり、地震保険によって支払われる保険金も異なります。物件の損傷度合いの把握や修繕依頼の段取りについて、管理会社や保険会社と連携を取って進めていくようにしましょう。
まとめ
今回の記事では不動産投資にかかわる地震のリスクや、そのリスクを抑えるための物件選び、災害発生時の対応について書きました。
地震を考慮すると、どうしても不動産投資のリスクの部分に目が行ってしまいますが、建築確認日やハザードマップをチェックすることで、地震の被害が少ない物件を選ぶことは可能です。また、震度7を想定した建築基準法や官民一体の地震保険のように、地震大国の日本ならではの法律や制度が整っています。東日本大震災で倒壊したマンションが0棟だったことからも、地震から国民を守る知恵は連綿と受け継がれていると言ってよいはずです。
とはいえ、地震対策のために購入物件のエリアを分散したり、各種保証制度を利用したうえで利益を出すには、初心者の方には難しいテクニックが必要となります。専門的な知見を活用しながら不動産投資に取り組みたい方は、ぜひ当社のコンサルタントまでご連絡ください。