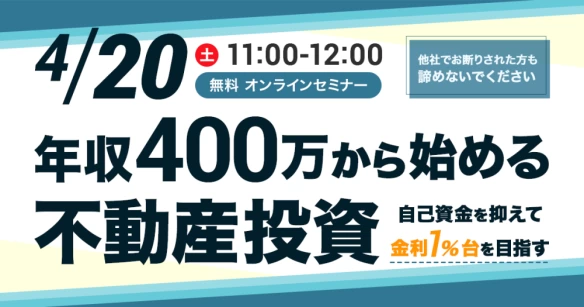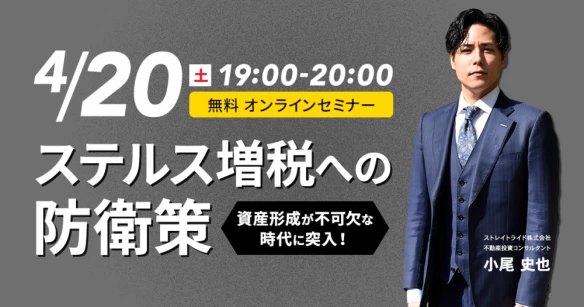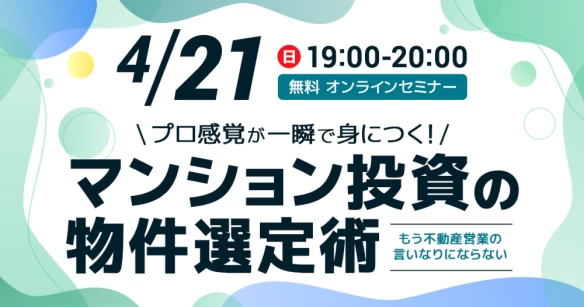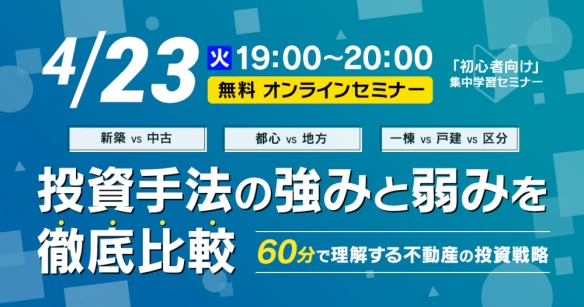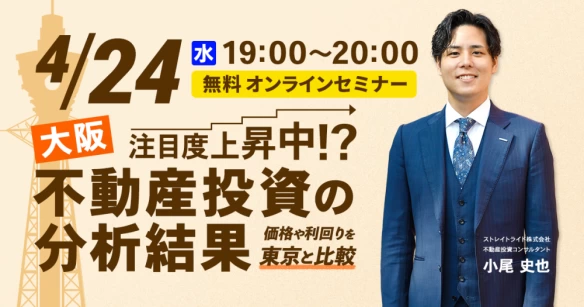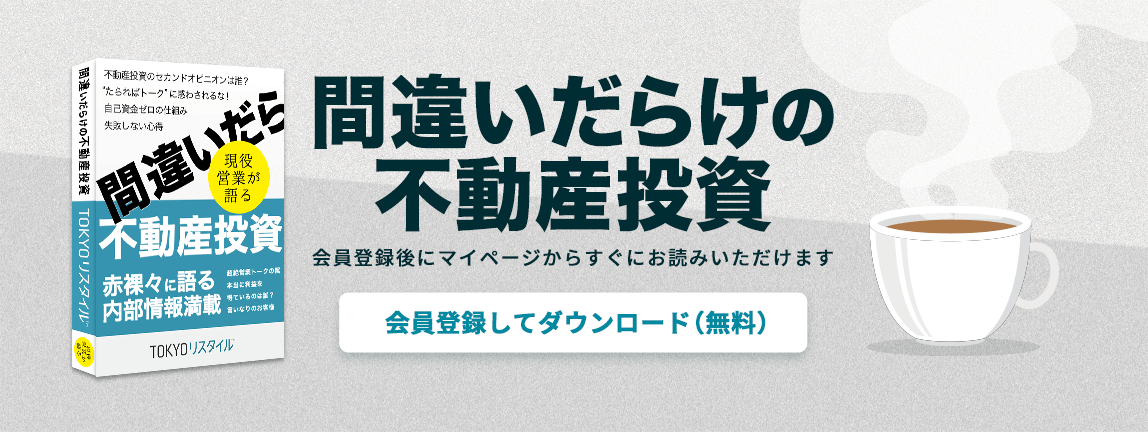不動産投資をする前に知って起きたい!地震のリスクとその対応方法
- 更新:
- 2023/08/02
本記事は動画コンテンツでご視聴いただけます。
不動産投資をはじめるにあたり必要不可欠なのが「保険」。不動産投資をはじめる際、火事になった時にカバーできる「火災保険」については加入していても、「地震保険」についてはまだまだ浸透していないのが現実です。確実に起こるとはいえなくとも、起こった時には避けることができないのが天災です。天災に関してのリスクヘッジを行うことも、不動産投資をする上では重要なこと。今回は天災の中でも、最近特に身近な「地震」に絞ったリスクヘッジ方法をお伝えしていきます。
自然災害発生のリスクについて
自然災害には様々な種類がありますが、特に不動産投資に影響を与える災害は「地震」と「水害」といわれています。特に日本は「地震大国」といわれているくらいですから、やはり地震への対策は必要不可欠です。ここでは、記憶に新しい東日本大震災における被害状況を例にみていきましょう。
東日本大震災による物件被害数
東日本大震災の被害は住居で約12万棟が全壊、約28万棟が半壊でしたが、これらの多くは木造住宅や耐震基準が古いものばかりだったといわれています。分譲マンションでの被害は大破はなかったものの、約18%は中破・小破といった被害がみられ、外観にはほとんど影響がない被害(軽微)は62%。逆に被害がなかったマンションは、全体の18%ほどでした。
東日本大震災は未曽有の事態だったとはいえ、このように災害による被害は甚大になるといえるでしょう。
地震による被害状況例
東日本大震災の際は、具体的に下記のような被害がでています。
- 玄関扉の破壊
- タイルの剥離や建物の損傷
- 立体駐車場や機械式駐車場の破損
- 屋上にある水槽タンクの破損
- 液状化による配管破損や浮き上がり
- エレベーターの破損による閉じ込め
- 下水道の停止
- 電気系統の不具合
- 津波による水害
このように、物件の大破とまでいかなくとも大小様々な損傷が起こり、修繕をしなくてはならない状況になりました。いつ起こるかわからない地震ですが、修繕費などの莫大な出費を避けるためにも地震保険の加入や見直しは今のうちにしておくべきです。
日本における地震の発生率(海外との比較)
そもそも「地震」は、なぜ起きるのでしょうか。
地震の原因は、地球全体に覆われたプレート(岩盤の板)です。この分厚いプレートは常に少しずつ移動しており、その際プレート同士がぶつかったり、重なり合うプレートがズレたりすることで地震が発生します。そうなると「プレートの境界線」が特に地震が発生しやすい場所になります。実は、日本は世界的にみても珍しい、4つのプレートがぶつかり合う場所に位置しています。そのため「地震大国」としてよく知られています。
日本の大地震発生率は全世界の20%を占める
世界中で起きている地震の中で、マグニチュード6.0以上の大地震の約20%は日本で起きています。さらにそれだけではありません。人が振動を感じるほどの地震は年に1,100回以上も起こっています(1日あたり3〜4回程度)。日本が地震大国と呼ばれるのも頷けます。
分散投資は地震にも有効?
このように地震大国といわれる日本では、絶対に安心といえる場所はないといえるでしょう。しかし同時に全ての地域で災害が起こるわけではないので、分散投資は非常に有効です。中でも自然災害に強いエリアを選ぶことで、しっかりとリスクヘッジができます。
自然災害に強いエリアとは?
自然災害や二次災害で考えられるリスクは、建物崩壊・津波・原子力発電所爆発・放射能汚染・土砂災害・台風などです。それらを踏まえた上で損害保険の活用をしっかりすることと、自然災害に強いエリアを見極め強度のある建物を選択することが重要です。
自然災害に強いエリアの例をいくつかご紹介します。
また、建物の選定基準には「新耐震基準」(1981年6月以降の建築申請)の建物であることを基準にすると良いでしょう。
地震はもちろん、景気変動のリスクにも対応できるので分散投資はおすすめです。
事前に入っておくべき、災害に関連する保険とは
不動産オーナーが加入すべき保険は義務ではなく、任意になります。とはいえ、保険未加入のオーナーはほとんどいないのが現実。それは予期せぬ災害によりでた損害をオーナー自ら負担することが、いかにリスクが高いのかを理解しているからでしょう。
加入を検討するべき保険としては「火災保険」「地震保険」「施設賠償責任保険」「孤独死保険」などがありますが、ここでは災害に関する保険を紹介します。 自然災害をカバーするおすすめの保険は「火災保険」と「地震保険」の2つです。
参考不動産投資を始める前に必ず理解しておくべき8個の保険制度
地震保険と火災保険はセット?
地震保険は単独では加入できず、火災保険の特約として加入する形になります。地震保険は地震・噴火・津波での損害を補償してくれるものです。火災保険は火事による損害をカバーするものですが、地震によって起こる二次災害での火災はカバーできません。
1923年に起きた関東大震災では、地震による建物崩壊数の18倍もの数が火災によって失われました。これは地震による二次災害の恐ろしさがわかる事例であると共に、火災保険と地震保険の融合が幅広い損害をカバーするのに有効であることの裏付けにもなるでしょう。
保険料は上がりますが、いつ大きな地震が起こるかわからない日本において地震保険は必須ともいえます。
火災保険は火事以外にも補償される
火災保険は自然災害時の被害においても補償されます。補償内容をみていきましょう。
火災保険で補償できること
- 排水設備の故障などによる水漏れ
- 落雷による建物損傷
- 大雨などによる床上浸水
- 強風によるベランダや屋根・窓ガラスの損傷
- 窃盗や盗難による建物損傷
このように火事以外の被害にも手厚い補償がついていますが、火災保険で補償できないパターンもあります。
火災保険で補償できないパターン
- 地震による建物損傷や津波などの被害
- 噴火による火事や建物損傷
- 故意に建物を破壊した場合
このように火災保険では補償できないケースもあります。しかし、火災保険+地震保険に加入していれば上記で紹介した全ての損害を補償することができます。
保険金額が足りないケースも想定しておく
保険に入ってるからといって、全てが補償されるわけではありません。火災保険の保険料の30〜50%の範囲内で地震保険の金額を定めるため、全ての自然災害を保険のみでカバーできない可能性もでてきます。
加えて、保険金額は5,000万円という上限が定められているので、高額物件にとっては痛手となるでしょう。それらを踏まえた上で、念のためキャッシュの確保はしておいた方が安全といえます。
物件購入時に確認しておくべき重要なこと
これまで自然災害のリスクや保険についてご紹介してきましたが、ここでは自然災害のリスクヘッジの一つでもある「建物選び」について詳しくお伝えします。
新耐震基準を満たしているか
まず、購入を検討している物件は「新耐震基準」を満たしているかを確認しましょう。建築基準法には耐震性の基準もあり、その基準は大地震がある度に改正されてきました。
新旧どちらも建物の耐震性を図るための一つの基準ですが、新耐震基準は1981年6月1日以降の建築から適用されるようになった耐震基準です。
旧耐震基準は「震度5で倒壊しない」というものでしたが、新耐震基準では「震度6〜7の地震でも倒壊しない」と更に厳しくなりました。
2016年に起きた熊本地震では、旧耐震基準の建物は32.1%が倒壊。新耐震基準の建物は7.6%が倒壊と、かなりの差がでています。このような背景も踏まえ、新耐震基準を満たしているかを確認することは物件選びで重要ともいえます。
新耐震基準を満たしているか見極めるポイント
物件を購入する際、新旧の耐震基準の見極めが大切になってきます。見極めるポイントは2つです。
建築確認済証の交付日
新旧の境目は1981年6月1日なので、建築確認済証の交付日がそれ以降か確認しましょう。
建物が完成した日にちが1981年6月1日以降であっても、建築確認済証の交付日がそれより以前の可能性もありますので注意が必要です。
木造建築は2000年以降がベスト
木造建築においても、阪神淡路大震災での木造建築物崩壊を受け耐震基準が改正されています。そのため、より高い耐震性を示すといえる2000年6月1日以降に建築確認済証が交付されているものを選ぶと良いでしょう。
中古物件を購入する際、「耐震基準適合証明書」があるか確認する
耐震基準適合証明書は、その建物の耐震性が現在の建築基準法に適合しているかを証明するものです。この耐震基準適合証明書があれば、築年数要件がある住宅ローン減税も受けられます。
住宅ローン減税対象物件
| 耐火構造(コンクリート造) | 築25年以内 |
|---|---|
| 非耐火構造(木造) | 築20年以内 |
つまり、築25年以上経過したコンクリートマンションや築20年以上経過した木造マンションでも、住宅ローン減税を受けることができます。築年数の計算は【建物登記日(新築年月日)〜引き渡し日】となるので、しっかりと確認しましょう。これは数日ズレただけで、数百万円もの損失がでる可能性もあります。
上記の年数を超えていても耐震基準適合証明書があれば減税を受けることができるので、要件に当てはまる物件購入を検討している際は、必ず売主に「耐震基準適合証明書」があるかを確認した方が良いです。売主が持っていない場合は、購入前であれば取得をお願いすることも検討しまましょう。
実際に災害が起こった時
実際に災害が起こってしまったら、どのように対処すれば良いのでしょうか?
保険以外にも公的支援制度があるので、そちらを活用することが大切です。
公的支援を利用する。災害の公的支援制度3つ
自然災害によって損害を受けた際に、支援を受けるためにもまずは「罹災(りさい)証明書」を取得しましょう。証明書の発行は無料で、この証明書は様々な被災者支援を受ける際に必要となります。
罹災証明書の発行には1ヶ月程の時間がかかる場合もあるので、その際はひとまず「罹災届出証明書」を活用しましょう。こちらは即日発行で、罹災証明書の代わりにもなります。
また、建物以外の自動車や家財が損傷した場合は「被災証明書」が使えます。
こちらも即日発行されるので、同時に取っておくと良いでしょう。
「被災者生活再建支援制度」
大きな自然災害(暴風・豪雨・豪雪・津波・洪水・台風・地震・噴火)により家屋が損害を受けた場合、最大300万円を無償で受け取ることができます。ただし、適用されるかは法律で定められた被害内により、都道府県の公示で確認できます。
この支援金は主に2つの柱からなっており、「基礎支援金」は全壊なら100万円・大規模半壊なら50万円と被害額によって異なります。
「加算支援金」は家屋の再建方法によって異なり、再建築・再購入なら200万円。補修なら100万円、賃貸なら50万円の支給となります。
それらを含め、最大で300万円ということです。
「災害復興住宅融資(住宅金融支援機構)」
家屋の全壊・大規模半壊・半壊のいずれかの罹災証明書が交付されている人対象の、特別融資です。受付は被災から2年間で、すでに修繕工事が進んでいる人は融資を受けることができないので、まずはじめに問い合わせてみることをおすすめします。
参考災害復興住宅融資
災害援護資金
災害援護資金とは、災害により財力を失い生活が困窮している人に対して、生活の立て直しを援助する特別な貸付制度です。
対象災害は「都道府県内で災害援助法が適用された市町村が1以上ある災害」となっており、都道府県のホームページから確認することができます。
家財の3分の1の被害または、家屋が半壊以上の被害を受けた人が対象になります。
最高貸付額は350万円、最低貸付額は150万円からです。貸付金額は所得や被害状況によって異なります。
返済が必要な貸付制度から無償の保証制度まで用意されているので、被害状況を確認した上で申し込みをすると良いでしょう。
知っておくべき!Googleが提供している「災害マップ」「防災マップ」
Googleが提供している災害情報マップは、日本全国の状況をリアルタイムで把握することができます。地震や津波の情報はもちろん、台風の進路まで把握することが可能です。
このマップは引越しや不動産購入時にも役に立ちます。
- 避難場所エリアの確認
- 非常時用の公衆電話の場所を確認
- 火災危険度をエリア別に確認
- 建物倒壊危険度をエリア別に確認
これら全てを総合的にみて算出された、総合危険度をエリア別にみることもできます。
その危険エリアを避けて物件購入や引越しを検討すると良いでしょう。
参考災害情報マップ
不動産投資に地震のリスクはつきもの。知識を養って備えるべし
地震のリスクを恐れて不動産投資を躊躇する人もいます。たしかに地震大国日本において地震を避けることは不可能と言えます。
しかしだからこそ、公的支援や耐震性を確認してから物件を購入し、地震保険に必ず加入するなどリスクヘッジをすることが大切です。逆にいえば、どんなビジネス・投資案件にもリスクはつきものです。リスクヘッジさえしていれば、今の日本でも不動産投資で利益を生んでいけるでしょう。