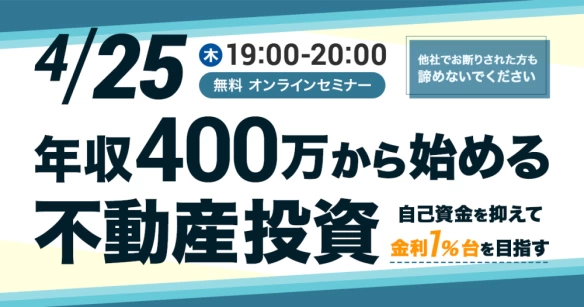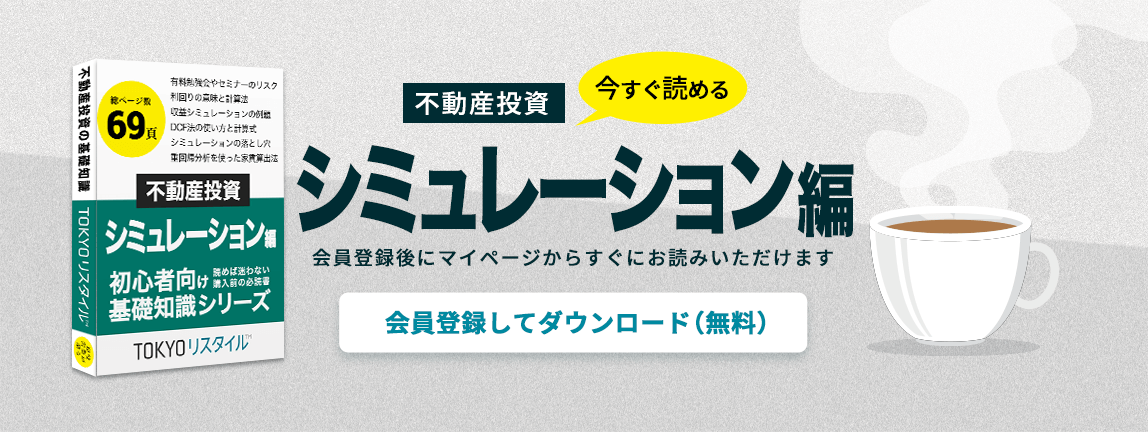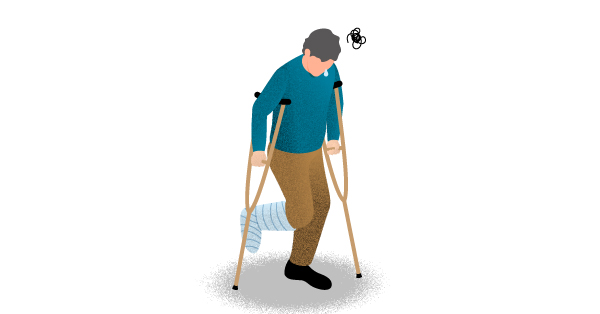不動産投資のポートフォリオとは?その重要性やノウハウを解説!
- 更新:
- 2022/11/21

金融庁の試算では「老後20~30年間で約1,300万円~2,000万円が不足する」と言われており、銀行預金だけでなく資産を運用することの重要度が高まっています。
資産運用のための投資先には株式・債券・FX・不動産など様々な種類があり、リスクやリターンの度合いが大きく異なります。どの投資商品で資産運用をすべきか、迷う方も多いと思います。
そこで重要になってくるのが、分散投資という考え方です。一つの投資先に資産を集中することはリスクを伴うため、投資先を分散することで安定した資産形成に臨むことができます。どの投資商品にどれほど資産を配分するかを定めることを「ポートフォリオ」と呼びます。
不動産投資を含めてポートフォリオを考える際、注意点としてはポートフォリオの意味合いが2種類ある点です。例えば、全体のポートフォリオの中に「不動産投資50%、株式25%、預金25%」といった形で、不動産投資という投資商品が組み込まれるケースが1つ目の考え方です。2つ目の考え方は、「物件A40%、物件B30%、物件C30%」というように、不動産投資自体でポートフォリオを組むことです。
つまり、不動産投資「を」ポートフォリオに組み込むことと、不動産投資「で」ポートフォリオを組むことの2種類があるのです。この点が投資初心者には若干ややこしく、また考えることが増えるためつまづくポイントでもあります。その結果、リスクの高い金融商品に資産を全てつぎ込んでしまい……。といった失敗を犯さないためにも、ぜひこの記事で不動産投資を含めたポートフォリオの作り方やメリットをご参照ください。
分散投資とポートフォリオについて
不動産投資を含めたポートフォリオについて説明する前に、初心者の方に向けて、改めて分散投資とポートフォリオについて簡単に解説していきます。
分散投資とは
分散投資とポートフォリオは似た文脈で使われることが多いですが、厳密には意味合いが異なります。まず分散投資とは、「投資対象やタイミングを1つに集中させず、いくつかに分けること」を指します。
金融庁作成の「投資の基本」という記事では、分散投資のやり方として「資産(銘柄)の分散」「地域の分散」「時間(時期)の分散」の三種類を挙げています。
株式や債券、不動産といった投資商品は常に同じ値動きをするわけではないため、資産(銘柄)を分けることはリスクヘッジの面でメリットがあります。地域を分散することで、特定の国や地域でハイパーインフレや株価の暴落が起こったとしても、他の資産でカバーすることができます。投資の時間(時期)を分散することで、景気や短期的な価格変動に資産が左右されるリスクを軽減することができます。
このように、分散投資のメリットは投資におけるリスクを抑え、なるべく安定した資産運用をおこなうことにあります。この分散投資の投資先を具体化したものが、ポートフォリオになります。
ポートフォリオとは
ポートフォリオとは、「どの投資商品にどれだけの割合で資産を配分するかを定めた金融資産の組み合わせのこと」を指します。複数の資産や時期にわけて投資をおこなう分散投資について、より具体的に表したものがポートフォリオです。
ポートフォリオは収益性やリスクと照らし合わせて、後から組みなおすこともできます。年金の運用をおこなうGPIF(年金積立金管理運用独立行政法人)は、2020年4月からポートフォリオにおける国内債券の割合を減らし、外国債券の割合を高めています。
上記のポートフォリオでは大枠の投資先とその割合のみを示していますが、ポートフォリオは基本的に、具体的な投資商品の銘柄までを考えて作成します。上記は公的機関の資産運用のポートフォリオであるため、具体的な銘柄は控えて発表されていると考えてよいでしょう。
分散投資における投資先の割合や銘柄を具体化したものがポートフォリオであるとお考え下さい。
不動産投資をポートフォリオに組み込むメリット
分散投資とポートフォリオの意味合いを理解したところで、不動産投資をポートフォリオに組み込むメリットを見ていきましょう。
ミドルリスク・ミドルリターンである
銀行預金がローリスク・ローリターン、株式やFXがハイリスク・ハイリターンな資産運用である中で、不動産投資はミドルリスク・ミドルリターンな投資先と言えます。家賃収入による安定した収入が見込める一方で、空室リスクや震災リスクといった懸念点もありますが、後述の不動産投資自体でポートフォリオを組むことによりリスクを抑えることができます。
インカムゲインとキャピタルゲインが得られる
不動産投資の特徴として、インカムゲインとキャピタルゲインの双方が見込める点です。
インカムゲインとは資産を保有することにより継続して受け取れる利益のことを指し、不動産投資では家賃収入がインカムゲインにあたります。キャピタルゲインとは保有していた資産を売却することにより得られる利益のことを指し、不動産投資では物件を売却することでキャピタルゲインが得られます。
築年数により物件の価値が目減りし、想定していたキャピタルゲインが得られないこともありますが、物件の適切な管理と立地の選定により売却時のキャピタルゲインを狙うことも可能です。ただし、不動産物件は買い手があらわれて初めて売却が可能になります。短期的な売買によるキャピタルゲインではなく、家賃収入のインカムゲインによるミドルリターンな投資先として、ポートフォリオに組み込むほうがよいでしょう。
他人資本を活用できる
不動産投資の大きな特徴として、金融機関による融資という他人資本を活用できる点です。
株式の現物取引のように自己資金のみでおこなう投資は、どうしても扱える金額が限られてしまうため、大きな資産を保有することが難しくなります。一方で、株式の信用取引やFXのように、レバレッジという自己資金の何倍もの金額で取引をおこなう方法は、ロスカット(強制決済)というリスクを伴います。
金融機関からの融資により物件を購入し、ローンを家賃収入から返済する仕組みをもつ不動産投資は、他人資本でありながら極力リスクが抑えられる投資と言えるでしょう。
インフレ対策ができる
日本経済の今後について、専門家の間でも意見が分かれるところですが、インフレという見方が強くあります。現物資産である不動産は、金融資産よりも価値が下がりにくいためインフレ対策に向いているとされています。
インフレとはモノの価値が上がり、お金の価値が下がる状態のことです。一概には言えませんが、インフレ時には「お金を貸している状態」が損になり、「お金以外の資産を保有している状態」が得になります。そのため、銀行にお金を預ける銀行預金や企業や機関にお金を貸し付ける債券は、インフレ時には旨みが減ってしまうと言えます。
そのため、インフレ対策として不動産投資をポートフォリオに組み込むことが有効と言えるのです。不動産投資とインフレについて、詳しくは当サイトのこちらの記事もご参照ください。
参考アフターコロナに備えよう!インフレ対策に不動産投資が効果的な理由とは?
不動産投資をポートフォリオに組み込む方法
不動産投資をポートフォリオに組み込むメリットをご紹介したところで、次は具体的にポートフォリオを作成する方法をご紹介します。
初期の投資金額や目標利回りを考える
ポートフォリオの作成にあたって、まずは自身が投資に使える初期の投資金額と、資産運用による年間の利回りの目標を考えましょう。
利回りとは、投資金額に対する収益の割合を指します。100万円の初期投資に対し、年間6万円の利益が出た場合、利回りは6%となります。似たような言葉で「利率」というものがありますが、利率は毎年受け取ることのできる利息の割合のことを指し、主に債券や預金に対して用いられます。
注意点として、年間の目標利回りが高すぎると投資のリスクも高まってしまうことが挙げられます。極端な例でいえば、年間で自己資金を2倍にしようとすると、100%の利回りを目指すことになります。利回り100%を見込むにはFXや仮想通貨でレバレッジを用いた取引をおこなうことになり、投資ではなく投機の分野になってしまいます。現実的な利回りを見込み、安定性を意識したポートフォリオを組むようにしましょう。
資産・地域・時間の分散を考える
投資のための自己資金と目標利回りをチェックしたところで、分散投資の項目でご紹介した資産・地域・時間の分散を考えてみましょう。
資産の分散には、株式・債券・投資信託・海外通貨・不動産・現金預金などが挙げられます。地域の分散は海外の通貨や株式を保有したり、後述のように複数の地域の不動産物件を保有することが当てはまります。時間の分散は、投資に使える自己資金のすべてを一度に使うのではなく、現金の余裕を持たせつつ投資のタイミングをズラす投資計画が当てはまります。
時間の分散について、特に不動産投資の場合、初心者の方と資産の運用実績・ローンの返済実績のある方では金融機関から降りる融資の金額が変わってきます。最初は1つの物件で不動産投資をおこない、運用実績がついたところで新たな融資を受けて物件を増やすというやり方も、効果的な時間の分散になります。
不動産投資でポートフォリオを作るメリット
投資商品全体でポートフォリオを作る方法を見たところで、不動産投資自体でポートフォリオを作成することを考えてみます。「物件A40%、物件B30%、物件C30%」といった形で、不動産投資の中でも分散投資をおこなうことには複数のメリットがあります。まずはそちらを見ていきましょう。
分散投資によりリスクを軽減できる
特定の地域やマンション1棟のみでの投資は、大学や企業の移転に伴った空室リスクが生じる可能性があります。また、地震による土砂崩れや地盤沈下、外壁やガラスの損壊といったリスクもあります。
空室保証や地震保険により空室リスク・震災リスクを抑えることができますが、どちらも満額が支払われるケースは稀であるため、これらの制度に依存しないほうがよいでしょう。複数のエリアで物件を所有することにより、これらのリスクを軽減することができます。
融資金額と所有物件を戦略的に拡大できる
先述のように、不動産運用の実績がつくことで金融機関からの融資金額を拡大することが見込めます。時間の分散を意識したポートフォリオを作成することで、計画的に運用実績を示し、金融機関という他人資本により2件目、3件目と所有物件を増やすことができるようになるのです。
所有物件を段階的に増やすにあたり、前もってポートフォリオを組んでおくことで、狙っている物件像を具体的に不動産会社に示すことができます。探している物件像が明確なほうが、不動産会社も物件に対しアンテナを張りやすく、好条件の物件を優先的に紹介してもらえる可能性が高まります。
ポートフォリオを組まずに不動産投資をおこなってしまうと、融資条件の満額で1棟マンションを購入するなどして、ローンの返済実績を作ったり所有物件を増やしたりすることが困難になってしまいます。よほどの好条件の物件が偶然見つかるようなケースを除けば、融資金額と所有物件を段階的に拡大する戦略をとったほうがよいでしょう。
不動産投資でポートフォリオを作る方法
不動産投資自体でポートフォリオを作成するメリットをご紹介したところで、次は具体的なポートフォリオの組み方をご紹介します。先述の「資産の分散・地域の分散・時間の分散」に照らし合わせてご説明しますので、それぞれ見ていきましょう。
物件の種類による分散
分散投資の考え方の中に資産の分散があるように、不動産投資自体も物件の種類で分散させることがリスクヘッジにつながります。
物件の種類は、まず商業用と居住用に分かれます。居住用の物件は戸建て・アパート・マンションに分けられ、特にマンションは1棟買いと区分所有に分けられます。さらに細かく分類すると、太陽光発電やコインランドリーなども投資対象となります。
商業用の物件は新型コロナウイルスの影響によりオフィスの移転が増加していることから、投資対象としてややリスキーと言えます。分散投資といっても闇雲にさまざまな種類に投資対象を分ける必要はないため、特に初心者の方は、「居住用の区分マンションと一棟マンションを所有する」といった形での分散がやりやすいでしょう。
物件のエリアによる分散
先述のように空室リスクや震災リスクを抑えるには、複数のエリアで物件を所有することが効果的です。一方で、例えば都内のマンションと田舎のアパートを所有した場合、物件の管理が大変になってしまいます。
物件の保有を段階的におこなうとして、1件目の地域の空室リスクや震災リスクを踏まえ、リスクの高いポイントをカバーできるような物件を、遠すぎないエリアで追加投資することが理想的なパターンのひとつです。
例えば千代田区は家賃が高く住民層がよい傾向にありますが、ハザードマップを参照すると神田川の氾濫の恐れがあるエリアが見られます。こうしたエリアで不動産投資をおこなう場合は、中野区や杉並区などで水害のリスクが低い地域の物件と組み合わせることにより、弱い部分をカバーできるポートフォリオを作ることができます。
物件の築年数による分散
時間の分散という観点からは、投資のタイミングに加えて物件の築年数で分散させる方法が有効です。
築年数が近い物件を複数所有していると、近いタイミングで修繕をおこなうことになり、修繕費で資金がショートしてしまう可能性があります。例えば築浅の物件と築20年の物件を組み合わせることで、修繕のタイミングだけでなく、減価償却期間や売却のタイミングもズラすことができます。
リスクを抑えたバランスのよい資産運用をおこなうためには、築年数の分散を意識することが効果的なのです。
まとめ
今回の記事では、不動産投資を含めてポートフォリオを作るメリットや方法をご紹介しました。
不動産投資を複数の投資商品の中に組み込みつつ、不動産投資自体でも投資先を分散させるという考え方は、初心者の方にはなかなかハードルが高いものだと思います。また、自己資金や目標利回りによって投資の戦略も変わってくるため、万人に共通する正解がないのが現状です。
お客様個々人のお望みに適した投資プランをご希望の方は、当社の投資コンサルタントまでお気軽にお問い合わせください。