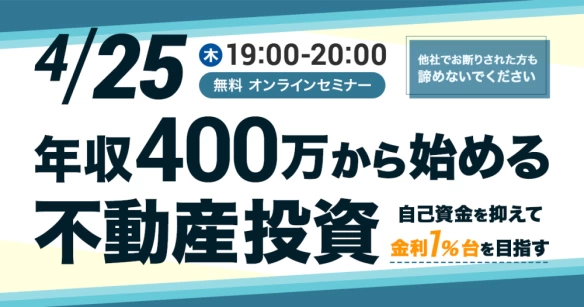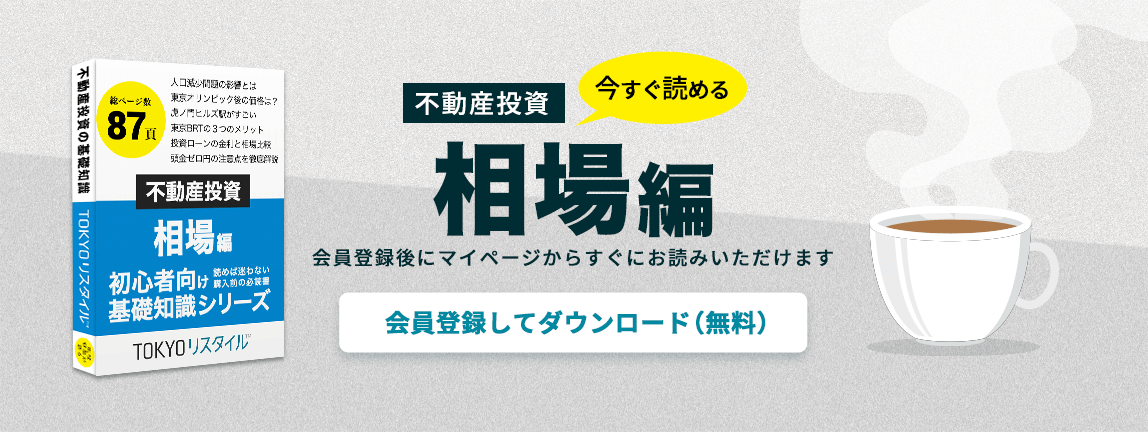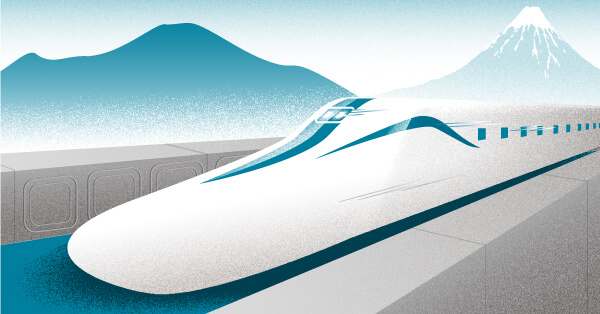最終的にどうなる!?マンションの寿命と出口戦略を解説!
- 更新:
- 2022/09/30

不動産投資で中古マンションの購入を考えている人の多くは、「購入したマンションはいつまで保つのか」というマンションの寿命が頭をよぎるのではないでしょうか。寿命が来た後もマンションを抱えていると負債になってしまうため、マンションの寿命が来る前に出口戦略を考えることになります。
こうした検討事項は、新築・築浅の物件のオーナーもいずれ向き合うことになる課題です。不動産は現物の資産である以上、年月の経過と共に損傷・劣化していくものだからです。しかし、マンションの寿命についての知識を持っておくことで、手放す前段階から余裕を持って準備が出来るようになります。
そこでこの記事では、マンションの寿命や築古マンションの出口戦略について、実在の不動産の例を交えながら解説します。特に中長期的な不動産経営を考えている投資家の方に有用な記事となっておりますので、ぜひ自身の投資計画にお役立てください。
マンションの寿命
この項目ではマンションの寿命について解説します。「いつマンションに寿命が訪れるか」は実のところ単純な話ではなく、何を基準とするかによって解釈が異なります。また、マンションが建てられた時期によっても寿命に差が生まれます。詳しく見ていきましょう。
一般的な寿命は68年
国土交通省が2013年に公表した「中古住宅流通促進・活用に関する研究会」報告書によると、鉄筋コンクリート造の住宅の平均寿命は68年とされています。また、同資料では鉄筋コンクリートの構造体としての持続年数は120年、適切な処置を施した場合は150年まで延命できるとしています。
一方で、東京カンテイによる2014年のプレスリリースでは、建て替えられたマンションの寿命は平均33.4年とされており、上記の寿命・耐用年数よりも大幅に短いことが分かります。
加えて、鉄筋コンクリート造の法定耐用年数は47年と定められています。これらの数字のバラつきをみると、マンションの寿命は一口に定まらないことが分かります。
| 内容 | 年数 |
|---|---|
| 国土交通省による平均寿命 | 68年 |
| 構造体としての持続年数 | 120年~150年 |
| 建て替えが起きたマンションの平均寿命 | 33.4年 |
| 法定耐用年数 | 47年 |
これらの数値に差が生じるのは、「何に着目して寿命としているのか」の定義が異なるためです。表の上2つの項目については、住宅用途としての寿命と、建物がその場に建ち続けるための寿命の差があります。外装・内装ともに廃墟同然にボロボロになった建物に住むことは実質的に不可能なため、構造体としての寿命より住宅としての寿命が先にくるのは理解しやすいでしょう。
また、法定耐用年数とは減価償却を行う際に用いる数値的な基準であるため、実際にマンションが居住に耐えうる年数とは異なります。あくまで便宜上の数字であることから、マンションの寿命の基準からは外しても問題ありません。
その上で、実際に建て替えが起きているマンションの寿命が平均33.4年と、他の数値より大幅に短いのにも理由があります。建て替えが起きた多くのマンションでは、配管・建材・耐震の面で問題を抱えています。
1960年~1970年代に建てられたマンションには、コンクリートに埋め込む形で配管設備を設置しているものが多くあります。配管のみを取り出して付け替えることが困難なため、水回りなどの配管設備に問題が生じた場合には、建物ごと建て替える必要に迫られます。
また、同じく1970年代のマンションには建材の質が悪いものが見られます。コンクリートの品質が悪いとひび割れや雨漏りに繋がり、居住用マンションとしての寿命を大きく引き下げます。
そして、1981年6月以前に建てられたマンションは「震度5程度の地震で建物が崩壊しない」という旧耐震基準を採用しており、震度6以上の地震に耐えうる構造をしていません。一方で、1981年以降のマンションでは新耐震基準が採用されているため、災害クラスの地震でも倒壊しない構造をしています。
旧耐震基準のマンションには、国土交通省主導で補強工事の実施が奨励されています。しかし、補強工事は高額で期間も長くなるため、補強という選択をせずに新耐震基準のマンションに建て替えてしまうことも珍しくありません。
| 建て替えの原因 | マンション建設時期 |
|---|---|
| 配管設備の構造 | 1960年代~1970年代 |
| 建材の質 | 1970年代 |
| 旧耐震基準 | 1981年以前 |
現在建てられているマンションの多くは、配管・建材・耐震の面で上記の課題をクリアしています。そのため、現在公表されている建て替えの統計データが33.4年を示しているとはいえ、これからのマンションの寿命を33.4年とするのは早計と言えます。建築技術や補強技術は年々進歩しているため、マンションの寿命は従来よりも伸びていくと考えてよいでしょう。
また、立地によってもマンションの寿命は異なります。例えば、海沿いの立地であれば潮風によって配管のサビや建材の腐食が起こりやすくなり、山沿いであれば日当たりの悪い箇所は湿気によるダメージが蓄積します。
そのため、マンションの平均寿命を数値的に提示することは可能ですが、建設時期や立地により寿命は大きく異なると言えます。ただし、「同様の条件をもつマンションがいつ頃建て替えに至ったか」を調べることで、より実際の寿命に近い数値を導き出せることは覚えておきましょう。
築年数の古い都心マンションの例
マンションの寿命は条件により異なることをお書きしましたが、築年数の古いマンションが長く使用された例を具体的にご紹介します。
1929年に竣工した同潤会の「上野下アパート」は、2013年の建て替えに至るまで84年間にわたり集合住宅として機能していました。先述の「建て替えが起きたマンションの平均寿命」の33.4年を大きく上回る事例であることが分かります。
上野下アパートが80年を超える寿命を持っていた背景には、1923年の関東大震災があります。同潤会は震災の復興支援を行うべく設立された団体であり、同潤会のアパートは防災を意識した設備・構造をもっています。当時に建設された集合住宅には珍しく、災害時でも機能する非常用電源や備蓄庫、地震の被害を抑える制振装置を備えています。
近年建て替えが起こったマンションよりも前に竣工したにも関わらず、上野下アパートが平均寿命よりも長く集合住宅として機能したのは、震災を意識したことで旧耐震基準のマンションよりも堅固な構造となっていたためです。こうした事例からも、建設時期や立地などの条件によりマンションの寿命が大きく変化することがお分かりいただけると思います。
築古マンションの「その後」にある選択肢とは?
寿命が訪れたマンションは、建物を解体して売却されるか、新しいマンションに建て替えられるかの二パターンに大きく分かれます。それぞれ具体的に見ていきましょう。
選択肢①:住民の引っ越しを経て解体して売却
一つ目は、すべての住民の同意を得て、住民の引っ越しが完了した後に建物を解体するという方法です。
マンションの売却費用が発生するため、住民には潤沢な資金が分配されると思われがちですが、実際には解体費用が差し引かれるため大きな貯蓄には繋がりません。引っ越しの費用や手間を考えると住民全員の同意を得ることは難しく、入居率の高い集合住宅で解体まで至るケースは非常に稀と言えます。
また、住民の同意を得られる可能性が上がる方法として、不動産仲介会社や建設会社に物件を売却した後、建設会社が新たに建物を建て直すという流れが挙げられます。
解体後に売却という流れでは、住民が引っ越ししてから売却益の入金までにタイムラグが発生します。この場合、引っ越し費用が金銭的な圧迫となる住民からは中々同意が得られません。そのため、売却後に解体という流れにより少しでも売却益の入金を早めることで、住民の経済的な負担を軽くすることが見込めます。
ただし、集合住宅の解体は1人でも同意が得られなければ実行に移せません。多くは管理組合主導で建て替えの審議が行われ、合意形成のもと承諾という手続きを踏みますが、マンションが区分所有されている場合は利害関係者が増えることもあり、決議が難航しがちです。
選択肢②:一定以上の住民の賛成を得て建て替え
住民全員の引っ越しという手続きを経ずに進められるのが、マンションの建て替えという選択肢です。集合住宅の解体は住民に新居を探して移ってもらう必要がありますが、建て替えであれば仮の住居に一定期間滞在してもらい、建て替え完了と共に帰ってきてもらう流れを組むことができます。
完全退去が必要な解体よりはエネルギーが少なくて済むものの、建て替えの場合は所有者の5分の4以上の賛成が必要になります。多くの場合、理事会から住民への啓蒙活動が行われ、実質的に住民が一体となり建て替えが推進されていきます。
ただし、建て替えは売却と異なり売却益が発生しないため、区分所有者は住民ローンを組むことで建て替え費用を捻出することになります。この点から所有者の賛成票を得ることが難しく、建て替えの準備が難航するケースが多発します。
この問題の解決方法として、建て替えにより新たな居住スペースを増設するやり方があります。例えば5階建て30部屋のマンションの場合、増設により7階建て42部屋となれば、12部屋分の販売額が見込めます。この新規販売益を既存の区分所有者に分配することで、建て替えによる負担額を抑えることが可能になります。
建て替えに至った事例として、「四谷コーポラス」という分譲マンションが挙げられます。1962年竣工の四谷コーポラスは、2006年の建て替え・大規模修繕工事の検討会の発足から、約10年後の2017年に建て替え決議が成立しました。
四谷コーポラスの建て替えにあたり、決議を通すべく区分所有者それぞれとの根気強い面談が行われました。特に重視されたのが、「建て替え後にどのような物件を所有したいか」についての具体的なすり合わせです。所有者の希望をなるべく実現できるよう間取りの調整を行い、実現が不可能そうであれば転出に向けて根強く話し合いを続け、1人ずつ合意を形成していきました。
2011年の東日本大震災により、老朽化したマンションに住み続けることの危険性が表面化したことも建て替えの後押しとなりました。9割近くの区分所有者が建て替え後の物件を再取得する形で審議が可決し、建て替えに至りました。
四谷コーポラスの事例からは、物件の建て替えはその必要性の啓蒙を含む、区分所有者や住民への根気強いアプローチが必要であることが分かります。
中古マンションの出口戦略
解体、建て替え双方の手続きが難航しうることを考えると、寿命を迎えるマンションの出口戦略は非常に難しい印象を持つかもしれません。しかし、寿命が訪れる前段階から売却に向けて動くことで、余裕をもって物件を手放すことが出来るようになります。具体的な戦略部分を見ていきましょう。
前提として、建て替え・解体が必要になる前から新たな買い手を探すことが推奨されます。不動産の売買には数ヶ月の期間が掛かるため、売却に動くのであれば1年間は余裕をもって行動しましょう。
人口が多く不動産の流通量の多い首都圏では、築古のマンションでも比較的簡単に買主を見つけられます。近年のトレンドとして、築古の物件をリノベーションすることで、購入費用を抑えて利回りを高く運用する投資方法があります。こうした背景から、リノベーションの自由度や取り組みやすさをアピールすることで、築古マンションの売却の実現性を高められます。
中古マンションを購入したい投資家向けの解説記事を以下にご紹介しますので、「魅力的な中古物件とは何か」を知る参考として併せてお読みください。
参考中古マンション購入時の注意点と、確認しておくべきポイント3選
また、どうしても買主の発見が困難であれば、不動産会社を売却先とすることで物件の買取をしてもらう選択肢もあります。買取は不動産会社がオーナー同士の仲介をしないため、クイックな売却が可能になる一方で、買取価格が大幅に下がるデメリットがあります。
| 仲介 | 買取 | |
|---|---|---|
| 売却先 | 買主 | 不動産会社 |
| 売却期間 | 数ヶ月 | 数日~1ヶ月 |
| 売却価格 | 市場価格 | 市場価格の7割~8割程度 |
買取は売却による利益があまり見込めないため、タイムリミットの迫る物件への救済措置とも言えます。買取しか選択肢のない状況に陥らないためにも、マンションに寿命が訪れる前段階から動くことを推奨します。
まとめ
今回の記事では、マンションの寿命と解体・建て替え、そして築古マンションの出口戦略について解説しました。
リミットが明確に存在する投資を行う上で、中古マンションに手を伸ばすのは中々リスクに感じるかもしれません。しかし、先述のように首都圏の築古マンションは充分に買い手が見つかりやすく、寿命の到来する前の段階であれば不動産会社の仲介によって出口戦略を取ることができます。
中古マンションの取り扱いにノウハウを持つ不動産会社と連携を取ることで、安定したマンション経営に臨むことが可能になります。中古マンション投資にご興味のある方は、弊社の個別面談をぜひご活用ください。