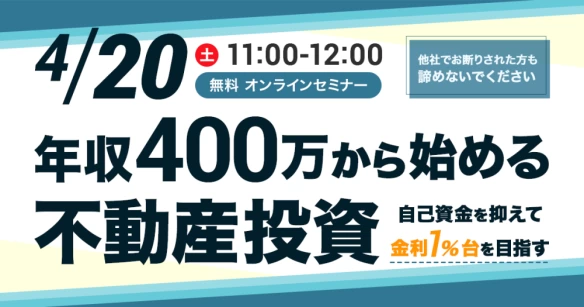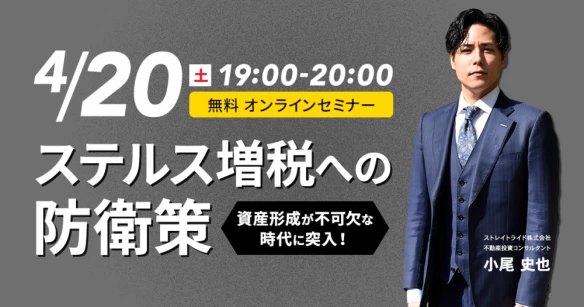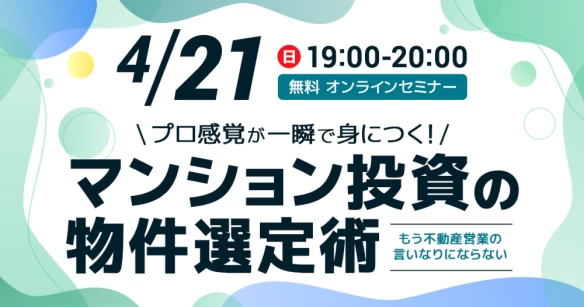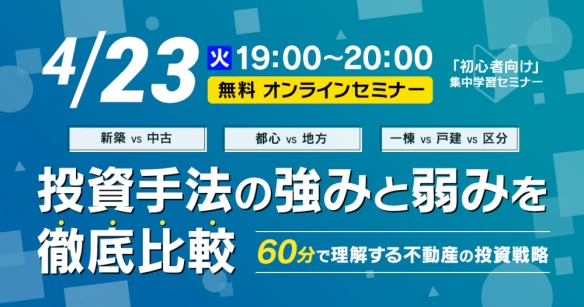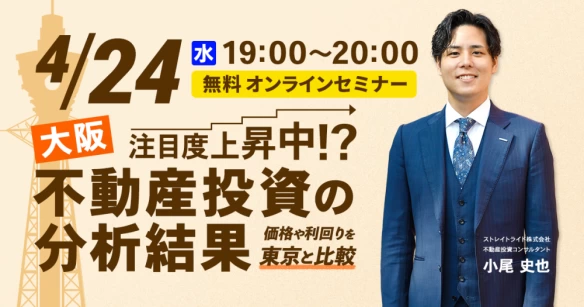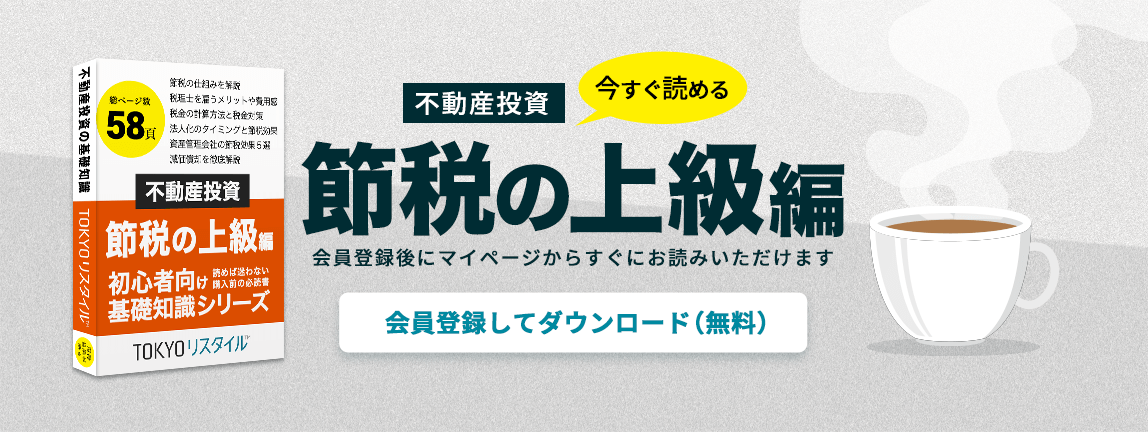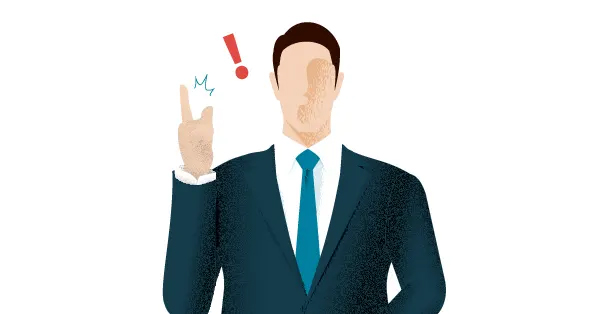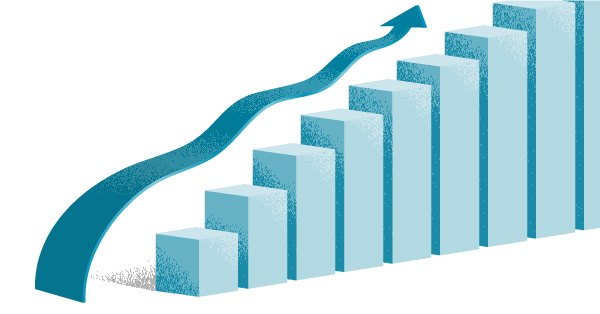【最新版】不要なケースも!家賃収入の確定申告を分かりやすく解説!
- 更新:
- 2022/08/18
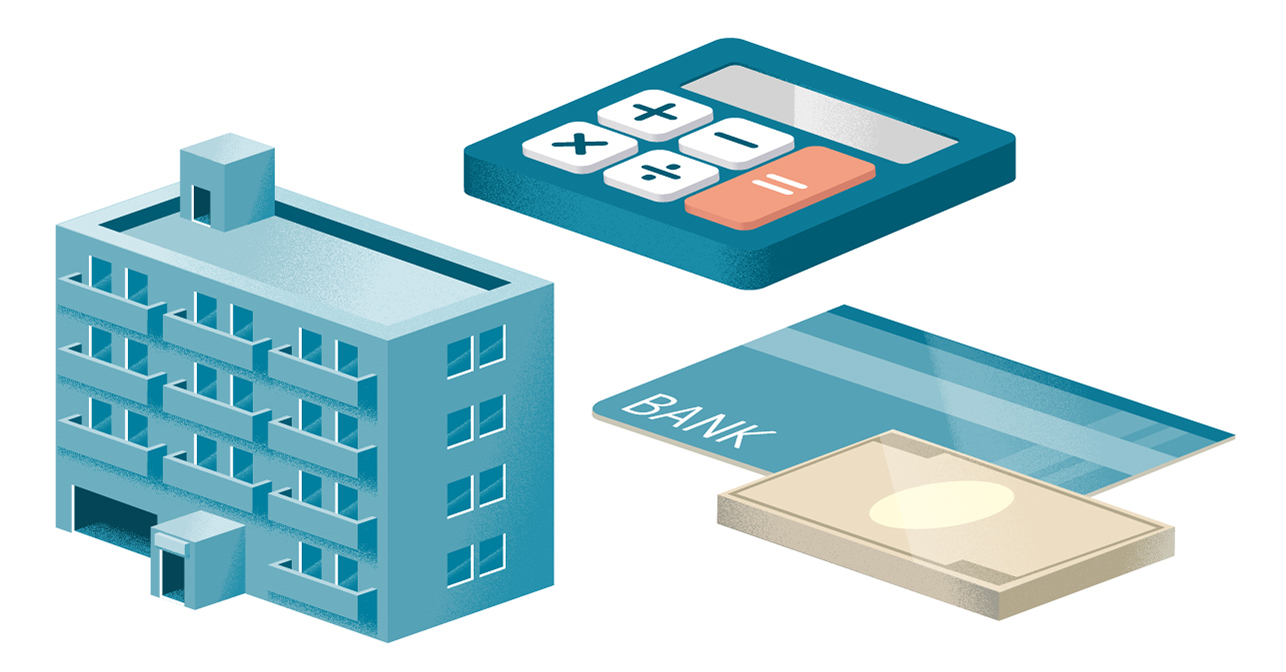
家賃収入や不動産所得がある方にとって、最も悩ましいイベントの一つが確定申告でしょう。色々と調べてはみるものの、どこも専門用語ばかりで、「結局のところどうなの!?」とお考えの方も多いのではないでしょうか。
まず結論から申し上げると、本業の給料以外の「不動産所得や事業所得・雑所得」の合計が年間20万円以内に収まっている場合には、確定申告は不要です。逆に言い換えれば、これらの所得の合計が20万円を超えていれば、確定申告を行う必要があるということです。
ここで一つ注意点があります。それは、「不動産所得」の考え方についてです。「家賃収入」が、入居者から受け取った家賃の金額を意味しているのに対して、「不動産所得」は、家賃などの不動産収入から必要経費を差し引いた、いわゆる利益の部分を指しています。
したがって、仮に家賃収入が合計で30万円であったとしても、必要経費が20万円であった場合には不動産所得は10万円ということになりますので、確定申告は不要となります。
初めて不動産投資を行われた方の中には、「不動産所得と家賃収入って同じじゃないの!?」と勘違いされる方もいらっしゃるのですが、実はこの2つは全く異なった意味を持っているので注意が必要なのです。
とはいえ、確定申告が不要であるからといって、申告をしてはいけない訳ではありません。むしろ、確定申告を行うことによって様々なメリットを享受できるのです。
本記事では、不動産に関わる確定申告について、とても分かりやすく解説をしています。確定申告を行う必要がある方や、「不要ではあるものの、申告をした方が得なのかな?」とお考えの方は、是非最後まで目を通していただければと思います。
確定申告が必要になる家賃収入の基準
確定申告が必要になるのは、給与以外の所得の合計が年間20万円を超えた場合です。
不動産所得のみではなく、事業所得や雑所得があればそれらを合算して20万円を超えるかどうかが判断基準となります。この判断基準に給与所得は含まれませんが、納税額は給与所得と合算した総所得をもとに決まります。
確定申告とは、自分の所得にかかる税金の額を計算し、税金を支払うための手続きです。家賃収入は複数の種類がある「所得」の中でも「不動産所得」に該当し、一定の条件に当てはまれば納税の手続きを行う必要があります。
不動産所得とは
「不動産所得」は「不動産収入」から「必要経費」を差し引き算出されます。不動産収入は1年間の家賃収入の合計を指し、「必要経費」とは修繕費や管理費といった不動産事業に必要な費用のことです。
- 不動産所得 = 不動産収入 - 必要経費
例えば、ある年にワンルームマンションを10万円/月で賃貸し、年間120万円の家賃収入を得て、必要経費として修繕費に100万円支出した場合、年間不動産所得は20万円です。20万円を超えていないので、申告は不要になります。逆に20万円を1円でも越えた場合は、申告が必要になります。
なお、「不動産所得」とは家賃収入だけではなく、次の3つの所得を指します。
- 土地や建物など、不動産の貸付けで得られる所得
- 地上権など不動産にまつわる権利の設定や貸付けで得られる所得
- 船舶や航空機の貸付けで得られる所得
これらのうち、事業所得や譲渡所得に該当しないのが不動産所得です。ここではおおまかに「家賃収入以外にも申告が必要な不動産所得がある」と覚えてください。
赤字でも確定申告すると損益通算で節税になる
不動産所得が赤字になった場合は、確定申告の義務はありません。しかし、給与など他の所得と損益通算することで所得税の節税が可能です。
損益通算とは、1年間の不動産所得が赤字の場合に、給与など他の所得と合算することです。
例えば、給与所得が400万円で不動産所得が赤字で100万円であれば、損益通算することで給与所得から不動産所得の赤字分を差し引くことができ、300万円のみに所得税が課税されます。
ただし、不動産所得で赤字を出した場合でも、次の内容に当てはまる場合は例外として損益通算できません。
- 別荘等のような生活に必要不可欠ではない資産の貸付け
- 一定の組合契約に基づいて営まれる事業から生じたものでその組合の特定組合員に係るもの
(個人が不動産投資をする場合には関係はありません) - 土地等を取得するための負債の利子に相当する部分の金額で一定のもの
確定申告しないとどうなるのか
確定申告対象者が申告を忘れたり、申告内容に漏れがあったりした場合、追徴課税されます。追徴課税には「重加算税」「延滞税」「過少申告税」の3つがあります。
申告していないと重加算税がかかる
重加算税は悪質なケースに適用されるペナルティです。所得の隠蔽又は仮装した時に課税されます。本来の納税額の35%、無申告で発覚した場合は45%が追加で課税されます。
遅れて申告すると延滞税がかかる
延滞税は、延滞日数・納税額・年度等によって税率が異なります。また、期日通り申告しても、修正申告が必要になった場合も延滞税がかかります。そのため修正申告が遅れるほど延滞税の金額が増えることになります。
延滞税には特例措置があり、規定の条件に当てはまれば一定の期間を延滞税の計算期間に含めないとすることができます。
申告額が少ないと過少申告加算税がかかる
過少申告加算税とは、個人における所得税などにおいて適正に申告を行ったものの、その後の税務署の調査で申告内容に誤りが発覚し、自主的に修正申告したり、税務署から更生処分を受けたりすることにより、本来納付すべき税金に加えてペナルティとして追加徴収される税金のことです。
家賃収入にかかる税金の計算方法
家賃収入にかかる税金は「不動産所得」と「所得税の税率」により算出されます。おおまかな計算方法は次の通りです。
- 家賃収入にかかる税金 = 不動産所得 × 所得税の税率 - 控除額
本来、税金は家賃収入だけで考えるものではありません。所得税には不動産所得以外にも、サラリーマンであれば給与やボーナスにあたる「給与所得」、事業主であれば事業からの儲けである「事業所得」など10種類の所得があり、税率は、この総額の大きさによって決定されます。課税所得の総額により決まる控除もあります。
参考不動産投資でかかる税金と「消費税増税の影響」について詳しく解説
不動産所得税の計算事例
例として、給与所得が480万円、不動産所得が120万円の場合の家賃収入にかかる税金の計算方法を示します。
(1)所得税率、控除額を求める
課税所得は、給与所得480万円と不動産所得120万円を加えた600万円です。この場合、所得税率は20%、控除額は427,500円です。
(2)控除額に家賃収入(不動産所得)の比率をかける
総所得に対する不動産所得の比率は【120万円 ÷ 600万円 = 20%】です。これを控除学にかけると、不動産所得にかかる控除額は【427,500円 × 20% = 85,500円】です。
(3)家賃収入にかかる税金の計算
【不動産所得120万円 × 所得税率20% - 控除額85,500円 = 154,500円】が不動産所得にかかる税金になります。
確定申告の方法
確定申告の手順は、以下のとおりです。
- 青色申告の申請書提出(事業開始後2ヶ月以内)
- 提出書類の準備
- 決算書の作成
- 確定申告書の作成
- 税務署へ提出
申請書の提出は2月16日~3月15日です。詳細は以下の記事にまとめています。
確定申告は青色申告がおすすめ
確定申告には青色申告と白色申告があり、何も申告しなければ自動的に白色申告になります。青色申告は事前に申請書を提出する必要がありますが、白色申告にはない控除があります。
青色申告の方が控除により節税効果が得られるので、お勧めです。青色申告にするだけで、利益から10万円を控除できます。10万円控除の場合は白色申告と同じ単式簿記なので、書類作成の難易度は白色申告と変わりません。
不動産投資の事業規模が大きい場合は、同じ青色申告で65万円を控除することも可能で、家族に給与を支払いや赤字の繰り越しも可能です。翌年度以降に赤字を繰り越せば、翌年の黒字が圧縮されて節税効果を生みます。ただし、単式簿記ではなく複式簿記になるため難易度は高まります。
まとめ
「確定申告」「税金」と聞くととても難しく、わずらわしく思う方もいるかもしれませんが、不動産投資を行うのであれば避けては通れません。最初は難しくても、一度やり方を覚えてしまえばそれほど難しいものではありませんので、拒否反応を持たずに取り組んでみてください。