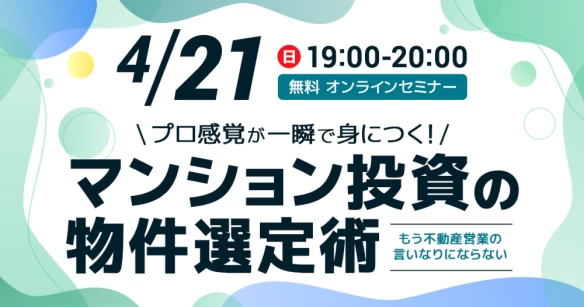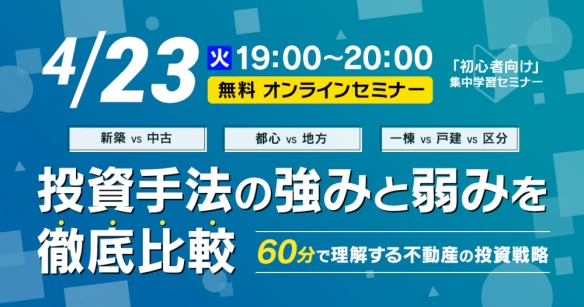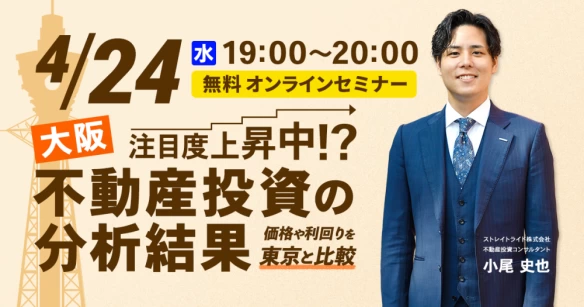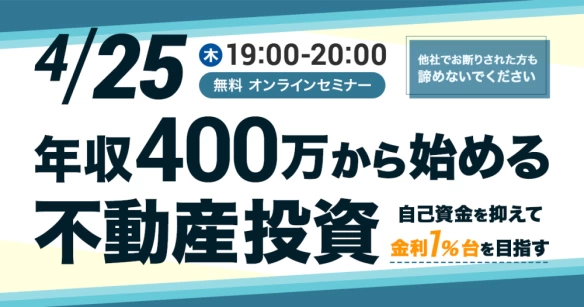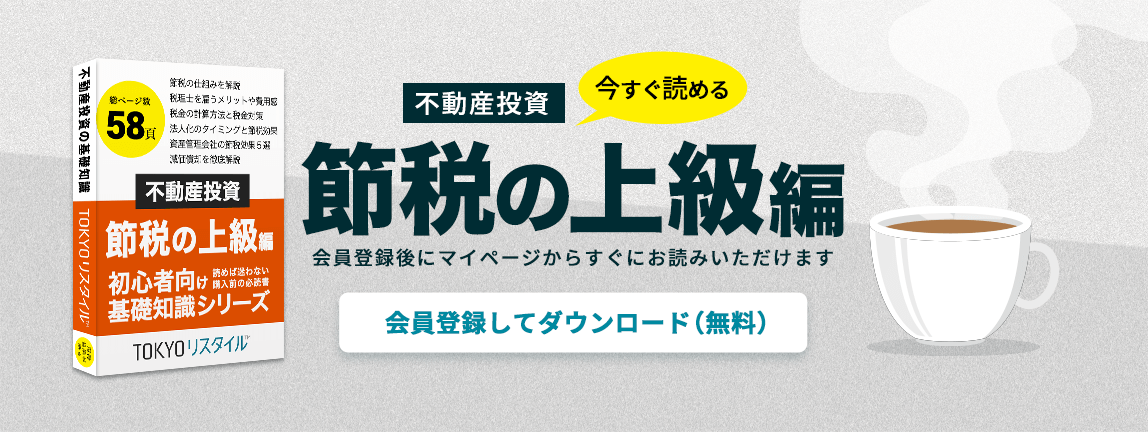ローンの利息分だけが経費?不動産投資の必要経費を正しく理解して賢く節税しよう
- 更新:
- 2023/06/23
本記事は動画コンテンツでご視聴いただけます。
不動産投資を行うには、様々な費用がかかります。その費用のうち、経費として確定申告で計上できるものは何か、知っていますか?必要経費を正確に理解して管理することは、節税対策にとても重要です。ここでは、不動産投資の必要経費について説明します。
なぜ経費は節税対策に重要なのか
そもそも、なぜ必要経費が節税につながるのでしょうか?
その理由は、所得税の計算方法にあります。不動産収入にかかる主な税金「所得税」は、収入ではなく「所得」にかかります。不動産所得は、不動産収入から必要経費を差し引いた金額です。青色申告をする人は、さらに青色申告特別控除額が差し引かれます。
- 不動産所得 = 不動産収入 – 必要経費 – 青色申告特別控除額
必要経費は引き算なので、これが大きければ不動産所得は小さくなります。同じ不動産収入であっても、必要経費をもれなく計上することで不動産所得を圧縮し、所得税の節税ができるのです。
必要経費と節税との関係は、このようになっています。
不動産投資の10個の必要経費
それでは、不動産投資の必要経費について順に見ていきましょう。
(1)減価償却費
最も大きな経費は、減価償却費です。減価償却費は、購入した物件の費用を数年間に分割して経費計上していきます。
もし物件価格を購入した年に一括計上するのであれば、初年度は大赤字になりますよね。そうならないよう数年間で分割計上することになっています。分割計上により、2年目以降も家賃収入に対する所得税を抑えることができます。
償却期間は物件の法定耐用年数で決まります。法定耐用年数とは、木造は22年、鉄骨は34年、RC造は47年といったように法律で定められた耐用年数です。中古の場合は、残った耐用年数を1.2倍した年数が償却期間です。
例1:新築、2500万円のRC区分マンション
→ 償却期間は法定耐用年数の47年間。年間約53万円を経費計上。
例2:中古、築22年、1000万円のRC区分マンション
→ 償却期間は (47年−22年)× 1.2 = 30年間。年間約33万円を経費計上。
参考【2023年】不動産投資の赤字と損益通算、減価償却を分かりやすく解説
(2)仲介手数料
不動産を購入した時の仲介手数料は、必要経費に含めることができます。仲介手数料は、売買価格が400万円以上の場合は、売買価格の3% + 6万円となります。発生するのは初年度のみですが、その金額は大きく売買価格1000万円の物件なら36万円となります。仲介手数料も消費税の課税対象になるので、消費税がプラスされます。
仲介手数料に含まれる費用
仲介手数料には、通常の仲介業務にかかった費用のみが含まれます。これは全額ではありません。例えば下記のような費用は含まれません。
- 不動産ポータルサイトにかかる費用
- 物件見学の同行費
このような必要経費は別途支払う必要があり、これはオーナー負担になります。
仲介手数料の上限ルール
不動産の仲介手数料は「宅地建物取引業法」により上限が定められており、規定を超える手数料の提示は法律違反となります。また、上限いっぱいに請求できるとは限らないので注意してください。
賃貸借の仲介手数料は、居住用かそれ以外かで計算法が異なります。
居住用物件
貸し主、借り主それぞれの仲介手数料は賃料の0.5ヶ月以内(+税)です。
依頼主の承諾があれば上限は1ヶ月分(+税)となり、仲介手数料を受け取ることはできます。しかし貸し主・借り主両方から受け取る報酬の合計は、賃料の1ヶ月分までという決まりがあります。
その他の物件
貸し主、借り主から受け取る仲介手数料の合計が賃料1ヶ月分(+税)以内であれば、支払額の比率は問いません。
(3)租税公課
租税公課とは、必要経費として認められている税金のことです。以下が該当します。
毎年納める税金
- 固定資産税
- 都市計画税
購入時・売却時のみ納める税金
- 登録免許税
- 不動産取得税(購入時のみ)
- 譲渡所得税(売却時のみ)
- 印紙税
必要経費にならない税金
以下の税金は必要経費になりません。
- 所得税
- 住民税
- 相続税
不動産投資の税金について詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。
(4)損害保険料
不動産が加入している以下の保険の保険料は必要経費です。数年分の一括支払いであっても、経費計上できるのは当年度分のみです。
- 火災保険
- 地震保険
- 物件価値下落対策の保険(孤独死・自殺の家賃保証・原状回復など)
- etc.
損害保険で経費計上できるもの
損害保険料(火災保険・地震保険)のうち、その年にかかったものは経費計上できます。 例)10年分の保険料を先に資産計上し、その後毎年10分の1ずつ損害保険料へ経費計上する ※必要経費外の金額のうち、本人の住居用物件にかかる保険料は地震保険料控除の対象になるため、損益通算を終えた後の総所得金額から控除することができます。参考損害保険って結局何なの!?その仕組みやメリット・デメリットを解説!
経費計上できないもの
自宅等、賃貸経営にあたらない部分の保険料は経費計上できません。損害保険でカバーできるメインのリスクは自然災害で、中でも不動産投資にとって大きな被害となるのは、地震と水害です。特に日本は「地震大国」と呼ばれており、全世界と比べてもその数20%(年に1100回以上)が日本で起きています。大きな地震が起こると、物件の大きな破損までいかずとも少なからず修繕が必要な状況が想定されます。
そんな地震や、その他身近な被害をカバーするためにも火災保険と地震保険は必須といえるでしょう。
特に賃貸経営においては、あらゆるリスクに備えて適切な保険に加入することが、長い目で見て賢明な選択となります。
参考不動産投資をする前に知って起きたい!地震のリスクとその対応方法
(5)管理費、修繕積立金
管理費と修繕積立金は、いずれも建物管理会社に支払う費用です。これは必要経費として認められています。
管理費は、建物管理会社に以下の業務を行ってもらうための費用です。
参考マンション管理組合の理事長とは?不動産投資家でもなれる!仕事内容やメリット・注意点を押さえて投資活動を有利に進めよう
- 建物設備の保守・点検(エレベーター・電気設備・給排水設備等)
- 共用部分の清掃
- 水道・電気代
- 管理組合の運営費
- 保険料
修繕積立金は、将来的に行われる建物の大規模な修繕のための積立金です。計画的に行われるため、その計画にもとづいて積立金額が決められています。
(6)修繕費
修繕費は修繕積立金と違い、通常の原状回復にかかる費用です。具体的には、エアコンや換気扇といった設備の修理・交換、壁の補修やペンキの塗り替えなどです。
ただし、物件の資産価値向上にあたる以下のような費用は、修繕費ではなく「資本的支出」となり、必要経費とはなりません。
参考【2023】資本的支出と収益的支出とは!?その違いをフローチャートでわかりやすく解説!
- 建物の避難階段の取付けなど、物理的に付け加えた部分の費用
- 用途変更のための模様替えなど、改造または改装に直接用した費用
(7)賃貸管理代行手数料
先ほどの「管理費」は建物の管理にかかる費用でした。こちらの「賃貸管理代行手数料」は、入居者関連の管理を行う会社への費用です。これも必要経費として認められています。
具体的には以下のような業務です。
- 入居者募集
- 家賃の集金
- 各種契約業務
- 入居者のトラブル対応
- 退去時の立会い、原状回復業者の手配
- エアコンや換気扇等の設備交換業務
- etc.
(8)借入金金利
ローン返済における利息分は必要経費です。必要経費となるのは利息のみで、元本は経費にはなりません。
ローン保証料も必要経費として計上できます。これはローンが支払えなくなった時に、信用保証会社に支払いを保証してもらうための費用です。
参考ローン返済方法の種類とは!元利均等返済と元金均等返済の違いや不動産投資における指標まで解説します
(9)税理士費用
確定申告書の作成を税理士に依頼する場合、その税理士費用も必要経費です。
税理士の費用相場は年間20〜30万円(月1〜1.5万円)程で、決算時は更に5〜10万円の費用が発生します。大きな額ですが、毎月の帳簿作成・チェックに加え年に一度の確定申告も行って頂けます。それに不動産投資には、購入から始まってリフォーム・家賃収入・修繕費・物件売却など、その都度経理業務が発生します。
税法が改定されることもありますし、その他の事業をしながら税務対策を自分で行うのは非常に大変です。自身で学び税務対策をする方法もありますが、節税対策にもなる不動産投資の税務処理は、複雑なものも多いので、プロに任せる方が効率的といえるでしょう。
(10)その他の必要経費
必要経費の大きなものは上記にあげたものですが、その他、不動産事業を行ううえで経費として認められる費用を5種類まとめます。自動車の交通費やインターネットの通信費などは、プライベートでも利用するものですので、事業用として利用した分のみを計上することになります。
交通費
管理会社との打ち合わせ、物件の確認、不動産セミナーへの参加などのための往復交通費
通信費
物件情報を調べるためのインターネット費用や管理会社とのやりとりのための電話代、郵送費用など
新聞図書費
不動産情報の収集のための書籍・雑誌の購入費用など
会議費・接待交際費
管理会社や税理士、不動産関係者との打ち合わせ等の飲食代、手土産代など
消耗品費
図面の印刷代や各種書類のコピー代、文房具代など
納税額は確定申告で決まる
これらの経費を管理していったうえで、最終的には確定申告書の提出によって納税額が確定します。確定申告は毎年2月16日~3月15日の1ヶ月間に、税務署へ前年分の申告を行います。
申告する経費は金額と用途だけでなく、領収書を所有しておく必要があります。領収書は提出しませんが、税務調査が入るときに提示を求められることがありますので、捨てないように整理しておきましょう。
法人化による節税対策
所得税は、課税所得が増えるほど税率が高くなると説明しました。先に説明した税率は個人の場合であり、収入が大きくなると、法人を設立して法人税として納税した方が節税になります。
法人化したほうが節税になるのは、課税所得900万円~1000万円以上が目安ラインです。サラリーマンであれば年収1500万円前後が目安になります。詳しくは以下の記事にまとめているので、参考にしてみてください。
参考不動産投資で法人化?資産管理会社のメリット・デメリットを徹底解説!
住宅ローン控除(住宅ローン減税)は使えない
自身の居住用の家を購入する際の住宅ローンは、住宅ローン控除が利用できます。年末のローン残高の1%が所得から控除され、確定申告で還付されるものです。不動産購入における節税のひとつとして、ご存知の方も多いと思います。
残念ながら、不動産投資ローンでは、この住宅ローン控除は使えません。住宅ローン控除は「自宅用」の不動産を購入するためのローンに対する控除であり、投資を目的とする不動産投資ローンとは性質が異なるためです。
住宅ローン控除について
住宅ローン控除は、住宅ローン等の年末残高の合計額から算出された金額を所得税から控除するものです。わかりやすくいうと、ローン残高の1%が10年間返ってくるというものです。上限は40万円です。所得税が少なく、控除しきれない人は住民税から控除できます。
これによりローン返済の負担が減らせるので、この制度はしっかり利用しましょう。
なお、申請初年度のみ確定申告をする必要があります。
住宅ローン控除を受けられる条件
住宅ローン控除は、条件をクリアしなければ利用できない制度なので物件を購入前にチェックしておきましょう。
①自身の住居であること
物件を手にしてから6ヶ月以内に入居すること。
②物件の床面積が50平方メートル以上であること
更に半分以上が住居用であることが条件になります。この場合の面積は不動産登記上の床面積であり、売買契約書や不動産会社の資料とは算出基準が違いますので、よく確認しましょう。
③住宅ローンの返済期間が10年以上あること
借入先は金融機関であり、返済期間が10年以上あるということが条件です。親族や知人からの融資は住宅ローンとは認められず、控除対象外になります。
④年収3000万円以下であること
ローンを組んだ後年収が3000万円を超えた場合、その時だけ控除対象外となります。
参考不動産投資は融資を受けたほうがいい?よくある疑問にお答えします
不動産投資ローンについて
不動産投資ローンは組むべきでしょうか?まずはメリットとデメリットを確認しましょう。
不動産投資ローンのメリット
メリットを解説します。分りやすく言えば、下記のようなことが挙げられます。
- 収益性が上がる可能性がある
- レバレッジ効果が高い
- 手持ち資金の確保ができる
- 団体信用生命保険に加入できる
レバレッジとは「小さな資金で高価な資産を手にすること」。ローンを使用することで自己資金の約10倍もの資産を手にすることができ、その分収益性も高まるというメリットがあります。
また、自己資金の持ち出しを減らすことで余力を持った経営ができますし、団体信用生命保険に加入できることも大きなリスクヘッジとなるでしょう。
※団体信用生命保険とは、ローンを組んだ人が病気になったり死亡した場合、ローン残高を肩代わりしてくれるものです。
不動産投資ローンのデメリット
不動産投資ローンのデメリットも見ていきましょう。
- 金融機関との交渉、審査に時間がかかる
- 利息が発生する
一番大きいのは利息であり、例えば3000万円の借入金を30年間、金利2%でローンを組んだ場合、1000万近くの利息が発生します。利息は工夫次第で安くすることが出来るものの、必ずかかる費用になるので大きなデメリットになるでしょう。
また、ローンを組むにあたり金融機関や仲介会社など経由したり、打診したりと手間や時間がかかるのもデメリットです。このように利息はかかるけど、より大きな利益を得られるなど、メリットとデメリットは紙一重です。もちろん自身の経済状況にもよりますが、多角的に見てバランスの良い判断をすることが大切です。
まとめ
いかがでしょうか。不動産投資において必要経費となる費用がお分かりいただけたでしょうか。これらの経費を把握し、支払った記録として領収書を保管し、もれなく確定申告を行うことで、着実に節税対策を行うことができます。
なお「不動産投資をすると節税になる」という言葉がよく聞かれますが、これは間違いです。所得税が所得によって変わる以上、収入を増やす目的の不動産投資を行なって成功すれば、納税額は増えます。
正しくは「不動産投資をするなら節税を意識しよう」です。納税額の総額は増えても、できるだけその額を押さえ、手元に残る利益を大きくするのが節税の本質です。あなたの資産を守るため、参考にしていただければ幸いです。