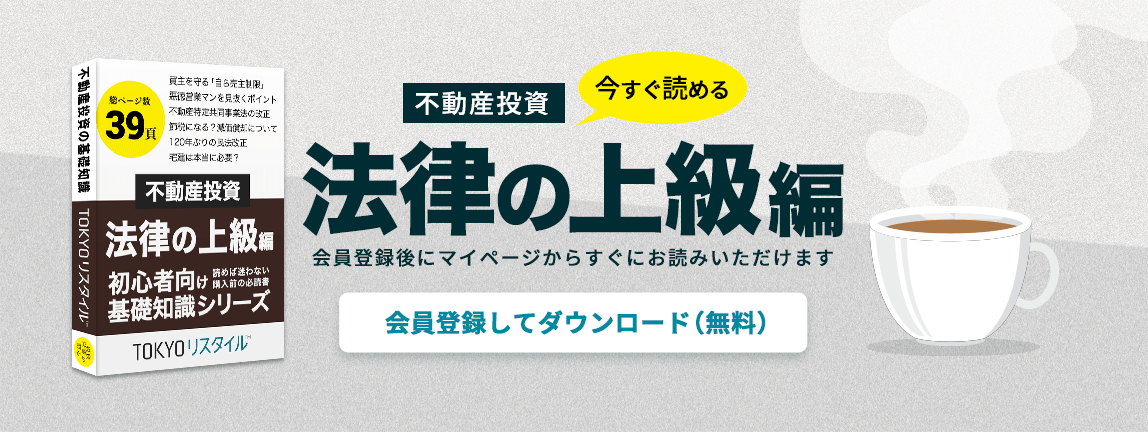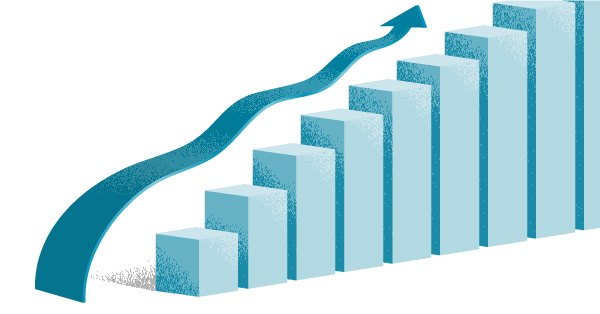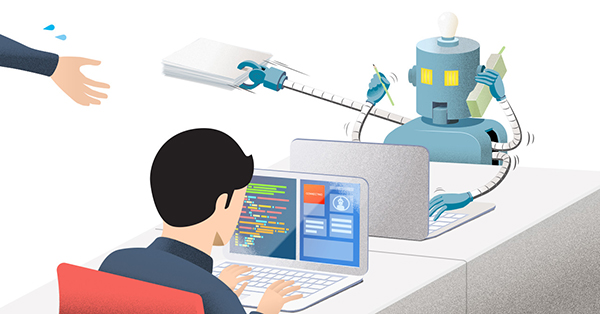120年ぶりの民法改正、不動産オーナーが押さえておくべき5つのポイント
- 更新:
- 2022/12/26

2020年4月1日、日本は改正民法が施行されました。
日本の民法は明治時代に交付されてから実に120年ぶりの改正となります。
民法とは、社会生活や事業において人々が守る法律ですが、明治以降変容する時代の中では当時制定された法律だけでは補えない部分も多々ありました。
大まかにいうと、今回の改正民法は現代に合わせた「用語の平易化」と「曖昧だった規定の明確化」を果たそうとしています。
しかし「120年ぶりの改正」とはいえ買い物などのように身近で変化を感じられない分、2019年10月の消費税増税に比べて人々の関心は薄いようです。
ですが、不動産投資家の方々にとっては無視できないポイントがあります。なぜなら、この改正には賃貸借契約や管理に影響する部分があるからです。
今回は民法改正で不動産オーナーが貸主として押さえておくべき5つのポイントをご紹介します。
- どこまでが貸主負担? 敷金のルールが明確化
- 退去時のトラブル回避へ 借主の原状回復義務も明確に
- 連帯保証人付きの賃貸借契約は注目! 極度額を定めない契約が無効に!
- 貸主は押さえておくべき! 「一部滅失」の指標とは?
- 修繕時の対応も明確化。貸主と借主のやりとりが円滑に
1.どこまでが貸主負担?敷金のルールが明確化

賃貸借契約では一般的になっている敷金ですが、実は改正前の民法では敷金が賃貸借の中で何をどの範囲まで担保するのか、はっきりとした規定がありませんでした。
改正後の民法では「敷金がなにをどこまで担保するのか」が明確化されています。
これにより、敷金返還をめぐるトラブルが未然に防げるとみられています。
ポイント:敷金が担保する項目
①借主が支払うべき費用
賃料、共益費、修繕費、原状回復費用、借主の債務不履行による損害賠償債務は敷金で担保される
②貸主から債務の相殺が可能
例えば借主が賃料を滞納した場合には、貸主が敷金から賃料を徴収できる(借主からの相殺は不可)
③敷金は賃貸借契約終了とともに借主に返還する
貸主に物件返還後、債務の額を差し引いた敷金の残額が借主に返還される(敷金から差し引かれた債務額の内訳も明示するものとする)
2.退去時のトラブル回避へ 借主の原状回復義務も明確に

原状回復費用については、貸主・借主どちらが何をどこまで負担するのか、という点は賃貸借トラブルとして長年係争されていました。
- 今回の改正では通常損耗や経年変化について、借主は原状回復義務を追わないことが明記されています。
ポイント:通常損耗・経年変化の扱いになるもの・ならないもの
通常損耗・経年変化に当たる例
※現状回復費用は貸主が負担- 家具設置による床、カーペットのへこみ・設置跡
- テレビ、冷蔵庫等の電気ヤケによる後部壁面の黒ずみ
- 地震で損壊したガラス
通常損耗・経年変化に当たらない例
※原状回復費用は借主が負担- 引っ越し作業で生じたひっかきキズ
- 日常の不適切な手入れまたは用法違反による設備等の毀損
- タバコのヤニ・臭い
- 飼育ペットによる柱、壁等のキズや臭い
管理会社によっては民法改正の前から現状回復費用の負担範囲を明記している賃貸借契約書もあります。事前に何をどちらが負担するのか、あらかじめ把握しておくことがトラブル回避にもつながります。
3.連帯保証人付きの賃貸借契約は注目!極度額を定めない契約は無効に?

改正後直近の新規・更新契約において、物件の賃貸借契約で借主が個人の連帯保証人を付ける場合は「連帯保証人がいくらまで借主の債務を担保するのか」という極度額を記載することが必要になります。
改正前の民法では連帯保証人の負担範囲が規定されていませんでしたが、改正後は貸主と連帯保証人との間で「賃料〇ヵ月分(〇〇円)」というように、具体的な金額の設定と記載が必要になります。
貸主によっては今までの極度額設定のない契約でも問題なかった、と思われるかもしれません。ですが、民法改正後は極度額の設定が費用の支払に大きく影響するといっても過言ではないのです。
たとえば、
- 入居者が家賃を3ヵ月滞納したので、連帯保証人に請求した
- 入居者が室内の設備を壊したので修理費用を請求するも支払わず、連帯保証人に請求した
こういった状況では改正前は連帯保証人が債務を履行して賃料や費用を支払うものでしたが、改正後は極度額を定めないだけで、これらの費用を連帯保証人に請求できなくなってしまいます。
つまり、極度額設定の有無が連帯保証人の保証有無に直結しているので、改正民法の中でも非常に重要なのです。今締結している賃貸借契約の債務担保が連帯保証人なのか、改正にそなえて確認してみましょう。
- ポイント:連帯保証人制度を利用した契約は必ず極度額を設定する必要がある!
もし極度額が契約書に記載されていなかったら?
⇒設定すべき極度額が決められていないために、保証契約が無効になってしまう
既存の連帯保証人制度を利用した契約はどうなる?
⇒2020年4月1日以降に契約を更新する場合は、
- 新たに極度額を設定した書面を作成して保証人と契約
- 現行の契約を継続して「極度額記載なし・保証人のサインなし」で更新
のいずれかとなります。
基本的には更新のタイミングで「連帯保証人承諾書」などの書面で連帯保証人と管理会社とが契約のやりとりをしていることが多いため、改正後は①のやり方になると見られています。
なお、賃貸借契約は連帯保証人ではなく、保証会社を付けての契約もあります。保証会社の場合は極度額の設定がなく、保証範囲が明確になっているので、貸主としても保証費用をめぐるトラブルを回避することができます。今後の賃貸借契約においては保証会社を付けた方が、貸主と借主お互いにとって安心で円滑なやりとりが可能となるため、保証会社を利用した賃貸借契約が増えていくと思われます。
参考不動産投資と家賃保証会社の関係は?最高裁「追い出し条項」判決まで解説
4.貸主は押さえておくべき!「一部滅失」の指標とは?

賃貸物の一部滅失による賃料の減額は改正前の民法にも規定されています。
たとえば「給湯器の故障でシャワーからお湯が出ない」など、借主が賃借物の一部を利用できなかった(一部滅失)期間の割合に応じて「賃料の減額を請求することができる」というものです。
改正前の民法では故障した設備や割合の明確な基準がないために、「シャワーの故障が一部滅失に当たるのか?」といったところから係争につながることがありました。
改正民法では一部滅失の場合「部分の割合に応じて賃料が減額される」となり、対象となる故障設備や割合についても公益社団法人日本賃貸社宅管理協会の「サブリース住宅原賃貸借契約書(改訂版)」で一部滅失に係る指標が確認できます。
一部滅失の指標一例
| 故障内容 | 減額割合 | 免責日数※ |
|---|---|---|
| トイレが使えない | 減額割合 30%(月額) | 1日 |
| 風呂が使えない | 減額割合 10%(月額) | 3日 |
| 水が出ない | 減額割合 30%(月額) | 2日 |
| エアコン不作動 | 減額割合 5,000円(月額) | 3日 |
| 電気が使えない | 減額割合 30%(月額) | 2日 |
| テレビが使えない | 減額割合 10%(月額) | 3日 |
| ガスが使えない | 減額割合 10%(月額) | 3日 |
※借主の通知から貸主が直ちに修理に応じても、修理業者の都合などで即日解決できない場合もあるため、各免責日数分は減額割合から除かれます。
ポイント:借主から故障の通知が入ったら、すぐに応じる!
「賃料が(滅失の)割合に応じて減額される」となっていますが、当然借主からの通知が前提となります。
ですが、もし夏にエアコン故障の通知を借主からもらったとしても、繁忙期のため業者が即日修理できない場合もあります。その場合貸主は「最短で〇日になります」という連絡をすぐに入れることが大事です。
賃貸物が使えない状況になったからといってただちに「賃料減額しなければならない」ということではなく、「修理まで〇日かかる」という点で双方合意があれば賃料減額せずとも問題はありません。
貸主側として大事なのは、借主側の通知に対して即時に対応すること、と言えるでしょう。
5. 修繕時の対応も明確化。貸主と借主のやりとりが円滑に

近年の大雨や台風による浸水や窓ガラスの損壊のような、賃貸物の修繕がすぐに必要な状況にある場合、借主が自ら修理できるのか?実はこれまでの民法ではこういった状況での借主側の修理対応可否が明文化されていませんでした。
改正民法では、借主が貸主に修理が必要であることを通知後、①貸主が一向に修繕に応じてくれない ②急を要する修理(窓ガラスや屋根の損壊など)の場合は、借主が自ら修繕対応して良いことが明文化されました。
ポイント:「一部滅失」の時と同様、借主・貸主双方の合意が必要!
①借主から貸主への通知が必要
通知のないままでは貸主負担の修繕対象とはなりません
②修繕するもの・条件・範囲・費用負担などを明確にして借主・貸主とも合意する
不必要な修繕をされ、貸主がその費用を請求されるというトラブルを防ぐため
まとめ
不動産オーナーが着目すべき改正民法として、賃貸借契約に係る主な5つをご紹介しました。
改正民法で共通しているのは、基準を明確化することによって借主・貸主のトラブルを未然に防ぐことができる、ということです。貸主として借主との間でやるべきこと自体に大きな変化はありません。
4月に改正されたポイントを踏まえておくことで、円滑な物件管理ができるでしょう。