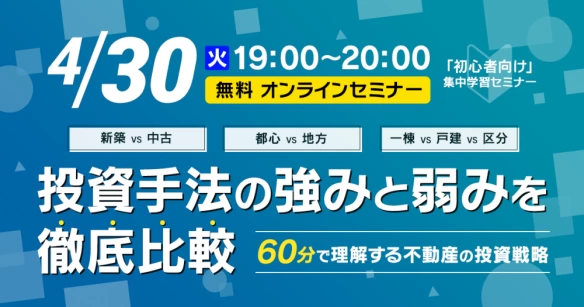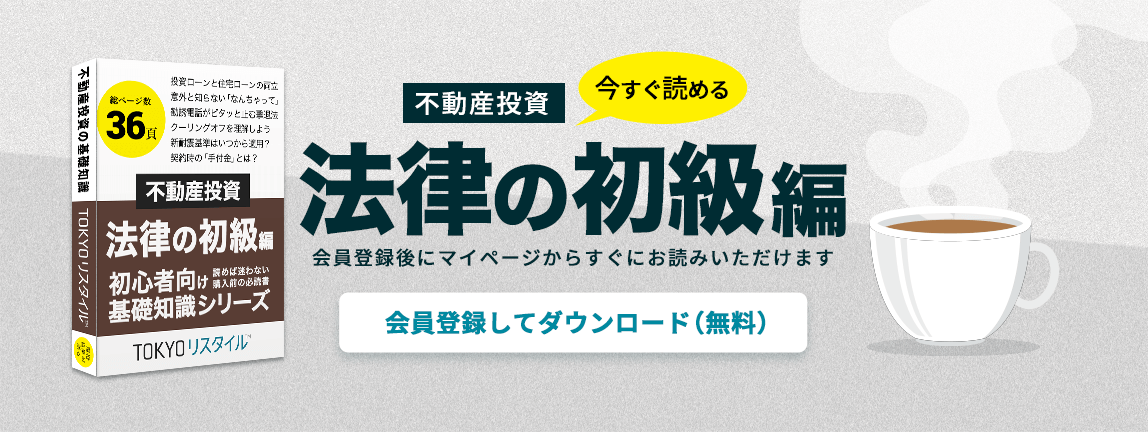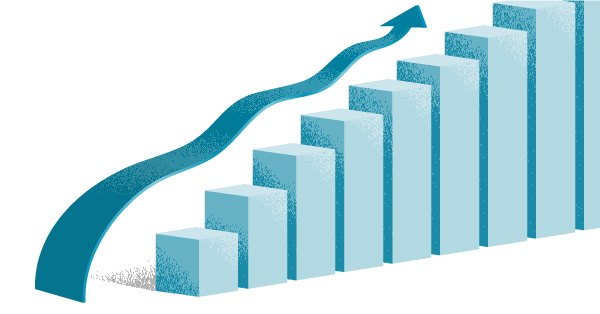不動産取引における買付証明書の書き方やキャンセルの方法を理解しよう
- 更新:
- 2023/04/17
本記事は動画コンテンツでご視聴いただけます。
不動産投資初心者の方からよくいただく質問に「物件購入までの流れが分からない」というものがあります。確かに、専門用語や法律も絡む不動産投資は、始めたての人にとっては未知の領域です。頭の中には多くの疑問が浮かぶでしょう。
しかし不動産投資は経験と知識を積めば、低リスクで始められる投資のひとつです。疑問点をひとつずつ解決し、何よりも早くひとつでも多くの経験を積むことが非常に重要です。
そこで初心者の皆さんに、まずやってほしいことは「買付証明書」を提出することです。業界内では「買付(かいつけ)」と呼ばれることもあります。この記事では買付証明書の書き方やメリットなど、買付証明書に関する基礎知識を解説します。
特に不動産投資を始めたばかりの人(これからはじめたい人)は、買付証明書の提出から物件購入までの流れも把握できるので、最後までしっかりと読んでイメージを膨らませてください。
不動産取引と買付証明書の関係
不動産物件を購入する際、大きく3つのステップを踏んで物件を購入します。
- 購入物件の選定
- 物件の契約
- 支払い
この流れで物件を所有することになるのですが、「①購入物件の選定」の際に買付証明書を使用することになります。
買付証明書とは
買付証明書とは、物件の購入を希望する人が物件の売主や不動産仲介業者に提出する書類のことです。分かりやすくいえば、「私はこの物件を〇〇円で購入したいです」という意思を示すエントリーシートのようなもの。あくまでも物件の購入を確定させるものではなく、物件を購入するための最初の申込書と考えましょう。
売りに出される物件は全国から購入可能
不動産は一度売りに出されると、物件情報がREINSというサイトに集約されます。これは不動産業者だけが見られるサイトです。ここに掲載されるとすぐに全国に拡散され、全国の不動産業者がその情報を見ることになります。
良い物件情報は不動産業者や、その先にいる顧客にまで伝わり、購入に至るという流れです。この際、同じ物件に多くの人から申し込みが重なることがあります。このような場合は優先順位を決めるために買付証明書が必要になってきます。物件への交渉権などを優先的に得られるのは、買付証明書を早く提出した順となります。
もちろん、購入額の高い人や現金一括で購入する人が優先されることもありますが、同条件の場合は買付証明書の提出順となるのが一般的です。
買付証明書は不動産会社が雛形を持っている
基本的に買付証明書は不動産会社が雛形を持っています。買付証明書の提出を検討している場合は、やり取りをしている不動産会社の担当者から雛形をもらいましょう。
買付証明書の内容は基本的にどこも同じで、売主に対して購入の意思を提示し、購入の諸条件を書いておく内容となります。購入者が書くための書類なので、内容を読んでも意味が分からないという場合は、必ず不動産会社に確認してください。
買付証明書を提出するメリット
次に買付証明書を提出するメリットに関して解説していきましょう。
物件購入の交渉権を獲得できる
先述した通り、希望する物件に数名の購入者が出た場合、基本的には買付証明書の提出順で交渉権を得ることができます。そのため、なるべく早く買付証明書を提出することは大きなメリットとなります。
また交渉権があることで値引き交渉も可能です。値引きが確実にできるわけではありませんが、買付証明書を提出することで「本気で購入する意欲がある」と売主にアピールできるので、場合によっては売主が値引きに応じてくれる可能性もあります。
また預貯金などを明記し「あと〇〇円下がったら預貯金で払うことが可能です」などと交渉することも可能です。具体的な数値が出ていることによって、売主としても見通しが立てやすく、値下げの検討のハードルが少し下がります。無理な値引き交渉は良くないですが、取引の状況などを良く見極めながら、上手く交渉していくのがポイントです。
売主に本気度をアピールできる
買付証明書は、売主側の視点で見るとそのメリットが分かりやすいでしょう。
売主としては買付証明書を提出してくれる買い手候補者は、物件の購入を本気で検討している可能性が高く見えるため、その分価格交渉などにも真剣に向き合おうとするのが一般的です。
特に、氏名・住所・勤務先・年収など、しっかりとした個人情報を記載した買付証明書を提出する買い手候補者に安心感が持てるのは、想像に難くありません。買付証明書を提出していて、なおかつ本気で物件の購入を希望しているような買い手には、売主側から能動的に情報を開示する場合もあります。その最たる例が、賃貸借契約書の開示です。
賃貸借契約書には、物件に住む入居者の「氏名」「性別」「年齢」「勤務先」などの個人情報が記載され、家賃の滞納履歴なども確認することが可能です。物件を購入する前に、物件の入居者の民度は気になるところ。良い住人であれば、より不動産投資の成功確率も高まりますので、重要な情報です。
加えて買付証明書には、物件詳細資料を求める項目もあります。これは「賃貸借契約書」だけではなく「登記事項証明書」「重要事項調査報告書」を見るためのものです。そのため、買い手側から要求があれば、この証明書も見せる必要があります。
買付証明書の作成方法
次は買付証明書の作成方法について解説します。先述した通り、買付証明書の雛形に関しては不動産会社が持っていることがほとんどなので、書類を作成するときはまずは不動産会社に相談しましょう。
買付証明書の内容は主に下記の通りです。
- 買付希望者の氏名・住所
- 希望物件の名称・所在地
- 希望価格
- 手付金額
- 融資特約の有無
- 物件詳細資料の請求
ここで気になるのは、「希望価格」「手付金額」「融資特約の有無」ではないでしょうか。それぞれについて解説していきます。
希望価格
希望価格とは、その名の通り「物件を幾らで購入することを希望します」という希望金額のことです。買付証明書に希望価格を提示することで、売主に対して購入の意思表示になります。
手付金額
手付金額とは、契約時に一時的に払う金額のことです。契約が順当に進んだ際は、その金額は購入金額に当てられることになります。
また手付金は、ただ単に購入金額の一部を先に支払ったものではなく、締結した契約を撤回するための解約金としての役割を担うこともあります。これは契約について、もしものことがあった際、売主と買主の双方を守るために存在しているルールです。そのため、手付金の金額もしっかりと明記しておく必要があります。
融資特約の有無
融資特約とは、簡単に言えば「融資が下りた際は購入しますが、融資が下りなかった場合は無条件でキャンセルします」という内容です。
融資を受ける場合は、有と明記しましょう。売主としては先にこの状況が分かっていれば、様々な対策を取ることも出来ます。また買主としても先に提示しておくことで、万が一融資が下りなかった場合も手付金を放棄することなく契約の撤廃が可能です。
参考不動産投資は融資を受けたほうがいい?よくある疑問にお答えします
手付金の相場について
では、手付金はいくら払うのが相場なのでしょうか?手付金の相場は、一般的に販売価格の10%以内と言われています。
また手付金には、大きく分けて3つの種類があります。
- 証約手付
- 違約手付
- 解約手付
実は、不動産取引においては、ほとんどの手付金が解約手付となります。それぞれの手付金についても説明しておきましょう。
証約手付
証約手付とは、不動産だけではなく、各種取引があった証明をするものです。相場金額は5~10万円といわれています。
- 証約手付が払われたら契約成立とみなす
という意味合いが多く、契約成立以外の目的はありません。現在の不動産取引においてはこの証約手付はほぼ利用されていません。
違約手付
違約手付とは、契約が当事者によって流れてしまった際の賠償予定額となる金額です。例えば、買主が違約手付金を10万円支払っていた場合、買主による債務不履行で契約が流れた際に違約手付金10万円は売主へ渡ります。逆に売主の債務不履行で契約が出来なかった場合は、売主から買主に20万円の賠償金が支払われます。
このように違約手付金は万が一の時の担保という役割がありますが、証約手付と同様に不動産取引で使うことはほぼありません。
解約手付
解約手付とは、締結後の契約に関して、その理由に関わらず契約を撤回するための金額です。
買主が契約を撤回する場合には支払った手付金を放棄すれば可能です。売主が撤回する際には、支払われた手付金の倍額を支払うことで可能となります。
不動産投資においては、ほぼ全てがこの「解約手付」となります。
手付金に関しては、契約の際に出てくることが多い言葉なので、内容と共に理解しておきましょう。
買付証明書のポイント
買付証明書を書く際のポイントについて解説します。これまで解説してきた通り、買付証明書は交渉の際にも重要になる証明書です。そのため、特に記載する金額に関して注意しましょう。
無理な価格交渉はしない
買主が「できるだけお得に購入したい」と思っているのと同じように、売主は「できるだけ高く売買したい」と思っています。
売買が商売である以上、これは当然のことです。買付証明書を提出した後、売主の多くは「希望額」と「手付額」を見て判断することも考えられます。買主が「安く買いたい」と思っているのは理解できますが、ここには出来るだけ自分が支払うことが出来る最大の数値を書きましょう。手付金も同様に最大値を書くべきです。
もちろん高額の方が物件を取得しやすいのは当然です。しかし、これは「安さ」ではなく「取得」に意識を向ける大切な考え方です。特に不動産投資を始めたばかりの人は「物件を安く購入する」ことに着目しがちですが、それよりも「物件を取得する」ことの方が重要です。残念ながら、安く購入する事ばかりを考えていると、物件の購入自体が出来ない人もいます。
不動産は物件を買い増ししながら利益を積み重ねていく投資です。そのためにも、物件を購入できないと意味がありません。まずは物件を取得するという目的であれば、購入金額をアピールするには、高い方が良いでしょう。払える範囲の最大値を記載し、売主にアピールした方が吉と出るケースが多いはずです。
買付証明書の法的効力とキャンセルについて
買付証明書は法的効力がないため、契約前であればキャンセルをしても問題ありません。
あくまでも買付証明書は、「購入の意思があります」というエントリーシートのようなものです。そのため、買取証明書が提出されただけでは、売買契約が成立するわけではないので安心してください。
この点が、初心者に対して「まずは買付証明書を提出しましょう」とおすすめする理由です。法的効力がない為、不動産投資を踏み出す第一歩としても有効ではないでしょうか。また「契約」や「証明書」という、普通の生活では聞き慣れない事項に触れる機会でもあります。
不動産投資を成功させるためには、何よりも経験が重要です。その一歩を踏み出すために、気になった物件には買付証明書の提出をしてみましょう。
まとめ
ここまで、不動産売買で重要な意味を持つ「買付証明書」について、その概要やメリット、キャンセルの方法などを解説してきました。「買付証明書」を提出することにより、交渉権の獲得や詳細資料の請求、指値交渉など多くのメリットを受けることができると理解してもらえたと思います。
また、買付証明書は出した後に撤回してもなんらペナルティはありません。実際、不動産投資に慣れている方ほど、「この物件はいいな」と思ったらすぐに買付を出し、交渉を有利に進めています。もし検討の段階でマイナスな情報が出れば、その時点で買付証明書をキャンセルすればそれで話は終わりなのです。
これまで買付証明書という名前に圧倒され提出するのをためらっていた方は、しっかりとその内容を理解し、買付証明書を自身の投資における武器にしていっていただきたいと思います。
本記事をご覧になって、「買付証明書を出したい物件がある」「具体的な書き方や提出方法について教えてほしい」といったご要望がございましたら、お気軽に当社コンサルタントまでお問い合わせください。