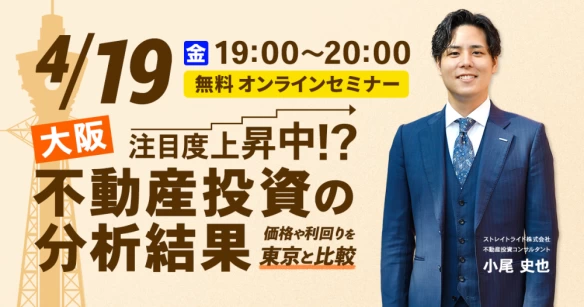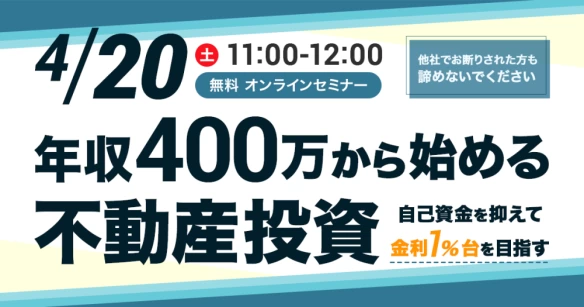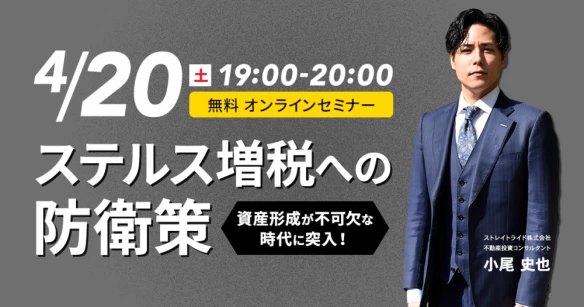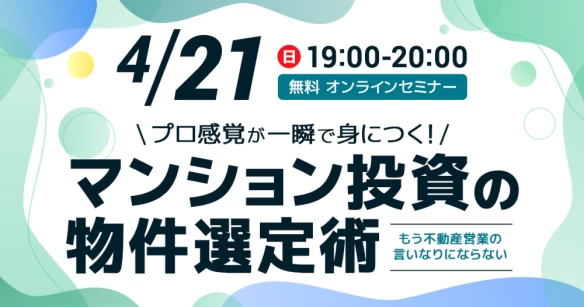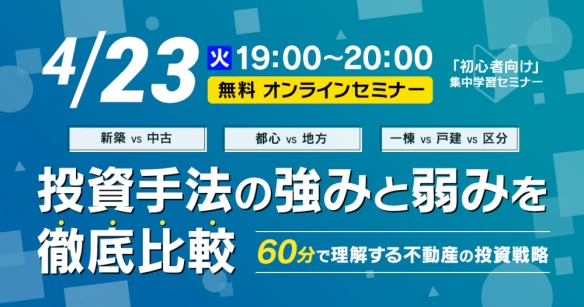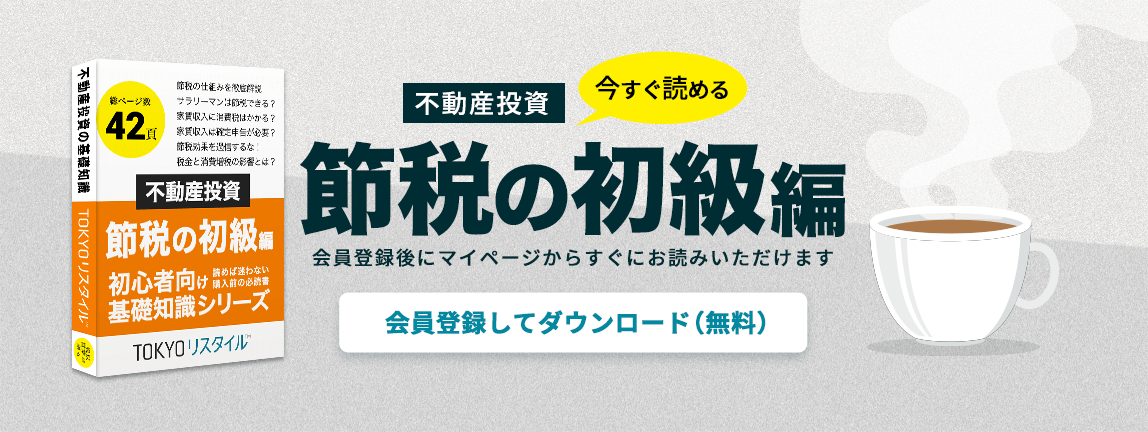マイナンバーで確定申告!マイナンバーid がわからない場合も解説(今ならマイナポイントも)
- 更新:
- 2021/09/10

ここ最近、マイナンバーという言葉を聞く機会も急激に増えました。マイナンバー、マイナンバーid、マイナポイントなどなど関連する言葉もたくさんありますよね...。しかし、マイナンバーカードを結局発行出来ていない...そもそも何に使うかわからない...という人もまだまだいらっしゃるでしょう。この記事では今さら聞けないマイナンバーカードの基礎知識や発行方法・マイナポイントについて詳しく解説します。
マイナンバーとは
マイナンバー(個人番号)とは、行政手続きなどを行う際に利用される「特定の個人を識別するための番号」のことです。日本に住民票がある全員に付与され、住民へは各市町村から12桁の番号を指定されます。
マイナンバーは、「公平・公正な社会の実現」「行政の効率化」「国民の利便性の向上」を目的として、2016年1月から行政手続きにおける利用が始まった制度です。
マイナンバーの情報セキュリティ
マイナンバーの利用範囲は「社会保障」「税」「災害対策」などに限定されています。
また、マイナンバーでの手続きを行う際には、必ずマイナンバーと顔写真付きの身分証明書での本人確認が義務付けれられているため、個人番号を他人に見られてしまった場合も、それだけで財産的被害が発生しないような仕組みになっています。財産的被害とは別に「国が国民を監視する仕組みではないか」という懸念から、マイナンバーの利用に抵抗がある人もいるでしょう。
しかし、マイナンバーでの情報は分散管理するよう、マイナンバー法により義務付けられており、情報を一ヶ所に集めて監視することが禁止されています。
そのため、例えば銀行にマイナンバーを提示しても、国やほかの機関に預金情報が知られるということはありません。
マイナンバーカードとは
マイナンバーは、12桁の個人番号そのものですが、一方でマイナンバーカードはマイナンバーが記載されたICチップ付きのカードのことを指します。マイナンバーカードには、顔写真、氏名、生年月日、性別が記載されています。
マイナンバーカードは、本人確認のための身分証明書として利用できるだけではなく、自治体サービスやe-Tax等の電子証明書を利用した電子申請の際に利用できます。
マイナンバーでできること
- 個人番号の正式な証明
- 各種行政手続きのオンライン申請
- 本人確認の際の公的な身分証明書
- 各種民間のオンライン取引
- 様々なサービスを搭載した多目的カード
- コンビニなどで各種証明書を取得
このように様々な役割をもつマイナンバーカードですが、マイナンバーカードの発行には申請が必要です。
マイナンバー発行のメリット
次にマイナンバーカードを発行するメリットについて解説していきましょう。
公的な身分証明書
先述した通り、1つ目のメリットは「公的な身分証明書になる」ことです。
一般的には運転免許証を身分証明書として使うケースがもっとも多いと思います。
しかし、車を運転しない人にとっては、本人確認のために数年に一度、免許証の更新をするというのは大変です。また運転免許をもっていない人は「健康保険被保険者証」や「住民台帳カード」で身分を証明することになりますが、顔写真がついていないものでは紛失や盗難時のリスクが高いこともリスクになります。
これらの従来の身分証明書に比べ、マイナンバーカードは顔写真が必ず記載されていることや、すべての人が発行可能なこと、また初回発行時の交付手数料は、無料であるなどさまざまなメリットがあります。さらにマイナンバーと本人確認が同時に必要な手続きでは、マイナンバーカードだけで両方をカバー可能です。
行政手続きをオンラインで申請できる
2つ目のメリットは、「各種行政手続きをオンラインで申請できる」ことです。
マイナンバーカードは年に一度の「確定申告」にも当然利用できます。また「特別定額給付金」や民間の「オンラインバンキング」などもマイナンバーカードを持っていれば、インターネット上から申請・利用することができます。
特に新型コロナウイルスによる生活様式の変化が求められる現代では、「窓口に行かなくても手続きができる」というニーズが増え、それにともなってオンライン申請を導入するサービスが増えています。これらのサービスを利用できるようになるというのは非常に大きなメリットといえるでしょう。
証明書を最寄りのコンビニで取得できる
3つ目のメリットは、「各種証明書を最寄りのコンビニで取得できる」という点です。
マイナンバーカードがあればコンビニなどの対応店舗で「住民票」や「印鑑登録証明書」を取得できます。
住民票などを市役所で発行する場合、窓口の営業時間(多くの場合、8時半~17時)の間に足を運んで手続きする必要がありました。しかし、コンビニでの取得であれば、朝6時半~23時の間で利用することができます。
マイナポイントが貯まる
4つ目のメリットは、2020年9月1日から開始された「マイナポイント」が付与されるということです。
マイナンバーカードの普及のための取り組みで、最大5,000円分のポイントを得ることができます。ここで特に今注目を浴びているマイナポイントについて詳しく見ていきましょう。
マイナンバーを発行してマイナポイントも貯まる
マイナポイント事業は、マイナンバーカードや電子決済の普及を目的に総務省が実施する消費活性化政策のポイントプログラムのことです。
マイナポイントは、事前に選択した電子決済サービス内に付与されるポイントで、対象の電子決済サービスを利用できるお店で使えます。
今回のキャンペーンでは設定した電子決済サービスで入金(チャージ)または購入した総額の25%がマイナポイントとして還元されます。つまり、20,000円分の購入、または、電子マネーへのチャージをすることで、上限の5,000円分のポイントを得ることができます。
例えば、対象のキャッシュレス決済サービスに「PayPay」を選択した場合、マイナポイントは「PayPayボーナス」というPayPayのサービス内のポイント名で付与され、PayPayが利用できるお店で1ポイント1円で使えるようになります。
対象のキャッシュレス決済サービスは、2020年9月1日時点で119サービスもありますので、期間など詳しくは、決済サービス一覧からご覧ください。
マイナポイント取得の4つの条件
マイナポイントの取得には、以下の4つの条件があります。
- マイナンバーカードの取得
- マイキーIDの発行
- マイナポイントの申込
- 選択したキャッシュレス決済での買い物、またはチャージ
マイキーIDは、マイナポイントの付与を行う上での本人認証に使用されます。申請の際は、マイナポイントを貯める対象のキャッシュレス決済サービスの選択・設定をしましょう。
マイナポイントの付与の対象期間は、2020年9月から2021年3月末までです。
マイナンバーカードの交付までの流れ
マイナンバーカードの申請には、市区町村から通知カードと一緒に送られてきた「交付申請書」が必要です。
もし、交付申請書を持っていない場合には、市区町村窓口で再発行することが可能です。「交付申請書」を持っている場合、マイナンバーカードは、以下の4つのうちいずれかの方法で発行手続きが可能です。
- スマートフォンで申請
- パソコンで申請
- 郵便で申請
- 証明用写真機で申請
以下、それぞれの申請方法を解説します。
スマートフォンで申請
郵送に比べてカードが手元に届くまでの時間が早く、発行手続きの際に必要な顔写真のデータなども比較的容易に送ることができます。
この申請の際に必要なものは「交付申請書」「スマートフォン」「顔写真データ」です。
パソコンでの申請
パソコンへの顔写真のデータの取り込みや、申請書IDなどが必要です。必要なものは「交付申請書に記載の申請書ID」「パソコン」「顔写真データ」です。
郵便で申請
スマートフォンからの申請に比べて、マイナンバーカードが発行されるまでの時間がかかります。必要なものは「交付申請書」「証明写真(過去6カ月以内に撮影したもの)」「封筒」です。
証明用写真機での申請
証明用写真機の申請で必要なものは「交付申請書」「写真代」「対応した証明写真機」です。
上記の申請を行って約1ヶ月後に「交付通知書」が届きますので、交付通知書に記載の必要書類を持参して、マイナンバーカードを市区町村の窓口へ受け取りにいきましょう。
マイナンバーカードが届かない場合の確認事項
マイナンバーカードは、上記にも記載した通り「交付通知書」を持って、市町村の窓口への受け取りに行く必要があります。通知交付書は、発行手続きを行ってから約1ヶ月で自宅へ届くので、忘れずに確認しましょう。
2020年9月から先に述べた通り、マイナポイント事業という、マイナンバーカードや電子決済の普及を目的とした政策が行われている影響もあり、交付通知書が届くまでの時間が通常に比べて遅くなっている可能性があります。
発行手続きから2ヵ月を過ぎても交付通知書が届かない場合は、各自治体、または地方公共団体情報システム機能に問い合わせてみてください。
このように、マイナンバーカードは現在発行手続きから手元に届くまで、時間がかかることが予想されるため、期間に余裕をもって発行手続きをしてください。特にマイナポイントの付与は、2020年9月から2021年3月末までのチャージもしくは買い物が対象のため、早めにマイナンバーカードの発行手続きをすることがおすすめです。
確定申告書へのマイナンバー記入方法
ここからは確定申告書へのマイナンバーの記入方法をご紹介します。現在、確定申告の際には、「マイナンバーの記載」と「本人確認書類の提示又は写しの添付」が必須です。
マイナンバーカードがあれば、確定申告書の「添付書類台紙」にマイナンバーカードの表面と裏面のコピーを貼るだけで申告することができますので、確定申告が非常に簡単になりますよ。
マイナンバーを持っていない場合
もし、マイナンバーカードを持っていなければ、確定申告の際に通知カードや住民票の写しなどの「番号確認書類」と運転免許証やパスポートなどの「身元確認書類」の2点を提出する必要があります。
さらに、顔写真のない身元確認書類の場合、2種類以上の提示又は写しの添付が必要なため、確定申告が必要な方は、マイナンバーカードの発行が断然おすすめです。
マイナンバーカードの発行手続き
ここまでで、確定申告をする人をはじめ、身分証明書や各種オンライン申請、マイナポイントでの還元など、多くのメリットがあることを紹介してきました。次に実際にマイナンバーカードの発行手続きを行った場合のステップを紹介します。
マイナンバーカードをスマートフォンやパソコンからオンラインで申請する場合、以下6つのステップで確認や操作を行います。
- 利用規約の確認
- メールアドレスの登録
- メールアドレス登録の完了
- 顔写真の登録
- 申請情報の登録
- 申請情報の登録完了
「申請書ID」は、上記2の操作で入力が求めらるので注意しましょう。申請書IDは交付申請書に記載されている23桁の数字です。
申請画面にQRコードからアクセスした場合は、申請書IDは自動的に入力されるため、自分で入力することは不要です。
マイナンバーカードの申請書IDがわからない場合
この申請書IDが不明な場合は、身分証を持って市区町村の窓口で、個人番号カード 交付申請書の再交付の手続きを行ってください。
再交付された用紙に「申請書ID」が記載されています。窓口での再交付は数分で完了し、手数料もかかりません。あとはスマートフォンまたはパソコンの画面に沿って、メールアドレスの入力や顔写真を送ればマイナンバーカードの発行手続きは完了です。
後日届く「交付通知書」をもって、市区町村の窓口へマイナンバーカードを受け取りに行きましょう。
まとめ
マイナンバーカードには、いくつもメリットがあり発行手数料も初回は無料のため、作っておいて損はありません。今後も機能が拡充していくことでしょうし、特に顔写付きの身分証明書をお持ちでない方や確定申告を行っている方にはおすすめです。
マイナポイントの期限間近はさらに受付が混雑することが予想されるため、早めにマイナンバーカードを発行して、お得にマイナポイント還元を受け、そして便利に確定申告をしましょう。