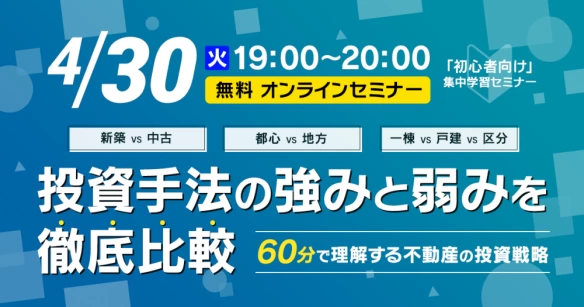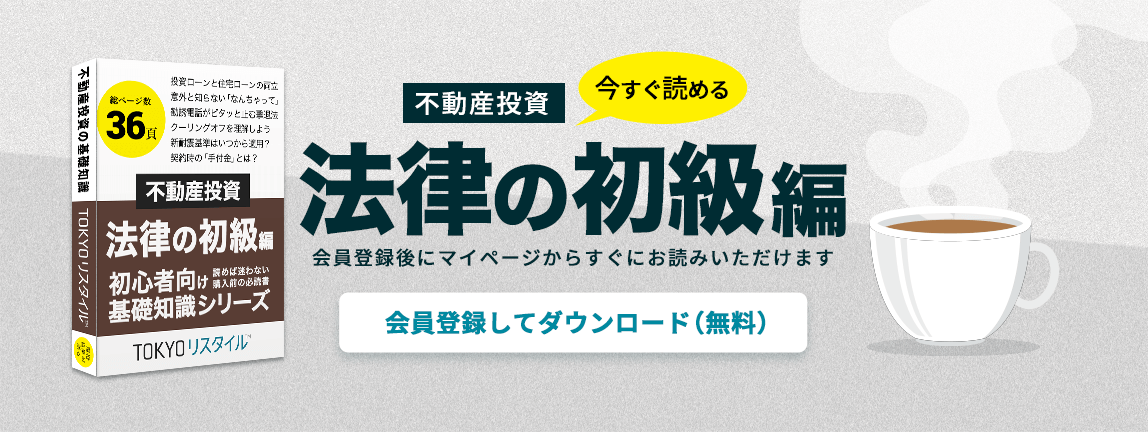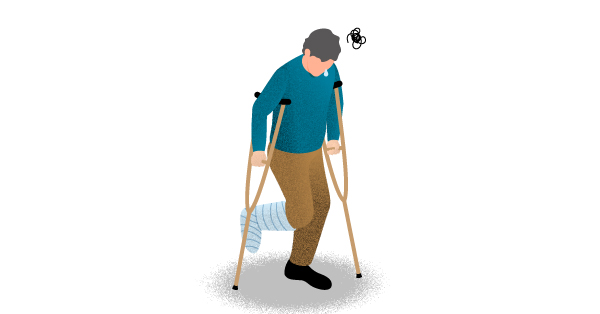権利能力とは?不動産取引で押さえておきたい「制限行為能力者」との取引のポイントを解説!
- 更新:
- 2023/06/19

権利能力とは、法律上の権利や義務の主体となれる資格のことです。具体的には「ものの売り買い」をはじめとする当たり前の行為ができる資格のことであり、基本的にはすべての人間および法人に与えられています。
押さえておきたいのは、こうした当たり前にできている「法律行為」を制限されている人がいるということ。法律行為を制限されている「制限行為能力者」と知識がない状態で取引することは、後から契約を取消されるなどのリスクを孕んでいます。
今回は不動産取引に関係する3つの「能力」と、法律行為を制限されている「制限行為能力者」について詳しく解説します。非常に難しい概念ではありますが、本記事では内容を嚙み砕いてわかりやすく説明するので、ぜひ最後まで読んでみてください。
- 目次
- 不動産取引にも関係する3つの「能力」とは
- 行為能力が制限されている「制限行為能力者」とは
- 制限行為能力者との不動産取引で押さえておきたいポイント
- 制限行為能力者との不動産取引が発生するケースの例
- 制限行為能力者かどうか疑わしい場合は確認できる
- まとめ
不動産取引にも関係する3つの「能力」とは
能力とは、法律上の一定の行為について要求される資格のことです。民法において「能力」は下記3つの概念に区別されています。
- 権利能力
- 意思能力
- 行為能力
上記3つの能力の概念は、それぞれ不動産取引にも関連します。まずは3つの能力の基本について見ていきましょう。
権利能力:法律上の権利・義務の主体となれる資格
権利能力とは、法律上の権利や義務の主体となれる資格のことです。つまり「権利能力がある」というのは、物の売り買いなど、人間として生活していれば当たり前の行為をする権利があることを指します。
物の売り買いでさらに具体的に説明すると、物を買った人には代金を支払う「義務」と物をもらう「権利」が、売った人には物を引き渡す「義務」が発生します。この権利・義務が本人に帰属するということは、それぞれに権利能力があるということです。
基本的に権利能力を有するのは「すべての人間と法人」ですが、「損害賠償請求」「相続」「遺贈」の3つにおいては、出生前の胎児にも権利能力が認められます。ただし、「出生した瞬間に、胎児の時からさかのぼって権利能力を持っていたものとして扱う」のであって、まだ胎児である間は相続等の対象にならないので注意しましょう。
参考不動産投資物件の生前贈与とは?相続税対策になるメリットと注意点を解説!
意思能力:自らの行為の結果を判断できる精神的能力
意思能力とは、自分がした法律行為の結果を判断できる精神的能力のことです。不動産の分野における法律行為には、「売買契約」や「賃貸借契約」などの契約行為が主に該当します。つまり「売買契約や賃貸借契約を行ったが、自分が契約を行ったことをしっかり理解できている」状態が、「意思能力がある」ということです。
これに対し、「意思能力がない」のは主に下記のような人を指します。
- およそ10歳未満の子供
- 重度な精神病の罹患者
- 泥酔者
- 認知症
意思能力がない人がした法律行為は、基本的にすべて無効となります。「およそ10歳未満の子供」と表記しているのは、年齢に明確な定めがないためです。たとえば6歳の子供が買い物をする場合について見てみましょう。
日常的な買い物の場合は、6歳程度でも十分に意味を理解して実行できるため「意思能力がある」という判断が可能です。対して車や不動産のような高額なものの購入について、6歳の子供が「日常的な買い物と比較してどの程度高額か」という定量的な意味を理解するのは難しいため「意思能力がない」といえます。
行為能力:単独で法律行為を行う能力
行為能力とは、単独で法律行為を行う能力のことです。つまり行為能力を持っていれば、不動産投資における売買契約・賃貸借契約などの取引はすべて問題なく行えます。注意すべきは行為能力が制限されている「制限行為能力者」の存在です。次の項で詳しく見ていきましょう。
行為能力が制限されている「制限行為能力者」とは
先述の通り、行為能力が制限されており、一人で売買契約や賃貸借契約などの法律行為ができない「制限行為能力者」に該当する人が存在します。制限行為能力者には特定の「保護者」がつき、保護者の同意がなければ制限された法律行為ができません。4種類の制限行為能力者とその保護者、制限の内容は下記の通りです。
| 制限行為能力者の種類 | どんな人が該当するか | 保護者は誰か | 制限の内容 |
|---|---|---|---|
| 未成年者 | 18歳未満の人 | 親権者か未成年後見人 | ほぼすべての法律行為が一人でできない |
| 成年被後見人 | 後見開始の審判(※)を受けている人 | 親族か弁護士などの士業者(法定代理人) | 日用品の購入以外の法律行為が一人でできない |
| 被保佐人 | 保佐開始の審判(※)を受けている人 | 親族か弁護士などの士業者 | 一部の法律行為が一人でできない |
| 被補助人 | 補助開始の審判(※)を受けている人 | 親族か弁護士などの士業者 | 家庭裁判所が定めた法律行為が一人でできない |
2022年4月に成人年齢の引き下げがあったため、制限行為能力者における未成年者も20歳から18歳に引き下げられました。なおすべての制限行為能力者について、制限された法律行為を一人で行った場合でも、契約は一時的に有効となります。ただし本人や保護者によってほぼ無条件で取り消せるため、ここでは「できない」という表現を用いています。
それでは4種類の制限行為能力者について、個別に見ていきましょう。
※「後見開始の審判」「保佐開始の審判」「補助開始の審判」とは、それぞれ精神障がいなどの理由で判断能力が欠けている人を保護するための、家庭裁判所で行う手続きです。
参考裁判所
未成年者
未成年者は18歳未満の人です。保護者の同意がなければ、ほぼすべての法律行為ができません。またもし法律行為を未成年者一人でしてしまったら、本人または保護者により取消ができます。つまり未成年者と直接の不動産取引は、基本的に一切できないので覚えておきましょう。未成年者の保護者に該当する人は下記の通りです。
- 親権者
- 未成年後見人
親権者は一般的に両親のことです。親権者がいない場合は「未成年後見人」として、祖父母等の親族を親権者の代わりとして選出します。親族が一人もいない場合は、法人が保護者として扱われる場合もあるので押さえておきましょう。
成年被後見人
成年被後見人とは18歳以上であるものの、精神障がい・重度の認知症などにより常にほとんど判断能力がなく、家庭裁判所で「後見開始の審判」を受けている人のことです。成年被後見人は、日用品の購入以外の法律行為は一人ではできません。
成年被後見人の保護者は、必ず親族や弁護士、司法書士などの「法定代理人」となります。法定代理人以外が保護者となることはないので押さえておきましょう。
被保佐人
被保佐人とは18歳以上で、精神障がいにより判断能力が著しく欠けており、家庭裁判所で「保佐開始の審判」を受けている人のことです。保護者は法定代理人に限りませんが、一般的に親族や弁護士、司法書士などの士業者となります。
被保佐人は基本的な法律行為を保護者の同意なく行えますが、一部の行為が制限されています。そのうち不動産取引に関わる行為は下記の通りです。
- 不動産の売買
- 5年超の宅地の賃貸借
- 3年超の建物の賃貸借
- 建物の新築や増築、大規模な修繕
- ローンを組むこと
- 相続を承認すること
- 他人の保証人になること
不動産取引においては、一般的なアパート・マンションの賃貸借契約以外、ほとんど被保佐人一人では行えないといっても過言ではないでしょう。
被補助人
被補助人とは18歳以上で、精神障がいにより判断能力が欠けており、家庭裁判所で「保佐開始の審判」を受けている人のことです。被保佐人と同様、一般的に親族や弁護士、司法書士などの士業者が保護者となります。
被補助人が制限される法律行為の内容は定められておらず、家庭裁判所の判断で臨機応変に設定されます。ただし不動産売買など高額な取引は制限され、一人で行えなくなるケースが多いです。
制限行為能力者との不動産取引で押さえておきたいポイント
制限行為能力者に該当する人と不動産取引をする場合、事前知識がないと取消されるなどのトラブルになりえます。下記の4つのポイントを押さえておきましょう。
- 制限行為能力者が行為能力があると偽った場合は取消されない
- 「追認」か「取消」かの催告ができる
- 「法定追認事由」に該当する場合は追認扱いとなる
- 保護者と一度面談して同意を得ておくとトラブルがない
それぞれのポイントについて詳しく解説します。
制限行為能力者が行為能力があると偽った場合は取消されない
制限行為能力者が一人で制限された法律行為を行ったとしても、「自分に行為能力がある」と偽った場合には行為の結果が取消されません。このことを「詐術」と呼びます。詐術に該当するのは下記のようなケースです。
- 免許証などの本人確認書類を偽造した
- 保護者の同意書を勝手に書いて提出した
- 保護者になりすまして電話で契約行為をした
判断能力が欠けていたとしても、他人をだます人を保護する必要はない、というのが法の解釈です。万が一取引相手が制限行為能力者だと後から判明した場合も、取り消されるリスクがないという点は押さえておきましょう。
「追認」か「取消」かの催告ができる
保護者の同意がないまま制限行為能力者と取引を行った場合、制限行為能力者自身や保護者により突然取引を取消にされてしまうリスクが発生してしまいます。このリスクを最小限にするため、1か月以上の期限内を定め、保護者に対して契約の了承(追認)をするか取消をするかの決断を求める「催告」が可能です。
期限内に保護者から回答がなかった場合は契約を了承したものとみなされるため、取消されるリスクがなくなります。また被保佐人・被補助人には直接の催告も可能ですが、このケースでは期限内に回答がない場合、契約は取消となるので覚えておきましょう。
「法定追認事由」に該当する場合は追認扱いとなる
保護者が追認の意思を表示していないものの、法律により「法定追認事由」を認められ追認扱いとなるケースがあります。6つの法定追認事由と、該当するケースを見ていきましょう。
| 法定追認事由 | 該当するケース |
|---|---|
| 第1号:全部又は一部の履行 | すでに代金のやり取りや登記を行った |
| 第2号:履行の請求 | 代金や物件のやり取りを請求してきた |
| 第3号:更改 | 契約を新しいものに差し替えした |
| 第4号:担保の供与 | すでに売買代金相当の担保をやり取りした |
| 第5号:取り消すことができる行為によって取得した権利の全部又は一部の譲渡 | 債権者(売却した)側の制限行為能力者が、第三者に売買代金の債権を譲渡した |
| 第6号:強制執行 | 債権者(売却した)側の制限行為能力者が、強制的に債務者に代金を支払わせた |
上記6つのケースに該当する場合は法定追認が認められ、契約が有効となります。法定追認が認められれば、契約を取消されることはありません。
保護者と一度面談して同意を得ておくとトラブルがない
いずれの制限行為能力者と取引する場合も、保護者としっかり面談して同意を得ておけば基本的にトラブルはありません。保護者の同意のもと行った制限行為能力者との取引は確定的に有効であり、取消されるリスクがないからです。保護者との面談を必ず一度は行いましょう。
制限行為能力者との不動産取引が発生するケースの例
ここではどのような場合に、制限行為能力者との不動産取引が発生するのか解説します。
購入相手が未成年だった
未成年でも不動産の相続を受けられるので、未成年が相続により引き継いだ不動産を購入する、というケースがありえます。この場合はもちろん相手に保護者がいるので、保護者の同意のもと取引を行う必要があるので注意が必要です。
ただし未成年なのに相続を受けているということは、両親・祖父母がすでに他界しており別の未成年後見人がついているケースが多いです。購入する物件に詳しい人がおらず難航する可能性があるため、信頼できる不動産業者の仲介やサポートのもと取引するのが良いでしょう。
購入相手が認知症だった
認知症を患っている人は、認知症の度合いに応じて「成年被後見人」「被保佐人」「被補助人」のいずれかの制限行為能力者に該当します。制限行為能力者の種類に応じて成年後見人・保佐人・補助人が保護者となっているので、基本的には保護者とやり取りをします。
売却する側の手続きは非常に面倒ですが、購入する側には特に煩雑な手続きはありません。「直接本人とやり取りしない」こと以外は、通常の不動産取引と思って差し支えないでしょう。
制限行為能力者かどうか疑わしい場合は確認できる
取引相手が「自分は成人だ」と言っているが見た目が未成年にしか見えない場合や、言動がおぼつかず認知症や精神障がい者の可能性がある場合など、制限行為能力者であることが疑われる際には確認する方法があります。ただし状況によって確認方法が変わるので、それぞれ見ていきましょう。
未成年者かどうかの確認:戸籍を提出してもらう
取引相手が未成年かどうか確認したい場合は、役所で取得できる戸籍を提出してもらいましょう。戸籍には正しい生年月日が確実に記載されているので、未成年者かどうかを間違いなく確認できます。
運転免許証などの本人確認書類でも簡易的に確認はできますが、詐術(偽造の免許証を提示する)を行っている可能性が0ではないので、戸籍を提出させるのが好ましいでしょう。
成年被後見人・被補助人・被保佐人かどうかの確認:法務局の登記情報を提出してもらう
取引相手が成年被後見人や被補助人、被保佐人に該当するかどうかは、法務局で取得できる「登記されていないことの証明書」を取得・提出してもらえば確認できます。もし証明書を提出できないと言われたら、制限行為能力者に該当する可能性が非常に高いです。この場合は相手方の親族などに確認を取りましょう。もしくは取引そのものを諦めるのもひとつの選択肢です。
参考「登記されていないことの証明書」ってなに?分かりやすく解説します
まとめ
売買などの法律行為は人間や法人すべてに認められた権利能力ではありますが、年齢や精神障がいを理由に能力が制限されている「制限行為能力者」がいるので、不動産取引の際は注意が必要です。制限行為能力者は基本的に保護者の同意がなければ、一人で取引を行えません。
制限行為能力者と直接取引してしまった場合には、後から契約を取消されるリスクがつきまといます。期限を定めて「催告」し、契約を承認するか取消するかの判断を求めれば、このリスクの期間を最小限にとどめられます。
もし制限行為能力者と取引する場合は、保護者と一度面談し、しっかり同意を得ておけば基本的にトラブルは起きません。また制限行為能力者であることが疑わしい場合には、戸籍や「登記されていないことの証明書」を提出してもらって確認しましょう。
とはいえ個人が取引相手が制限行為能力者ではないかと疑うことに、ハードルを感じてしまう方もいるのではないでしょうか。そのような方は、信頼できる不動産会社のサポートや仲介を受けながら取引することも検討してみてください。

この記事の執筆: 及川颯
プロフィール:不動産・副業・IT・買取など、幅広いジャンルを得意とする専業Webライター。大谷翔平と同じ岩手県奥州市出身。累計900本以上の執筆実績を誇り、大手クラウドソーシングサイトでは契約金額で個人ライターTOPを記録するなど、著しい活躍を見せる大人気ライター。元IT企業の営業マンという経歴から来るユーザー目線の執筆力と、綿密なリサーチ力に定評がある。保有資格はMOS Specialist、ビジネス英語検定など。
ブログ等:はやてのブログ