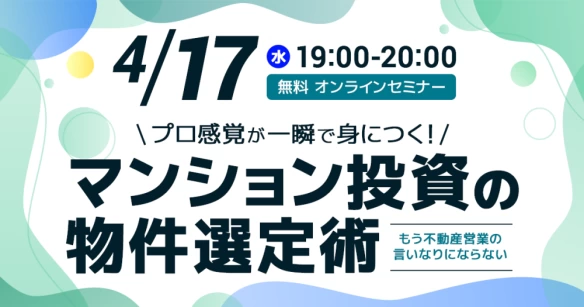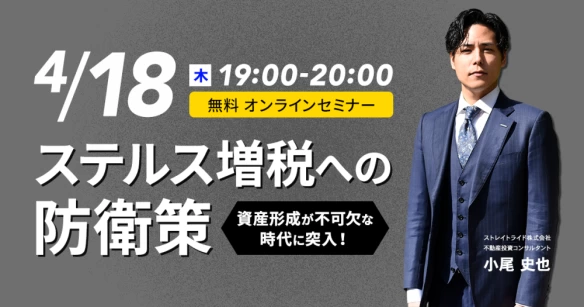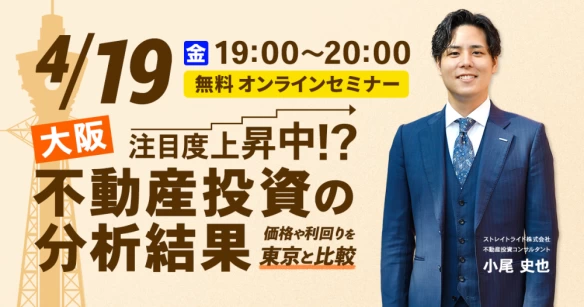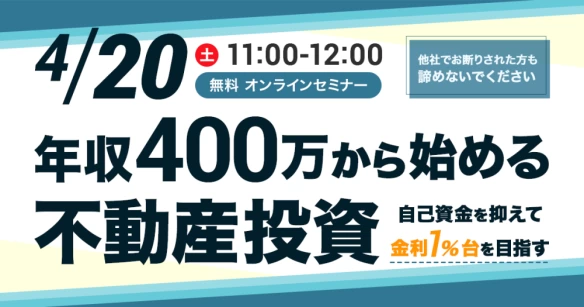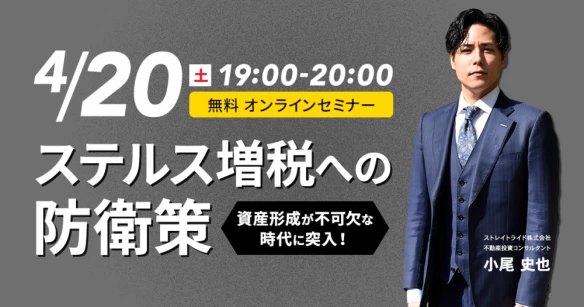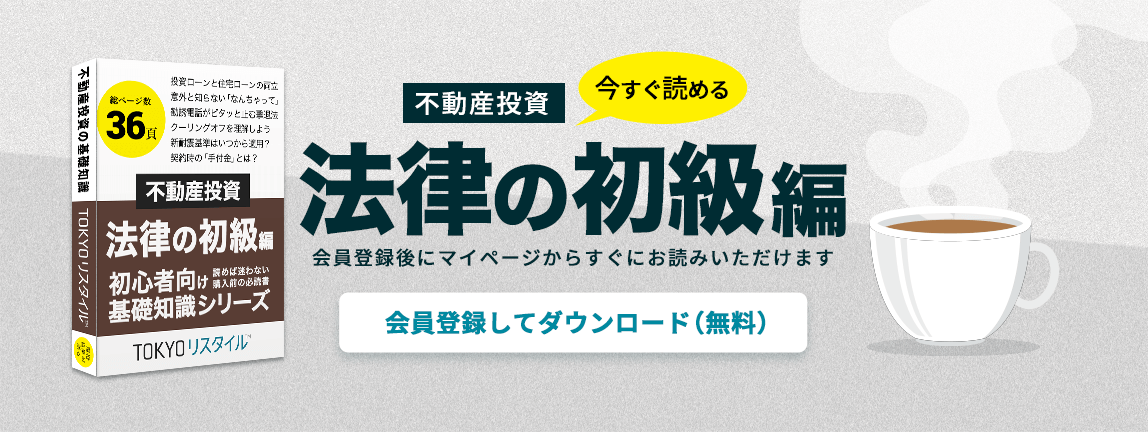法律用語の善意・悪意とは?不動産売買におけるケース別の判断基準などを解説!
- 更新:
- 2023/06/19

一般的に「善意」というと、良い感情や好意を指し、反対に「悪意」は悪い感情や敵意を指します。しかし、法律用語で頻出する善意と悪意は、全く違う意味合いを含んでいるため、注意が必要です。
法律用語における「善意」とは、知らなかったことを意味し、「悪意」とは知っていたことを意味します。これが法律における重要な判断基準となり、自分または相手が善意だったか悪意だったかによって結果が異なることも少なくありません。
この記事では、法律用語としての善意と悪意を解説し、万が一不動産売買で騙されて契約した時の判断基準や取得時効などについてもご説明します。
法律用語としての善意・悪意とは
まずは、法律用語としての善意・悪意とはどのようなものかを解説します。
善意とは
法律用語における善意とは、ある事情を知らないことです。日常的に使われるような親切心などの道徳的な意味はなく、ただその事情を知っているかどうかだけが焦点になります。
例えば、Aさんが他人の不動産を自分のものだとして売却したケースで考えてみましょう。売却した不動産が、本当は他人のものであると知らなかった場合、Aさんは善意だと判断されます。
尚、法律的に保護されるためには、善意であり、かつ本人に落ち度もないという「善意無過失」が求められることが多いです。通常であれば行うべき注意を怠ったなど、落ち度が認められる場合は「有過失」となり、無過失よりも保護されにくくなります。
悪意とは
悪意は、善意の反対の意味となります。法律用語における悪意とは、ある事情を知っているということです。法律用語の善意と同様に、悪意にも道徳心や人格は関係ありません。
例えば、Aさんが他人の不動産を自分のものだとして売却したケースでは、その不動産はAさんのものでないとAさん自身が知っていたのであれば、Aさんは悪意となります。
不動産売買におけるケース別の判断基準
不動産売買において、後から契約を取り消したいということがあるかもしれません。一般的な契約では、契約内容に従って取り消しの可否が決まりますが、以下の5つのケースの場合、当事者または第三者の善意・悪意が重要な判断基準のひとつになります。
- 相手と共謀した(虚偽表示のケース)
- 勘違いだった(錯誤のケース)
- 嘘をつかれた(心理留保のケース)
- 騙された(詐欺のケース)
- 脅された(脅迫のケース)
ここから、善意・悪意による判断基準と、5つのケースそれぞれについて解説します。
善意・悪意により判断する
不動産売買などの契約を取り消す場合、自分か相手、または第三者に不利益が生じることがあります。そこで、民法によって保護されるべき人の判断基準を定めています。
民法では、個人や法人が自由に契約できるという原則がありますが、契約の成立には確定性・適法性・社会妥当性の3つの要件が求められます。契約は、当事者同士が確実に理解し合い、法律に則って、一般的な社会秩序や道徳に反していない必要があるということです。
このことから、多くのケースでは善意無過失の場合は保護されやすく、悪意の場合は保護されにくい傾向にあります。
それでは、これより5つのケース別に判断基準を解説します。
相手と共謀した(虚偽表示のケース)
当事者間で共謀し、実際とは違う意思表示をすることを「虚偽表示」と言います。このケースでは、売主・買主が共に加害者側という側面があるため、保護されにくくなっています。

例えば、借金をしているAが、資産の差し押さえを逃れるためにBと共謀して、Bに不動産を売却したことにして、Bに所有権を移転させた場合は虚偽表示となります。
売主買主双方が共謀しているので、そもそもこの契約は無効となります。しかし、もし登記上の所有者となっているBが善意の第三者に売却した場合、第三者が共謀の事実を知らない「善意の第三者」であれば、AとBは第三者から不動産を取り返すことはできません。
この場合、AとBはそもそも共謀して悪さをしているため、保護しなくても良いと判断されます。ここでは、第三者は善意でさえあれば良く、無過失である必要もありません。
勘違いだった(錯誤のケース)
当事者間に思い違いがあり、それをお互い知らなかったという勘違いを「錯誤」と言います。

例えば、Aが1,000万円で不動産を売却するつもりで、間違って契約書に1,000円と記載したとしましょう。契約書を見たBが、不動産を1,000円で買えると勘違いして購入した場合、錯誤が生じます。
このケースでは、Aが「間違いだったので契約を無しにしたい」と主張すれば、売買契約は取り消せます。契約のうえで金額という非常に重要なことを間違ってしまったのであれば、間違えてしまったAには大きな落ち度はないとして保護されます。
もしBが第三者Cに不動産を転売していた場合、第三者Cが善意無過失であれば、第三者Cが保護され、AとBは第三者Cに対抗できません。しかし、第三者Cが悪意または有過失であれば、AまたはBは契約取り消しを理由に、第三者Cに対抗できます。
嘘をつかれた(心理留保のケース)
売主または買主の一方が、真意とは違う内容の意思表示をすること、つまり嘘をつくことを「心理留保」と言います。

例えば、Aが本当は売るつもりのない不動産を冗談で契約し、買主Bがその契約を信じていた場合、売買契約は有効です。たとえAは冗談のつもりでも、信じて購入したBが保護されます。
ただし、Aが本当は売るつもりがないことに対してBが知っていた「悪意」または通常の注意をすれば気付けた「有過失」であれば、契約は無効となります。
また、買主Bが第三者Cに不動産を転売していた時は、第三者Cは善意であれば保護されます。
騙された(詐欺のケース)
自分に有利な状況にするために、当事者の一方が相手を騙すことを「詐欺」と言います。詐欺では相手についた嘘によって相手に不利益を与える、または自分が利益を得ようとしているため、ただ嘘をつくだけの心理的留保とは異なります。

例えば、Aが「この不動産は価値がないので今すぐ売った方が良い」とBに言われて、Bに不動産を売却したとしましょう。実際は価値のある不動産で、相場より極端に低い価格で売却してしまったケースでは、Aが詐欺に遭ったと言えます。
詐欺は、その契約自体は有効です。しかし、Aが後から契約を取り消すことはできます。ただし、Bが安く購入した不動産を、既に第三者Cに売却している場合は要注意です。
第三者Cが善意の時は、騙されたAにも多少の落ち度があるとして第三者Cが保護され、Aは第三者Cに対抗できません。しかし、第三者Cが悪意であれば、Aは契約の取り消しを理由に第三者Cに対抗できます。
参考どう見抜く!?不動産投資の「詐欺まがい商法」を完全解説!
脅された(脅迫のケース)
相手を脅すことを「脅迫」と言います。直接取り引きの相手から脅迫される他に、第三者から脅迫されて取り引きをしたケースでも同じルールが適用されます。

例えば、Aが本当は売りたくなかった不動産に対して、Bが脅して無理に売却させた場合、AはBからの脅迫によって契約したことになります。脅迫による契約も有効ではありますが、後から取り消すことができます。
脅されたAに落ち度がないと判断されるのが、脅迫の特徴です。すでにBが第三者Cに不動産を転売していた場合、第三者Cが善意無過失だったとしても、脅されたAが保護されます。Aは契約を取り消し、第三者Cに対抗できます。
不動産投資にも関係する取得時効
取得時効に関係する土地を不動産投資として購入したら、実は登記とは別の人が所有権を持っていたというトラブルに繋がりかりかねません。ここでは、不動産投資をするうえでも問題になることがある「取得時効」について解説します。
取得時効とは
取得時効とは、「二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した物は、その所有権を取得する」または、「十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する」という民法162条に規定されるルールです。
つまり、自分のものであるという意思を持って、平和的に、隠したりせずに不動産を占有していた場合は、10年または20年間占有していた人がその不動産の所有者になるということです。
例えば、Aが不動産を占有している場合、Aが占有開始時点で、本当は自分の所有物ではないと知っている「悪意」であれば20年間占有し続ける必要があります。ただし、占有開始時点でAがその不動産は本当は自分の所有物ではないと知らず、落ち度もない「善意無過失」だった場合は、10年間占有していればAが不動産の所有権を取得します。
ただし、取得時効により所有権を取得した人が登記をしていなければ、所有権を持つ人と登記上の所有者が違うという複雑な状況になります。
更に取得時効に関わる不動産を登記上の所有者BがCに売却した場合、関係は以下の図のようになります。

これより、取得時効完成前に売却した場合と取得時効完成後に分けた場合について解説します。
占有中に不動産を購入した場合
Aが占有している不動産をCが購入して、所有権移転登記をしたケースで考えてみましょう。登記簿上の所有者であるBと買主Cが売買契約を結んでCが登記したとしても、その後に取得時効が完成した占有者Aは「この不動産は自分に所有権がある」と主張できます。
このような事態に気付かず、更に取得時効完成まで放置していたCは、保護する必要はないと考えられるからです。
取得時効完成後に不動産を購入した場合
占有者Aの取得時効完成後、第三者Cが登記簿上の所有者Bから不動産を購入した場合は、AとCのうち登記を先にした方が相手に所有権を主張できます。
この状況では、登記簿上の所有者Bが占有者Aと買主Cに二重譲渡をしたということになり、先に登記をした方が優先されるのです。
不動産投資における注意点
不動産投資では、複雑なトラブルを避ける意識が必要です。ここでは、不動産投資をする前に覚えておきたい注意点をご説明します。
事実関係を確認する
投資用不動産を購入する際には、登記と実際に住んでいる人に違いは無いかなど、事実関係をしっかり確認しましょう。
不動産投資では実際の現地を見ずに購入することも珍しくありませんが、現地を見ないのであればより一層の注意が必要です。
登記を早めに行う
先に登記をした方が優先されるケースも多いため、不動産取り引きを行った後は、なるべく早く登記を行いましょう。不動産を売却した場合も、買主に問題なく所有権が移転しているかの確認が必要です。
ただし、これらの点を完璧に行い、トラブルの無い取り引きをするには、多くの知識と経験が要求されます。不動産投資においては、信頼できるパートナーを見つけることも重要です。
参考誰でもわかる!登記簿謄本・登記事項証明書の交付申請書の書き方を解説!
まとめ
この記事では、法律用語における善意・悪意について解説し、ケース別の判断基準、取得時効について解説しました。
トラブルが起きた際には、知らなかったという「善意」かつ落ち度のない「無過失」の方が保護される傾向にあります。それ以前に、可能な限りトラブルが起きないよう、事前に登記簿の事実関係を確認するなどの注意が必要です。
不動産投資における善意・悪意についてのより詳しい情報や、トラブルを未然に防ぐ不動産投資にご興味のある方は、ぜひ当社コンサルタントまでお気軽にご相談ください。

この記事の執筆: 丸岡花
プロフィール:宅地建物取引士・FP検定2級を持つ主婦ライター(2児の母)で、300本以上の不動産関連記事の執筆実績を有する。得意ジャンルは不動産・税金・英語・育児。不動産が大好きで、不動産関連のニュースや法改正、市況のチェックが日課となっている。豊富な知識に裏付けされた独自性の高い切り口と、公的機関や学術論文などの1次情報に基づく正確性の高い文章に定評がある。元バックパッカーで旅行・キャンプをこよなく愛し、過去に20か国以上を訪問した経験を持つ。保有資格は宅建士・FP2級に加え、TOEIC895点(米国居住経験あり)、秘書検定1級、保育士など多岐に亘っている。
ブログ等:シュフリーランス