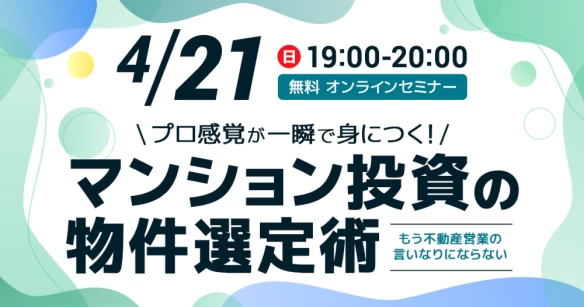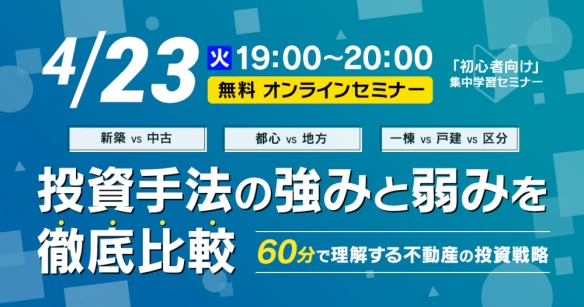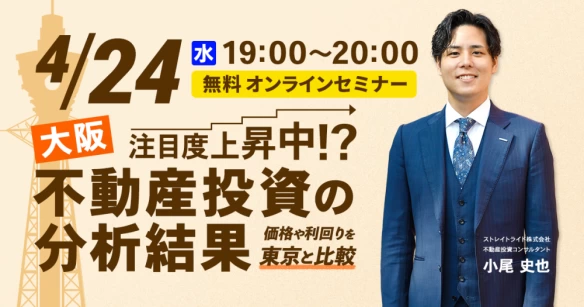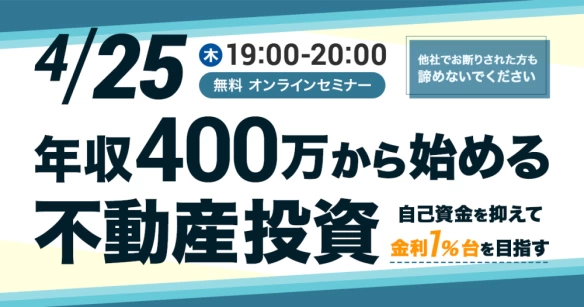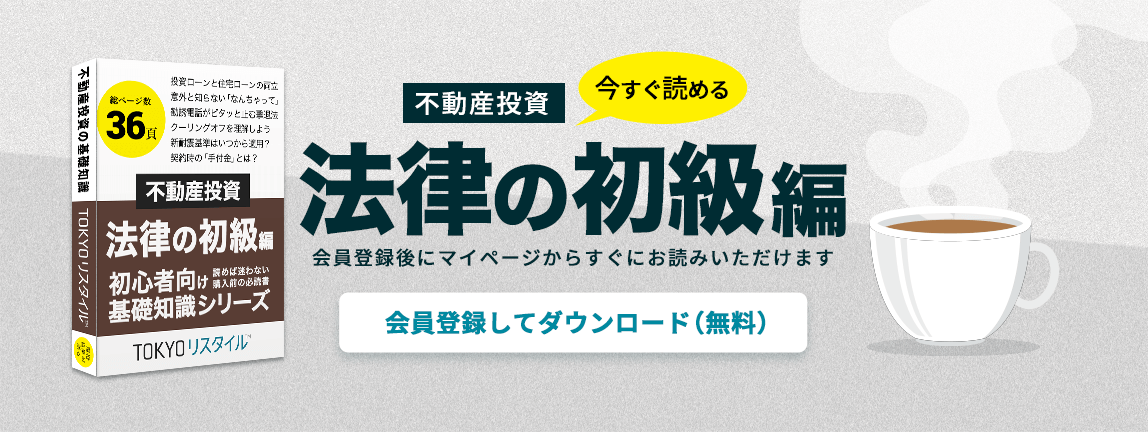求償権とは?行使できる人や請求できる金額を分かりやすく解説!不動産投資との関係も
- 更新:
- 2023/06/19

保証人などの人が債務者の代わりに債務を返済した際に得られる「求償権」という権利があります。求償権を行使すれば、債務者の代わりに返済したお金を取り戻すことが可能です。求償権はケースにより請求できる金額が変わったり消滅したりするので、自分が行使する側の場合はしっかりと仕組みを押さえておく必要があります。
不動産投資において求償権がかかわってくるのは、主に自分がローンを返済できなくなった場合です。万が一の場合に備えて求償権の仕組みを知っておけば、裁判になり財産を差し押さえられるような最悪の事態を避けられるかもしれません。
今回は求償権の基本的な部分や行使した場合に請求できる金額、実際の不動産投資における具体的なケースを解説します。普段の投資活動にはほとんど影響しませんが、ぜひ「もしも」の可能性に備えて求償権について知っておきましょう。
求償権とは
求償権とは、ほかの人の債務を代わりに返済した場合に、本来の債務者に対して支払った金額の返還を求める権利です。後ほど詳しく解説しますが、不動産に関係するのは主にローンの支払い関連でしょう。
イメージとしては「一度立て替えておくので、あとでお金を返してください」という使い方。ただし、ほかの人の債務を立て替えたからといって、無条件で権利が得られるわけではありません。また混同されがちですが、求償権は損害賠償請求権とは異なります。
求償権と損害賠償請求権の違い
求償権は、細かくいうと「債権者の損害賠償請求権を代わりに取得し、債務者に請求する権利」といえます。下記の3者でやり取りをした場合で見ていきましょう。
- A:債務者(お金を借りている人)
- B:債権者(お金を貸し付けている人)
- C:保証人等(お金を代わりに返す人)
債務者のAがもしBに借りていたお金を返せなかった場合、BはAに対して損害賠償を請求する権利を得ます。しかし、保証人のCがAの借金を肩代わりし、Bに支払いました。すると、Bの持っていた損害賠償請求権はなくなり、Cが同様の権利を取得します。
ここでCが得た権利が、損害賠償請求権から名前を変えて「求償権」となるわけです。似ているものですが微妙に違うので、ぜひ押さえておいてください。
債務者が亡くなっていても相続人に求償権を行使できる
求償権は、もし債務者が亡くなってしまった場合でも消滅しません。債務者の抱えていた債務は、相続人に引き継がれます。そのため、相続人に対して求償権を行使すれば、立て替えたお金を取り戻せます。
ただし相続人全員が相続放棄をしてしまった場合のみ、求償権を行使する相手がいなくなってしまうので注意が必要です。とはいえ一方的に債権者が不利になってしまうので、相続人となるはずだった人に請求できる場合もあります。万が一相続人全員に相続放棄をされてしまったら、弁護士に相談するのが得策です。
参考親が亡くなったら何をすればいい!?相続の手続きやよくあるトラブル、その回避方法まで解説!
求償権の時効は5年
求償権の時効は5年と定められているので注意が必要です。求償権を得ても、5年以内にお金を取り戻さなければ、求償権そのものが消滅してしまいます。ただし下記のようなケースでは時効が更新されたり、一定の猶予期間が与えられたりするので5年で時効になるとは限りません。
| ケース | 時効の扱い |
|---|---|
| 裁判中に時効期間満了となってしまった | 裁判確定まで時効が猶予され、確定したら5年間の時効が再スタートする |
| 裁判を一度取り下げた | 取り下げてから6ヶ月は時効が猶予される |
| 債権者・債務者間で合意があった | 1年間時効が猶予される 1年ごとに更新すれば最大5年まで時効の猶予が可能 |
裁判には時間がかかる可能性があるので、裁判中に時効が成立して求償権が消滅しないように定められています。債務者にお金の余裕がなく、時効までに返済してもらえない場合も合意があれば時効の延長が可能です。
求償権を行使できる人は?
求償権を行使できる人は、大まかにいうと「ほかの人の債務を代わりに返済した人」ですが、誰でも該当するわけではありません。具体的に求償権を行使できる人を見ていきましょう。
連帯債務者・連帯保証人・保証会社など
求償権を行使できるのは、連帯保証人・保証会社など、契約書上「債務者が返済できなかった場合に、代わりに返済する」と定められた人や法人です。また複数人で債務を負う連帯債務者となっており、そのうちだれか1人が全ての債務を返済した場合、返済した人は残りの連帯債務者に対する求償権が発生します。
なお、口約束だけで連帯債務や保証契約は発生しないので注意が必要です。いずれの場合も後からトラブルにならないよう、債務者と合意のうえで必ず契約書を取り交わしておきましょう。
「物上保証人」も求償権を行使できる
物上保証人とは、他人の債務を担保するために、所有する土地や建物をはじめとする財産に担保権を設定した人です。債務者が何らかの理由で返済できなくなり、物上保証人が担保としていた財産を手放して債務を返済した場合、物上保証人は債務者に対して求償権を行使できます。
ただし連帯債務や連帯保証契約と同じように、求償権が発生するのは債務者と合意のうえで契約を結んでいた場合のみです。口約束だけでは求償権が発生しないので注意しましょう。
求償権で請求できる金額
求償権によって債務者に請求できる金額は、ケースによって大きく変わります。まずは大まかに、ケースごとの金額一覧を見ていきましょう。
| ケース | 請求できる金額 |
|---|---|
| 全額を立て替えて返済した連帯債務者 | ほかの債務者それぞれに対し債務を均等に割った金額 |
| 債務者に頼まれて保証人になった人 | 全額 |
| 自分の意志で保証人になった人 | 返済時に債務者が利益を受けた範囲 |
| 債務者に反対されたのに保証人になった人 | 請求時に債務者が利益を受けた範囲 |
| 債務者に伝えず勝手に返済した人 | 0円 |
| 債務者の合意のもと返済したが、支払ったことを伝えなかった人 | 0円 |
それぞれのケースについて具体的に解説します。
連帯債務者の場合
複数人で債務を負う「連帯債務者」として契約しており、そのうち1人が債務を全額返済した場合は、ほかの債務者それぞれに対し債務を均等に割った金額を請求可能です。
たとえば、A・B・Cの3者が連帯債務者として契約し、1,200万円の債務を負った場合を見ていきましょう。Aは1,200万円の債務を、B・Cの合意のもと全額返済しました。すると、AはB・Cそれぞれに対して「1,200万円 ÷ 3 = 400万円」の求償権を取得します。
つまり、一時的にAが1,200万円の負債を全額肩代わりしたとしても、最終的な負担額は3人とも400万円です。誰か1人が不利益を被ることはないと押さえておきましょう。
債務者に保証人になるのを頼まれた場合
債務者に「保証人になってほしい」といわれて保証契約を結んでいた場合は、民法459条の記載に則り、代わりに返済した金額の全額を請求できます。ただし債務者の同意なく勝手に返済した場合や、返済後に債務者へ通知しなかった場合は求償権が発生しません。この点については、後ほど詳しく解説します。
自らの意思で保証人になった場合
自分から名乗り出て保証人になった場合は「返済時に債務者が利益を受けた範囲のみ」が求償権の請求対象です。たとえば債務者Aが債権者Bから10,000円を借り、6,000円をギャンブルに、3,000円を生活費に使い、1,000円を現金で残していたとします。そして保証人Cが債権者Bに対して、債務者Aの代わりに10,000円を返済しました。
この場合、ギャンブルに浪費した6,000円は「利益を受けた」ことにはなりません。それに対して、生活費の3,000円と現金で残していた1,000円は「利益を受けた」ことになり、保証人Cは債務者Aが利益を受けた合計の4,000円を請求できます。「利益を受けた」ことになるのは、あくまで生活費や物品の購入などに使った分のみです。
ただし不動産におけるローンのやり取りでは「債務者が利益を受けた範囲」には、基本的に代わりに返済した金額の全額が該当します。まれに異なる場合もあるので、不明な場合は弁護士に相談しましょう。
債務者に反対されたのに保証人になった場合
債務者に反対されたのに保証人になった場合は「請求時に債務者が利益を受けた範囲のみ」が求償権の請求対象となります。「自らの意思で保証人になった場合」と異なるのは「返済時」ではなく「請求時」に債務者が利益を受けた範囲を請求するという点です。
たとえば同様のケースで、保証人Cが債権者Bに対して返済を行ってから、保証人Cが債務者Aに対して請求をかける間に、債務者Aが現金で残していた1,000円をまたギャンブルに浪費してしまった場合には扱いが変わります。この1,000円については「債務者が利益を受けた範囲に含まれない」とみなされるため、保証人Cが請求できるのは債務者Aが生活費として使った3,000円のみとなってしまいます。
とはいえ自らの意思で保証人になった場合と同様に、不動産関連のやり取りでは基本的に全額を請求できるので覚えておきましょう。
勝手に返済してしまった場合
契約を結んで保証人になっていた場合でも、債務者の同意を得ず勝手に返済してしまった場合は1円も請求できなくなります。非常にまれなケースではありますが、債務者が債権者に対して別の債権を持っており、お互いの債権を相殺して差額だけ返済すれば済む可能性があるためです。
上記のようにお互いの債権を相殺できる状態ではなかったとしても、勝手に返済した場合は絶対に求償権が発生しません。トラブル防止のため、必ず事前に債務者へ通知しましょう。
支払った旨を債務者に伝えなかった場合
保証契約を結び、しっかりと同意を得て債務を代わりに返済した場合でも、支払った旨を債務者に通知していなかった場合には1円も請求できません。個人間や一般の法人との契約の場合は、支払った旨を通知しないと下記のような事案が発生するリスクがあるからです。
- 保証人が債務者に代わり、債権者にお金を支払う
- 債権者が「お金を受け取っていない」とウソをつき、債務者にも同額を請求する
- 債務者が知らずにお金を支払ってしまい、2重に支払った状態になる
上記の事案で2重に支払った状態になり、そのお金を取り戻せなかったとしても、保証人は立て替えた金額を債務者に請求できません。なお不動産に関連するローンの立て替え返済において、債権者である金融機関がウソをつく可能性はほぼ0といえます。しかし、それでも支払った旨を債務者に伝えなかった場合は、求償権が発生しないので注意しましょう。
不動産投資で求償権がかかわるケース
改めて、不動産投資において求償権がかかわる、主な2つのケースを紹介します。
- ローンが払えなくなったケース
- 連帯保証人が代わりにローンを払ったケース
基本的に不動産投資をしている側が求償権を行使できるケースはありません。万が一の事態が発生して返済ができなくなった場合に、求償権を行使される側となる可能性があります。それぞれ詳しく見ていきましょう。
ケース①:ローンが払えなくなった
不動産投資において求償権がかかわってくるもっとも多いケースは、ローンが払えなくなってしまった場合でしょう。ローンでは万が一債務者が返済できなくなった場合に金融機関が不利益を被らないよう、保証会社をはさんで契約するのが一般的です。
ローンが払えなくなっても、金融機関と交渉すればしばらく返済期間を延ばしてもらえる可能性があります。しかし返済の見込がないと判断され、保証会社が代わりに金融機関へお金を支払った場合、保証会社は債務者に対する全額の求償権を得ます。
保証会社が求償権を得た場合、抵当権を行使してあらゆる財産を差し押さえる動きをするので注意が必要です。万が一ローンを返済できなくなってしまった場合は、保証会社が金融機関にお金を払う最悪の事態を避けるよう対策しましょう。
ケース②:連帯保証人が代わりにローンを払った
保証会社が一般化したので昨今では非常にまれですが、ローンを契約する際に連帯保証人をたてる場合があります。債務者がローンを返済できなくなり連帯保証人が代わりにお金を金融機関へ支払ったケースでは、連帯保証人が債務者に対する全額の求償権を得ます。
連帯保証人が求償権を得た場合は、保証会社のように抵当権を駆使して強制的に財産を差し押さえられることはありません。ただし裁判を起こされてしまえば、強制的な財産・給与の差し押さえもあり得るでしょう。
もし求償権を行使されたものの、5年以内に連帯保証人に対して返済ができない場合、交渉すれば時効期間を最大10年まで延ばせる可能性があります。そのため万が一の事態を考慮して、連帯保証人との関係は良好な状態を保っておくのが得策です。
参考不動産投資ローンと住宅ローンは両立可能か?互いの影響やローン借り換えには要注意!
まとめ
求償権とはほかの人の債務を代わりに返済した場合に、本来の債務者に対して支払った金額の返還を求める権利です。「一度立て替えておくので、あとでお金を返してください」というイメージで使います。求償権を行使できるのは、契約書に記載された連帯債務者や連帯保証人などです。
請求金額は、ケースによって異なります。自分が行使する側の場合、立て替える前後に債務者への通知を忘れると、求償権が消滅してしまうので注意しましょう。
不動産投資で求償権がかかわってくるのは、主に自分がローンを返済できなくなってしまった場合。求償権の仕組みを知っておけば、裁判による財産差し押さえなどの最悪の事態を避けられるかもしれません。
とはいえ、そもそも無理のない返済計画を立てて不動産投資をスタートするのがもっとも大切です。当社ではお客様の予算に応じて、できる限りリスクの小さいご提案をいたします。ぜひ一度お気軽にご相談ください。

この記事の執筆: 及川颯
プロフィール:不動産・副業・IT・買取など、幅広いジャンルを得意とする専業Webライター。大谷翔平と同じ岩手県奥州市出身。累計900本以上の執筆実績を誇り、大手クラウドソーシングサイトでは契約金額で個人ライターTOPを記録するなど、著しい活躍を見せる大人気ライター。元IT企業の営業マンという経歴から来るユーザー目線の執筆力と、綿密なリサーチ力に定評がある。保有資格はMOS Specialist、ビジネス英語検定など。
ブログ等:はやてのブログ