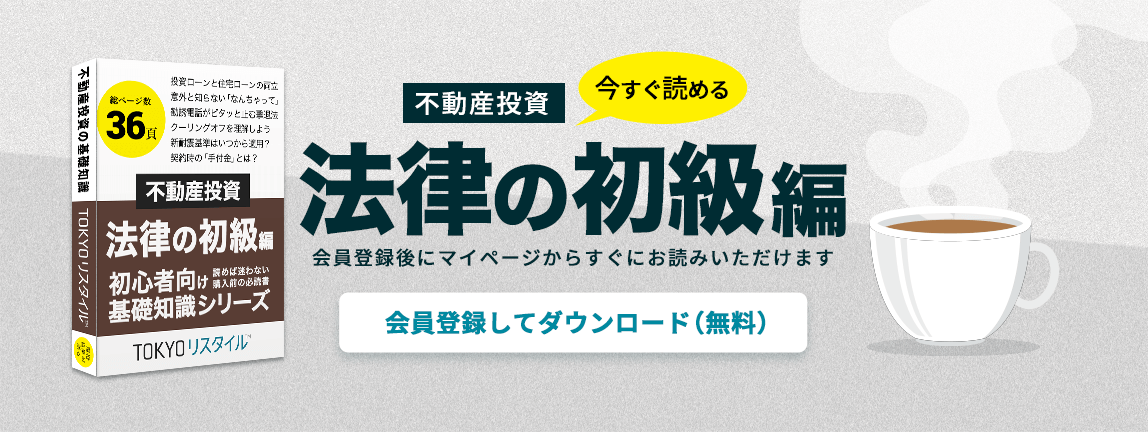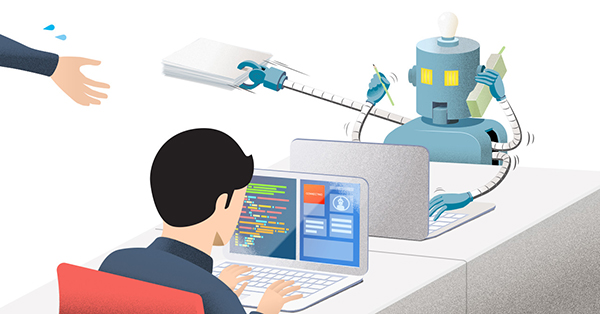道路と不動産投資の関係は!?「みなし道路」や「再建築不可物件」まで解説します!
- 更新:
- 2023/06/19

みなさんが当たり前に普段歩いたり、車を走らせたりしている「道路」。実はこの道路にはさまざまな種類があり、物件に接する道路の種類によって不動産価値に大きな影響を及ぼすことはご存じでしょうか?
今回解説するのは、主に「みなし道路」と呼ばれる道路に接する物件と、建築基準法の道路に関する条件を満たせず「再建築不可」となっている物件についてです。これらの物件は低価格で購入でき、高利回りが見込める物件ではありますが、非常にリスクが高いため投資初心者にはかなり難易度が高いと言えるでしょう。
この記事を読めば、これらの物件に投資するメリット・デメリットやリスクの全容が分かります。ぜひ不動産投資で損をしないための知識を身に付けていきましょう。
道路は不動産価値に大きく影響する
不動産投資において、隣接する道路の状況は不動産価値に大きく影響します。なぜなら道路の幅員などの条件に応じて、建てられる物件の種類が変わったり、再建築の際に使える土地の幅が狭くなったりするからです。
そもそも道路に面しておらず「接道義務」を満たしていない物件の場合は、再建築ができない物件となっていることもあります。まずはこの接道義務が何なのかという部分や、建築基準法で定められた道路の種類について見ていきましょう。
押さえておきたい不動産の基本「接道義務」
建築基準法第43条において、「都市計画区域」または「準都市計画区域内」にある建物が建っている土地は、建築基準法上の道路と2メートル以上接しなければいけないと定められています。このことを「接道義務」と呼んでいます。
接道義務を満たしていない土地の上には、許可が下りないため新たな建物の建築ができません。再活用ができないために、土地の価値が大きく下がってしまうのです。このような状態の物件のことを「再建築不可物件」と呼びます。再建築不可物件については、記事の後半で詳しく見ていきましょう。
建築基準法上の道路は6種類
先述したように一般的な建物は、建築基準法上の道路と2メートル以上接しなければいけないと定められています。この「建築基準法上の道路」は6種類あるので、それぞれの分類をざっくりと見ていきましょう。
| 道路の種類 | 特徴 |
|---|---|
| 法第42条第1項1号道路 | ・道路の幅員が4m以上の国道・県道等 ・幅員4m以上の道路はほぼこの道路 |
| 法第42条第1項2号道路 | ・都市計画法等における開発行為等により造られた道路 ・基本的に幅員6m以上の道路 |
| 法第42条第1項3号道路 | ・1950年以前からある幅員が4m以上の道路 |
| 法第42条第1項4号道路 | ・2年以内に事業開始予定の都市計画道路 |
| 法第42条第1項5号道路 | ・幅員4mの私道 ・「位置指定道路」と呼ばれる |
| 法42条2項道路 | ・1950年以前からある幅員4m未満の道路 ・「みなし道路」と呼ばれる |
「法第42条第1項」に該当する5種類の道路は、基本的に大きな制約なく新たな建物を建築できます。注意すべきは「みなし道路」と呼ばれる、「法42条2項道路」です。みなし道路に接する物件の扱いについては、記事の後半で解説します。
再建築不可・みなし道路物件はどうやって確かめる?
再建築不可物件やみなし道路に接する物件は投資のリスクが高いため、不動産を購入する前に確実にチェックしておきたいポイントです。これらの物件に該当するかどうかをチェックする方法を見ていきましょう。
売主に確認する
再建築不可物件やみなし道路に接している物件かどうかは、売主に確認することで教えてもらえるケースがもっとも多いです。また売買の過程でやり取りする「重要事項説明書」には、「敷地等と道路の関係」の項目にみなし道路と接していることが分かる記載があります。
ただし重要事項説明書をやり取りするのは、一般的に契約の直前です。いざ契約というタイミングでリスクの高い物件であることが分かる、というケースは少なくありません。購入を検討する段階で、早めに確認しておいた方が良いでしょう。
役所で調査する
役所の道路関係・建築関係の部署で、再建築不可物件やみなし道路に接している物件かどうかの確認ができます。ただし下記の4つの書類を、事前に法務局で取得する必要があるので注意しましょう。
- 登記事項証明書
- 建物の図面
- 公図
- 地積測量図
法務局の窓口、もしくは法務局のホームページで取得が可能です。取得の際には「地番」という法務局が定めた住所情報が必要になりますが、こちらは土地を管轄する法務局に電話すれば確認できます。また取得には合計1,800円前後の手数料がかかるので注意しましょう。
「みなし道路」の物件には注意が必要
「みなし道路」と呼ばれる、「法42条2項道路」に接する物件には注意が必要です。本来であれば幅員4m未満のみなし道路に接して建っている物件は、「接道義務」を満たせず建築基準法違反となります。みなし道路は、あくまで建築基準法が制定される1950年以前から道路や建物がある場合の特例です。
つまり、みなし道路に接する物件は、そのままの状態では物件を解体して再建築できません。これを避けるために「セットバック」という措置をする必要があります。セットバックについて詳しく見ていきましょう。
みなし道路では「セットバック」が義務
みなし道路に接した物件を解体し再建築するためには、建築基準法上の道路幅である4m以上の幅員を確保するために、土地の境界線を後退させる「セットバック」を行う必要があります。
セットバックする幅は、道路の中心線から2mずつの幅を確保できるように決定します。道路の反対側の土地が宅地であるか、川など境界線を後退できない宅地以外であるかによって異なるので注意が必要です。例えば道路幅が3mの場合を見てみましょう。
道路の反対側が宅地の場合は、所有している土地の境界線を50㎝、反対側の宅地の境界線も50㎝後退させます。つまり自分でセットバックをする必要があるのは50㎝のみで、残りの50㎝はいずれ再建築を行うタイミングで、反対側の宅地の所有者に後退してもらう必要があるのです。
道路の反対側が境界線を後退できない宅地以外の領域の場合は、所有している土地の境界線を1m後退させる必要があります。このケースはセットバックをする幅が大きいので注意が必要です。
セットバックした部分は使えなくなる
最大の注意点として、セットバックした部分は道路になってしまうため、建物を建てたり、駐車場として活用したり、門を設置したりといった活用が一切できなくなります。土地の面積が減るため、建てられる建物の種類を決定づける「建ぺい率」や「容積率」も減ってしまうのです。
つまり事前にセットバックする幅を把握しておかないと、再建築しようと思っていた建物が、建築基準法違反により建てられなくなってしまう可能性があります。そのため、みなし道路に接した物件を購入する際は、セットバックすることを前提とした計画が重要です。
接道義務を満たさない物件は「再建築不可」なので注意
みなし道路にすら接しておらず、セットバックによっても「接道義務」を満たすことができない「再建築不可」物件は、そのままの状態では新たな物件を建てられないため注意が必要です。再建築不可が疑われる物件は、東京都内の物件のうち5%ほどあるといわれています。
なぜ接道義務を満たさない物件がある?
接道義務の内容を含んだ「建築基準法」が制定されたのは1950年です。1950年以前は一切道路に面していない建物や、道路に接する幅が2m未満の建物でも違法とはなりませんでした。また都市計画法が制定されたのも1968年のため、1950年から1968年に建てられた建物の中にも一部再建築不可物件が残っています。
再建築不可物件の運用後の活用法は?
先述したように再建築不可物件は、そのままの状態では新たに建物を建てることはできません。それでも以下の3つの活用方法があるので見ていきましょう。
- リフォームして物件価値を上げる
- 更地にして駐車場や資材置き場にする
- 隣地を取得して再活用する
活用法①:リフォームして物件価値を上げる
再建築不可物件の場合は物件を解体せずリフォームすれば、物件の価値を上げて再度活用できる可能性があります。解体して再建築することはできませんが、大規模なリフォームであれば再建築にあたらないからです。
ただし基本的に築古である再建築不可物件においてリフォームで物件の価値を上げるためには、基礎的な物件構造がある程度優れている必要があります。場合によってはリフォームをすることすら叶いません。賃貸としての活用後にリフォームを検討する場合は、専門家によるインスペクション(住宅診断)を受けてから購入するのがおすすめです。
活用法②:更地にして駐車場や資材置き場にする
物件を解体して更地にしてしまい、駐車場や資材置き場にする方法も考えられます。この方法であれば、継続して収益を得ることも可能です。
ただし再建築不可物件、すなわち接道義務を満たさない物件は、車すら通れない道路幅であるケースも少なくありません。事前にどの程度の車が出入りできるか確認しておきましょう。
活用法③:隣地を取得して再活用する
接道義務を満たすことのできる隣地を取得すれば、土地を合体させ再建築ができるようになります。一見ベストな方法にも思えますが、この方法を使うにはそもそも隣地が空き地となっている必要があるので注意が必要です。
みなし道路物件や再建築不可物件は不動産投資に向かない?
結論から言うと、みなし道路に接する物件や再建築不可物件はメリットこそあるものの、デメリットが非常に大きいので不動産投資にはあまりおすすめしません。特にほとんど投資経験がない初心者の場合は、みなし道路に接する物件や再建築不可物件であることが分かった時点で購入を控えた方が無難でしょう。
この章ではみなし道路物件や再建築不可物件のメリット・デメリットを改めて解説します。もしこれらの物件への投資を検討する場合は、リスクもしっかり押さえておいてください。
みなし道路物件や再建築不可物件に投資するメリット
みなし道路物件や再建築不可物件に投資するメリットは以下の2つです。
- 高利回り・低価格のケースが多い
- 固定資産税が安い
それぞれ詳しく見ていきましょう。
メリット①:高利回り・低価格のケースが多い
みなし道路物件や再建築不可物件は、建て替え時に利用できる土地が減ってしまったり、そもそも建て替えができなかったりという理由で資産価値がほぼ間違いなく減少します。そのため物件価格が安く設定されているケースが非常に多いです。
物件価格が安くても、特別な理由がなければ家賃は相場に近い金額を設定できるため、高利回りを維持した効果的な投資ができる可能性があるでしょう。
メリット②:固定資産税が安い
物件価格が安いことにより、固定資産税の金額も安くなります。固定資産税の金額はランニングコストに大きく関わる部分のため、運用にかかる負担を大きく軽減できます。メリット①とあわせて、コスト負担が小さく実質利回りも高くなりやすいのがポイントです。
みなし道路物件や再建築不可物件に投資するデメリット
みなし道路物件や再建築不可物件に投資するデメリットは以下の2つです。
- 災害で倒壊や消失が起きた際のリスクが高すぎる
- 売却・再活用などの「出口戦略」に困る
それぞれ詳しく解説します。
デメリット①:災害で倒壊や消失が起きた際のリスクが高すぎる
みなし道路物件や再建築不可物件は、予期せぬ災害で倒壊・消失が発生してしまった場合のリスクが高すぎるので注意が必要です。建築基準法制定前に建てられていることがほとんどなので、現在の耐震基準を満たしていない可能性がある点も押さえておいてください。
みなし道路物件の場合は再建築に強制的にセットバックが必要になるため、早期に資産価値が減少してしまうリスクがあります。再建築不可物件の場合はそもそも再建築ができず、途方に暮れてしまう可能性があるでしょう。
ローンや固定資産税などの維持負担だけが残ってしまうケースも少なくありません。もしこれらの物件を購入するのであれば、リスクを考慮し一括購入するのが得策です。
デメリット②:売却・再活用などの「出口戦略」に困る
みなし道物件の場合はセットバックの影響で、新たに建てられる建物の種類が制限される場合があります。再建築不可物件の場合はリフォーム、駐車場、隣地取得による再活用などの方法がありますが、条件によってはいずれの方法も使えません。売却をしようにも買い手が見つからないケースも少なくありません。
購入を検討する段階から「どのような出口戦略を取るのか」ということをしっかりとイメージしておきましょう。具体的なイメージができない場合は、これらの物件には手を出さない方が賢明です。
まとめ
購入する物件が「みなし道路」に接している場合や、接道義務を満たさず「再建築不可」となっている場合には高いリスクがあります。高利回りとなるケースが多いですが、基本的に投資初心者は手を出さない方が無難でしょう。
もしこうした購入を検討する場合には、さまざまなリスクケースを想定したうえで、現金一括購入をするのが得策です。しっかりとリスクマネジメントをして、損をしない投資を実現しましょう。投資のリスクについてお悩みの点がある場合は、ぜひ当社に一度ご相談ください。

この記事の執筆: 及川颯
プロフィール:不動産・副業・IT・買取など、幅広いジャンルを得意とする専業Webライター。大谷翔平と同じ岩手県奥州市出身。累計900本以上の執筆実績を誇り、大手クラウドソーシングサイトでは契約金額で個人ライターTOPを記録するなど、著しい活躍を見せる大人気ライター。元IT企業の営業マンという経歴から来るユーザー目線の執筆力と、綿密なリサーチ力に定評がある。保有資格はMOS Specialist、ビジネス英語検定など。
ブログ等:はやてのブログ