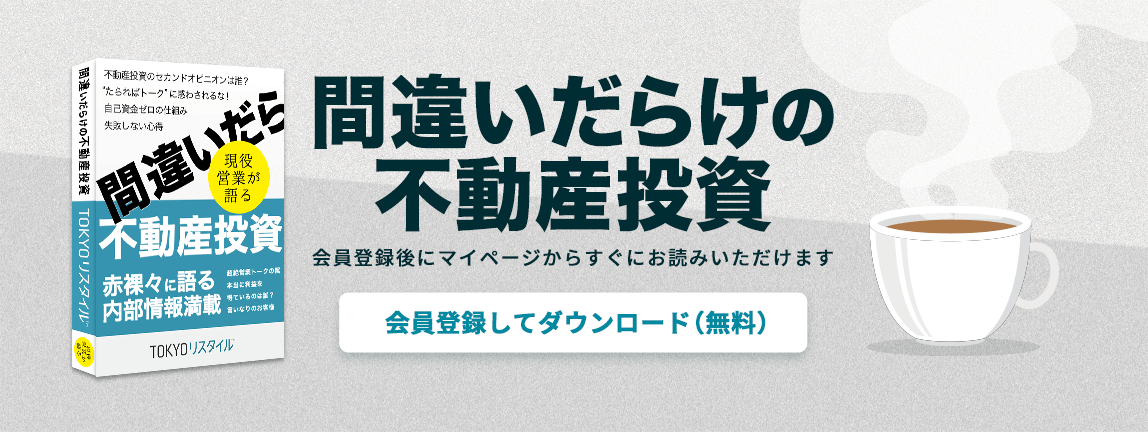タワーマンション、通称タワマンはやばい!?その光と闇を徹底解説!
- 更新:
- 2022/11/18

近年、高所得者や資産家、外国人投資家から人気を博してきたタワーマンション、通称『タワマン』。きらびやかな街にたたずむその姿が、社会での成功の証として考える人も多く、雑誌でのタワマン特集などが組まれるくらいの注目がされてきました。
一方で、タワマン人気が過熱する中、様々なデメリットや危険性が徐々に指摘され始めているのも事実です。特に、自然災害に対する脆弱性や、膨大な維持費、マンション内での格差など、看過できない問題点が出てきました。
そこで、本記事ではまず、なぜタワーマンションが人気なのか、どういった機能を有しているのかなど、光の面に焦点を当てたのち、ここ最近叫ばれているタワマンの影の部分についてもできる限り説明をしていきたいと思います。
憧れの『タワーマンション』
日本のタワーマンションの歴史は、それほど長いものでは有りません。日本初のタワーマンションは1976年に住友不動産によって建設された『与野ハウス(埼玉県与野市)』で、高さ66m、22階建て、総戸数463個の大規模な分譲マンションでした。
その後、1990年代からタワーマンション熱が過熱し始め、今では、東京都内だけでも棟数448、総戸数142,570戸という恐るべき数のタワマンが林立しています。
引用2021年1月28日時点 東京カンテイ:タワーマンションのストック数(首都圏)
その豪勢な見た目に、多くの人々がタワーマンションを「憧れの的」とし、成功の証として考える風潮が出てきました。実際、タワーマンションには多くの高所得者や資産家、芸能人が居住していると言います。
また、見た目だけでなく機能性や利便性の点でも、ホテルと同様かそれ以上のメリットがあると言われます。以下に、その具体例をいくつか並べてみたいと思います。
メリット①:眺望が抜群である
やはりタワマンのメリットとして一番に挙げられるのが、高層階から見える素晴らしい眺望だと思います。目の前に景色を遮る建物も存在しないため、展望台にいるような心地で、街の景色や海を眺められます。

引用PAKUTASO
メリット②:充実した共用施設
タワマンには、大変充実した共用施設が存在します。中にはスポーツジムやラウンジ、コンシェルジュがいるマンションなど、高級ホテルのような施設を有するタワーマンションもあるほどです。
例えば、麻布十番徒歩三分の場所に位置する『パークコート麻布十番ザタワー』は、地上36階建ての超高級タワマンとして知られていますが、数々の充実した施設が含まれています。例えば、25階に設けられたゲストルーム「タワースウィート」には東京タワーなどの夜景が見れるジャグジーがあったり、その他にも二階吹き抜けの「アクアラウンジ」や屋内庭園、フィットネスジムなどの豪華施設が目白押しです。

引用KEN RENT
メリット③:交通の便が良い
次に、タワマンのメリットとしてよく挙げられるのが、好立地にあるため交通の便がとても良いという点です。一般的に住居を決める際の大きな要素の一つとして、「駅からの距離」があります。どれだけ室内が綺麗で住みやすかったとしても、駅まで歩いて20分かかるような物件は、なかなか入居者が付きづらいというのは想像に難くないと思います。
もちろん、地方に行けば、駐車場付きの物件が安く借りられますし、職場まで車で移動するといったことも珍しく無いでしょう。しかしながら、東京都内の場合にはそもそも駐車場の金額が高く、車を所有していない世帯も多いことから、主な移動手段は電車であることがほとんどだと思います。
その場合、駅までの距離が近ければ近いほど、日々の生活の負担は減り、より快適な通勤ライフを送ることが出来るという訳です。そのようなニーズを反映する形で、タワーマンションは駅からの距離が近かったり、複数路線利用可能であったりと、交通の便が非常に良い物件が多いのが特徴です。
そのような中で、タワーマンションの中には、驚くべきことに駅直結型の物件が存在しています。雨が降っていても、一切濡れることなく電車に乗ることが出来るというのは、非常に大きなメリットではないでしょうか。
駅直結型のタワーマンションの例としては、勝どき駅にある勝どきタワービュー、白金高輪駅直結の白金タワー、豊洲駅の豊洲シエルタワー、麻布十番駅直結のアクシア麻布などが有名です。
メリット④:セキュリティが万全である
4つ目のメリットとして、セキュリティが万全であるという点は多くの方が重視しているポイントでもあると思います。
住居を決める際、特に女性の場合にはセキュリティ面を重視される方が多いのではないでしょうか。例えば、駅から家までの道が夜間でも明るいかどうか、オートロック機能はあるかどうか、コンシェルジュが24時間いるかどうか、などチェックするポイントは数多く存在します。
そのようなニーズに応えるべく、タワーマンションには非常に強固なセキュリティシステムが備わっていることが多いです。例えば、豊洲にあるシティタワーズ豊洲ザ・ツインには、共用部分に74台もの防犯カメラが設置されています。また、24時間のオンラインセキュリティシステムにより、不審人物等がいればすぐに通報されるように設計されています。
これほど多くの機能を備え、外観も豪華なタワーマンションですから、庶民のあこがれの的である、という気持ちも良く分かります。一方で、ここ数年、タワーマンションの問題点や危険性が声高に叫ばれるようになってきました。
タワマンの闇について
2019年10月12日、タワマンを巡る大きな悲劇が起きてしまいました。それは、日本中を脅かした「台風19号」の東京上陸によってもたらされたのです。
その舞台は、川崎市の武蔵小杉。住みたい街ランキング2019でも関東9位にランクインするなど、近年注目を集める武蔵小杉は、都心部へのアクセスも非常によく、大変な人気を博していました。ところが、先の台風被害によって、武蔵小杉の街は停電や冠水、汚泥にもがき苦しむこととなってしまったのです。
これによって、タワーマンションも停電が発生し、エレベーターも完全に停止してしまいました。マンションの最上階に住む住人は、50階近くの階段を、わざわざ上り下りしなくてはいけない事態にまで発展してしまいました。
また、地下の配電盤が水害によって壊れた影響により、マンション内のトイレが使えなくなったというのも有名な話です。上の階で無理にトイレを流そうとすると、下層階のトイレから汚水が噴き出してしまうというのですから悲惨です。
今回の武蔵小杉の件を皮切りに、「タワーマンションはやばいのではないか」と不満の声や後悔の声が聞かれるようになりました。そこで、特に問題視されているタワマンのデメリットを、以下で説明していきたいと思います。
デメリット①:大規模修繕に莫大な費用が掛かる
タワーマンションの歴史は、建物全体の歴史と比するとかなり短い、ということは冒頭でお伝えをしました。このことはそのまま、「ノウハウが無く、どうなるか分からない」という問題に繋がってしまいます。この問題が特に顕著なのが、タワマンの維持管理面でしょう。
通常マンションというのは、15年〜20年に一度大規模修繕工事を行います。その際のコストはどれだけ安く見積もっても数千万円にのぼると言われており、その費用は基本的に住民から徴収する修繕積立金によって充当されます。
タワマンではない、一般的な高さのマンションでさえこれほどのコストがかかるのですから、通常の足場が使えないタワーマンションの場合、この費用はさらに大きくかさんでしまいます。今後大規模修繕を行うとなった際に、それまでの修繕積立金だけでは足りないとなった場合、どうなってしまうのでしょうか。
タワーマンションの修繕工事は日本国内でもあまり実績が無く、予想が立てにくいと言われています。ですから、今後10年〜20年後のタワマンの資産価値がどうなっているかというのは、今の時点では判断が難しいと言わざるを得ない状況なのです。
デメリット②:不要な設備と膨大な管理費
冒頭でも述べたように、タワーマンションの中には豪華な共用施設が数多く存在します。外見的には、いつでもジムに行けたり、ラウンジがあったりと憧れの対象に見えますが、その裏には闇があることも事実です。それは、「膨大な管理費用」を支払う必要がある点にあります。例えば、あなたがタワーマンションの住人だったとして、そのジムを一切利用しなかったとします。それにも関わらず、そのジムの維持費として毎月毎月一定の金額が徴収されるとしたら、どのように感じるでしょうか。
おそらく、「なんで自分が、ジムを利用する人の分までお金を払わなくてはいけないのか」と考えることでしょう。実際、タワーマンションの住人の中には、無駄に豪勢な共用施設の存在に疑問を呈したり、支払いに不満を感じている人も多いと言います。これが、マンション内の人間関係にまで大きく影響を与える可能性もあることから、気を付けるべき点であると言えるでしょう。
デメリット③:マンション内格差
タワーマンションに特有の問題、それが「マンション内格差」です。同じマンションでも、低層階と高層階とで、時に数千万円もの価格差がある部屋も存在しており、生活水準も大きく異なります。
それが、「高い階層ほど偉い」「低層階であることに引け目を感じる」といったブラックな考えを引き起こしているというのです。
「そんなこと本当にあるのか」という疑問をお持ちの方もいらっしゃると思います。ただ、残念ながらこれは実際に起きている問題なのです。
例えば、同じタワマン内であっても、人々の生活レベルや資産背景は大きく異なっています。ある若夫婦は、憧れのタワマンに住むために、夫婦二人の共同で、与信枠いっぱいまでローンを組んでタワマンの一室を購入しました。そういった人々は、毎月の給与所得から高額なローンの支払いを行い、上手くやりくりしながら生活を維持しています。
その一方で、節税目的や投資目的でタワマンを買う資産家も存在します。特にタワマンを爆買いする外国人投資家は一時社会問題ともなりましたが、彼らは現金で一括で購入をしているのです。
「融資枠いっぱいまで借入をして購入した世帯」と「節税目的で現金購入した世帯」とでは、その生活水準に大きな差があることがお分かりいただけるかと思います。このような差が、普段の生活における劣等感やストレスとなることは、想像に難くないかと思います。
デメリット④:エレベーターの待ち時間が長い
4つ目のデメリットとして、タワーマンションにおけるエレベーターの待ち時間が非常に長いことが挙げられます。確かに、これは指摘されてみれば至極当然のように思われますが、実際に住んでみないと実感できないため、「住んでみて初めて知った」という購入者の方も多いようです。
このエレベーター問題は、一日の中でも特に朝の時間帯に頻繁に起こるということが様々なブログやSNS等で報告されています。朝の忙しい通勤時間にエレベーターで何分も待たされてしまうような事態が起これば、住民が不満に思うのは当然かもしれません。
デメリット⑤:ベランダで洗濯物が干せない
このデメリットは、特に家事をメインで行っている主婦層には大きな問題となります。タワーマンションというのは、高層階になるほど風当たりが強くなるため、ベランダで洗濯物を干すことを禁止されている事が多いです。
その場合、浴室乾燥機を使用することになる訳ですが、そもそも浴室乾燥機は洗濯物を干すスペースが狭かったり、生乾きになってしまったりと様々な問題点があり、「自宅に浴室乾燥機があるが、ほとんど使っていない」という方も多いかと思います。特にお子さんが複数いらっしゃる家庭だと、洗濯物の数も多くなるので、浴室乾燥機だけではどうしても足りなくなるケースが多々あるでしょう。このように、洗濯物を干すスペースの確保というのは、盲点となりがちながらも、タワーマンションで暮らすにあたっては大きな問題点となっているのです。
デメリット⑥:宅配物の受け取りやゴミ出しが不便
タワーマンションの特に高層階においては、宅配物の受け取りやゴミ出しに大きな負担がかかってしまうというデメリットも存在しています。例えば、セキュリティが非常に強固で、3重にも4重にもオートロックがかかっているような物件もある訳ですが、宅配物を部屋で受け取るためには、配達員がオートロックのインターホンを押すたびに通す必要があり、荷物を受け取るだけでも一苦労といった話もあります。
またゴミ出しに関しても、一部の高級タワーマンションにおいては各階にゴミ置き場が設置されているという便利な物件もあるものの、ほとんどが1階部分のみに位置しており、ゴミ出しのたびに長い時間エレベーターを待つ必要があります。このように、物件の入口から部屋までの距離が遠いというタワーマンションの特性が、マイナスな面で目立ってしまっているのが、この宅配便やゴミ出しの問題点なのです。
デメリット⑦:外に出るのが億劫になってしまう
タワーマンションの高層階に住むと、移動が面倒くさくなってしまい、必要な時以外外出の意欲も機会も極端に減退してしまう、という問題点が度々報告されています。特に、出勤する必要のない専業主婦の場合、朝から晩まで高層階に閉じこもり、買い物もネットで行うなど、自宅で完全に孤立してしまう方が多くいるようです。
一般的な戸建や低層マンションであれば、気軽に近くのスーパーや公園に出かけることも出来ますが、エレベーターで何分も待たされ、さらに何重にもオートロックを解除しなければならないという面倒臭さが、外出自体を億劫にしてしまい、精神的にも身体的にも不健康な状態になってしまう恐れもあります。
「夢のタワーマンションに住んだものの、妻が閉じこもり気味になってしまい、結局一軒家に引っ越すことにした」というケースは、想像以上に多く存在しているようです。
まとめ
ここまで、タワマンの光と影の両面について焦点を当てて解説してきました。世の中で言われている「成功者の証」であるというタワマンにも、実は数々の問題点があることがお分かりいただけたかと思います。
もちろん、決して「タワマンの全てが悪い」ということをお伝えしたいわけではなく、あくまで現実的にどのような問題に面しているのか、という事実を知っていただくために、本記事の執筆を行いました。
不動産というのは一生に一度の高価な買い物です。理想や、夢というのももちろん大事ではありますが、一方でしっかりと現実を見据えて、冷静に意思決定をできるよう心がけましょう。
また、弊社には、第三者的の中立な視点からアドバイスをすることができるコンサルタントがいます。何かお困りのことや不明な点が有りましたら、是非ご一報いただけますと幸いです。