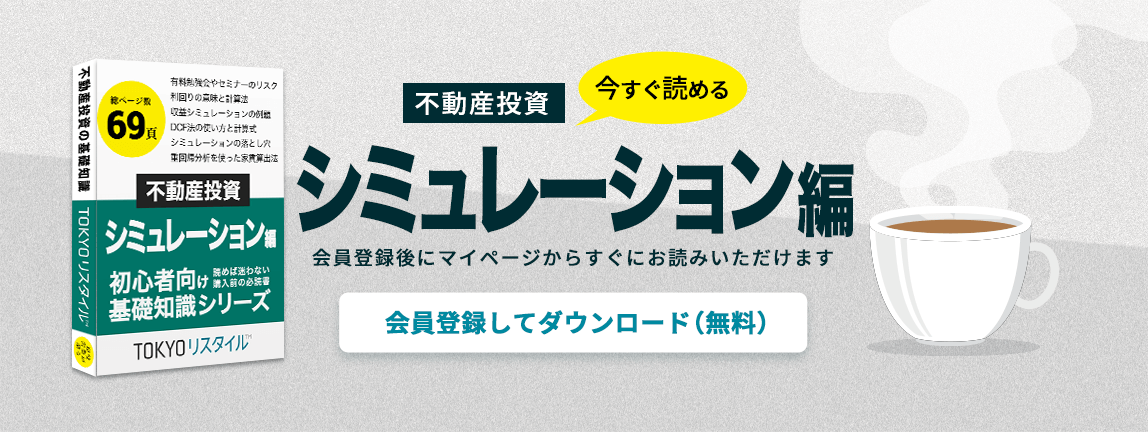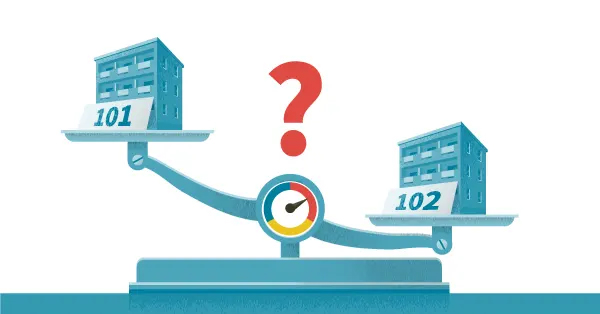不動産投資ではCCRが重要!メリットや注意点、併用したい指標まで完全解説!
- 更新:
- 2024/01/16
本記事は動画コンテンツでご視聴いただけます。
不動産投資で使われる「CCR(自己資金配当率)」とは、「投資効率」にフォーカスした指標です。他の投資では用いられない用語であることから、聞き慣れない方がほとんどではないでしょうか。
不動産投資にはCCRをはじめ多数の指標があります。その指標の多さから、どの指標を参考に物件を選べばよいか分からない方も多くいらっしゃいます。
本記事では、不動産投資ならではの指標「CCR」の意味や計算方法、活用のメリットなどを解説します。CCRと関連する指標である、LTVやROI、IRRについても解説。不動産投資のCCRとは何か、他の指標との違いを知りたい方は最後までご一読ください。
- CCR(自己資金配当率)とは
- CCRが不動産投資独自の指標である理由
- CCR(自己資金配当率)を活用する3つのメリット
- CCRを活用する注意点
- CCR(自己資金配当率)と併用したい指標~LTV・ROI・IRR
- まとめ
CCR(自己資金配当率)とは
CCR(自己資金配当率)とは「Cash on Cash Return」の略で、物件購入時に支払った自己資金(自己資本)に対する年間キャッシュフローの割合を指します。
キャッシュフローとは、家賃収入から物件の運営費・税金・融資返済額を引いた金額。つまり、キャッシュフローとは「手元に入ってくるお金」です。空室や家賃の滞納が発生した場合は、本来の家賃収入から空室や滞納分を差し引いて算出します。
CCRは、効率がいい投資や投資した自己資本の回収予測にも役立つ数値です。CCRが高いほど「少ない自己資本で大きな利益を得ている」、つまり投資効率がよいことを示しています。
CCRの計算方法
CCRの計算方法は以下になります。
- 年間のキャッシュフロー ÷ 物件購入に用いた自己資本 × 100
例えば年間のキャッシュフローが200万円、物件購入に用いた自己資本が800万円だった場合、CCRは「200万 ÷ 800万 × 100 = 25%」となります。
CCRの特徴
CCRの特徴は大きく2点。金融機関の借入金を計算に使わないことと、投資した自己資本を回収するまでの期間を算出できることです。
借入金を含めた計算は後述の「ROI」という指標に用います。CCRはあくまで「自己資本の運用効率」を示す指標。そのため、金融機関からの借入金を計算に使いません。CCRを算出する際は、自己資本と年間のキャッシュフローのみを使います。
なお、借入金を含めた割合を算出する指標は「ROI」です。「ROI」については、後ほど詳しく解説します。
CCRは「投資した自己資本を回収するまでの期間」を算出できることも大きな特徴です。自己資本を回収するまでの期間を算出する式は「100 ÷ CCR」となります。先ほどのCCRが25%の例では「100 ÷ 25 = 4」。つまり、自己資本を回収できるまでに4年かかることが分かります。
CCRが不動産投資独自の指標である理由
CCRは不動産投資独自の指標で、不動産投資以外では使われません。その理由は、不動産投資の性質にあります。
不動産投資は、金融機関からの融資 =「他人資本」を用いることで少ない自己資本で利益を得る投資方法です。他人資本を活用し、かつ中長期目線で投資計画を立てて運用するのが不動産投資と他の投資で異なる部分となります。
従って、自己資本とキャッシュフローの割合を算出するCCRは、少ない自己資本でどれだけ効率よく利益が出せているかを計る、不動産投資独自の指標となります。
CCR(自己資金配当率)を活用する3つのメリット
では、不動産投資においてCCRを活用するメリットを見ていきましょう。本記事で紹介するメリットは、次の3つです。
- レバレッジ効果がわかる
- 追加物件の購入計画を立てやすい
- 表面利回りよりも現実的な収支を算出できる
「効率よく他人資本を用いることで投資金額を早めに回収すること」が不動産投資のひとつの成功戦略と考えると、メリットが理解しやすくなります。
メリット①:レバレッジ効果がわかる
CCRが高い、すなわち「少ない自己資本で大きな利益を得ている」という状態を指すため、効率のよい投資につながります。
他人資本を用いて利益を得ることを、投資では「レバレッジ」と呼びます。レバレッジとは「てこ」のこと。他人資本を用いて少ない自己資本で利益を得ることを「レバレッジを効かせる」と言います。「レバレッジ効果こそが不動産投資の魅力である」といっても過言ではありません。
CCRを求めることで、レバレッジ効果も算出できます。2つの物件を比較しながら、CCRを用いたレバレッジ効果の算出方法を見ていきましょう。
価格2千万円の物件Aを、全額自己資本で購入したとします。全額自己資本なので、借入金額は0円です。物件Aで得られるキャッシュフローは、年間200万円。この場合、物件AのCCRは、「200万 ÷ 2,000万 × 100 = 10%」となります。自己資本の回収までに必要な期間は「100 ÷ CCR」で算出するので、「100 ÷ 10 = 10年」です。
では、価格4千万円の物件Bを、自己資本1千万円、借入金額3千万円で購入したケースを見てみましょう。物件Bの年間キャッシュフローは400万円です。物件BのCCRは「400万 ÷ 1,000万 × 100 = 40%」となり、自己資本の回収までは「100 ÷ 40 = 2.5年」となります。
各物件の想定される実質利回りを「キャッシュフロー ÷ 購入価格 × 100」として計算すると、両方とも10%です。しかし、自己資本の回収年数では4倍もの差が出ました。
| 物件A | 物件B | |
|---|---|---|
| 購入価格 | 2,000万円 | 4,000万円 |
| 自己資本 | 2,000万円 | 1,000万円 |
| 借入金額 | 0万円 | 3,000万円 |
| 年間キャッシュフロー | 200万円 | 400万円 |
| 想定される実質利回り | 10% | 10% |
| CCR(自己資金配当率) | 10% | 40% |
| 自己資本回収までの年数 | 10年 | 2.5年 |
自己資本の回収年数に差が生じた原因は、借入金という他人資本を活用して不動産投資をおこなったことです。このように、レバレッジ効果が可視化できる点がCCRを活用するメリットとなります。
メリット②:追加物件の購入計画を立てやすい
自己資本の回収期間がわかることで追加物件の購入計画を立てやすくなることも、CCRを活用するメリットです。
不動産投資のコツは「いかに自己資本を早く回収するか」。自己資本をなるべく早く回収し、手元の資金を増やしながら運用実績を作り2件目以降の物件を購入し、さらに利益を上げていくことが重要になります。
先ほど例に挙げた物件Aの場合、すべて自己資本で物件を購入しました。CCRを算出した結果、自己資本の回収までは10年必要です。一方、物件Bの場合は自己資本回収までの期間は2.5年。物件AとBでは、2件目を購入するまでの期間にも7.5年の差が生じることがわかります。
このように、CCRにより自己資本回収までの期間がわかり、追加物件を購入する場合に中長期の計画が立てやすいこともCCRを活用するメリットといえます。
メリット③:表面利回りよりも現実的な収支を算出できる
CCRを活用すると、表面利回りよりも現実的な収支を算出できます。投資用の不動産で公示されている運用利回りは、基本的には表面利回りです。表面利回りとは、年間の家賃収入を物件の購入価格で割って計算される指標。物件の費用対効果を簡易的に知るために役立ちます。簡易的に知る指標なので、不動産投資にかかる諸費用だけでなく、空室リスクや家賃滞納の損失額が考慮されていません。
CCRの算出に使うキャッシュフローは、家賃収入から物件の運営費・税金・融資返済額といった諸費用、空室や家賃滞納時の損失額を引いた額となります。表面利回りと異なり諸経費や損失額を指標に組み込むCCRは、より現実的な収支を算出することができる点もメリットです。
利回りについては、こちらの記事も合わせてお読みください。
参考【2023年最新版】不動産投資の利回りとは?注意したい物件や利回りUP方法まで完全解説!
CCRを活用する注意点
CCRは、自己資本の回収効率を示す指標として効果的です。しかし、CCRを活用する場合、いくつかの注意点があります。
ここからは、CCRを活用する際の注意点を3つ紹介します。
注意点①:フルローンの場合CCRを算出できない
CCRは、自己資本ゼロのいわゆる「フルローン」の場合は算出できません。
例えば2千万円の物件を借入金額2千万円、すなわちフルローンで購入した場合、自己資本はゼロとなります。CCRの計算式に当てはめると年間のキャッシュフローをゼロで割ることになり、結果CCRが無限になるため算出できません。
CCRは自己資本に対するキャッシュフローの割合を表す指標です。そのため、自己資本を用いないフルローンの場合は指標として活用できないことを押さえておきましょう。
注意点②:CCRはあくまで「予測」であることを念頭に置く
CCRで算出できるのは「投資した自己資本に対してどれだけ収益を上げられるか」という「予測」である点にも注意が必要です。
年間のキャッシュフローは、物件が破損、故障して修繕費が発生したりや管理費用が変動したりして、年ごとに増減する可能性があります。つまり、CCRで使うキャッシュフローはあくまで目安であり予測です。CCRの数値どおりに収益が上がり、自己資本が回収できるわけではないことを念頭に置いて活用しましょう。
注意点③:金利リスクが生じる可能性がある
CCRが高いことにより、金利リスクが生じる可能性もあります。金利リスクとは、金利の変動によって収支が大きく変わること。CCRが高い投資は他人資本の割合が多いため、借入利率の変動がローン返済額の増減につながります。借入利率が上昇すると利息が増え、ローン返済額も増加。結果、キャッシュフローに大きな影響を与えてしまいます。
以上のことから、CCRの高さのみを追求して収支計画を立てることはおすすめできません。不動産投資をする際は、CCRだけでなく複数の指標を併用することが大切です。どの指標を使うべきか、次の章で解説します。
CCR(自己資金配当率)と併用したい指標~LTV・ROI・IRR
CCR(自己資金配当率)と併用したい指標として、次の3つを解説します。
- LTV(融資比率)
- ROI(投資利益率)
- IRR(内部収益率)
指標①:LTV(融資比率)
LTV(融資比率)とは「Loan To Value」の略で、不動産の購入価格に対する借入金額の割合を指します。LTVの計算式は以下のとおり。
- LTV = 借入金額 ÷ 物件購入価格 × 100
CCRを高く運用することを考えると、他人資本の活用によるレバレッジを高くする = LTVを高くする投資計画に偏りがちです。しかし、先ほど解説したように借入金額の多さは金利リスクにつながります。
LTVは、リスクやリターンを踏まえて自己資本と他人資本の割合を定める際に用いる指標です。借入金額が多いと、LTVも高くなります。一般的に、LTVは80%以下(自己資本の割合が20%以上)とすることが理想です。
ROI(投資利益率)
ROI(投資利益率)とは「Return On Investment」の略で、不動産の購入総額に対する年間キャッシュフローの割合を指します。ROIの計算式は以下のとおり。
- ROI = 年間キャッシュフロー ÷(物件購入価格 + 諸費用)× 100
ROIとCCRの違い
ROIとCCRの違いは、他人資本(借入金額)を考慮して利益率を求めているかどうかです。
ROIは自己資本だけでなく他人資本(借入金額)を含めて利益率を計算しています。CCRは自己資本のみでの計算です。レバレッジを効かせるために自己資本をなるべく少なくし、CCRの高さのみを追求すると他人資本が増え金利リスクが発生します。「CCR25%以上、ROI5%以上」など自分なりの基準を設けることで、自己資本と他人資本のバランスを考え安定した投資計画を立てられるでしょう。
IRR(内部収益率)
不動産投資においては、IRR(内部収益率)も役立ちます。IRRは「Internal Rate of Return」の略で、物件の売却までを考えて収益を計算する指標です。投資に用いた金額の現在価値と、投資によって得られる収益の現在価値の総和を等しくするために用いる割引率となります。IRRが高く数年後にも高額での売却が見込める物件は、CCRが低くても検討の余地があります。
IRRについては、以下の記事をご覧ください。
参考IRR(内部収益率)とは!?その全貌やNPVとの違いまで徹底解説! | 不動産投資の基礎知識
まとめ
不動産投資においては、CCR(自己資金配当率)や各種指標を活用して投資計画を立てることが必須です。しかし、どの指標をどこまで重視するかといった投資計画はケースバイケースとなるため、記事で個別の事例を挙げるのは困難です。CCRについても、基準となるパーセンテージはなく、個々の状況により最適な割合が変わります。
「自分の場合、どれくらいのCCRがいいのか」「CCRとLTVやROI、IRRをどのように関連付けるといいのかわからない」。そんなときは一度当社へご相談ください。当社では、無料相談を随時開催中です。CCRの割合、他指標との関連、どのように投資計画を立てればいいのかなど、不動産コンサルタントが豊富な経験に即した中立の目線でアドバイスします。もちろん、個別の状況に即した投資計画の提案も可能です。どんなことでもお気軽にご相談ください。

この記事の執筆: 堀乃けいか
プロフィール:法律・ビジネスジャンルを得意とする元教員ライター。現役作家noteの構成・原案の担当や、長野県木曽おんたけ観光局認定「#キソリポーター」として現地の魅力を発信するなど、その活躍は多岐に亘る。大学および大学院で法律や経営学を専攻した経験(経済学部経営法学科出身)から、根拠に基づいた正確性の高いライティングと、ユーザーのニーズに的確に応えるきめ細やかさを強みとしている。保有資格は日商簿記検定2級、日商ワープロ検定(日本語文書処理技能検定)1級、FP2級など。
ブログ等:堀乃けいか