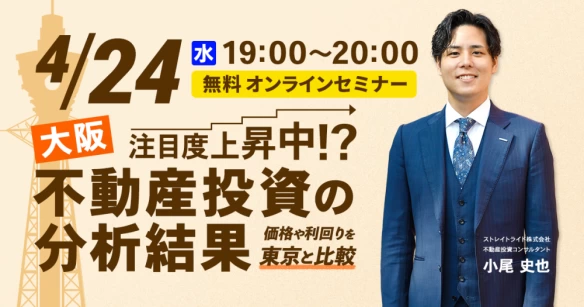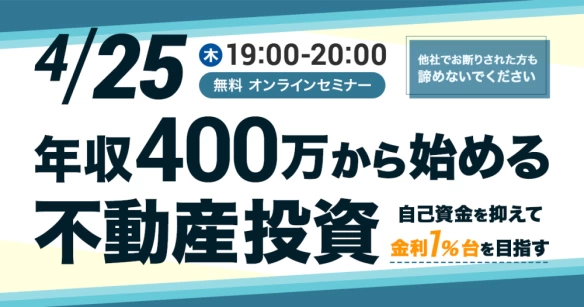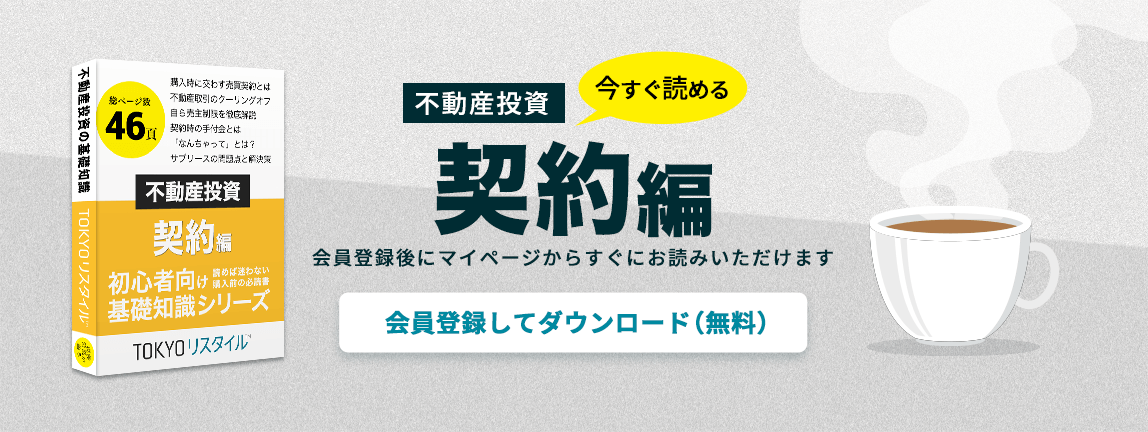【2023年】登記簿謄本と登記事項証明書の違いを徹底解説
- 更新:
- 2022/12/26

不動産売買において登記簿謄本は必要不可欠な情報が記載されているため、必ず取得する必要があります。現代では「登記事項証明書」と呼ばれることも多く、少しわかりづらい(または手続きが難しそう)というイメージを持っている方も多いかも知れません。
そういったイメージから登記簿謄本の取得は、専門家へ依頼するしかないと思っている方も多いかもしれませんが、登記事項証明書の取得は、実は難しくありません。自宅からオンラインで取得することもできます。今回は、登記簿謄本とはなにかという基本の解説から取得方法までを詳しく解説していきます。不動産売買で登記簿謄本が必要な方はぜひ参考にしてみてください。
登記簿謄本と登記事項証明書は同一のもの
「登記簿謄本」とは、法務局が保管している個々の不動産記録である登記簿のうち、特定の物件につい記載されたものです。不動産記録とは、
- 不動産の所在地
- 所有者
- 担保の有無
等、不動産物件における詳細な情報となります。物件毎にこれらの情報がまとめられており、「登記簿謄本」とは紙媒体で記載されいる登記簿のことを指します。
実は「登記簿謄本」とは古い呼称で、現在では「登記事項証明書」というのが正式名称です。
以前は紙媒体で登記情報が管理されており「登記簿謄本」と呼ばれていたのですが、現在ではデータ化が進んだことで登記情報がコンピューター管理となりました。そこから発行した証明書を「登記事項証明書」と呼ぶことになったのです。
しかしながら、これまで長く呼ばれていた名残から一般的に「登記簿謄本」と呼ばれる場面が多く発生しているのが今の状況です。そのため「登記簿謄本」と言われているにも関わらず、それが指しているものが実は「登記事項証明書」であることがありますので注意が必要です。大前提として「登記簿謄本」と「登記事項証明書」は同じものであるということを覚えておきましょう。
登記簿謄本(登記事項証明書)は役割毎に4種類存在する
先述した通り「登記簿謄本」と「登記事項証明書」は同じものですが、その中にもさらに細かく4種類の証明書があることを覚えておきましょう。
- 全部事項証明書
- 現在事項証明書
- 閉鎖事項証明書
- 一部事項証明書
以上の4種類です。
登記簿謄本の取得の際には、目的に応じて適切なものを選択しましょう。それぞれについて解説します。
登記事項証明書
「全部事項証明書」とは、特定の不動産についての全ての登記情報が記載された証明書です。過去から現在までの期間記録され所有権の移転履歴や抵当権の設定・抹消、そして差し押さえに至るまで物件の詳細が記載されています。
そのため、「登記事項証明書が必要」となった場合は特別な理由を除き、この「全部事項証明書」を取得しておけば問題ありません。
現在事項証明書
次に「現在事項証明書」について解説します。現在事項証明書は現在の権利関係の項目のみに絞って記載のあるシンプルな証明書です。過去の情報は記載されないため、例えば不動産を担保に借金した事例があっても、その情報は記載されません。
物件が自分の所有物であることを証明するだけであればで「現在事項証明書」で十分ですが、金融機関などからの融資を受ける際は「全部事項証明書」が必要なこともあるため注意が必要です。
取得には取得手数料がかかるのですが「全部事項証明書」も「現在事項証明書」も、どちらも1通50枚までは同一金額で取得できます。再発行になってしまうと、二重で手数量を払うことになってしまうので、そう言ったリスクを回避する意味でも「全部事項証明書」の取得をオススメします。
閉鎖事項証明書
3つ目に「閉鎖事項証明書」について解説します。閉鎖事項証明書に記載されている情報は、「全部事項証明書」にも記載されていない内容です。その情報とは、これまでに閉鎖された不動産の情報です。土地の合筆や建物の取り壊しなどによって不動産が消滅すると、登記記録が閉鎖されるため、こうした登記情報を証明するために必要になります。
注意が必要なのは、登記情報の保存期間は土地と建物によって違うことです。閉鎖してから
- 土地なら50年
- 建物なら30年
と決まっており、それ以上古い情報となると取得が難しくなる可能性があります。
一部事項証明書
最後に「一部事項証明書」について解説します。
これは、登記情報に記載された内容の中から一部を切り出した登記事項証明書です。
証明書を発行したい不動産によっては、全部事項証明書を発行するとその記載内容が膨大になる可能性もあります。
登記情報は不必要な部分も多く含まれるため、必要な部分だけ欲しい場合などには一部事項証明書の取得の方が便利です。
例えば、分譲マンションで自分の保有分を証明したい場合など、一部事項証明書で十分といえるでしょう。全部事項証明書を取得した場合は、全室の所有者や担保権などが全て記載されると1通で100ページを超えてしまう場合があります。こうなると確認だけで相当な時間がかかってしまうので、適宜選択して取得するようにしましょう。
ここで一点注意しないといけないのは、現在「一部事項証明書」はオンライン取得に対応していないという点です。そのため法務局の窓口に出向く必要があります。これは注意しましょう。
参考心強い武器になる?「買付証明書」について分かりやすく解説!
登記簿謄本(登記事項証明書)の3つの取得方法
登記簿謄本の取得に関して解説します。登記簿謄本は、不動産所有者だけではなく手数料を支払うことで誰でも取得することが可能です。取得方法は「法務局窓口」「郵送」「オンライン」の3つがあります。取得せずに閲覧だけであれば、オンラインでも可能です。
では3つの取得方法について解説して行きましょう。
窓口での交付請求
まず法務局窓口での交付請求について解説します。
全国各地にある法務局や出張所、支局などの窓口へ出向き、希望する不動産の登記簿謄本の交付請求をすることで誰でも取得可能です。(開庁時間には注意しましょう)
現代はデータ化が進んでおり、全国どの法務局からでも登記簿謄本の取得が可能です。以前は紙媒体の管理が基本だったため、管轄する地域の登記簿しか保管していませんでした。そのため、不動産を管轄する法務局まで出向いて取得しないといけなかったのです。
交付請求には、窓口にある「登記事項証明書交付申請書」に必要事項を記入して提出しましょう。その際に手数料が掛かります。手数料は登記簿謄本1通に対して600円です。申請書に600円分の収入印紙を貼り、窓口に提出すれば完了です。本人確認は不要となり、収入印紙も法務局内で販売しているため、事前準備は特に必要ありません。
郵送での交付請求
次に郵送で交付請求する方法について解説します。基本的に交付請求方法は法務局の窓口と同じです。申請書を提出し、法務局に郵送すれば問題ありません。
申請書は法務局のホームページからダウンロードしましょう。
参考ダウンロード先:登記事項証明書等の交付請求書の様式(請求書様式1)
この申請書に必要事項を記入し、登記簿謄本1通に対して600円の収入印紙を貼って返信用封筒を同封し郵送します。郵送先は最寄りの法務局や地方法務局です。
返信用封筒に貼る切手の金額は注意しましょう。
登記簿謄本1通なら84円、2通なら94円で問題ありませんが、登記内容によっては登記簿謄本が分厚くなる可能性があります。そうなると送料が上がる可能性もあるため、事前に法務局で確認してください。
返送期間に関しては1週間以内程度が目安となります。あまりにも返送が遅い場合は問い合わせた方が良いかもしれません。
オンラインで交付請求
最後にオンラインで交付請求する方法について解説します。オンラインの交付請求は、特別なアプリケーションのダウンロードといった難しい作業は一切不要です。Internet Explorerなどの一般的なWebブラウザで「登記・供託オンラインシステム」にアクセスして必要事項を入力するだけで、登記簿謄本が取得できます。
法務局関連の窓口は通常午前8時30分から午後5時15分となりますが、オンラインは夜9時まで交付請求可能です。午後9時までの交付請求により、翌日には郵送されることがあります。遠方の場合は、翌々日の可能性もあります。
受取り先は、自宅、勤務先会社、もしくは最寄りの法務局や市役所庁舎内などに設置された法務局証明サービスセンター窓口から選択できます。
オンライン登記事項証明書請求の手数料はインターネットバンキングかPay-easy(ペイジー)のいずれかで支払うことになります。Pay-easy(ペイジー)は、収納機関番号や納付番号などの必要事項をメモしてATMで支払う流れとなるので、これは覚えておきましょう。
参考知ってためになる不動産用語 - 不動産投資家への第一歩 -
登記簿謄本の基本的な読み方
登記簿謄本の内容について解説します。登記簿謄本は主に、以下の4項目が記載されています。
- 表題部
- 権利部(甲区)
- 権利部(乙区)
- 共同担保目録
それぞれについて解説していきます。
表題部
まずは表題部について解説します。
表題部とは、物件の所在地や広さ、現在の所有者などが記載される部分です。対象となる不動産が土地か建物で構成が異なるため、注意が必要です。
土地の場合
土地に関する表題部には以下が記載されています。
- 所在
- 地番
- 地目
- 地積
- 原因
- 所有者
建物の場合
建物に関する表題部には以下が記載されています。
- 所在
- 家屋番号
- 種類
- 構造
- 床面積
- 原因
- 所有者
さらに付属建物に関しても同じような内容が記載されることになります。では、少しわかりにくい専門用語について見ていきましょう。まずは土地に関してです。
所在と家屋番号
「所在」には番地までが記載され、敷地の特定が可能になります。そして、番地とは別の項目である「家屋番号」によって建物の特定が可能です。
地目
宅地や田・畑、山林や公衆用道路、雑種地などの土地用途のことです。しかし記載されていますが、現状況とは異なっている可能性もあるため注意が必要です。
地積
その土地の面積です。この数字も必ず正しいとは限らないため、売買などの取引をする際には正確な数字を把握することが重要です。
原因及びその日付(登記の日付)
その土地が登記された原因と日付です。
所有者
その土地が登記された時点での所有者の情報が記されています。住所や氏名が記載されていますが、この部分の目的は「不動産の特定」であるため、ここに名前があるからといって第三者に対して対抗力は皆無です。
次に建物の場合について解説します。土地と同じ項目は、基本的に同じ意味と考えてください。
種類
居宅や店舗、共同住宅、事務所や倉庫・車庫など、その建物の用途が記されています。
構造
その建物の建築材料と屋根の種類、何階建てかという3点が記載されています。
床面積
各階ごとの面積です。原則として1つの建物に対して1つの登記簿が作られますが、物置や車庫といった「主である建物」とともに使用する建造物は「附属建物」として記載します。なお、これも土地と同様に記載されている種類や構造、床面積などは、現状と異なっている場合もあるため、取り引きの際は注意しましょう。
権利部(甲区)
次に、権利部(甲区)についてです。ここは所有権に関する記載がされています。最初に登記した所有者から現在の所有者に至るまで、いつどのようにして所有権が移転していったのかが詳しく記されている部分です。
売買だけでなく相続や贈与、競売、差押え、仮登記、買戻特約といった内容も権利部(甲区)に記載されるため、そうした内容が記載されている場合は、次に解説する権利部(乙区)の内容をしっかり確認するようにしましょう。
権利部(乙区)
権利部(乙区)は、所有権以外の権利に関する記載がされています。この項目で注意しなければいけないのは、抵当権や根抵当権といった担保権に関わる記載がある場合です。この場合、いくらのお金を借りてこの不動産が担保として抵当に入ったかまでは分かりますが、負債が住宅ローンなのか、その他の理由なのか、そして負債が現在いくら残っているのかといったところまでは判断できません。
不動産を購入しようとしている場合は、記載されている負債状況に関しては、しっかりと調査して確認した方がいいでしょう。
まとめ
登記簿謄本に関して解説してきました。登記簿謄本と登記事項証明書は同じものであり、その取得は容易であることが理解出来たと思います。また記載内容に関しても詳細にお伝えしてきましたが、これらは不動産投資をする上で覚えておいた方が良い情報です。特に売買に関わることでもあるため、しっかりと理解しておきましょう。記載されている内容については現状と異なっている場合や負債についての現状把握が出来ない、など確認が必要な部分もあるため、売買の際はしっかりと注意するようにしましょう。
少しでもご不明な点がございましたら、お気軽に弊社コンサルタントまでご連絡いただけますと幸いです。