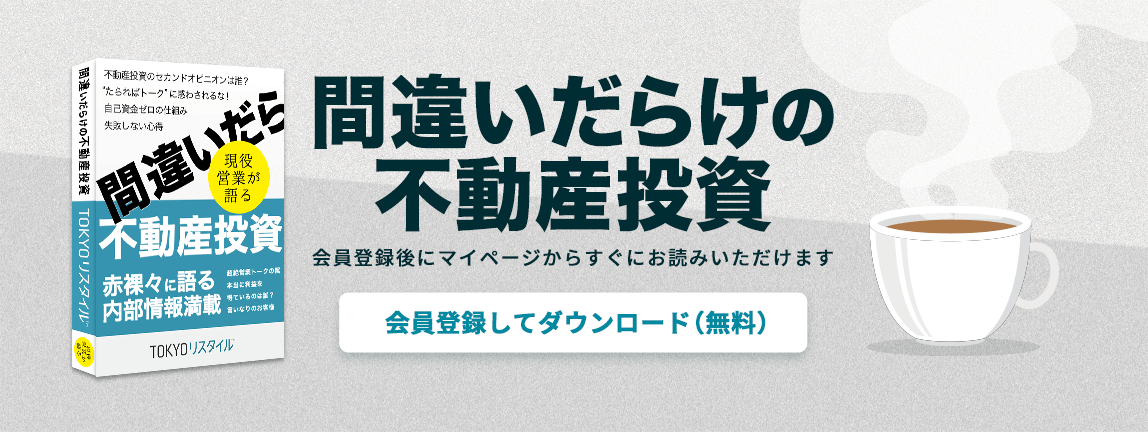これだけはおさえたい!絶対に知っておきたい不動産用語まとめ
- 更新:
- 2023/06/06

近年、年金問題をはじめとした先行きの不安から、資産運用のひとつとして不動産投資への注目度は高まっています。
しかし、いざセミナーに参加したり専門業者に相談しても、投資のメリットばかりに気をとられて不動産独自のよくわからない用語を受け流したまま勢いで契約した結果、大きな負債を抱えてしまうのではないか、という失敗への不安で二の足を踏んでしまっている人も多いのではないでしょうか。
そこでここでは不動産投資初心者の方に、事前に知っておくと便利な不動産投資の専門用語を3項目に分けてご紹介していきます。
- 基本的な専門用語
- 業者や営業マンがよく使う業界用語(隠語)
- 契約の前に知っておきたい用語
- 物件を所有してからかかる費用
ネットで拾える基礎的な知識から一歩進んだ内容です。
物件を検討する時、ここでご紹介する用語と知識は良い物件を選び取る一助になります。業者で通用する隠語もあるので、あらかじめ知っておくと「この人は不動産投資のことを調べてきているな」と営業マンに投資への意気込みをアピールできます。
基本的な専門用語
不動産に関わると耳にするようになる用語。投資のための大事な情報でもあります。
坪単(つぼたん)
坪単価の略。家を建てる時の1坪当たりの建築費のこと。建物の本体価格をのべ床面積(坪)で割った数字で、1坪 = 3.025平米。およそ畳二枚分。
マイソク
不動産広告のこと。賃貸会社でよく店頭に張り出されているので、見たことある人も多いのでは。間取り、物件の概要、地図などをまとめた資料の通称で、仲介不動産会社の情報源である。
残債
残存債務の略。住宅ローンなどで、未払いの借入金残高を意味する。
この残高は融資の可否や融資額にも影響するので、すでに住宅ローンなどある場合や複数の物件投資を検討したい時には計画性を持ってローンを組む必要がある。
賃貸管理会社
賃貸の入居募集をはじめとする賃貸管理業務全般を請け負ってくれる会社。入居者に直接関わる管理会社の手際の良し悪しは家賃収入にも影響する。
家賃保証
サブリースともいう。不動産会社が部屋を借り上げ、空室になってもオーナーには家賃が入ってくる賃貸管理契約形態のひとつ。
代行契約
オーナーの代わりにすべてのオーナー業務を代行してくれる賃貸管理契約形態のひとつ。
管理会社
物件の維持修繕を行う会社。賃貸管理会社とは別。
管理費
物件の維持管理を行うための費用。入居者が払う管理費とは別に、管理会社に支払う。
修積
修繕積立金の略。物件の維持修繕を行うための費用。管理会社に支払い、管理組合によって管理する。
管理組合
集合住宅(マンション)を管理、修繕するために設立される組合で、管理会社が運営にあたる。所有者は必ず組合員となる。適時、総会が開催され、現況の管理状況の確認、予算の確認などが行われる。
区分所有
区分所有とは、集合住宅(マンション)など、1棟の建物内で区分された各部分を所有することを意味する。平たくいうと、マンションやアパートの一室を所有することと同義。初めての投資は、一室のオーナーから始める人がほとんど。
専有部分
区分所有権建物において、購入者が自由にできる部分のことで、“住戸部分”とも言われる。具体的には、天井・床・壁などのコンクリート躯体で囲まれた内部空間を指す。
共用部分
集合住宅(マンション)で区分所有者たちが一緒に使っている共有スペースのこと。エントランスやエレベーター、玄関前の廊下などの空間を指す。
管理調査報告書
その建物の修繕履歴や現在の修繕積立金の額などが記載されている、管理会社から取り寄せる書類。
REINS(レインズ)
不動産会社が物件の情報を登録しているネットワークシステム。業者間で物件情報が共有できる、仲介業者のデータベース。
参考一般公開されないレインズの問題点とは?個人で閲覧・利用する方法も解説
専任媒介契約
不動産の売主が物件売却の仲介不動産会社を一社のみにした契約。
仲介手数料が発生する分、不動産会社が積極的に販売を促してくれ、定期的な業務報告もある。自ら買主を見つけて直接取引することも可能(その場合は仲介手数料がかからない)。
専属専任媒介契約
専任媒介と同じく、契約した一社のみを通して不動産売却を行う。
専任媒介とほぼ同じ契約形態だが、買主探しから売却までの取引全て契約した不動産会社を介して行われる。買主との直接取引はできないが、売却を専門業者に一任できる。
一般媒介契約
不動産取引において複数の不動産会社を介することができる契約。
上記2点と異なり業者の拘束力はないが、業者の積極度合いも低く、窓口が複数となるためやりとりが煩雑になりがち。
業者や不動産営業マンがよく使う業界用語(隠語)
直接口にすることはないかもしれませんが、知って損ナシの業界用語です。
ハマる
いくらまでローンが組めるかということ。「罠にはめる」といった悪い意味ではなく、お客様の条件と金融機関の条件をパズルのように「はめる」という意味。ローンが組める条件は金融機関によって異なるので、お客様にハマる金融機関を提供するのも営業マンの腕の見せ所となる。
返比(へんぴ)
返済比率の略。毎月いくらまで返済できるかの比率。金融機関ごとに定めがある。
あて物件
営業対象物件と比較させるために見せる物件。
潰し物件
比較させることを目的として見せる条件が厳しい物件。
両手
不動産会社が売主から物件を仕入れ、買主に販売することで売主・買主双方から仲介手数料を取得すること。片方の仲介の場合は「片手」となる。両手の場合双方から手数料を取得できるので、業者から買主に諸費用の値引きが適用されることもある。
契約の前に知っておきたい用語
契約の前に押さえておきたい重要事項や、契約のおおまかな流れもつかめます
耐用年数
資産として利用できる年数のこと。売買価格にも影響する。
減価償却
使用度や年数によって減ってゆく資産価値を損失計上する処理。
キャッシュフロー
お金の流れ。不動産投資の場合、手元に入ってくるお金には、ローン借入額や賃貸家賃による収入だけでなく、自分の属性(配偶者や副業の有無など)が反映される税額や減価償却費が影響する。複雑だが購入前の試算は重要。
瑕疵担保責任
売買物件に「隠れた瑕疵」がある時、売主側が買主に対して負う責任のこと。 シロアリ被害など、契約時に分からなかった場合でも買主が瑕疵に気づいた時点で損害賠償請求や契約解除もできる。ただし、請求の期限や責任範囲が契約時の特約に定められていることもある。
売契(ばいけい)
売買契約書のこと。土地や建物の売買の内容を売主・買主相互間で約束する書面。高額な取引のため「課税文書」という扱いになり、書面に貼る印紙代金も必要になる。
重説(じゅうせつ)
重要事項説明書のこと。取引する宅地建物に関する一定事項が記された書面で、宅地建物取引主任者が相手方に内容を説明しなければならない(宅建業法35条)。
重要事項の説明は契約を締結する前に行われ、取引する土地や建物についての詳細を確認した上で契約へ、という流れになる。
物件を所有してからかかる費用
税金をはじめとした諸費用は、購入時点でしっかり把握しておくことが大事です。
不動産取得税
土地や家屋を購入する、家屋を建築するなど、不動産を所得した年にのみにかかる税金のこと。
固定資産税
土地や家屋など、固定資産の所有者に課税される地方税所有者。毎年かかるものなので、購入する際のシミュレーションに含んでおいたほうがよい。金額の問い合わせなどについては、都税事務署や各市税事務署へ行う。
青色申告
不動産所得のある個人が所得を申告する手続き。事業性の有無で控除額が異なり、10部屋以上所有していない場合は非事業性に当たる。事前の承認申請書が必要で、複式簿記による正確な申告が義務付けられているが、非事業性であっても最低10万円控除ができる節税効果や、減価償却費を経費として申告できるなど、税金面のメリットが多い。
白色申告
事前の承認申請が不要で青色申告より手続きが簡易だが、控除や節税の特典が適用されないことがある。
修繕費用
固定資産の修繕にかかる費用。専有部分における設備の修繕、取り替え等はオーナー負担(空調設備、水廻りなど)、また、入居者の退去時にかかる修繕費用も一部オーナー負担となる。
管理費
建物の維持管理をするため、毎月管理会社へ支払う手数料のこと。建物の総戸数が少なかったり、共有スペースが多い場合、管理費はおのずと高くなる。
賃貸管理委託手数料
建物の賃貸管理にかかる手数料。会社ごとにさまざまだが、家賃の約4~5%が目安。
まとめ
以上、不動産投資入門として、知って便利な用語を簡単にご紹介しました。
ここまで読んでいただいたところで、「思ったよりもいろんな費用が発生するな」「税金は具体的にどのくらいかかるんだろう」「こんなに一気に用語を覚えられない」など、疑問点や不安が新たに芽生えた方もいるかもしれません。
そんな時はわからないままにせず、ぜひ不動産投資のエキスパートに相談してみましょう。
「初心者の自分が購入できる物件はどんなものか?」といった素朴な疑問から、「管理費・修繕積立金は安いほうが良いのか?」「気になる物件をローンで購入してみたいが、自分の収入でハマりますか?」など、この記事をきっかけに知りたくなった事があればぜひご相談ください。
TOKYOリスタイルのコンサルタントが、あなた自身の条件・希望に最適な提案でお応えします。