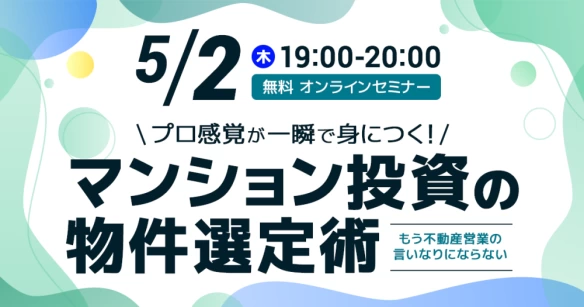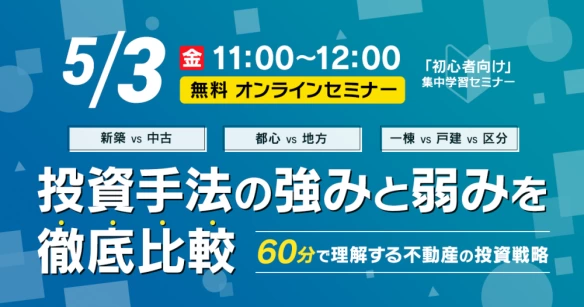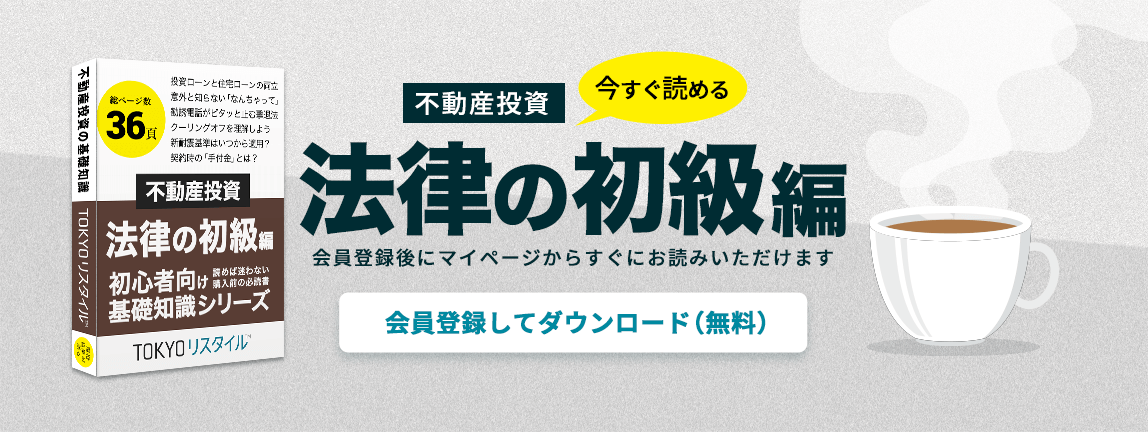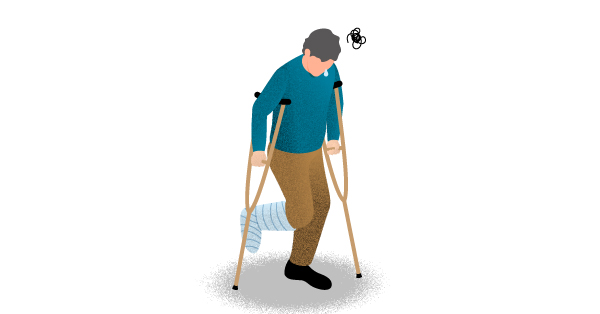不動産登記法とは?8つの登記のタイミングと必要書類、3つの改正予定を解説
- 更新:
- 2023/08/08

「不動産登記ってよく聞くけど、自分で説明できるほど知識がない…」という方は少なくありません。すべての不動産登記は「不動産登記法」という基本ルールに則って行われています。不動産登記については、本記事で解説する不動産登記法で定められた「登記事項証明書」の記載内容や、実際に登記をするタイミングを知っておく必要があるでしょう。
また本記事の後半でも解説するように、不動産登記法には時折改正が入るので、しっかりと変更点を知って法律に沿った登記をする必要があります。この記事を読んで、登記の基本とこれからの変更点をぜひしっかり押さえておいてください。
不動産登記法とは建物や土地の登記について定めた法律
不動産登記法とは、建物や土地の「登記」についてのルールが記載された法律です。建物や土地が誰のものであるか、どのようなものであるかが分かるのが「登記」で、不動産登記法のルールで守られていることによって不動産取引をトラブルなくスムーズに行えます。
不動産登記法が施行されたのは1899年。そこから105年後の2004年まで制度改正なく、不動産登記法に基づく登記が執り行われてきました。しかし2004年以降はオンライン化や条文の微修正がときどき行われており、徐々に時代に即した形に変わってきています。詳しくは記事の後半で解説しますが、2024年には相続に関するルールが大幅に変更される予定となっているのでしっかり押さえておきましょう。
不動産登記法と深くかかわる登記事項証明書とは
不動産登記法と深いかかわりを持つのが、土地・建物の情報(登記情報)が詳しく記載された「登記事項証明書」です。登記事項証明書について詳しく解説します。
不動産登記の内容は登記事項証明書で確認できる
わたしたちが「登記情報を確認したい」と思ったときには、登記事項証明書を確認すればOKです。不動産登記法に基づく登記(以下、不動産登記)が行われると、土地や建物の情報が法務局のデータベースに記録されます。このデータベースの内容を出力したものが登記事項証明書というわけです。
なお不動産の登記情報は会社の運営や不動産取引に必須のものと考えられているため、個人情報には当たりません。不動産を購入する前などには必要書類を揃え、該当の土地・建物の地番や家屋番号などの情報を収集し、法務局へ登記事項証明書を請求しましょう。なお登記事項証明書の取得申請等については、下記の記事で詳しく解説しているので参考にしてみてください。
参考誰でもわかる!登記簿謄本・登記事項証明書の全貌や申請方法を徹底解説!
登記事項証明書に記載されている内容
登記事項証明書に記載されている内容は、主に下記の3つです。
- 土地・建物の基本情報
- 不動産の所有者の情報
- 所有権を除く権利の情報
便宜上、土地と建物の登記事項証明書についてまとめて解説しています。しかし土地と建物の登記事項証明書は別々のものとなっているので覚えておきましょう。それでは、それぞれの記載内容について詳しく解説します。
記載内容①:土地・建物の基本情報

引用法務局
登記事項証明書の「表題部」には、下記のような土地や建物の基本情報が記載されています。
- 所在地・地番
- 地目(宅地か農地かなど)
- 地積・床面積
- 建物の構造
- 登記の理由
表題部を見れば、その土地の広さや建物の造り、どこにあるかが一目で分かります。なおマンションなどの区分所有する建物の登記事項証明書には「敷地権」という建物に付随する土地の権利についても記載されている場合があります。敷地権については下記の記事で詳しく解説しているので、ぜひチェックしてみてください。
参考敷地権とは!?不動産投資におけるメリット・デメリットを徹底解説!
記載内容②:不動産の所有者の情報
登記事項証明書の「権利部(甲区)」には、下記のような不動産の所有者の情報が記載されています。

引用法務局
- 所有者の住所
- 所有者の氏名
- 不動産の取得理由
権利部(甲区)の情報は蓄積されていくので、過去の所有者の情報をまとめて確認できます。不動産を購入する際には「所有者の入れ替わりが激しい物件だから、何かリスクを抱えていそうだしやめておこう」といった判断基準として活用できるでしょう。
記載内容③:所有権を除く権利の情報
登記事項証明書の「権利部(乙区)」には、下記3つの「所有権以外の権利」について記載されています。

引用法務局
- 抵当権:住宅ローンを組む際に購入する不動産を担保にする金融機関側の持つ権利
- 地上権:自分の建物などを設置するためにその土地を借りる他の人の持つ権利
- 地役権:一定の目的の範囲内でその土地を利用する他の人の持つ権利
権利部乙区の注意点は、主に「自分以外の人が持っているその土地・建物についての権利」が記載されていること。特に土地を購入する際にはしっかりチェックしておかないと、せっかく買った土地が思うように使用できない場合があります。3つの権利のうち地上権・地役権については個別の記事で解説しているので、ぜひ確認してみてください。
参考地上権とは?借地権・賃借権・地役権との違いやメリット・デメリットを詳しく解説
参考地役権とは?不動産を買うなら絶対に押さえておきたい3つのポイントと注意点を解説
不動産登記法で定められた登記をするタイミングとは
登記事項証明書の記載内容について詳しく解説しましたが、これらは登記をするたびに更新・追記されていきます。ここでは、その「登記」を行う8つのタイミングについて解説します。
- 家を建てたとき
- 不動産を購入・譲受したとき
- 不動産を相続したとき
- 住宅ローンを借りたとき
- 住宅ローンを返し終わったとき
- 住所・氏名が変わったとき
- 建物を建て替え・取り壊ししたとき
- 不動産を売却・譲渡したとき
それぞれ具体的な登記の内容や、申請書以外の必要な書類などを詳しく見ていきましょう。(なおほとんどの登記は司法書士に依頼するのが一般的です。必要書類に「委任状」と記載があるものは、司法書士への依頼を前提としています。)
登記をするタイミング①:家を建てたとき
もっとも基本となる登記のタイミングは家を建てたときです。建物の基本情報や所有者の情報を登録し、土地の所有者情報を移動しなければならないため、下記3つの登記が必要となります。
| 登記の種類 | 内容 | 必要書類 |
|---|---|---|
| 建物の表題登記 | 建物の種類・構造など基本情報を登録する | ・検査済証/建築確認通知書 ・工事完了引き渡し証明書 ・申請者の住民票 ・建物の図面/平面図 ・案内地図 など |
| 所有権の保存登記 | 1人目の建物所有者が発生する際の登記(※) ※ローンを組まない場合は義務ではない |
・住民票 ・委任状 ・住宅用家屋証明書(※) ※自分で住む場合 |
| 土地の所有権移転登記 | 土地の所有者を移動する | ・住民票 ・委任状 ・身分証 ・固定資産評価証明書 |
所有権の保存登記はローンを組まない場合は義務ではありません。しかし、保存登記を行わないと増築や取り壊し、売買などのあらゆる行為ができなくなってしまいます。義務ではないものの、実質的には保存登記も必須と覚えておきましょう。
登記をするタイミング②:不動産を購入・譲受したとき
不動産を購入・譲受したときには、文字通り所有権を他人から自分に移動する「所有権移転登記」をしなければいけません。所有権移転登記の必要書類は下記のとおりです。
- 住民票
- 委任状
- 身分証明書
- 固定資産評価証明書
所有権移転登記を正しく行わないと、前の所有者が実質的な権力を持ってしまうので注意しましょう。
登記をするタイミング③:不動産を相続したとき
親族から不動産の相続を受けたときには「所有権移転登記」が必要です。ただし下記のように、必要書類が購入・譲渡の場合と異なります。
- 被相続人・相続人の戸籍
- 遺産分割協議書
- 委任状
それぞれの戸籍情報のほか、相続時の遺産の分割について相続人同士で話し合った際に作成する「遺産分割協議書」の添付が必要です。ただし相続の形式によって必要書類は若干異なる場合があるので注意してください。
登記をするタイミング④:住宅ローンを借りたとき
住宅ローンを借りて不動産を購入する場合には「抵当権設定登記」が必要です。抵当権設定登記とは、金融機関が貸し倒れを防ぐために不動産を担保にすることを記す登記のこと。登記申請の際には、ローンを借りる人が下記の書類を用意する必要があります。
- 権利証または登記識別情報
- 印鑑証明書
権利証または登記識別情報は法務局から発行される書類です。紛失した場合でも抵当権設定登記はできますが、5 ~ 10万円の費用が別途かかるので注意しましょう。
登記をするタイミング⑤:住宅ローンを返し終わったとき
住宅ローンを返し終われば不動産を担保にする必要がなくなるので「抵当権抹消登記」を行います。抵当権抹消登記の必要書類はすべて金融機関が持っているので、借り手がなにかを用意する必要はありません。ただし金融機関が勝手に抹消登記を行ってくれるわけではなく、完済後に自分で手続きを行うか司法書士に依頼する必要があるので注意しましょう。
登記をするタイミング⑥:住所・氏名が変わったとき
結婚・離婚・転勤などの理由により住所や姓が変わった場合には「住所の変更登記」や「氏名の変更登記」をします。必要な書類は下記のとおりです。
- 本籍記載の住民票
- 戸籍の附票(住所が変わる場合)
- 戸籍謄本(姓が変わる場合)
なおこの登記は現在義務ではありませんが、2026年4月までに義務化されるので押さえておきましょう。
登記をするタイミング⑦:建物を建て替え・取り壊ししたとき
建物の建て替え・取り壊しをした際には「建物の滅失登記」をする必要があります。揃えるべき書類は下記のとおりです。
- 取り壊し(取毀)証明書
- 解体会社の登記事項証明書
- 解体会社の印鑑証明書
いずれも解体会社から受け取る書類のため、なくさずにまとめておきましょう。
登記をするタイミング⑧:不動産を売却・譲渡したとき
不動産を売った・譲渡した時には「所有権移転登記」をしなければいけません。自分が不動産を手放すので、下記のように購入・相続で入手した場合とは必要書類が異なります。
- 売買契約書
- 印鑑証明書
- 登記識別契約書
- 固定資産評価証明書
売買契約書や登記識別契約書は不動産を購入・譲受した際に受け取っている書類です。なお売却・譲渡時にローンが残っていた場合には「抵当権抹消登記」も同時に行う必要があります。抵当権抹消登記の必要書類等は「住宅ローンを返し終わったとき」と変わらないので、そちらを参照してください。
不動産登記法の今後の改正予定
2023年8月現在、不動産登記法は今後下記3つの改正が予定されています。
- 相続登記の申請義務化(2024年4月1日)
- 相続人申告登記制度(2024年4月1日)
- 住所等変更登記の申請義務化(2026年4月までに施行)
ここ数年で不動産登記法は大きく変わります。しっかりチェックしておきましょう。
2024年4月1日:相続登記の申請義務化
2024年4月1日には、相続登記の申請が義務化されます。今までは相続で不動産を取得した場合の相続登記は義務ではありませんでした。2024年4月1日以降は、相続から3年以内に「所有権移転登記」をしなければいけません。
なお「相続人が多すぎて戸籍謄本の収集が間に合わない」など正当な理由がある場合を除き、期限内に登記をしないと10万円以下の過料が発生する可能性があるので注意が必要です。
参考宇都宮地方法務局「知っていますか?相続登記の申請義務化について」
2024年4月1日:相続人申告登記制度
同じく2024年4月1日から「相続人申告登記制度」がスタートします。これまで放置されてきた相続登記が一斉に義務化され膨大な数の登記が集中したり、相続人にあたる人の負担が一気に増加したりするのを防ぐための制度です。
通常、相続登記(所有権移転登記)には煩雑な手続きをしなければいけません。そこで相続人申告登記制度を使えば、戸籍謄本の提出と簡単な法務局への申請で相続登記の義務を果たしたことになります。
ただしあくまで相続人申告登記制度による申請は一時的な対応です。最終的には相続人同士でしっかりと話し合って「遺産分割協議書」を作成し、正式な所有権移転登記を行う必要があるので注意しましょう。
参考仙台市法務局「相続登記の申請の義務化と相続人申告登記について」
2026年4月まで:住所等変更登記の申請義務化
具体的な施行日はこれから決められますが、2026年4月までに住所・氏名の登記申請(「住所・氏名が変わったとき」に相当する登記)が義務化されます。転勤の際に登記申請を求められる場合があるので、今後発表される施行日をしっかりチェックしておくのがおすすめです。
参考法務局
まとめ
不動産登記法とは建物や土地の「登記」についてのルールが記載された法律です。登記をすると法務局のデータベースに登録され、登録されたデータの内容は「登記事項証明書」で確認できます。
登記をするタイミングは家を買ったとき・売買・相続が発生したときや、ローンを借りた・返し終わったときなど。所有者などの土地・建物情報が変わったり、ローンの有無に変化があったりした場合に登記をしなければならないので覚えておきましょう。
また不動産登記法は2024年4月1日に2項目、2026年4月までに1項目が改正されます。不動産投資において直接関係するケースは少ないですが、改正の内容はぜひ確認しておきましょう。もちろん当社でも登記に関する丁寧な解説やアドバイスが可能ですので、不安のある方はぜひ一度ご相談ください。

この記事の執筆: 及川颯
プロフィール:不動産・副業・IT・買取など、幅広いジャンルを得意とする専業Webライター。大谷翔平と同じ岩手県奥州市出身。累計900本以上の執筆実績を誇り、大手クラウドソーシングサイトでは契約金額で個人ライターTOPを記録するなど、著しい活躍を見せる大人気ライター。元IT企業の営業マンという経歴から来るユーザー目線の執筆力と、綿密なリサーチ力に定評がある。保有資格はMOS Specialist、ビジネス英語検定など。
ブログ等:はやてのブログ