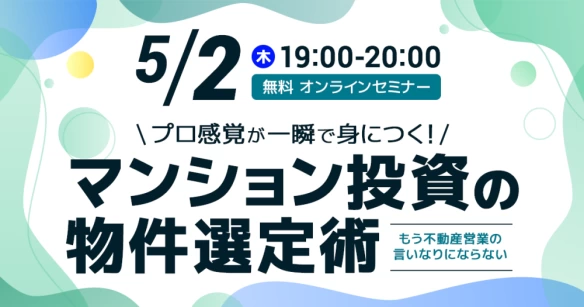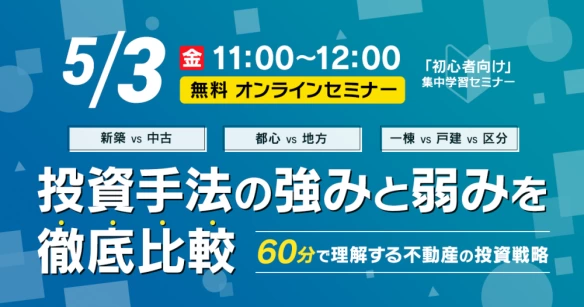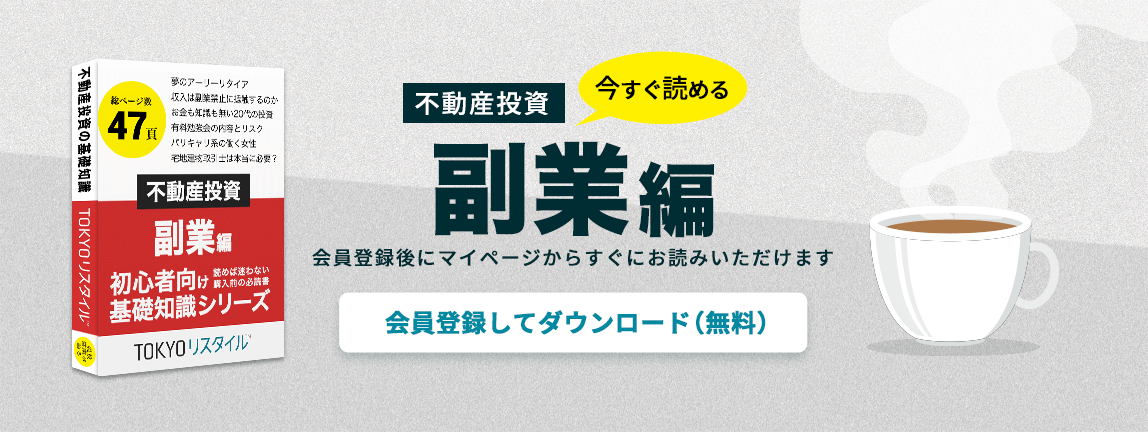日商簿記検定取得によるメリットと不動産投資に役立つ知識をご紹介します!
- 更新:
- 2023/06/05

日ごろお客様とお話ししていると、以下のような話が出てくることがあります。
- これまで自分で確定申告をしたことがないため、どうしていいかわからない
- 物件選定以外の細かいことはよくわからないため、経理関係の作業は全て税理士に任せる予定
このような方をはじめ、不動産投資を検討している方にぜひ身につけていただきたいのが簿記の知識です。簿記と聞くと、会計士などの専門家や会社の経理担当しか使わない知識と思う方が多いかもしれませんが、実は不動産投資においても簿記の知識が大変役に立ちます。
なぜなら、投資用物件は融資が通ればどなたでも購入することができますが、その購入した不動産は実際に収益性があるのか、今より収益を生むように改善するにはどうしたらよいかを検討する際に、簿記や会計、税法の知識が必ず関わってくるためです。
本記事では簿記検定の取得によるメリットと投資活動に与える影響、留意点について、特に多くの方が受験する日商簿記検定の2・3級を主として解説します。
簿記検定とは何か?
簿記は企業規模の大小や業種、業態を問わずに、日々の経営活動を記録・計算・整理して、経営成績と財政状態を明らかにする技能です。
その技能を測る簿記検定には、「日商簿記」、「全商簿記」、「全経簿記」の3種類がありますが、最も有名で受験者数が多い日商簿記検定についての概要と特徴について見てみましょう。
日商簿記検定の基本情報
日商簿記検定の基本的な情報は次の通りです。コロナの影響により、2020年12月からこれまでの会場受験に加えてネット試験が開始されました。会場受験を指す「統一試験」と「ネット試験」で形式が異なるところがあるため、そちらも併せてご紹介します。
| 統一試験 | ネット試験 | |||
|---|---|---|---|---|
| 3級 | 2級 | 3級 | 2級 | |
| 実施頻度 | 年3回 | 年3回 | 指定日を除くほぼ毎日 | 3級と同じ |
| 受験料 | 2,850円 | 4,720円 | 2,850円 | 4,720円 |
| 合格率(商工会議所)※ | 30.2% | 20.9% | 41.5% | 37.7% |
| 試験時間 | 60分 | 90分 | 60分 | 90分 |
| 合格基準 | 70%以上 | |||
| 解答方法 | 紙面に記入 | 紙面に記入 | パソコン入力 | パソコン入力 |
| 必要な学習時間(TAC調べ) | 120~140時間 | 250~350時間 | 120~140時間 | 250~350時間 |
| 合否判定 | 2~3週間後 | 2~3週間後 | 即日 | 即日 |
※対象期間 統一試験:2022年11月実施分 ネット試験:2022年4月〜12月実施分
日商簿記検定の特徴
日商簿記検定は日本商工会議所および各地商工会議所が実施している検定で、3級の試験科目は商業簿記、2級からは商業簿記と工業簿記に分かれています。それぞれどのような内容なのか見ていきましょう。
商業簿記の特徴
商業簿記は、購買活動や販売活動など、企業外部との取引を記録・計算する技能で、経営者や投資家などのステークホルダーに対し、適切かつ正確な報告を行うためのものです。3級と2級の大枠は同じですが、2級で取り扱われる論点もあるため、2級の出題範囲が広くなっています。具体的な出題内容は以下のとおりです。
| 3級 | 2級 |
|---|---|
| 第一 簿記の基本原理 1.基礎概念 2.取引 3.勘定 4.帳簿 5.証ひょうと伝票 |
第一 簿記の基本原理 1.基礎概念 2.取引 3.勘定 4.帳簿 5.証ひょうと伝票 |
| 第二 諸取引の処理 1.現金預金 2.売掛金と買掛金 3.その他の債権と債務等 4.手形 5.債権の譲渡 6.引当金 7.商品の売買 8.有形固定資産 9.収益と費用 10.税金 |
第二 諸取引の処理 1.現金預金 2.有価証券 3.売掛金と買掛金 4.その他の債権と債務等 5.手形 6.債権の譲渡 7.引当金 8.債権の保証 9.商品の売買 10.様々な財又はサービスの顧客への移転 11.有形固定資産 12.無形固定資産 13.投資その他の資産 14.リース取引 15.外貨建取引 16.収益と費用 17.税金 18.税効果会計 19.未決算 |
| 第三 決算 1.試算表の作成 2.精算表 3.決算整理 4.決算整理後残高試算表 5.収益と費用の損益勘定への振替 6.純損益の繰越利益剰余金勘定への振替 7.帳簿の締切 8.損益計算書と貸借対照表の作成 |
第三 決算 1.試算表の作成 2.精算表 3.決算整理 4.決算整理後残高試算表 5.収益と費用の損益勘定への振替 6.純損益の繰越利益剰余金勘定への振替 7.その他有価証券評価差額金 8.帳簿の締切 9.損益計算書と貸借対照表の作成 10.財務諸表の区分表示 11.株主資本等変動計算書 |
| 第四 株式会社会計 1.資本金 2.利益剰余金 3.剰余金の配当など |
第四 株式会社会計 1.資本金 2.資本剰余金 3.利益剰余金 4.剰余金の配当など 5.会社の合併 |
| 第五 本支店会計 | |
| 第六 連結会計 |
工業簿記の特徴
工業簿記は、企業内部での部門別や製品別の材料・燃料・人力などの資源の投入を記録・計算する技能で、経営管理に必須の知識で、2級から試験科目に追加されます。具体的な出題内容は以下のとおりです。
| 2級 |
|---|
| 第一 工業簿記の本質 |
| 第二 原価 |
| 第三 原価計算 |
| 第四 工業簿記の構造 |
| 第五 材料費計算 |
| 第六 標準原価計算 |
| 第七 原価・営業量・利益関係の分析 |
| 第八 原価予測の方法 |
| 第九 直接原価計算 |
| 第十 製品の受払い |
日商簿記検定を取得するメリットとは?
ここからは日商簿記を取得するメリットについて解説します。具体的には次の3点です。
- 自分で確定申告ができる
- 専門性の高いスキームを組成できる
- 収入アップにより手元資金を増やすことができる
では早速1つずつ見ていきましょう
メリット①:自分で確定申告ができる
メリットの1つ目は自分で確定申告ができるようになる点です。不動産投資を始めると、毎年税務署へ確定申告書の提出が必要になります。これまで会社員として仕事をしてきた方のうち、不動産投資開始後、初めて確定申告をする方も多いことでしょう。確定申告書の作成は、税理士に任せきりにすることもできますが、年間数十万円もの費用がかかってしまいます。
不動産投資ではローンの支払以外にも、修繕費や固定資産税といった付随費用がかかってくる中、多額の税理士費用まで発生すると、家賃収入よりも支出の方が多いという事態になりかねません。
個人事業の確定申告書はシンプルで簡単に作成できるため、簿記の知識をつけて自分で作成できるようになれば、税理士に支払う費用を減らすことが可能となります。
参考【最新版】不要なケースも!家賃収入の確定申告を分かりやすく解説!
メリット②:専門性の高いスキームを組成できる
2つ目は専門性の高いスキームを組成できる点です。投資を行ううえで、簿記で学んだ専門的な知識を大きく役立たせることができるでしょう。通常であれば、税理士に依頼するような高度なスキームにおいても、簿記で学んだ知識をもとに自身で組み立て、投資に活かすことが可能になります。
例えば、法人設立がその最たる例と言えます。法人を設立することは、往々にして投資に大きなメリットをもたらします。例えば、個人の申告であれば計上できない費用を支出としてあげることができたり、法人ならではの優遇措置を受けることができたりするなどのメリットを享受することが可能です。このことが、自身の投資生活に非常に有益であることは火を見るよりも明らかでしょう。
参考不動産投資で法人化?資産管理会社のメリット・デメリットを徹底解説!
しかし、メリットばかりではなく、法人化することで手間が増えることもあるため、慎重な判断が必要になります。その手間の一つが決算書の作成です。
法人の確定申告には決算書が必要となります。法人の申告書は複雑なため、作成する際は税理士の力を借りることをおすすめしますが、申告書に添付する決算書は簿記2級までの知識で作成することが可能です。
また、銀行から融資を受ける際にも確定申告書が必要となります。税理士に任せきりにせず、申告書の内容をきちんと理解し、銀行の担当者に対して説明ができるようになることで、経営者としての評価が高まり、融資を受けやすくなるでしょう。
必ずしも法人を設立することが良いということではなく、当社のお客様も個人で不動産投資をしている方が多いですが、いずれにせよ、簿記や会計、税務の知識がなければ、このような選択肢を取ることはできません。これらの知識は、不動産投資を成功に導く武器の一つになると言えます。
メリット③:収入アップにより手元資金を増やすことができる
3つ目は手元資金を増やすことができる点です。投資を成功に導くためには、手元資金を増やし、投資に使えるお金を増やすことは重要な要素の一つと言えます。その点において、本業や副業での収入アップに注力することも大切になるでしょう。
そこで役立つのが日商簿記です。現在、多くの企業が社員に対して、日商簿記の取得を奨励しています。それは簿記を理解することによって、財務諸表を読む力や分析力、コスト意識の向上が期待されるためです。財務諸表を読むことで取引先の経営状況を把握できようになるため、経理部以外の部署でも、簿記を昇格試験の必要項目にする会社が増えています。
日商簿記の取得によって、上記のような仕事でのキャリアアップだけでなく、現在のスキルとの掛け合わせで業務が広がる可能性も上がるでしょう。興味があれば、会計や税務などのより専門的な知識を習得し、キャリアチェンジや副業を始めるのも良いかもしれません。いずれにせよ、簿記の知識の習得は不動産投資に直接役立つだけでなく、本業の収入アップという観点でも大変役立つことは自明でしょう。
投資で役立つ簿記の知識
では、ここからは具体的に投資活動において役立つ、簿記の知識の一例として、減価償却費についてご紹介しましょう。
減価償却とは?
高額の資産を購入することになる不動産投資では、減価償却の理解が必須であると言えます。
減価償却とは、建物などの長期にわたって使用する高額なものを、購入した年に全額費用とせず、時間の経過に合わせて費用計上する会計処理です。すなわち、減価償却の対象となる資産については、取得した段階で全額経費計上するのではなく、資産を使用できる期間で分割計上します。
例えば、使用できる期間が10年の物件を1,000万で購入した場合、購入した年に1,000万全額を費用計上するのでなく、1年に100万ずつ、10年に渡って費用計上するようなイメージです。
この資産を使用できる期間のことを「法定耐用年数」と言い、その資産の内容によって使用可能年数が定められています。そして、その法定耐用年数をもとに配分した金額をそれぞれの年に費用計上する際に使う科目が「減価償却費」です。
高額の物件を取り扱う不動産投資においても、減価償却費は確定申告時に大きな影響を与えます。減価償却費は、購入後2年目以降も経費計上できるにも関わらず、実際の支出は伴いません。経費を計上すると利益が減るため、その分利益をもとに計算される税金の額は少なくなります。すなわち、2年目からは手元資金を減らさずに税額を減らすことが可能です。
減価償却の概念を理解することで、手元資金がどの時期にどのくらい必要になるのか、正しく把握することができるようになるため、非常に重要な項目であると言えるでしょう。
参考【2023年】不動産投資の赤字と損益通算、減価償却を分かりやすく解説
まとめ
日商簿記の取得には時間や費用がかかりますが、知識をつけることによって、投資活動や仕事に大きなメリットをもたらすことは言うまでもありません。
また、将来を見据えてその他の資格取得を検討している場合でも、資格の中には、簿記の考え方を習得しておくと理解が速く進むものが多く、日商簿記は最初に取り掛かる検定として大変おすすめです。日商簿記の勉強は、資格スクールでの講座受講や参考書を使用した独学など、様々な手段があるため、ぜひ自分に合った勉強方法をご検討ください。
当社のコンサルタントは、不動産投資に関する豊富な経験と知識を有し、お客様の疑問や不安を解消するお手伝いをしています。より専門的な不動産投資情報をお求めの方は、ぜひ我々コンサルタントにご相談ください。