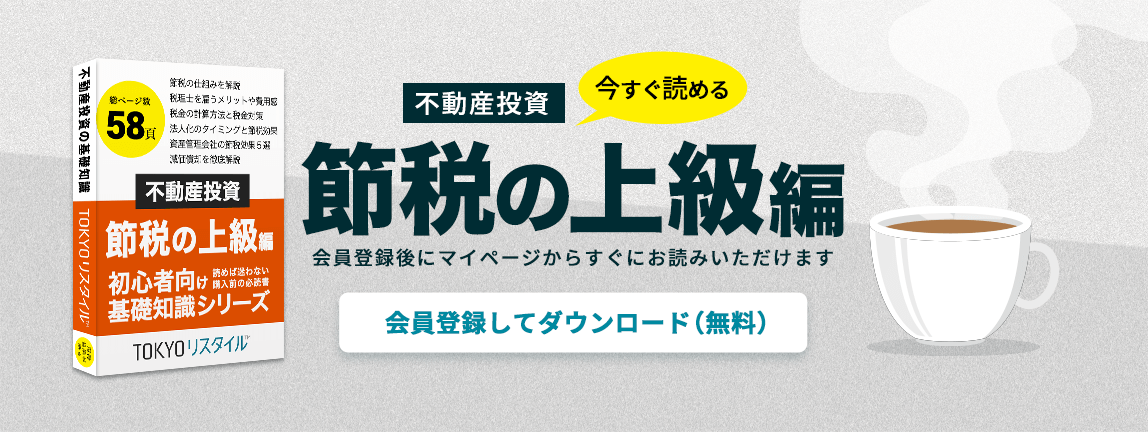3,000万円の特別控除!その全てを分かりやすく解説
- 更新:
- 2023/05/01
本記事は動画コンテンツでご視聴いただけます。
マイホームを売却する際、「3,000万円の特別控除」が受けられることを知っていますか?高額な売買取引となる家の売却は、利益分に税金がかかります。
税金を減らすためにも「3,000万円の特別控除の特例」は理解しておいた方が得策です。今回はこの3,000万円の特別について解説していきます。
3,000万円特別控除とは
3,000万円の特別控除とは、住居のための不動産物件を誰かに売却(もしくは譲渡)して得た金額から最高で3,000万円を控除するという特例のことです。
これは物件を所有していた期間に関わらず適用することが可能です。
売却金額が3,000万円にいかない場合は、売却金額まで控除することが出来ます。その場合、税額は0円となります。
対して売却の金額が3,000万円以上となる場合は、超える金額に対する「短期譲渡所得」もしくは「長期譲渡所得」としての税率が適用となります。
この特例は相続で得た物件にも、要件を満たせば使用することが出来ます。物件を相続したけれど、売却を考えているという人におすすめの特例です。
特別控除適用時の計算方法
3,000万円の特別控除は、物件を売却した時の「譲渡所得」から最高で3,000万が控除されます。馴染みのない言葉かもしれませんが、譲渡所得とは、売却金額そのものではなく、その金額から「取得費」と「譲渡費用」が引かれたものです。
取得費とは
取得費とは、その物件を購入した際の金額と共にその時にかかった費用です。
<取得費の主な内容>
- 土地建物の購入金・建築金
- 測量費、整地費、建物解体費など
- 設備費、改良費
- 購入しやときにかかる税金(印紙税・登録免許税・不動産取得税等)
- 購入にかかる仲介手数料
- 借入金利子
譲渡費用
譲渡費用とは売買でかかった、不動産業者へ支払った仲介手数料等の費用を指します。
<譲渡費用の主な内容>
- 売買にかかった仲介手数料
- 違約金
- 借地権の名義書換料など
- 印紙税
- 立退料
- 建物解体費など
主にこれらの金額が引かれることになります。
取得費の計算
取得費は土地と建物の場合で計算方法が変わってきます。
土地の場合、土地の購入代金や購入手数料などの合計額となります。
建物は購入金額等の合計金額から、所有している期間中の減価償却費相当額を差し引いた額が取得費となります。
減価償却費の計算
減価償却費はこのような計算式によって算出することができます。
- 減価償却費 = 取得価額 0.9 ✕ 償却率 ✕ 経過年数
取得費が分からない場合
もしも売却する土地や建物が先祖から引き継いだものであったり、買い入れ時期が不明等の理由により取得費が分からないという場合は、売却金額の5%相当額を取得費とすることも可能です。
それだけではなく、実際の取得費が売却金額の5%相当額を下回ってしまった場合でも、売却金額の5%相当額を取得費とすることができます。
例えば、土地建物を2,000万円で売った場合、取得費が不明でも売却金額の5%相当額にあたる100万円を取得費に出来るのです。
こういった場合、まずは国税庁へ相談することをおすすめします。
譲渡所得の計算
先述した通り、譲渡所得および譲渡所得税額はこのような計算式で算出されます。
<譲渡所得の計算式>
- 譲渡所得 = 販売金額 - 取得費 - 譲渡費用
この計算式を使い、3,000万円の特別控除を適用することで数十万円~数百万円の譲渡所得税の支払いを無くすことが可能です。
またマイホームが共有名義の際は、控除額は共有者の合計で3,000万円というわけではなく、共有している一人あたりが最高3,000万円まで適用されます。
参考税金を正しく理解しよう!サラリーマンは不動産投資で節税できるのか?
3,000万円の特別控除が受けられる条件とは
次に3,000万円の特別控除が受けられる条件を見ていきましょう。
他の特例を適用していない
3,000万円の特別控除は、前年や前々年に下記の控除を受けていないことが前提条件となっています。
- 3,000万円控除
- 居住用の買換え特例
- 居住用財産の買換えの場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
- 特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
3年に一度しか適用できない
3,000万円控除は3年に一度しか適用できない仕組みです。
参考2020年(令和2年)最新版 家賃収入にかかる税金の計算方法や税金対策について
マイホームの場合の特例条件
前述した条件以外に、マイホームの売却の条件を解説します。
まず3,000万円の特別控除は「住まいとしている家の売却」が前提です。投資用の不動産物件は適用外となるため注意しましょう。そのため「住まいかどうか」という点は厳しく確認されます。
自分が住んでいた家かどうか
3,000万円の特別控除は「住んでいた家かどうか」が重要なポイントです。そのため、控除を受けるために一次的に入居した場合などは特別控除が受けられません。
基本的には、この特例はマイホームの所有期間は関係ありませんが、特例のための入居であると判断された場合は適用外となるので注意しましょう。
また、マイホームを建設中のため一時的に仮住まいとして住んでいた、という場合も適応外となります。
同様に別荘などの娯楽目的で建設・購入した物件も対象外です。あくまでも日常で使用していた住居物件に限り適応される特例となります。
また、3,000万円の特別控除は、住まなくなってから3年を経過した年の12月31日までに売却した場合に適応されます。
物件を取り壊した場合
物件を取り壊した場合が、下記の3つの要件に当てはまった場合に限り適応されます。
- 家屋を取り壊した日から1年以内に譲渡契約が締結されている
- 住まなくなった日から3年を経過した12月31日までに売却する
- 家屋を取り壊してから譲渡契約を締結した日まで、その敷地を貸駐車場等のその他の利用をしていない
災害で家屋を滅失した場合
災害によって滅失した場合に3,000万円の特別控除を適応するには、住まなくなった日から3年目の12月31日までに売却しなくてはなりません。
売り手と買い手が特別な関係
売手と買手が、親子・夫婦など特別な関係である場合は特別控除は適応されません。「特別な関係」とはこれだけではなく、生計を一緒にする親族・家屋を売却後に売った物件で同居する親族、内縁関係の人物、特殊な関係の法人も含まれます。
次に相続した土地や空き家の場合の条件を見ていきましょう。
相続した土地(空き家)の場合の条件
相続した空き家に関しても、3,000万円の特別控除を適応することが可能です。条件として平成28年4月1日~令和5年12月31日までの間に売却した場合に限り、下記の3つの要件を満たす空き家に関して譲渡所得の金額から最高3,000万円の控除が可能となります。
- 昭和56年5月31日以前の建築物件である
- 区分所有建物登記がされている建物でないこと。
- 相続開始の直前に、被相続人以外に住んでいた人がいない
特例を受けるための適用要件
その他の適応条件も見ていきましょう。
- 売却した人が相続もしくは遺贈によって物件及び物件の敷地等を取得したこと
- 相続開始から3年の12月31日までに売却すること
- 売却代金が1億円以下
- 売却した物件や土地が相続財産を譲渡した際の「取得費の特例」「収用等の場合の特別控除」等の他の特例を受けていないこと
- 売買契約が親子・夫婦など特別の関係でない
相続に関してもこのような条件が定められています。
3,000万円特別控除の注意点
3,000万円の特別控除は他の控除との併用が出来ません。特に住宅ローン控除と併用可能と思っている人も多いので注意しましょう。
参考2020年(令和2年)最新版 不動産投資ローンの金利はどのくらい?相場を比較
住宅ローン控除と併用はできない
新しいマイホームを購入する時にこれまで住んでいた古いマイホームを売却する人が多いと思いますが、この際に住宅ローンを組む人もいるでしょう。
基本的には「3,000万円の特別控除」と「住宅ローン控除」の両方を適応することは出来ません。
住宅ローン控除とは住宅ローンを組んでマイホーム(新築・購入・改築・建て替えに関わず)を取得する際に、一定の条件を満たすことで控除が受けられる制度のことです。これは年末に住宅ローンの残高から所得税が差し引かれ、その分が還付されるという「税額控除」です。住宅ローン控除は、日本国が推進している制度で国民の住宅購入を促進させる目的があります。
住宅ローン控除は新しいマイホームに住み始めた年と、その前後2年である合計5年間の間に3,000万円の特別控除の適用を受けた場合は住宅ローン控除を適用をすることはできません。
住宅ローン控除と3,000万円の特別控除は、新しいマイホームに住み始める前後5年間の間に、3,000万円の特別控除を適応していなければ住宅ローン控除の適応可能と思う人もいるかもしれませんが実際には難しいでしょう。
そもそも新築住宅で住宅ローン控除を受ける場合の条件の中に「特例な課税適用を受けていないこと」も明記されています。
そのためもしも3,000万円の特別控除と住宅ローン控除のどちらを適応すべきかと悩んだ場合は、両方をシミュレーションしてより有利な方を選択する必要があります。
3,000万円の特別控除に関しては、先述した通りの計算式で譲渡所得額を出し、所得税率も計算しましょう。
住宅ローン控除に関しては、控除額は最大400万円までと定められています。しかしこれはあくまでも最大の金額であり、住宅ローン控除は下記の条件に当てはまる人のみが対象となります。
- ローン残高が4,000万円以上
- 年間の所得税・住民税が40万円以上
上記の場合に上限の400万円が控除されます。
しかし控除はローン残高の1%となり10年間で毎年40万円ずつと分けられます
また住宅ローン控除は、低収入の場合は控除される所得税や住民税が少ない為、減税の効果はそこまで感じられません。
また住宅ローン控除を受けるための物件の平米数や物件の築年数なども細かく明記されています。
収入が多くそもそも支払う納税額が高額な場合は、住宅ローンでも十分な恩恵を感じるかもしれませんが、まずは計算して確かめることをおすすめします。
それに比べて、3,000万円の特別控除は売却による譲渡益があれば大きな節税効果も期待できるといえます。
もちろん、個人の状況や属性、物件の売却金額によっても変わってくるため一概にどちらがいいとは言えません。
マイホームの売却で「住宅ローン控除」か「3,000万円の特別控除」か悩んだ場合は、国税庁が受け付けている相談窓口で相談してみるのもおすすめです。
もちろん、信頼できる不動産会社に相談してみることもおすすめです。まずは専門的な知識を持っている業者等に相談し、自分の状況を確認することも重要です。
参考住宅ローン控除を確実に申請しよう!必要書類からスケジュールまでを解説
軽減税率の特例は併用可能
先述した通り、3,000万円の特別控除は他の特例との併用はできませんが、所有期間が10年を超えている場合、税率が低くなる「軽減税率の特例」は併用可能となります。当てはまる場合はチェックしましょう。
事前準備しておきたい、確定申告時の必要書類
3,000万円の特別控除を適用するために確定申告をしましょう。
確定申告の際に必要な添付書類は、下記となります。
- 譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)【土地・建物用】
- 確定申告書B
- マイナンバーカード
- 各種健康保険証 or 運転免許証等の本人確認書類
- 売買契約書
- 売却に関する費用の領収書
- 売買契約書
これらを確定申告の基本的な書類と共に税務署に提出し、確定申告をしましょう。 確定申告書Bや売買契約書などの基本的な必要書類と合わせて、税務署に提出してください。
参考2020年(令和2年)最新版 家賃収入に確定申告は必要?不要?
相続の場合の確定申告書類
先述した「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」を適用を申し込む際の確定申告では、上記の書類だけではなく下記の書類も必要となります。
- 売買契約書の写し
- 被相続人居住用家屋等確認書
- 譲渡所得の内訳書
- 登記事項証明書等
- 耐震基準適合証明書 or 建設住宅性能評価書の写し
確定申告は期限が決まっているため、締め切り日ギリギリになる前に準備しておくことをおすすめします。
まとめ
3,000万円の特別控除について解説してきました。不動産投資とは関係ないと思いがちなこちらの特例ですが、自分がマイホームを購入した際の売却計画の際にも使える特例です。また不動産投資家として成功するためにも不動産に関係する様々な知識は持っておくべきでしょう。本記事を自分の知見を広げるためにお役立てください。